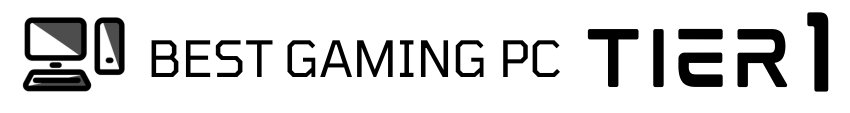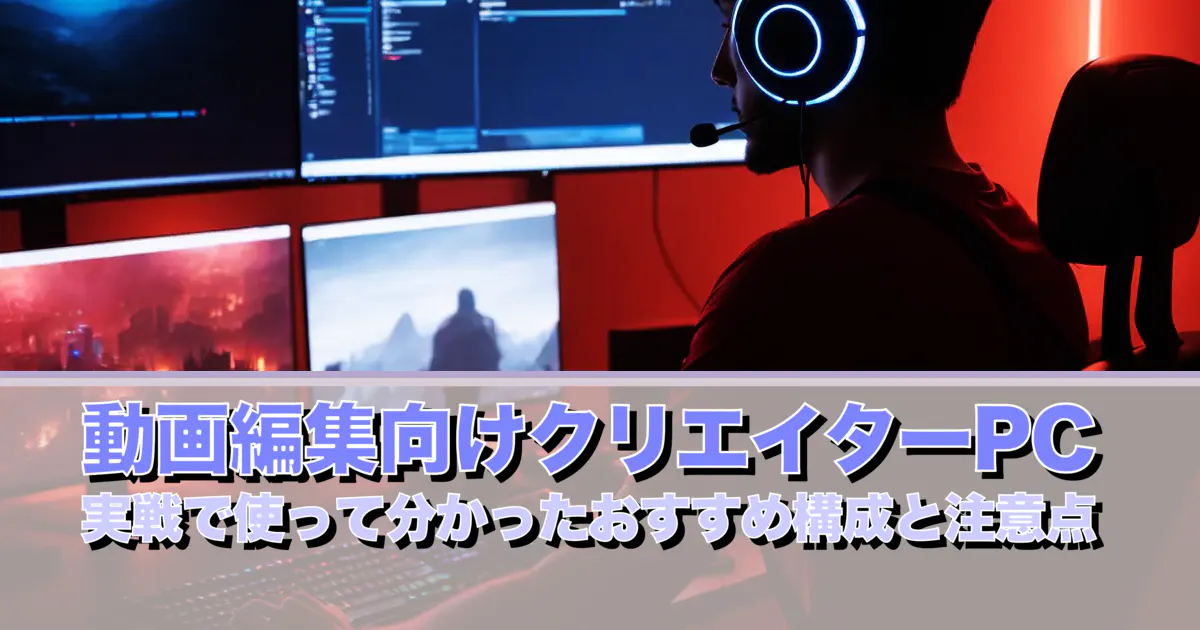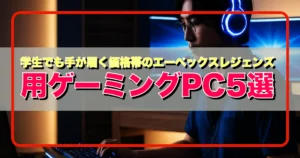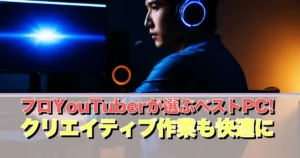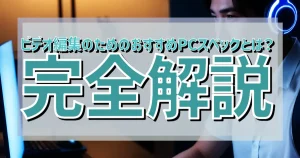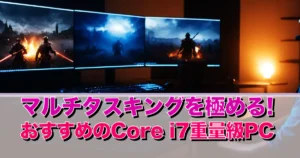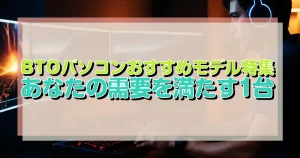動画編集向けに選ぶクリエイターPC、実作業で必要だったスペック目安
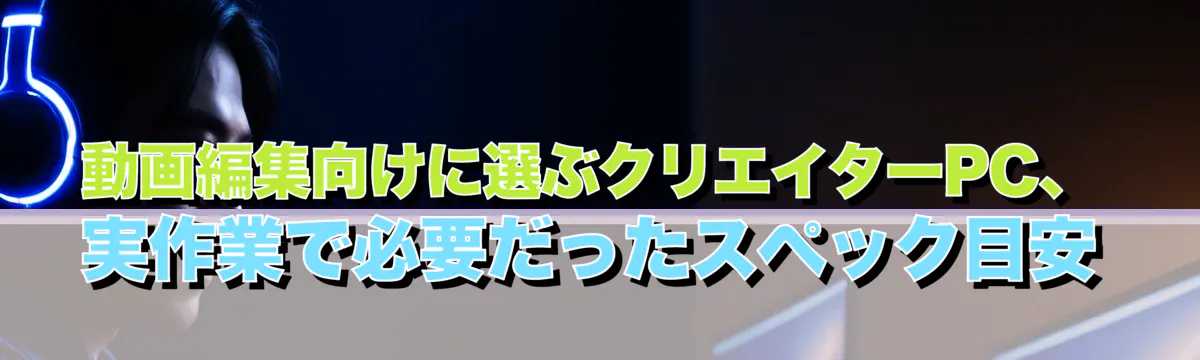
CPUはCore UltraとRyzen、使ってみて感じた違いと選び方
実際に両方を手に取って作業環境で使ってみると、やはりRyzenの底力は圧倒的でした。
動画編集、それも尺が長く解像度も高い案件をこなすとき、時間の短縮効果はまさにビジネスに直結します。
一方で、移動が多い私にとってCore Ultraの利点も無視できません。
バッテリー消費が少なく静かで作業に集中できる環境を作ってくれるあの安心感は、数字だけでは測れない大切な価値です。
結論として性能の単純な優劣ではなく、使う場面によって答えが変わるのだと実感しました。
Core Ultraを実際に触ってみて、「軽やかだな」と感じたのはAI処理の速さでした。
最新の編集ソフトに搭載されている自動補正やノイズ除去、これらを複数同時に走らせても処理が滞らない。
それもホテルの狭いデスクで出張編集をしているときです。
正直、こういう環境ではPCが熱を持ってファンが唸り出し、集中力をそがれるのが常でした。
しかしCore Ultraは静かに淡々と仕事を進めてくれる。
この働きぶりには心底助けられました。
「やるじゃないか」とつぶやいてしまいました。
逆にRyzenだと負荷のかけ方によっては一瞬ですが処理に引っかかりが出るときもあります。
映像がカタッと止まる、その小さな瞬間が気持ちを緊張させるんです。
そして比較にならない差を見せてくれたのは、やはりレンダリング速度でした。
しかもその間にもブラウザで参考動画を開いて別作業を並行できてしまう余裕。
この差を体感したとき、「これは馬力の次元が違う」と思わざるを得ませんでした。
時間が武器に変わる。
もちろんCore UltraにもRyzenにない快適さが存在します。
夜の静かな時間帯、クライアントとつないだオンラインレビューの最中、Core Ultraはほとんど無音のまま粛々と動いてくれました。
相手に「ファンの音、なんだかうるさいね」などと指摘される心配がないのは大きな強みです。
特に在宅ワークと外出先とを行き来する私の働き方では、この静けさこそが見落とせない要素でした。
だから使い分けるようになったんです。
重い案件をがっつり処理しなければならないときにはRyzen。
まさに頼もしい相棒。
一方で移動中やビジネスホテルの一室で効率的に下準備を進めたいときにはCore Ultra。
状況次第で切り替える柔軟さを持つことで、私の仕事はぐっとやりやすくなりました。
単純に「どちらが上か」ではなく、「自分がどんな場面でPCを必要としているのか」に目を向けることが大事です。
机上のスペックシートだけを並べても、そこには現場で感じる違和感や、意外なやりやすさは出てきません。
私自身の体感では、4K以上の案件を納期前提で走り抜くならRyzenの一択。
それ以外、特に移動仕事やスピーディに下作業を整えたいときには静かで省電力のCore Ultraが頼れる道具になります。
こうして振り返ってみると、数年前にAppleのM1チップが登場し、一気に業界が揺れた瞬間を思い出します。
Ryzenはあのときに匹敵する衝撃を与えてくれました。
ただし今回の違いは、Core Ultraもまた十分に存在価値があるという点です。
二つを同じ時間軸で比べられることで、選択の幅が広がっているわけです。
静けさ。
爆速。
この二つはまるで相反する価値ですが、日々のビジネスではどちらも欲しい。
私が行きついたのは「シーンで切り替えて両方を使う」というごくシンプルな答えでした。
移動続きの日々にはCore Ultra。
働き方が多様化した今だからこそ、この緩急の付け方がストレスを減らしてくれます。
最終的に重要なのは一人ひとりの働き方や案件の質に合わせてどう配分するか。
最新CPU性能一覧
| 型番 | コア数 | スレッド数 | 定格クロック | 最大クロック | Cineスコア Multi |
Cineスコア Single |
公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 9 285K | 24 | 24 | 3.20GHz | 5.70GHz | 43230 | 2437 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 42982 | 2243 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X3D | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 42009 | 2234 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900K | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.00GHz | 41300 | 2331 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X | 16 | 32 | 4.50GHz | 5.70GHz | 38757 | 2054 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X3D | 16 | 32 | 4.20GHz | 5.70GHz | 38681 | 2026 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265K | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37442 | 2329 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265KF | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37442 | 2329 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 9 285 | 24 | 24 | 2.50GHz | 5.60GHz | 35805 | 2172 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700K | 20 | 28 | 3.40GHz | 5.60GHz | 35664 | 2209 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900 | 24 | 32 | 2.00GHz | 5.80GHz | 33907 | 2183 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.60GHz | 33045 | 2212 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700 | 20 | 28 | 2.10GHz | 5.40GHz | 32676 | 2078 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X3D | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.50GHz | 32565 | 2168 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7900X | 12 | 24 | 4.70GHz | 5.60GHz | 29382 | 2017 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265 | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28665 | 2132 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265F | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28665 | 2132 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245K | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25561 | 0 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245KF | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25561 | 2150 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9700X | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.50GHz | 23187 | 2187 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9800X3D | 8 | 16 | 4.70GHz | 5.40GHz | 23175 | 2068 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 235 | 14 | 14 | 3.40GHz | 5.00GHz | 20946 | 1838 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7700 | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.30GHz | 19590 | 1915 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7800X3D | 8 | 16 | 4.50GHz | 5.40GHz | 17808 | 1795 | 公式 | 価格 |
| Core i5-14400 | 10 | 16 | 2.50GHz | 4.70GHz | 16115 | 1758 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 5 7600X | 6 | 12 | 4.70GHz | 5.30GHz | 15354 | 1959 | 公式 | 価格 |
グラフィックボードはどのグレードから快適さを実感できるか
単にレンダリング時間が短くなるかどうかという数字だけの話ではなく、作業のテンポや集中の持続、さらには自分の気持ちの波にまで影響してくる。
だからこそ私は、動画編集を業務として続ける以上、GPUに対する投資は決して軽視してはいけないと痛感しています。
特にフルHD中心の制作ならRTX4060Tiでも何とか耐えられますが、4Kを本格的に扱うなら躊躇なくRTX4070以上を選ぶべきだと断言できます。
実際、私はRTX4060Tiで半年間ほど働いていましたが、徐々に限界が見えてきました。
最初は素材を切って並べる程度なら十分いけると自分に言い聞かせていたのですが、案件が進むにつれてエフェクトやカラー調整の負担が重なり、プレビューが途切れ途切れになる瞬間が増えていく。
その時の苛立ちは本当に堪えました。
作業の手が勝手に止められ、思考の流れがぶち壊される。
あの時のストレスは今でも忘れられません。
だから最終的にRTX4070へと乗り換えたのです。
費用負担は確かに大きかったのですが、あの選択は正しかったと心の底から思っています。
流れるようなプレビュー。
この快適さが、編集者にとって何より大切な支えになります。
映像の流れをそのまま目で確認できるかどうかは、作業全体を左右します。
滑らかであれば自分のペースを保ち続けられるし、逆に途切れると気持ちも切れてしまう。
その消耗感は、経験した人にしか分からないでしょう。
だから私は、GPUがもたらす真の価値とは「心の安心感」だと考えています。
以前、8K案件を担当したことがあります。
RTX4070のマシンでは処理が追いつかず、プレビューがカクついてしまって、正直作業環境としては不十分でした。
ためらわず操作できるあの解放感は、まさしく別世界でしたね。
これが本当の効率化か、と唸らされました。
決してオーバーに言っているわけではありません。
GPUの性能は、今や単なる贅沢ではなく必須条件です。
動画編集ソフトもCUDAやNVENCをフル活用するよう設計されています。
つまり、ハードとソフトが同時進行で進化しているのです。
そのなかで「予算を抑えればとりあえず大丈夫だろう」と甘く考えて選ぶと、後でとんでもないツケを払うことになる。
安く抑えたはずが結局買い直しで余計に出費し、しかも作業効率まで削られる。
この二重苦を私は何度も経験しました。
妥協すれば後悔。
最終的には高性能モデルを買い直さざるを得ません。
仕事で使う以上、ここは迷わずしっかり投資しておくことが賢明です。
私の判断基準としては、1080p中心ならRTX4060Ti、4K本格運用ならRTX4070、そして8Kや長期的な案件を見据えるならRTX4080以上。
この区分けは実経験の積み重ねから導き出した私なりの結論です。
40代の今、私は若い頃と違って時間の価値を以前よりも強く感じるようになりました。
20代30代の頃は多少処理がもたついても「まあ仕方ない」と笑ってやり過ごせましたが、今は納期との戦いがあり、家庭との両立もあり、体力だって確実に落ちています。
効率を落とすだけではなく、気力を削られてしまう。
そのもどかしさは、年を重ねるほど痛感するようになりました。
私がRTX4070へ切り替えた当時は、財布へのダメージも確かに覚悟が必要でした。
けれども、その投資で守れたものは金額以上に大きかった。
その安心感はやがて自分の信頼や成果にもつながっていきました。
結局のところ、グラフィックボードは贅沢品などではなく、仕事を支える必須の道具なのだと強く思います。
だから私が皆さんに伝えたいのは一つ。
日常的に編集するなら、迷ったら性能が高い方を選ぶべきです。
ケチって後悔するより、最初にしっかり投資した方が結果的に得をする。
同じ現場に立つビジネスパーソンとして、その判断が現場の信頼や成果の積み重ねに直結するのだと、私は胸を張って言います。
後に残るのは安心感と信頼。
私はこれを身をもって経験しましたし、これからもそう信じて選び続けます。
最新グラフィックボード(VGA)性能一覧
| GPU型番 | VRAM | 3DMarkスコア TimeSpy |
3DMarkスコア FireStrike |
TGP | 公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | 32GB | 48879 | 100725 | 575W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5080 | 16GB | 32275 | 77147 | 360W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9070 XT | 16GB | 30269 | 65968 | 304W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7900 XTX | 24GB | 30192 | 72554 | 355W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5070 Ti | 16GB | 27268 | 68111 | 300W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9070 | 16GB | 26609 | 59524 | 220W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5070 | 12GB | 22035 | 56127 | 250W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7800 XT | 16GB | 19996 | 49884 | 263W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 16GB | 16625 | 38905 | 145W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 16GB | 16056 | 37747 | 180W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 8GB | 15918 | 37526 | 180W | 公式 | 価格 |
| Arc B580 | 12GB | 14696 | 34506 | 190W | 公式 | 価格 |
| Arc B570 | 10GB | 13796 | 30493 | 150W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 | 8GB | 13254 | 31977 | 145W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7600 | 8GB | 10864 | 31366 | 165W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 4060 | 8GB | 10692 | 28246 | 115W | 公式 | 価格 |
メモリは32GBで実用的か、それとも64GBにして余裕を持たせるべきか
4K動画の編集を本格的にやろうと考えているなら、私は64GBのメモリを選ぶのが安心だと思います。
なぜなら32GBでは何とか動くものの、いざ案件の規模が大きくなったり、複数ソフトを並行して走らせたりした瞬間に動きが鈍くなり、リズムを崩すことが多いからです。
映像編集は勢いが大事で、作業が止まるたびに気持ちまで切れてしまう。
だから止まり方が小さくても積もれば山となり、最終的には納品のペースに影響してしまうのです。
私は実際に32GBと64GBの両方を経験しました。
覚えているのはDaVinci ResolveとAdobe After Effectsを同時に立ち上げて、RAW素材を扱ったときの衝撃です。
32GBだとノードを重ねただけで動作が詰まり、プレビューもひっかかってストレス。
思わず「ちょっと待ってくれよ」と声が出ました。
けれど64GBに増設した途端、嘘みたいに滑らかに動く。
映像が途切れずに流れていくと、まるで自分の作業そのものが呼吸を取り戻したように感じられるのです。
この体験ははっきりとした分かれ目になりました。
複数のソフトを同時に走らせたときの差は、さらに大きく現れます。
Premiere Proで素材を切りつつ、Photoshopで静止画を補正し、横でブラウザを開いて資料を参照する。
64GBならその圧迫感を感じません。
作業のスピード感がそのまま維持できて、心の余裕まで違ってきます。
作業に没頭できるかどうかは、案外こういう環境面に左右される、と改めて実感しました。
もちろん、すべての人に64GBが不可欠と言うつもりはありません。
軽い動画編集や趣味レベルでの制作なら32GBで問題なく済みます。
私も実際、YouTube用の短いクリップを扱う場面では32GBでも困りませんでした。
ただ、それが本業として収益を伴う案件なのか、それとも趣味なのかで、投資と回収のバランスは変わります。
趣味ならコストを抑えた方がよい。
でも仕事なら64GBを選んだ方が結局は堅実です。
その違いは、効率と精神的な安定に確実に現れます。
安心感。
最近の編集ソフトは生成AIの機能を多く取り込み始めています。
自動ノイズ除去やアップスケーリング、AIによる映像生成などです。
便利に見えても、その裏ではメモリを大きく消耗していて、想定よりも負担が大きくなる。
AIは便利でありながら、時にやっかいな相棒です。
だからこそ私は余裕を持ったシステムを選びます。
未来の変化に備えるなら、そのほうがずっと無難です。
正直、64GBは安くはない。
買うときに財布の痛みを感じました。
けれど、ひとたび納期が迫り、秒単位で修正を繰り返しているときに作業が詰まらない安心感には、それ以上の価値があります。
納期直前でマシンが止まる、その恐怖心を考えれば、機材投資を惜しまない方が結局は心も楽になる。
私の場合、この差が仕事の速度とクオリティに直結しました。
効率を支えるのは道具です。
ただし誤解しないでほしいのは、32GBにも意味はあるということです。
小規模な案件だけを扱うなら不満は少なく、導入コストを抑えたい人にはむしろ最適な選択です。
だから「どこを目指すか」がすべてを決めます。
私の場合、収益を伴う案件が中心なので64GBが間違いのない答えでした。
しかし知人の中には、趣味でしか動画を触らない人もいて、その人は32GBで十分に満足しています。
正解はひとつではなく、自分のスタンスに応じて変わるものです。
とはいえ、もし本気で仕事に使うつもりなら64GBを勧めたい。
導入時は出費に見えても、効率化によって時間を取り戻せるし、精神的な余裕が跳ね返ってきます。
経験上、道具への投資を後回しにすると、必ずどこかでストレスや時間の浪費となり、結果的に大きな負担を背負うことになる。
投資は未来の自分を守る行為でもありますから。
そのとき頼りになるのは結局マシンの安定感です。
ソフトが動き続けるか止まるか、その一点が成果物の質と締め切りに直結するのです。
だから私は、自分の安心を確保するために64GBを選びました。
そして今も答えは変わらない。
それが、私がたどり着いた一番確かな選択肢なのです。
ストレージ速度はGen.4で十分だったか、それともGen.5で体感差が出るのか
ストレージ選びで大切なのは、今の作業環境で本当に必要な力を持っているかどうかだと私は思っています。
実際に検証してみて強く感じたのは、現時点での動画編集用途においては、無理してGen.5 SSDを導入する必要はないということです。
4K素材を中心に扱うのであれば、Gen.4で十分に実用的だからです。
数値的には確かにGen.5が勝っているのですが、いざ現場で使って確かめると、期待していたほどの飛躍は得られませんでした。
導入前は「これで一気に作業効率が跳ね上がるのでは」と思っていただけに、プレビューや基本的な素材の読み込みでその差がほとんど体感できなかったのは残念でしたね。
もちろん大容量のRAW映像を一気にコピーしたときのスピードは圧倒的でした。
その瞬間はあまりに速く、「おいおい、もう終わったのか!」と思わず声が出ました。
それでも日常的な作業をどれほど楽にするかという点で見れば、インパクトは限定的なんです。
安定感。
これがやはり重要です。
むしろ普段の作業ではGen.4のほうが安心できる印象があります。
Gen.5は性能面こそ華やかですが、発熱に悩まされるのは無視できません。
熱が出すぎて速度が落ちてしまうこともあり、大きめのヒートシンクや追加ファンが必要になります。
結局、コストも手間もかさむわけです。
私は長年自作PC環境で作業してきましたが、冷却や発熱の問題は想像以上に神経を使います。
小さなトラブルが積み重なると、時間を奪われるのと同じ。
これは編集現場において致命傷になりかねない、そう身にしみて感じています。
安定性は命綱。
そう言い切れますね。
ただし未来の視点を持つなら話は変わります。
8K素材のプロジェクトや巨大なRAWのマルチカム編集を行う場面、そこではGen.5の真価は間違いなく現れます。
最近はLog素材を使うプロジェクトも増え、一つのファイルが数百GBになることも珍しくありません。
今はまだ4Kを中心とした現場が多いと思いますが、将来的に高解像度や膨大なファイルを扱う比率が高まれば、Gen.4ではどうしても追いつかなくなります。
だから未来への投資としてGen.5を選択する価値は確実にある。
ここは現場のスケール感と将来像をどう描くかが判断のカギになります。
検証を重ねた結果、外部レビューもチェックしてみました。
PhotoshopやPremiere Proの実測データではキャッシュ読み込みに数秒から十数秒の差が出る程度でした。
つまり、普段の作業風景で「一気に仕事が変わる」という実感はほとんど生まれません。
もちろんそのわずかな時間を積み上げればプロジェクトによっては大きな差になるのかもしれません。
ただ、私自身はそこに強い価値は見出せませんでした。
それよりも目に止まったのは電力効率の差です。
Gen.4は全体的に消費が控えめで、長時間の作業に向いています。
正直に言います。
最新スペックを追いかけていても、実際の仕事の効率が上がらなければ意味がないんです。
私も以前は「新しいモノは常に正義」と考えて、無理に投資をした時期がありました。
でも現実は違った。
発熱トラブルに足を取られ、解決に時間を費やし、気づけば余分にお金も失っていた。
あの苦い経験から学んだのは、必要な部分にだけ冷静に投資するということでした。
最新に飛びつくより、鈍臭くても確実に安定したほうがいいんです。
そう思うようになりましたね。
では、今の段階で何を導入すべきなのか。
答えは単純です。
理由は明確で、コストと発熱対策、そして安定性。
そのバランスにおいてGen.4が今もっとも優れているからです。
Gen.5を選ぶべきは、毎日のように数TB規模の素材を扱う人や、8Kといった超大規模制作が前提となる人だけでしょう。
大多数の現場においてそこまでの性能は不要です。
技術の進化は本当に速いと感じます。
ただ、次々と登場する最新スペックに余計に振り回されるのは得策ではありません。
数秒の差よりも、当たり前に安定して動く環境こそが必要なんです。
私と同じ世代の方なら、日常の安心感を一番に優先したいという気持ち、きっと理解してもらえると思います。
だから私はあえてGen.4を使い続ける。
悔いはまったくありません。
必要な場面に応じて投資すればよい。
SSD規格一覧
| ストレージ規格 | 最大速度MBs | 接続方法 | URL_価格 |
|---|---|---|---|
| SSD nVMe Gen5 | 16000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD nVMe Gen4 | 8000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD nVMe Gen3 | 4000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD SATA3 | 600 | SATAケーブル | 価格 |
| HDD SATA3 | 200 | SATAケーブル | 価格 |
実際の作業を通して見えたクリエイターPC向きパーツの組み合わせ
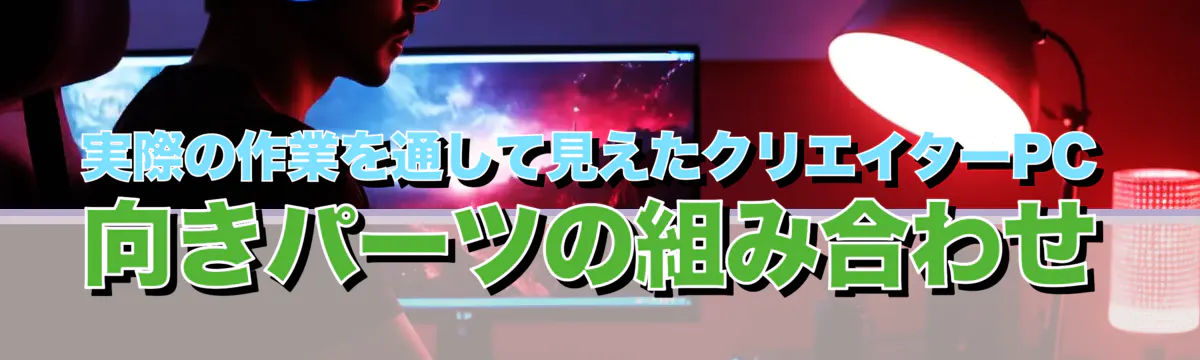
動画編集を安定させるために気を付けたいCPUクーラーの選び方
動画編集を続けてきて強く感じるのは、パソコンが熱に負けず安定して動いてくれるかどうかが、最終的に仕事の成果を大きく左右するということです。
どれだけ性能の高いパーツを組み込んでも、冷却が追い付かなければ力を発揮しきれないのです。
実際、私は何度もそこに苦しめられてきました。
だからこそ今ははっきり言えます。
動画編集を快適に行いたいなら、冷却への投資を惜しむべきではない、と。
昔の私は正直、空冷で十分だろうと軽く考えていました。
大きめの空冷クーラーを積んでおけば余裕だろう、とタカをくくっていたのです。
軽い編集なら問題ないのですが、4K編集に入ると途端にファンがフル回転になり、部屋の空気まで熱を帯びて集中どころではなくなる。
作業机に座り続けるのが本当に辛かったのです。
「これはもう無理だ」と感じた瞬間がありました。
そのとき初めて気づいたのです。
冷却の出来が、作業効率やモチベーションをこんなに左右するものなんだと。
藁にもすがる思いで簡易水冷を導入してみたのですが、結果は劇的でした。
温度は安定し、ファンの騒音も大幅に減って、静けさすら感じられるようになった。
思わず「なんでもっと早く試さなかったんだろう」と口にしてしまったほどです。
ただし、水冷という響きだけに惑わされてはいけません。
製品選びを誤れば、結局は後悔します。
ポンプが耳障りに鳴りっぱなしになれば、むしろ空冷以上にストレスを感じることだってありますし、ケースに収まらず設置に苦労して動作が不安定になるなんてこともある。
どれだけ熱を逃がすかだけでなく、自分の作業環境全体との相性をシビアに見る必要があるのです。
冷却は奥が深い。
それでも動画編集の観点に絞れば、水冷の優位性はほぼ揺るぎません。
数時間単位でエンコードを続けるようなときこそ、冷却力の余裕がものを言います。
CPUの性能を最大限発揮できるかどうか。
その差ははっきり現れます。
パフォーマンスの維持は、精神的な安心にもつながる。
私は本当にそう思っています。
いま私が常用しているのはフルタワーに280mmクラス以上の水冷ラジエーターを搭載した構成です。
十分な冷却性能はもちろん、最近の水冷クーラーに付いているライティング機能が意外に気持ちを和らげてくれるんですよ。
緊張が和らぎ、妙な安心感すら持てます。
「仕事環境って思いがけない部分で変わるんだな」としみじみ感じました。
後輩に「動画編集用にパソコンを作るなら何を重視したほうがいいですか」と聞かれることがあります。
そのとき私は迷わず答えます。
なぜなら、冷えない環境ではいくら高いパーツを入れても結局は持ち腐れになってしまうからです。
安心して作業に没頭できるかどうか。
それはスペック表の数字以上に価値のあることなんです。
水冷にするなら、私は推奨します。
360mmクラスの簡易水冷を選び、しっかりとケースに収める。
空冷で性能と静音性を両立させるのは非常に難しく、調整に時間をかけるより最初から水冷を導入してしまう方が安心です。
個人的にはこれが自分の失敗と経験から導き出した、一番納得のいく結論です。
実際、私自身は空冷でひどい失敗をしました。
騒音に苛立ち、室温に体力を削られ、思考が鈍る。
たった数度の差がこれほど自分の仕事に影響するという驚きを今でも鮮明に覚えています。
その時投じた水冷代は決して安くありませんでしたが、結果的に効率の向上を考えれば十分ペイしたと断言できます。
冷却こそが編集環境の土台。
欠かすことのできない基本です。
長時間レンダリングを見据えて選ぶべきケースの条件
動画編集や3Dレンダリングに本気で取り組むなら、PCケースには絶対に投資すべきだと私は考えています。
これは単なるパーツの一つではなく、作業環境の安定性そのものを握る土台だからです。
熱がこもって処理落ちしたり、途中でクロックダウンが発生して時間を浪費する経験を一度でもした人なら、二度と同じ失敗をしたくないと思うはずです。
あの時は「もっと早く正しいケースを選んでいれば」と心底感じました。
ケース選びで最も大きなポイントは、エアフローです。
CPUやGPUが高負荷時に発する熱は容赦なく、冷却が追いつかないと一気に処理速度が落ちていきます。
私はかつて密閉型のガラスパネルデザインを選んだことがありましたが、数時間のレンダリングを続けると熱が籠もって効率が急激に下がるのを体感しました。
それに比べて前面メッシュ構造のケースを使った際は、温度が8度から10度下がり、作業中の快適さが段違いでした。
あの差は作業効率以上に、心の余裕に直結するんですよね。
入口が肝心。
さらに、内部スペースの余裕も決して軽く考えるべきではありません。
十分な奥行きがないと大型のラジエータが収まらなかったり、増設ファンをつけられなかったりして、結局あとで苦しくなるのです。
レンダリング作業は短距離走ではなく、マラソンに近いものです。
序盤は気持ちよくても、最後に熱と騒音で息切れするようなマシンは仕事の相棒にはなれません。
内部に余裕がある構造こそ、長く使える証拠です。
そして忘れがちなのが清掃のしやすさです。
これは本当に重要です。
長時間の稼働を前提にしていると埃は必ず溜まります。
工具が必要でフィルターを外すのが面倒だと、人間はどうしても「また今度」と先延ばしにしてしまうものです。
その結果、騒音が増し、温度も上がり、結局大きなストレスに繋がります。
私は以前、工具不要で簡単にフィルターが外せるケースを選んだことがありましたが、そのときは自然に掃除する習慣が身につきました。
掃除を苦痛と感じないだけで、精神的にもずっと軽いものです。
気楽さ。
清掃のしやすさはスペック表に書かれていなくても、毎日の仕事の質を大きく左右します。
ほんの数分で埃を取り除けるというだけで、安心してソフトを走らせられる。
これは経験した人にしか分からない実感かもしれませんが、大げさではなく「作業効率の裏にある静かな力」だと私は思います。
静音性も忘れてはいけません。
夜中に長時間レンダリングを走らせるとき、うるさいケースを選んだ代償を文字通り「体で」味わいました。
深夜に布団の中でファンの高回転音が響き渡り、眠れないまま朝を迎えたときの疲労感。
ただ、密閉すれば静かになるものではなく、冷却を犠牲にした遮音は逆効果になります。
遮音材とエアフローをバランスよく共存させる設計こそが肝心で、そこを突き詰めているケースに出会うと、本当に「こういうものを待っていた」と素直に感動します。
私は最近MSIのバランスのとれたケースに触れる機会があり、その時の印象は実に鮮烈でした。
静かで冷える。
この両立をきちんと体現しているケースを使うと、深夜も安心してPCを走らせられるのです。
実際に手に取ってみると「これは長く使える」と納得できるものでした。
こうして振り返ると、ケース選びの条件は決して複雑ではありません。
前面がきちんとメッシュで冷気を取り込めること、内部に余裕があり拡張性を確保できること、掃除が簡単で手間が少ないこと、そして静音と冷却を両立できる設計であること。
この四点に尽きます。
私は様々な失敗や試行錯誤を経て、最終的にこのシンプルな結論にたどり着きました。
多くを求めるのではなく、必要な基礎を外さない。
それが結果的に最も安心できる道です。
つまり、便利さと安定性を両立できるケースこそが、私たちが持つ限られた時間と労力を無駄にしない唯一の答えだと心から思います。
先延ばしにすると必ず後悔しますから、これだけは妥協してはいけません。
ゲーミングPC おすすめモデル5選
パソコンショップSEVEN ZEFT R60GU

| 【ZEFT R60GU スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | AMD X870 チップセット GIGABYTE製 X870M AORUS ELITE WIFI7 ICE |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60CT

| 【ZEFT R60CT スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 9900X 12コア/24スレッド 5.60GHz(ブースト)/4.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Fractal Pop XL Silent Black Solid |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット GIGABYTE製 B850 AORUS ELITE WIFI7 |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R67H

| 【ZEFT R67H スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5000Gbps/3900Gbps KIOXIA製) |
| ケース | DeepCool CH160 PLUS Black |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60SM

| 【ZEFT R60SM スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 DIGITAL WH |
| マザーボード | AMD B850 チップセット MSI製 PRO B850M-A WIFI |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60CYA

| 【ZEFT R60CYA スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) SSD SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | NZXT H9 FLOW RGB ホワイト |
| CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 360 Core II White |
| マザーボード | AMD X870 チップセット GIGABYTE製 X870M AORUS ELITE WIFI7 ICE |
| 電源ユニット | 1000W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (アスロック製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
静音性や温度管理を含めた全体バランスの取り方
動画編集用のPCを考えるとき、最初に頭に浮かぶのは性能ですが、私が身をもって実感しているのは「静音性と温度管理こそが本当の快適さを決める」ということです。
4K映像をレンダリング中に熱がこもって処理が一気に遅くなるときの焦りと苛立ちは、もう二度と味わいたくない種類のストレスでした。
ケース選びほど悩ましいものはありません。
密閉型は確かに音を抑えてくれますが、数時間も作業していると内部に熱が溜まり、じわじわと処理が鈍くなる。
それを我慢して進めるべきか、心地よさを優先するべきか。
私も最初は静音性を取ってDefineシリーズを使っていました。
ところが案件が重なるにつれ、CPU周りの発熱で性能が下がり、納品前に待ち時間ばかり延びる状態に。
正直、夜中のオフィスで「またかよ」と苦笑いした瞬間を今でも覚えています。
その後フロントメッシュ型に替え、大型の空冷クーラーを組み合わせたら、ようやく安定感と静かさを両立できました。
CPUクーラーも同じです。
水冷システムには高い冷却力がありますが、ポンプ音が常に低く響き、どうしても気持ちが乱れる。
さらに長期使用で故障や水漏れのリスクを考えだすと、夜間作業で集中したい私には安心できませんでした。
その点、大型の空冷クーラーは安定感が抜群です。
単純な構造だから壊れにくく、しかも静か。
カタログ上の性能よりも、数十時間におよぶ編集の現場で静かに息をしてくれる存在は頼もしく、それに何度も救われました。
もちろん、GPUの発熱対策を優先して水冷をうまく活用する場面もあるのですが、無条件に「最強だから水冷」という発想は違うと思っています。
作業環境が何より大切で、心が落ち着かない環境ではどんな高性能も無駄になる。
本音です。
そして絶対に見落とせないのが電源ユニットです。
容量がギリギリの電源だと、負荷がかかった瞬間にファンが唸り声を上げる。
真夜中の集中タイムにその音が混ざると、一気に気持ちが萎えます。
だから私は常に80PLUS Gold以上を使い、余裕のある容量を確保するようにしています。
ここにケチったら、後で必ず後悔するとわかっているからです。
最近導入したSeasonic製の電源は特に印象が強いものでした。
レンダリング中でもファンがほとんど回らず、部屋に静けさが保たれる。
電源の存在を意識しないほどに静かで、それでいて安定供給。
無音に近い環境で安心できる、その価値は仕事の質を左右します。
これはオーバーではありません。
特に深夜のオフィス。
静まり返った空間でキーボードの打鍵音とマウスのクリック音だけが響く中に、冷却ファンが轟音で割り込んでくると、集中の糸が簡単に切れてしまうんです。
ちょっとしたことのようでいて、この差が最終的な成果に直結します。
GPUもCPUも適切に冷やされて音も静か、電源も安定している。
このバランスを保てるかどうかが、ストレスなく続けられるPC環境を築く鍵だと確信しています。
静音であること。
高性能パーツを追いかけても、それだけでは本当の効率は得られない。
だからこそ全体の調和を最優先に考えるべきで、それに投資する価値は確かにあると私は感じています。
数字では表れない安心感。
けれど、その積み重ねが最終的に成果を守ってくれる。
要するに、高性能を求めるだけでは環境は整わないということです。
本当に必要なのは、静けさと冷却のバランスを大切にした構成。
私はこれを何度も試行錯誤した経験から断言できます。
自分にとって信じられる構成こそが、最高の投資なのです。
BTOと自作、クリエイターPCを購入する際に知っておきたい違いと注意点
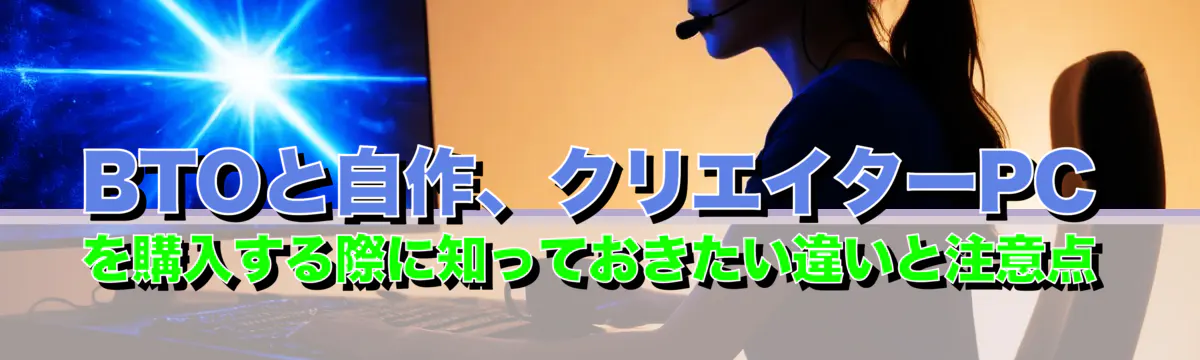
BTOパソコンで得られる安心感とカスタマイズ範囲
BTOパソコンを購入して本当に良かったと、私は強く感じています。
メーカー製は一見便利でも選択肢が狭く、自作は部品を選ぶ楽しさがある反面、時間と手間を膨大に食ってしまう。
それならば仕事に直結する安定性と柔軟性を両立したBTOこそ、最も現実的で賢い選択だと胸を張って言えます。
そんな失望を二度と味わいたくないと心から思い、勇気を出してBTOへ切り替えました。
その結果、4K動画を重ねても安定して動く環境が実現し、もう作業中に不安が頭をよぎることはありません。
何より感じたのは安心感です。
この「安心して任せられる」という気持ちが、どれだけ仕事の集中を助けてくれることか。
以前の私は作業中、いつ落ちるか、いつ処理が止まるかと常に神経をとがらせていました。
それが今では杞憂です。
穏やかに、淡々と集中できる。
これは大げさに聞こえるかもしれませんが、精神的な余裕の有無が成果物の質に直結するのを実感しています。
そしてもう一つの大きな魅力、それは自分の用途に合わせて構成を変えられることです。
CPUを最新世代にしたり、必要に応じてGPU性能を上位にしたり、メモリを大容量に調整したりと、まるで私の仕事スタイルに合わせて最適化できるのです。
メーカー製のモデルだと、どんなに魅力的な仕様に見えても「ここだけは強化したい」と思う部分に手が届かないことが多い。
あの感覚は小さなストレスの積み重ねとなり、やがて大きな不満に膨らんでいきます。
一方でBTOだとその壁がなく、自由度の高さに思わず笑ってしまうほどです。
そう、自由なんです。
もちろんコストの問題は無視できません。
スペックを強化すれば価格は確実に上がっていきます。
それでも私は、それを短期的な浪費ではなく未来への投資だと考えています。
たとえばGPU性能に数万円余分に投資した結果、動画の書き出し時間が従来の三分の一に短縮されたことがありました。
30分かかっていた処理が10分で終わる。
その差は1回だと小さなものかもしれませんが、一年を通した積み重ねは数十時間に及びます。
その数十時間を別の業務や新しい学びにあてられるとしたら、価格差なんて簡単に回収できてしまう。
これほど生産性を押し上げるものはないと痛感しました。
時間の重みを知る。
これは社会人になって日に日に強く感じています。
若い頃は「根性で何とかなる」と思って無駄に夜を過ごすこともありましたが、今は一分一秒の意味が違う。
体力も集中力も有限です。
だからこそ、無駄を削ってくれる道具にお金を投じることは本当に価値があるのだと実感しています。
さらに未来の変化にも備えられるのがBTOの強みです。
私は購入時にあえて電源を大きめにしておきました。
正直、そこまでする必要はないかと思ったのですが、後々GPUを強化したくなったときにスムーズに対応できたので、自分の判断を褒めたい気持ちになりました。
ソフトや規格は容赦なく進化し、今日の高性能が数年後には当たり前になります。
そのとき買い直すのではなく、一部を入れ替えて持続的に使える。
この柔軟さは、これからも何度も自分を救ってくれると思っています。
あえて例えるなら、将来を見据えて少し広めの家を買ったようなものです。
最初は持て余す空間でも、家族が増えたときや新しい暮らし方を始めるときに効いてくる。
BTOの拡張性はまさにそういう余裕を与えてくれるのです。
安心。
心強さ。
そんな二つがいつも背中を支えてくれます。
確かに、自作で究極を追い求めるのも魅力的でしょうし、完成品をサッと買って済ませるのも合理的に見える選択かもしれません。
ただ現実には、限られた時間とリスクを意識せざるを得ないビジネスパーソンにとって、そのどちらも決定打に欠けるのです。
だからこそBTOがベストバランスなのです。
自作の自由さとメーカー製の安定さ、その両方をいいとこ取りできるから。
私は迷わず選びました。
これからも私はBTOを選び続けるでしょう。
理由は単純です。
自作PCにおけるパーツ選びの自由度と実際に起こりやすいリスク
自作PCというものは、自由に組み立てられる楽しみがある一方で、経験を重ねるごとに「安定して動くことの大切さ」を強く感じるようになりました。
若い頃は最新のパーツを追い求めて、数字の上で高性能であることに喜びを感じていましたが、今の私が一番に考えるのは「毎日安心して使えるかどうか」なんです。
それが自作PCに長く向き合ってきた私の実感です。
最初に身をもって思い知ったのは電源の重要性でした。
パーツのリストだけを見て、必要そうな数字を満たしていれば大丈夫だろうと軽く考えていた頃がありました。
700Wなら余裕だろうと高性能GPUと大容量SSDを組み合わせた結果、作業中に突然パソコンが落ちるという恐怖に何度も直面しました。
まるで停電にあったかのように、一瞬で画面が真っ暗になるんです。
その時の焦りは、今でも鮮明に思い出せますよ。
冷や汗が一気に噴き出して、仕事どころではなくなる。
数字遊びではなく、現実の稼働を支える安定性を理解したきっかけでした。
悔しさと学びが同時に押し寄せてきた出来事でした。
それに続いて悩まされたのが、相性問題です。
CPUもメモリも最新のものをそろえたのに、電源を入れても画面は沈黙。
サポートに問い合わせたところ、まだ正式対応されていないβ版のBIOSを試すしかないと言われました。
怖かったんですよ、本当に。
自分の現役で使っているマシンを壊してしまうかもしれないという恐れを抱えながら作業を進めるあの緊張感。
結局なんとか立ち上がりましたが、「組み合わせれば必ず動く」という甘い考えが砕かれる瞬間でした。
それ以来、私はどんなに欲しいパーツがあっても必ず動作検証情報を探し尽くしてから決定しています。
今思えば、あの時の冷や汗と苛立ちが、自分の慎重さを育ててくれたのだと思います。
そして冷却。
これも見落としがちな落とし穴でした。
私は初めて高負荷の動画エンコードを走らせたとき、CPU温度が90度近くに跳ね上がって慌てふためきました。
レイアウトを考えずにファンをつけただけでは、熱は逃げてくれないんですよね。
結果、処理が落ちるたびに苛立ちが募り、本当に落胆しました。
熱はパーツの寿命を削り取るし、何より安心して任せられないマシンになってしまう。
以来、私は新しいパーツに心を奪われる前に、冷却の設計を最優先で考えるようになりました。
派手さよりも堅実さ。
これこそが私が40代になった今、声を大にして伝えたいことです。
もちろん、だからといって自作が楽しくないわけではありません。
むしろ逆です。
最新のGPUを入れて作業時間が大幅に短縮された瞬間の気持ちよさといったら、何物にも代え難いんですよ。
以前は40分かかっていた動画書き出しが25分で終わった時は、思わず「うわ、速すぎるだろ!」と声が出てしまい、家族に笑われました。
笑われてもかまわない。
その時間が積み重なれば、余裕が生まれて心まで軽くなる。
だからこそ私は思うのです。
パソコン作りで本当に考えるべきは「優先順位」だと。
高価なCPUやGPUばかりに投資しても、電源や冷却、そして相性に問題があれば一瞬で崩れ落ちます。
見た目だけ立派でも土台がなければ意味がない。
ビジネスでも家庭でも、それは同じことですよね。
しっかりした基盤があって初めて実力が活きるのです。
安心できる構成。
信頼できる組み合わせ。
これがなければ、自作マシンはただの不安の種になってしまう。
特に仕事で使う場合は「止まらないこと」こそ最大の性能です。
私は昔、性能競争に全力を注いでいましたが、今は実務を確実に支える堅実さを一番に求めています。
電源に余裕を持たせ、冷却設計を外さず、パーツの相性を調べ尽くす。
それだけで、自作PCは立派な相棒になります。
そして私は、その安心感にこそお金以上の価値を見出しています。
新しいパーツの情報を見るといまだに胸は高鳴ります。
正直、ワクワクしますよ。
でも衝動に任せて飛びつくのではなく、一歩引いて考えるようになりました。
ただ、自由とリスクは常に表裏一体。
組み合わせの自由を楽しめるのは、その代償に伴うトラブルと真正面から向き合った人間だけなんだと思います。
だから私は同世代の仲間や若い世代に伝えたいんです。
自作PCの本当の魅力は単なる性能競争にあるのではなく、自分の手で組み上げたものが日々の暮らしや仕事を確かに支えてくれるという安心感にあるのだと。
コスパで失敗しないために考えるべき視点
パソコンを選ぶときに私が大切にしているのは、スペックの数値ではなく、最終的に自分の仕事でどんな結果を得られるかという点です。
どれほど最新で高性能と宣伝されていても、それが実際の現場でストレスばかり生むようでは意味がありません。
つまり、後悔しない選び方とは「バランス感覚を持つこと」だと、これまで痛い思いをしてきた自分ははっきり言えます。
単純に性能の高さを追うのではなく、きちんと全体を見て調整する。
その考え方こそが最終的に自分を助けてくれるのです。
特に動画編集用のPCでは顕著で、CPUだけ突出していても、反対にGPUにだけ力を入れても、結局はどちらかがボトルネックになり期待していた性能には届きません。
私自身、数字の羅列を見て「これはすごい」と購入したことがありますが、蓋を開ければ処理がもたつき、時間ばかり奪われてしまいました。
夜遅く、納期に追われてレンダリングを眺めながら「こんなはずじゃなかった」と頭を抱える瞬間は、何とも言えない虚しさだったんです。
お金の無駄以上に、自分の時間が流れていくのを感じるあの悔しさ。
二度と味わいたくない気持ちでした。
ありがちなのが、高額なグラフィックカードを無理して買い、CPUのレベルを落としてしまうケースです。
「ハイエンドGPU」という響きに惹かれる気持ちはわかります。
でも実際に使ってみると、編集作業のプレビュー再生で映像がガクガクと止まり、書き出しの最後の数分で無意味に待たされる。
こうなると「一体何のために投資したんだ」と強い後悔に襲われます。
4K編集では力不足を感じる面がありましたが、通常のフルHD案件では大きなストレスなく進められたのです。
当時は資金に限りがあり、正直「もう少し上を選ぶべきだったか」と迷いましたが、結果的には無理をせずCPUとのバランスを優先した判断が奏功しました。
過剰にGPUに予算を割かなくて、本当に助かったと心底思った瞬間があります。
あの悩みは決して無駄ではなかったんです。
しかし動画編集を重ねていくうち、その重要性を痛感しました。
ある案件で、容量をケチって512GBで始めたところ、数本のプロジェクトでいっぱいになり、作業が止まりそうになった経験があります。
その時の焦りは今でも忘れられません。
キャッシュや素材ファイルでSSDがパンパンになるのは本当に一瞬です。
私はその後、最低でも1TB以上を前提に組むように変え、さらに外付けHDDでのバックアップを常にセットしました。
これで初めて「安心して進められる環境」が整ったのです。
電源や冷却は「見えない部分」だからと軽く見ていた時期もありました。
ファンの「ゴーッ」という音が深夜の作業を邪魔するストレスと言ったら、もう笑えません。
私がCorsair製の電源を使い始めたとき、その静かさと安定性に本当に救われました。
妙な不安やイライラから解放されたことで、集中力も格段に向上しました。
日常での安心感の積み重ねがどれだけ大きいかを思い知らされましたね。
結局のところ、CPUとGPUの釣り合いを意識し、SSDに余裕を持たせ、電源や冷却までケアするバランス型の構成が、最も長く快適に使える選択でした。
誤解のないように言うと、もちろんハイエンド構成そのものを否定してはいません。
ただし「本当にそこまで必要か」と自分の業務や生活に照らして考えなければ、高いだけでメリットが限定的になってしまうのです。
つまり自分なりの最適解を探すことが本当の賢さであり、単なる最新スペック主義とは違うと私は強く思います。
私はこれまで勢いでパーツを選んでは「やってしまったな」と後悔し、そのたびに学び直してきました。
その経験を経て確信しているのは、極端に偏らず全体の安定を軸に考えることが最も信頼できる道だということです。
机上の情報ではなく、実際に現場で日々繰り返す作業を通して身体に染みついた実感なのです。
余裕。
少し先を考えて、ほんのわずかに上の構成を選ぶことで、数年後に「やっておいてよかった」と思える安心感が手に入ります。
その変化を見越せるかどうかは、大きな分かれ道です。
最後に伝えたいのは、「納得感のある選択」が最も人を支えるということです。
逆に「これでいい」と胸を張れる構成であれば、毎日の作業は前向きに進む。
だからこそ、これから購入を考える皆さんにもぜひ伝えたい。
予算ごとに考えるクリエイターPCの構成例
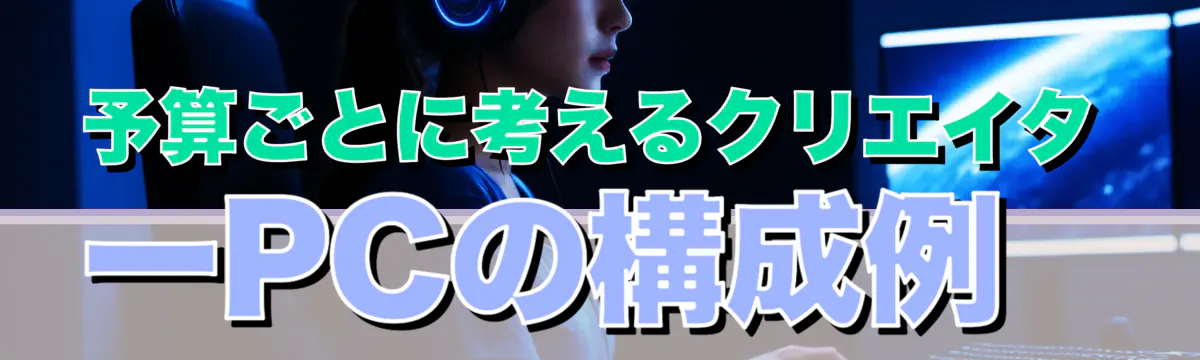
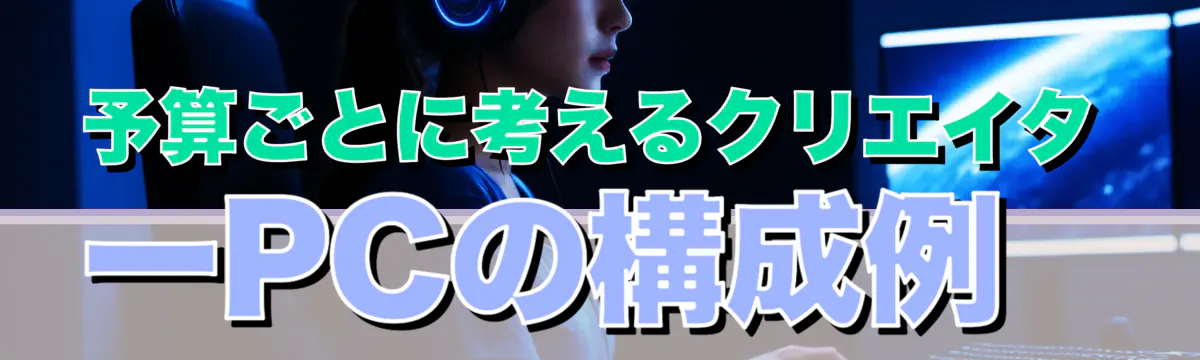
20万円クラスで組める堅実なミドルレンジ構成
20万円前後の予算でPCを組む場合、私が長く使ってきた経験から言えるのは「Core i7クラスのCPU」と「RTX4060 Tiから4070あたりのGPU」を組み合わせるのが一番安心できるということです。
派手ではないけれど、過不足ない。
その塩梅が大切です。
動画編集というのは結局、エンコードの待ち時間と編集中の操作感、この2点で快適さが決まります。
だからこそ、このクラスの構成を選んでおけば、日常的な制作作業で困る場面はそう多くはないのです。
安心感があるんですよね。
GPUは4060 Tiでも現実的には十分戦えるのですが、少し余裕を見て4070を選んでおくと心理的にも安心できます。
経験上、動画編集ではGPUに余力があることで後々助かることが何度もありました。
メモリ32GBは今や必須に近い。
4K映像をタイムラインに並べて、さらにカラー補正やエフェクトを同時に適用すると、意外なほど容量を食います。
少なくとも32GBを積んでおけば「しまった、足りない」と焦る場面はかなり減ります。
ストレージについては1TBのNVMe SSDを選んでおくと快適度が段違いです。
書き出しやキャッシュ保存で待たされる時間が減るだけでなく、作業全体が軽快になります。
私は実際にこの構成でPremiere Proを使い、数十分の長さの動画を編集したことがあるのですが、タイムライン上でカラー補正とトランジションを重ねてもほとんどカクつかず、とてもスムーズに動いてくれました。
そのとき、旧マシンでは30分以上かかっていた書き出しが20分ちょっとで済んだときの嬉しさといったらない。
イライラが消えるんです。
ただ、当然のことながら「万能」というわけではありません。
AIエフェクトを多用するような高負荷の作業や、After Effectsで複雑な映像を組み立てていくと、もっと上のクラスのGPUが欲しくなります。
やはりトップクラスの作品作りを志すなら、限界を感じる瞬間は来るものです。
でも逆に言えば、この20万円クラスのPCは現実的に必要十分。
毎日しっかり動いてくれる信頼できるマシン、そういう位置づけです。
そこが大事なんです。
忘れてはいけないのがケースや電源です。
正直、この予算帯だとついCPUやGPUにばかり目が行ってしまい、ケースや電源が後回しになりがち。
でも、この部分を軽く見ると後悔することになります。
冷却が甘いケースだと夏場はGPUが熱を持ち、途端にパフォーマンスが落ちます。
ファン音が大きいケースなら夜間作業の集中力は一気に削がれる。
私は声を大にして言いたい。
見た目の派手さなんかより、冷却と静音こそが本当の選択基準だと。
外観はどうにでも工夫できますが、作業中の環境は冷却と静音性に守られるものだからです。
私が以前BTOショップで試した同価格帯のモデルでは、ストレージに古いGen3のSSDが使われていて正直驚きました。
CPUとGPUが優秀でも、SSDが遅いと全体のパフォーマンスは確実に鈍化します。
実際、書き出しのスピードで足を引っ張られる場面が何度もありました。
これには本当にがっかりしましたね。
今の時代、せめてGen4のSSDを標準にしてほしいと強く思います。
せっかくスペックを整えても宝の持ち腐れになるのはもったいなさすぎます。
では、私なりのベストバランスを書きます。
Core i7とRTX4060 Ti、余裕を見て4070でも良い。
メモリは32GB、SSDは1TBのNVMe Gen4。
この組み合わせこそが、20万円という予算の中で最大限の納得感を得られる構成です。
このPCなら4K編集にも気後れせず素材をガンガンと突っ込める。
長時間作業にも耐え、仕事用としても十分に信頼できる。
これ以上の安心はなかなかありませんよ。
パソコン選びは結局、限られた予算の中でどこに投資するか、その優先順位を決める作業です。
最高を求めれば確かに上には上があります。
しかし私の経験では、20万円クラスのマシンこそ「ちょうどいい相棒」なんです。
派手さはないけど地に足のついた信頼性がある。
真面目で飾らないが長く一緒にいられる存在。
そういうものにこそ惹かれるのです。
使いやすさがある。
安定して働く力がある。
この2点を備えたPCを選んだとき、動画編集の現場は本当に快適になります。
ゲーミングPC おすすめモデル4選
パソコンショップSEVEN ZEFT R65E


| 【ZEFT R65E スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 7800X3D 8コア/16スレッド 5.00GHz(ブースト)/4.20GHz(ベース) |
| グラフィックボード | Radeon RX 9070XT (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 360 Core II Black |
| マザーボード | AMD X870 チップセット ASRock製 X870 Steel Legend WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60SN


| 【ZEFT R60SN スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II White |
| マザーボード | AMD B850 チップセット MSI製 PRO B850M-A WIFI |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60RH


| 【ZEFT R60RH スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S100 TG |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R63H


| 【ZEFT R63H スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 9950X 16コア/32スレッド 5.70GHz(ブースト)/4.30GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ホワイト |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II White |
| マザーボード | AMD B850 チップセット MSI製 PRO B850M-A WIFI |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R61K


| 【ZEFT R61K スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 7950X3D 16コア/32スレッド 5.70GHz(ブースト)/4.20GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7300Gbps/6300Gbps WD製) |
| ケース | Fractal Design Pop XL Air RGB TG |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B650 チップセット ASUS製 TUF GAMING B650-PLUS WIFI |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
30万円台で作業の安定性を重視した構成
なぜなら、動画編集や長時間のエンコード中に一番厄介なのはフリーズやクラッシュで、作業が止まると集中力は一気に崩れ、締め切り前の不具合は精神的にも大きなダメージになるからです。
過去に嫌というほど痛い経験をしたからこそ、私は安定性を最優先にするようになりました。
私の仕事では動画編集が日常的にあり、CPUにRyzen 9クラスを採用し、メモリを64GB積んだ構成に変えてから作業環境は大きく変わりました。
それまではカラーグレーディングをかけた瞬間にPCのファンが轟音を立て、まるで部屋の隅に掃除機が常駐しているような状態でした。
夜中に集中したくても妻や子どもに「うるさい」と言われて肩身が狭かったのですが、今はそのストレスがほとんどなくなったのです。
静かな夜に黙々と作業でき、周囲の空気を乱さないことが、日々の気持ちの安定にもつながっています。
GPUにはRTX 4070 Tiを選びました。
実際に使ってみると、CUDAの恩恵ははっきり体感できます。
4Kのマルチトラック編集でもタイムラインがカクつかず、再生が止まらない。
この差は本当に大きいと感じました。
以前は数秒進んでは止まり、そのたびに小さく舌打ちするような編集環境で、積み重なる苛立ちが地味にきつかったのです。
「助かった…」と声に出た瞬間を未だに覚えているくらいです。
同僚に試してもらった際も「これはストレスが減る」と驚いていました。
やはりGPUの存在感は無視できません。
ストレージ周りも侮れません。
最初は「1TBで足りるはず」と思ったのですが、数本プロジェクトを並行して進めるとあっという間に容量がパンクしました。
素材はすぐに膨らみますし、読み込み時にわずかな待ち時間が積もると、集中が切れて効率が落ちるんです。
限られた時間の中で作業する40代にとって、この数秒のロスが侮れない。
だから私はSSDへの投資を後回しにしないことを決めました。
これは本当に痛い経験が教えてくれたことです。
Adobe系のソフトでは特に違いが歴然で、レンダリングに入る前のリアルタイム編集が格段に滑らかになるのです。
以前はGPUさえあれば大丈夫だと思い込んでいましたが、それは大きな誤解でした。
編集を本気で仕事にするのであれば、CPUやGPUに加えてメモリ強化を重視することを心からおすすめします。
安心して仕事などできません。
私は1000Wのプラチナ認証モデルを採用しましたが、これには理由があります。
以前、安価な電源を使っていたときに、作業中に突然画面が真っ暗になり、肝心なデータが危うく消えかけた経験があります。
背筋が凍るような瞬間でした。
「なぜここで?!」と叫んだのを今もはっきり覚えています。
安定した電源がなければ、どれほど強力なパーツでも安心して稼働させることはできません。
冷却もまた軽視できません。
私は昔、エアフローの悪いケースに無理してハイエンドパーツを押し込み、真夏に作業中の強制終了が頻発しました。
締め切り間際に何度も作業が止まり、家族との週末の予定まで吹き飛んでしまったことを思い出すと、今でも後悔が残ります。
その後、冷却重視のミドルタワーケースに変えてからは、夏場の不安が一気になくなりました。
静音性の高いファンを組み合わせた結果、作業環境の安心感はまったく違うものになったのです。
家族に迷惑をかけずに済むということも、大きな価値でした。
最終的に私が信頼している30万円台の構成は、Ryzen 9クラスのCPU、RTX 4070 Ti、メモリ64GB、NVMe Gen4の1TB以上、1000Wのプラチナ電源、そして冷却性に優れたケースです。
何よりも「安定性への不安がなくなった」という安心感でした。
その結果、自分の集中力を最大限に本業へ注ぐことができるようになり、時間の余裕すら生まれました。
これが私にとって最大の収穫です。
私は40代になってから、効率性だけでなく「確実さ」の価値が前より大きくなったと感じます。
若い頃のように徹夜で無理を押し通すことはもうできません。
だからこそ、機材の信頼性が自分を支え、家庭と仕事の両立を可能にしてくれる。
多少の出費はあっても、不安を減らし日々の生活に余裕を持てるなら、その投資は決して無駄にならないと思います。
安心感がある。
信頼できる。
その二つの軸が揃ったときにこそ、真に頼れる動画編集環境だと私は実感しています。
私が得た経験は、小さな失敗や後悔の積み重ねの上でたどり着いた答えですが、これから同じようにPCを組もうとする方にとって、少しでも参考になれば嬉しいと思います。
そして私自身も、今後も安定を主軸にした選択を重ねていくつもりです。
40万円超で狙うプロ向けのハイエンド構成
周囲の人から「そこまでの金額をかけなくてもいいんじゃないか」と言われることもありますが、私にとって40万円を超えるハイエンド環境は単なる贅沢品ではなく、仕事の成果そのものに直結する投資だと感じています。
映像編集という仕事は、人から見れば派手で華やかに思えるかもしれませんが、実際は待ち時間やトラブルとの戦いの連続です。
ほんの数秒の処理停止やプレビュー落ちが、クライアントの信頼を損ねることにつながる。
その現実を知ってしまうと、妥協は怖くてできません。
ストレスで胃が痛くなることだってありましたから。
私が組んだ構成は、24コア以上のCPUとRTX 4090クラスのGPUを軸にしたものです。
自分でも「ここまでやるのか?」と思いましたが、実際に動かしてみて納得しました。
4K ProResを複数同時に扱っても止まらない。
これまでの環境ではぐっと待たされていた処理も、嘘みたいにスムーズです。
そのとき、「ああ、これが本当の作業速度なんだ」としみじみ感じました。
大げさに聞こえるかもしれませんが、こういう体験が仕事のモチベーションまで支えるんです。
電源も冷却も妥協できないので、私はオールインワン液冷を入れました。
夜中に作業をしていても静かで、リビングで休んでいる家族に音で気を遣わなくていい。
ほんの些細なことなんですが、毎日の積み重ねを考えると非常に大切です。
結果として、この静けさが私にかなりの安心感をもたらしてくれました。
実際に導入したのは昨年の秋のことでした。
あのとき進めていた案件は90分超のドキュメンタリー。
以前の環境では、一度のプレビューをするだけで落ちることが多く、心臓に悪い日々が続きました。
「間に合わないかもしれない」と不安で夜も眠れなかったほどです。
それが新しいマシンに変えた瞬間、一度も落ちずに最後まで進んだ。
本当に胸がすく思いでした。
エクスポートの速度も大幅に短縮され、徹夜明けに画面を眺めながら「よし、まだ走れる」とひとり呟いたことを今でもはっきり覚えています。
ストレージに関しても同じ考え方です。
私はOSとアプリ用にGen4 NVMeのSSDを使い、作業用データには4TBのNVMe、さらにNASでのバックアップも併用しています。
三重の構成にしたのは、過去に痛い経験をしたからです。
大切な案件のデータが突然消えた時、あの冷や汗と絶望感は二度と味わいたくない。
だから保険の意味も込めて投資をしました。
ただし、やはり気になるのは消費電力です。
特に夏場のエアコンと重なる時期などは「ちょっと厳しいな」と感じる瞬間もあります。
ただ、後悔はしていません。
むしろ「あの効率をお金で買えるなら安い」とさえ思っている。
編集作業が安定していて焦ることがなくなった今、その安心は数字以上の意味を持っています。
少し未来の話をすれば、GPUのエンコード技術はさらに進化するでしょうし、AIによる編集支援も当たり前になっていくはずです。
けれど、現時点で確実に言えるのは、何よりも止まらない環境が必要だということ。
どれほど便利な新機能や効率化が生まれても、現場で動かなくては意味がありません。
納期に追われる状況で一番怖いのは、不意に止まること。
だからこそ、40万円の投資は決してためらう必要のないものだと私は考えています。
時間の価値はお金を超えます。
もし高価でも、そこに確実なリターンがあるなら導入すべきであり、むしろ導入しないこと自体がリスクになります。
「無駄に待たされない」「納品前に慌てない」「自分の力を出し切れる」。
この三つが揃うだけで投資した価値は十分に回収できるんです。
これは結局、仕事に向き合う姿勢の問題でもあります。
依頼してくれた人に対して、期待以上の結果を出したい。
そのための道具を惜しむのは矛盾です。
根性や気持ちだけでは補えない部分があることを、私は痛いほど理解しています。
だからこそ迷わない。
改めてまとめると、ハイエンド環境への投資は自己満足ではなく、プロとしての必然です。
成果物のクオリティも、納期への信頼も、その上で得られる安心も。
すべてが一つの答えに向かっています。
私が思う一番の価値は「迷いなく作品に向き合える環境を持てること」です。
そこに尽きる。
本気の選択。
購入前に押さえておきたいクリエイターPCに関する素朴な疑問
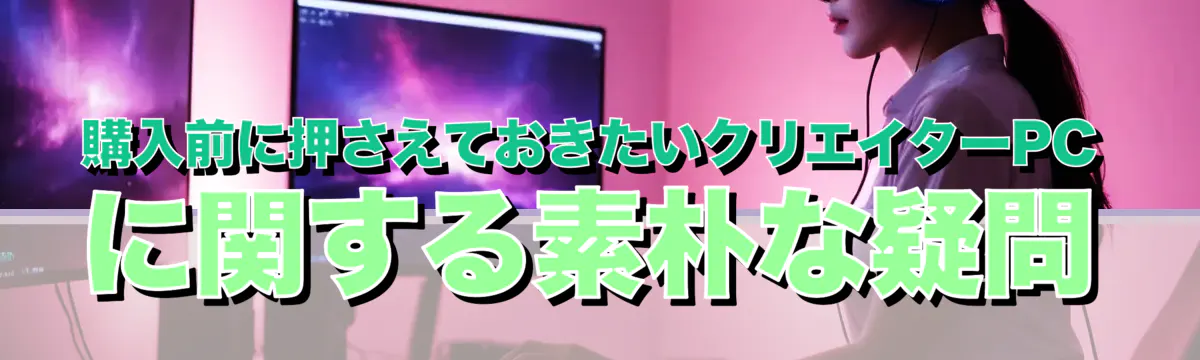
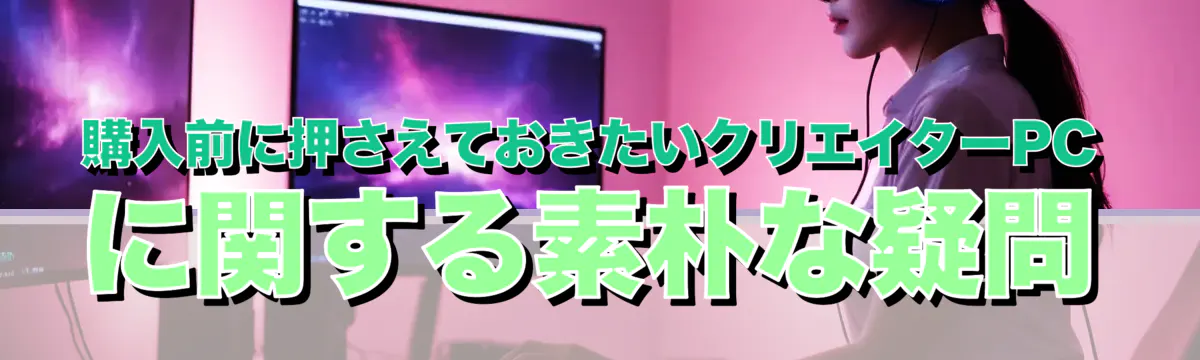
グラフィックボード無しの環境でも編集はどこまで快適にできるか
グラフィックボードがなくても動画編集はある程度こなせる、そう感じたのは実際に自分で試したからです。
最初は「これで本当に大丈夫か」と心配でしたが、フルHDくらいまでの動画なら意外となんとかなってしまう。
CPUに内蔵されたGPUであっても、カット編集や簡単な色の補正程度なら止まることなく進められました。
SNS用に短い動画を作るくらいであれば、わざわざ専用のGPUを用意しなくても困らなかったのです。
ただし、やはり用途が広がるにつれて違いはハッキリと出てきます。
その現実と正面から向き合うことになりました。
数分程度の映像編集なら耐えられますが、10分を超えたあたりからプレビューがガタつく。
エフェクトを少し加えた途端に映像が止まってしまう。
書き出しに実時間の3倍以上かかり、並行して別作業を進める余裕もゼロ。
まるで足枷をはめられた気分になりました。
私はそのとき、迷いながらも専用GPUを導入するしかないと決断しました。
さらに印象的だったのはマルチタスクのしんどさです。
リモート会議をしながら編集を進めたい場面は仕事柄よくあるのですが、内蔵GPUだけの環境では会議の音声が途切れ、画面が止まる現象が現実に頻発しました。
最初は「まさかここまでとは」と驚きましたね。
ところがRTXシリーズを積んだPCに変えてからは、その不自由さが嘘のように消えたのです。
同じ条件で会議と編集を同時進行しても映像は滑らか。
その快適さに「これは別世界だ」と感じました。
GPUの性能が作業全体を大きく左右するのは、生成AIを試したことがある方ならきっと理解できるはずです。
ChatGPTなどをGPU搭載の環境で処理する際の速さと、そうでない環境との差は歴然。
その経験を持つ私には、創作活動でも同じ理屈が働くことがよくわかります。
つまり、GPUをどう扱うかが、仕事の効率とストレスの差を決めるのです。
実際、GPUがなければ発熱も小さく、稼働中の音も静か。
電気代も抑えられるため、家庭用として使う分にはむしろ合理的とすら言えます。
たとえば夜遅くに部屋で作業してもファンの音が響きにくいので、落ち着いた雰囲気のまま仕事を続けられます。
そこには思わぬ快適さがありました。
静けさの価値を改めて知った瞬間でした。
ただ、映像を扱う仕事をしている身からすると、それだけで割り切れるものではありません。
そのたった一度の案件が自分の環境を限界に追い込み、結局スケジュール全体を狂わせる事態につながる。
そう考えるとやはり余裕を見越して設備を整えたほうが安心だと悟りました。
その安心感は小さな投資以上の価値があります。
一時期は「GPUの導入なんて過剰じゃないのか」とも思いました。
実際、動画クリエイターやゲーム開発者のような専門職に必要な装備だと考えていたのです。
GPUによって救われるのは処理速度だけでなく、日々積み重なるストレスや、生活全体のリズムまでもが守られるという事実でした。
思い通りに動かないプレビューや止まる書き出しに時間を奪われるたび、心の余裕まで削られていたのです。
それは作業環境の「保険」だと表現してもいいでしょう。
とはいえ、個人の利用用途次第で最適な環境は変わってきます。
たとえば私自身も、趣味で旅先の映像を撮り、後日まとめてSNSにアップする程度ならGPUのないノートPCをよく使っています。
そこではむしろ静かで落ち着いた時間が得られるので、不快どころか心地よさを感じているのです。
やはり環境は使い方に応じて選ぶべきものだと知りました。
簡単に言えば、フルHDくらいの短い映像を主体に編集している方にとってはグラボがなくても充分仕事になります。
その差は単なる性能差ではなく、日々のストレスをどう和らげるかという生活レベルにまで直結しています。
数字では測れない違いがそこには確かに存在します。
私が実際に仕事や生活で感じた答えはとてもシンプルです。
フルHDを中心に取り組むのであれば、GPUなしでも現状維持で困らない。
一方で、4Kや3Dを扱うならGPUは必須。
必要か不要かで迷うより、自分の用途を見極めることが大事なのです。
これは理屈や情報からではなく、実際に身をもって得た実感です。
心の底から納得した結論だからこそ、私は胸を張ってそう断言できます。
SSDは1TBで足りるのか、それとも最初から2TBを積んだ方が良いか
動画編集を本格的に続けていくなら、私は最初から2TBのSSDを選ぶべきだと思っています。
作業をしているのに、気持ちはずっと残り容量のメーターとにらめっこです。
これは私自身が経験したことだからこそ言える実感です。
最初に私が組んだ編集用のPCでは、予算を抑えたくて1TBのSSDを搭載しました。
4K動画を数本扱っただけで一気に容量は埋まり、キャッシュやプレビューの一時データでさらに圧迫されます。
その状態で残り容量を監視しながら作業を進めるのは本当に神経を削られるものでした。
心のどこかで「これ以上は落とせない」という焦りを常に抱えたまま進める仕事は苦しいものでした。
容量不足になると、どうしても外付けHDDへの移動を繰り返す羽目になります。
時にはNASに頼ったこともありましたが、コピーや移動の待ち時間にイライラが募るばかりで、生産性はがくんと落ちました。
効率の悪さに気づきつつ、どうにもならない状況に苛立ちが募り、自己嫌悪にまでつながったことをよく覚えています。
複数の案件を並行して扱っても容量が余りやすく、残りを確認する頻度もぐっと減りました。
そのことが心の余裕へとつながります。
余裕があるからこそ、急な修正依頼にも冷静に対応できますし、「安心して任せられる」とクライアントに思ってもらえる信頼にもつながる。
私はSamsungやWestern Digitalといった定番のSSDをよく利用してきました。
これらは速度や安定性も十分で、一定の業務をこなすには不満をほとんど感じませんでした。
特にNVMe Gen4の2TBを導入したときは、「ようやくストレージの不安から解放された」と肩の荷が下りた気持ちになりました。
予想していたよりもずっと快適で、ストレスの少なさに驚きさえしました。
やはり実際に投資してみないと分からない変化がありますね。
ただ、ここ数年で事情はまた変わってきています。
生成AIで作られた動画ファイルや高解像度・高ビットレートのRAWデータは、従来の素材以上に容量を圧迫していきます。
正直、笑えないペースでストレージが消えていくのです。
だから2TBですら「心許ない」と思う瞬間がありました。
もし今ゼロから編集環境を作るなら、私は迷わず4TBを選択肢に入れるでしょう。
なぜなら容量不足は単に作業効率が下がるだけにとどまりません。
納期の遅延につながり、さらにその案件全体の信用問題に直結するリスクがあるのです。
これは編集者にとっては事故と同じレベルの損失だと私は思っています。
よく考えてみると、容量をケチって削られるのはコストではなく自分の集中力や成果物の完成度なのです。
ストレージが余って困ることなどまずありませんが、足りなくて困る場面は頻発します。
「あと少し大きい容量にしておけば良かった」と思った瞬間、もうやり直しが利かない。
これが現実です。
ですから私は声を大にして伝えたいのです。
もちろん、2TBという容量は現在では標準的になりつつあります。
それでも「自分にはそこまでいらない」と考える人は少なくないでしょう。
しかし、実際に仕事として編集をするとなれば、数々の予想外に直面します。
大規模な素材を扱う案件が増えれば、保存と削除の選択を迷うたびに時間を取られ、判断も鈍っていくものです。
その積み重ねがミスを呼び込むことすらあります。
そうならないために、あらかじめ余裕を積んでおくことが何より重要になるのです。
ここを軽んじるのは危険です。
安心できる余裕。
SSDを2TBへ切り替えたことは、効率を改善しただけではなく、心にゆとりをもたらす投資でもありました。
作業の余裕は精神的な余裕、そのまま成果の質に跳ね返ってくるのです。
だから今、これからPCを組む人に対して迷わず伝えることがあります。
最初から2TBを選んでください。
これ以上ない選択です。
ゲーミングPC おすすめモデル5選
パソコンショップSEVEN ZEFT R60GV


| 【ZEFT R60GV スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 9950X 16コア/32スレッド 5.70GHz(ブースト)/4.30GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | NZXT H9 FLOW RGB ホワイト |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II White |
| マザーボード | AMD X870 チップセット GIGABYTE製 X870M AORUS ELITE WIFI7 ICE |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55GD


| 【ZEFT Z55GD スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra5 245KF 14コア/14スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.20GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ブラック |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R61BK


| 【ZEFT R61BK スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 9950X3D 16コア/32スレッド 5.70GHz(ブースト)/4.30GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | AMD B850 チップセット MSI製 PRO B850M-A WIFI |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R44CG


高速な実行力で極限のゲーム体験を支えるゲーミングモデル
直感的プレイが可能、16GBメモリと1TB SSDでゲームも作業もスムーズに
コンパクトなキューブケースで場所を取らず、スタイリッシュなホワイトが魅力
Ryzen 9 7900X搭載で、臨場感あふれるゲームプレイを実現
| 【ZEFT R44CG スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 7900X 12コア/24スレッド 5.60GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (8GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B650 チップセット MSI製 PRO B650M-A WIFI |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
CPUクーラーは空冷と水冷、実際に使いやすいのはどちらか
CPUクーラーを選ぶうえで、私は最終的に空冷を選ぶのが一番安心だと考えています。
静かに、そして粘り強く動き続けてくれるその安定感は、日々の業務に追われている自分にとっては何よりありがたい存在です。
実際、私がこれまで何台もPCを組んできた中で、余計な心配を減らしてくれたのは常に空冷でした。
水冷に心を動かされたことももちろんあります。
以前、240mmのラジエーター付きの水冷を導入したとき、最初は驚くほど性能が伸びました。
ベンチマークを回した瞬間にCPU温度が下がり、思わず声が出たくらいです。
正直、すごいと思いました。
しかし数か月使い続けて感じたのは、わずかなポンプ音が耳に残り続ける現実でした。
夜中に作業していると、そのかすかなノイズが、じわじわと気持ちを削っていくんです。
小さなストレスの積み重ね、それが一番怖い。
一方で、空冷の構造はシンプルそのもの。
大きなヒートシンクとファン、それ以上でもそれ以下でもない。
もしファンがダメになったとしても、すぐに取り替えてまた動かせる。
この即応性は、時間勝負のビジネス現場では本当にありがたいものです。
修理のために本業を止めていられない。
だからこそ、余分な故障リスクのない空冷に魅力を感じるのです。
水漏れなんて一度でも想像すると、とても安心して任せられない。
そう思ってしまいます。
ただし、見た目や演出を求める方にとっては水冷に大きな価値があるのも事実です。
先日、展示会でARGB搭載の最新モデルを見たときは、素直に「格好いい」と感じました。
ケース内が鮮やかに光り、まるで舞台の照明を見ているような迫力です。
自分のPCをただの道具ではなく作品として楽しみたい人には、これは強く響くでしょう。
そこに気持ちが高まる、という感覚は私にも理解できます。
性能と安定感。
あるいはデザインと気分の高揚。
そのどちらを重視するのかで選び方は大きく変わります。
私は日常的に動画編集やエンコードを長時間回すため、結局のところは空冷一択です。
安定して作業が継続できることの方が、派手さよりもはるかに価値があるからです。
ただ、例えばゲーマーや配信者で「パフォーマンスと同時に見映えも大事」という人なら、水冷が候補に入るのは自然なことだと思います。
それぞれの立場が違うからこそ、片方が絶対的に優れているとは言い切れません。
私が空冷を特に信頼するようになったのは、過去の痛い経験があるからです。
あるとき納期直前の深夜、エンコードの途中でPCが突然落ちました。
画面が暗転する瞬間の冷や汗、今もはっきり覚えています。
その後で分かったのは、冷却系統のトラブルでした。
もしそれが空冷だったら、ファンを差し替えるだけで済んだはずです。
そんな経験が積み重なって、私は結局「壊れてもすぐ直せるシンプルさ」に心を寄せざるを得なくなったんです。
怖い夜を乗り越えるための安心感というやつです。
もっとも、すべての場面で空冷が絶対正解というわけではありません。
発熱の大きなハイエンドCPUを組み込んだうえで静音性まで求めるなら、水冷の方が現実的になる場合も確かにあります。
そのうえで光るパーツやカスタマイズ性に喜びを感じる人なら、迷いなく水冷を選ぶのでしょう。
スタイルの問題です。
ただ、私個人は効率と確実性を優先しなければならない。
そういう立場だからこそ、はっきり言います。
「私の答えは空冷です」。
むしろ自分の予算や使い方に合わせて選ぶことが一番大事だと思っています。
まとめると、長時間の安定動作を最優先するなら空冷。
PCを魅せたい、所有する楽しさを最大化したいなら水冷。
その両者の特徴を理解したうえで、自分がどこを大事にしたいのか考えることが必要です。
私はこれからも空冷を使い続けると思いますが、水冷を選んだ人が自分のPCを大切に楽しんでいる姿を見ると、羨ましい気持ちになることもあります。
要するに、価値観の問題なんですよ。
私が最も伝えたいのは、CPUクーラーという一見ただの部品に思える選択が、実はその人の働き方や生き方を象徴しているという点です。
その積み重ねが自分自身のスタイルを作っていくのだと思います。
安心感。
結局のところ、自分の価値観に正直に選べばよいのです。
私は空冷で走り続けますが、水冷で自分の世界を広げている仲間を見て、「それもいいな」と思わず口にしてしまう、そんな柔らかさも持ち続けたいのです。
将来的にパーツ交換を見据えるなら選んでおきたいケース
将来的に自分の暮らしや仕事に欠かせないパソコンを長く安心して使っていくためには、拡張性に余裕を持ったケースを選ぶことが本当に大切だと私は確信しています。
GPUやストレージを増設しようとしたとき、「あのとき少し大きめにしておけば…」という悔しさが胸に込み上げるのです。
その苦い経験を私は何度か繰り返してきました。
だからこそ後進には最初から余裕のある選択をしてほしいと願っています。
最近のGPUはとにかく大きい。
数年前なら2スロットで収まったものが、今では3スロットは当たり前。
新しいGPUを手に入れてワクワクしながら開封した瞬間、「これは無理だ、前のケースじゃ絶対入らない」とため息をついたことが何度もあります。
せっかく高いお金を払ったのに、ケースに収まらずに焦り、結局計画を変える羽目になる。
そのときのがっかり感といったら、本当に力が抜けるようなものです。
だから私は、ケースに余裕を持たせることは贅沢ではなく不可欠な条件だと痛感しました。
無駄をなくしたいなら、そこを軽視してはいけないのです。
さらに重要なのが冷却性能です。
静音性ばかりを優先して排熱設計を軽視したケースを選んだことが私にはあります。
最初は静かで快適だと喜んでいたのですが、動画編集を始めた途端にCPUの温度が一気に上がり、処理性能が頭打ちになってしまう。
その瞬間、パソコンに注ぎ込んだ金額を思い返して頭を抱えました。
音が少し大きくても安定する方がよほど安心なんです。
私は40代に入り、仕事でミスを減らしたい、余計な不安を抱えたくないという気持ちが以前より強くなりました。
安定こそ力です。
ケーブルの配線も意外に侮れません。
ケース内部の裏配線スペースが狭いと、硬いケーブルを指で押し込んで擦り傷を作ったり、パネルを力任せで閉じる羽目になります。
すると「もう開けたくない」という気持ちが先に立ち、清掃やメンテナンスを放置してしまう。
これは実際に私が味わったストレスです。
逆に余裕のある設計ならケーブルが驚くほど整理しやすく、掃除も増設も楽しくなる。
日々の小さな快適さが積み重なることで、大切な時間を余計な作業で奪われずに済む。
その経験をした今だからこそ、私は声を大にして配線のしやすさを強調したいのです。
ストレージに関しても同じです。
動画編集や写真データを扱う私のような立場だと、作業用の高速SSD、保存用の容量重視HDD、キャッシュ専用SSDと、性格の異なるストレージを次々に追加したくなります。
そのときのやるせなさは今でも覚えています。
つまりケース選びひとつで、日々の生産性と満足感が根本から変わるのです。
実は先日、海外メーカー製のケースを試す機会がありました。
吸気フィルターがワンタッチで外せる仕組みだったのです。
正直、そこまで期待していなかったのですが、実際に掃除してみて心底驚きました。
「フィルターを簡単に外せるだけでこんなに気分が違うのか」と。
掃除へのハードルが下がれば自然にこまめにやるようになるし、システムの安定性にもつながる。
こういう細かいユーザー目線の工夫こそ、多忙な社会人にとって大きな助けになるのです。
要するに、私が本当におすすめしたいのは、余裕を持った拡張性があり、冷却性能がしっかりしていて、メンテナンス性も高いケースです。
フルタワーである必要はありませんが、少なくともミドルタワー以上で空間的に余裕があるものを選ぶのが最適解です。
デザインや省スペースを理由に小さなケースへ飛びつくと、後で確実に後悔します。
その結末を私は嫌というほど味わいました。
広い空間と余裕。
安心できる排熱設計。
この二つを叶えるケースを選ぶだけで、数年後の自分の笑顔を守れます。
私は40代半ばになり、ようやく「無駄な我慢はもうやめにしよう」と思えるようになりました。
仕事も家庭も、時間も体力も有限だからこそ、パソコンに悩まされるような小さな後悔は避けたい。
だからこそ最初に少し大きめで、整備が行き届いたケースを選ぶだけで精神的にとても楽になるのです。
投資したお金が自分の成果に直結する。
その安定感は若い頃には見えなかった、経験を積んだからこそ分かる価値なのだと思います。
私は今ではケースをただの箱だとは思っていません。
だから迷ったら余裕のあるケースを選ぶべきです。
私の実体験から、その選択こそが最も後悔を減らせる道だと、心から伝えたいのです。
クリエイターPCとゲーミングPC、使ってみて感じた違い
正直に話すと、動画編集を本格的にやるなら、最初からクリエイター向けPCを選ぶべきだと断言できます。
世の中では「ゲーミングPCでも十分じゃないか」とよく言われていますが、実際に仕事として長時間使えば、その差は嫌というほど自分の身に返ってくるんです。
表面的には似ていても、中身はまるで違う。
私はその違いに何度も痛い思いをしてきました。
最初に突き当たったのが安定性の壁でした。
ゲーミングPCは確かに高性能なGPUを積んでいるので、プレビュー再生は軽快で書き出しも速い。
ただ、それだけなんです。
長時間の編集作業になると突然アプリが落ちたり、メモリ不足のエラーが出て強制終了したりする。
そのたびに「せっかく集中して編集していたのに」と頭を抱える羽目になる。
たった一度の強制終了でも、その瞬間に削られるのは作業時間だけじゃなく、心の方なんです。
地味にきつい。
結局、動画編集に本当に必要なのはGPUパワーだけではなく、複数のソフトを立ち上げても安定して動き続ける全体のバランスだということに気付かされました。
特にCPUの処理能力とメモリ容量の重要さは、嫌でも痛感しましたね。
そこから思い切って64GBメモリとマルチコアCPUを搭載したクリエイターPCに切り替えました。
高額でしたが、振り返れば本当に正解の決断でした。
一日編集してもエラー一つ出ない。
作業が止まらない。
ただそれだけで、どれだけのストレスが減ったことか。
心からの安堵でした。
もちろん、ゲーミングPCにも魅力はあります。
流通量が多く価格も手頃で、最初に触れるマシンとしては選びやすい。
私自身、最初に買ったのもゲーミング仕様でした。
趣味でちょっと動画を触るくらいなら、その選択は全然悪くないと思います。
映像制作の現場では、一度のトラブルが案件全体に響くことだってある。
いや、本当に響くから怖い。
そこでようやく「やっぱり道具はちゃんと選ばないと」と痛いほど思い知りました。
一番鮮烈に差を感じたのはマルチカメラ編集です。
複数の映像素材を並べて、さらにカラーグレーディングまで同時に行うと、処理が重くて仕方ない。
ゲーミングPCでは映像がカクつき、編集どころか確認すらまともにできないこともありました。
そんな状態ではアイデアも熱量も全部冷めてしまうんですよね。
一度止まった流れは簡単に戻せない。
その点、クリエイターPCは安定してリズムを維持できる。
本気で編集を長く続けるなら、この違いは致命的なくらい大きいんです。
最近は私も仕事の都合でマウスコンピューターのDAIVシリーズを触る機会が増えましたが、正直言って「よく考えて作られているな」と感心しました。
部品構成や冷却設計が徹底的に詰められていて、何時間連続で稼働させても不安を覚えない。
その安心感は、ただの数字やスペックの高さだけでは得られないものです。
長年のノウハウがぎっしり詰まっている。
では、全員がクリエイターPCを買うべきか。
ここは用途で分かれると思います。
趣味として不定期に動画を触るなら、ゲーミングPCでも十分楽しめるはずです。
でも仕事として日常的に使う人間にとっては、間違いなくクリエイターPCが唯一の選択肢になります。
だからこそ自分の立ち位置をはっきりさせることが欠かせないんですよね。
「趣味か仕事か」。
たったそれだけの差で必要な環境は大きく変わる。
私もそこできっちり踏み切るまで時間がかかりました。
正直、遠回りしましたが本心を明かすなら「最初からクリエイターPCを選ぶ方が結局は得」です。
余計なトラブルに振り回されるより、最初から落ち着いて作業に集中できる環境がある方が圧倒的に効率的。
価格は確かに高いですが、精神的な安定や失われない時間を考えれば、十分にペイできます。
私は当時、もっと早く切り替えればよかったと何度も後悔しました。
でも現実はそうじゃない。
パソコンはスペック表の数字以上に、日々の現場でどう動くかがすべてです。
数字では測れない信頼性。
これこそが心底大切でした。
今の私はクリエイターPCに完全に移行して、あの頃の苛立ちから解放されています。
もう途中で作業を諦める必要もないし、編集に没頭できる。
その心地よさを味わったからこそ言い切れます。
動画編集を本気でやるなら、選ぶべきはクリエイターPCです。
人気PCゲームタイトル一覧
| ゲームタイトル | 発売日 | 推奨スペック | 公式 URL |
Steam URL |
|---|---|---|---|---|
| Street Fighter 6 / ストリートファイター6 | 2023/06/02 | プロセッサー: Core i7 8700 / Ryzen 5 3600
グラフィック: RTX2070 / Radeon RX 5700XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Monster Hunter Wilds
/ モンスターハンターワイルズ |
2025/02/28 | プロセッサー:Core i5-11600K / Ryzen 5 3600X
グラフィック: GeForce RTX 2070/ RTX 4060 / Radeon RX 6700XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Apex Legends
/ エーペックスレジェンズ |
2020/11/05 | プロセッサー: Ryzen 5 / Core i5
グラフィック: Radeon R9 290/ GeForce GTX 970 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| ロマンシング サガ2
リベンジオブザセブン |
2024/10/25 | プロセッサー: Core i5-6400 / Ryzen 5 1400
グラフィック:GeForce GTX 1060 / Radeon RX 570 メモリ: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| 黒神話:悟空 | 2024/08/20 | プロセッサー: Core i7-9700 / Ryzen 5 5500
グラフィック: GeForce RTX 2060 / Radeon RX 5700 XT / Arc A750 |
公式 | steam |
| メタファー:リファンタジオ | 2024/10/11 | プロセッサー: Core i5-7600 / Ryzen 5 2600
グラフィック:GeForce GTX 970 / Radeon RX 480 / Arc A380 メモリ: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| Call of Duty: Black Ops 6 | 2024/10/25 | プロセッサー:Core i7-6700K / Ryzen 5 1600X
グラフィック: GeForce RTX 3060 / GTX 1080Ti / Radeon RX 6600XT メモリー: 12 GB RAM |
公式 | steam |
| ドラゴンボール Sparking! ZERO | 2024/10/11 | プロセッサー: Core i7-9700K / Ryzen 5 3600
グラフィック:GeForce RTX 2060 / Radeon RX Vega 64 メモリ: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE | 2024/06/21 | プロセッサー: Core i7-8700K / Ryzen 5 3600X
グラフィック: GeForce GTX 1070 / RADEON RX VEGA 56 メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ファイナルファンタジーXIV
黄金のレガシー |
2024/07/02 | プロセッサー: Core i7-9700
グラフィック: GeForce RTX 2060 / Radeon RX 5600 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Cities: Skylines II | 2023/10/25 | プロセッサー:Core i5-12600K / Ryzen 7 5800X
グラフィック: GeForce RTX 3080 | RadeonRX 6800 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ドラゴンズドグマ 2 | 2024/03/21 | プロセッサー: Core i7-10700 / Ryzen 5 3600X
グラフィック GeForce RTX 2080 / Radeon RX 6700 メモリー: 16 GB |
公式 | steam |
| サイバーパンク2077:仮初めの自由 | 2023/09/26 | プロセッサー: Core i7-12700 / Ryzen 7 7800X3D
グラフィック: GeForce RTX 2060 SUPER / Radeon RX 5700 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ホグワーツ・レガシー | 2023/02/11 | プロセッサー: Core i7-8700 / Ryzen 5 3600
グラフィック: GeForce 1080 Ti / Radeon RX 5700 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| TEKKEN 8 / 鉄拳8 | 2024/01/26 | プロセッサー: Core i7-7700K / Ryzen 5 2600
グラフィック: GeForce RTX 2070/ Radeon RX 5700 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Palworld / パルワールド | 2024/01/19 | プロセッサー: Core i9-9900K
グラフィック: GeForce RTX 2070 メモリー: 32 GB RAM |
公式 | steam |
| オーバーウォッチ 2 | 2023/08/11 | プロセッサー:Core i7 / Ryzen 5
グラフィック: GeForce GTX 1060 / Radeon RX 6400 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| Monster Hunter RISE: Sunbreak
/ モンスターハンターライズ:サンブレイク |
2022/01/13 | プロセッサー:Core i5-4460 / AMD FX-8300
グラフィック: GeForce GTX 1060 / Radeon RX 570 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| BIOHAZARD RE:4 | 2023/03/24 | プロセッサー: Ryzen 5 3600 / Core i7 8700
グラフィック: Radeon RX 5700 / GeForce GTX 1070 メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| デッドバイデイライト | 2016/06/15 | プロセッサー: Core i3 / AMD FX-8300
グラフィック: 4GB VRAM以上 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| Forza Horizon 5 | 2021/11/09 | プロセッサー: Core i5-8400 / Ryzen 5 1500X
グラフィック: GTX 1070 / Radeon RX 590 メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |