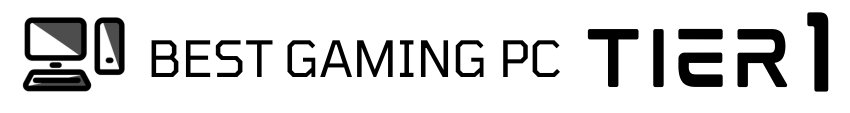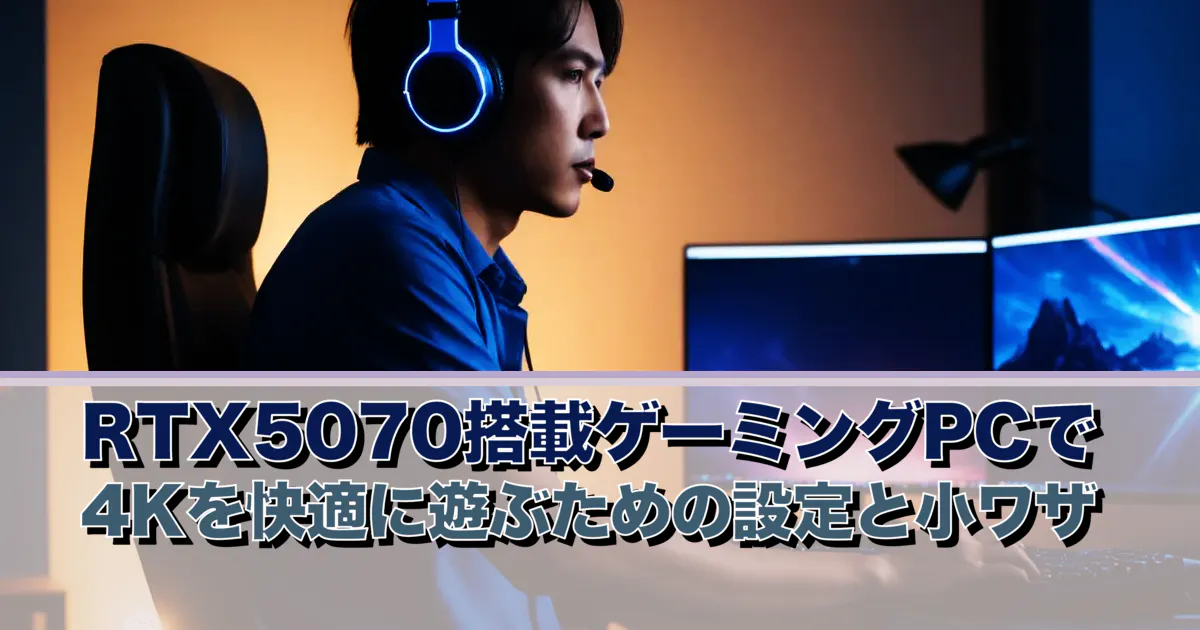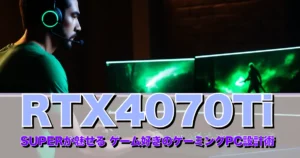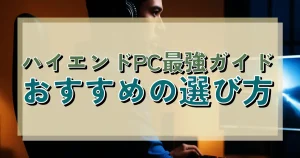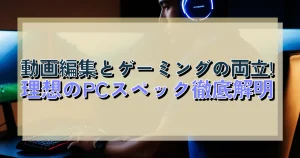RTX5070で4Kゲームを快適に遊ぶためのチェックポイント
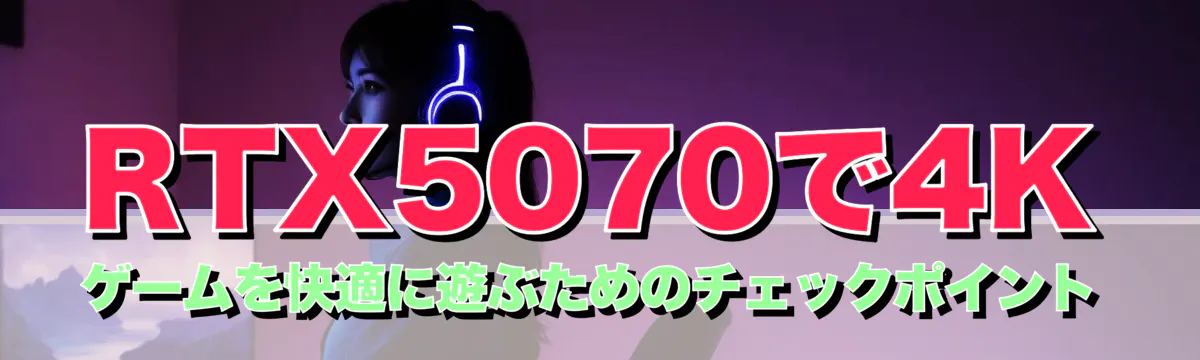
画質設定とフレームレート、実際の落としどころ
4K解像度でRTX5070を最大限に活かすには、結局「どのポイントにこだわりを残すか」がすべてだと私は考えています。
というのも、最新のモデルであっても全タイトルを最高設定のまま安定的に動かすのは難しいですからね。
実際、私も試行錯誤の末にようやく気づいたのですが、少し設定を調整するだけでゲーム体験が大きく変わるんです。
つまり、鮮やかな映像を取るか、操作の滑らかさを取るか、その選択次第で満足度が大きく左右されてしまいます。
贅沢な悩みですよね。
例えば、レイトレーシング。
もちろん最高にすれば映像は驚くほどリアルになりますが、その一方でフレームレートの落ち込みが明らかに体感できるほど大きくなることが多いんです。
最初は感動しながらプレイを始めても、ラグや操作遅延が出てくると不満が勝ってしまう。
これでは本末転倒です。
だからこそ、DLSS 4や新しいシェーダー技術の価値を実感します。
少し負荷を下げつつも、目で見たときの映像のクオリティを守れる。
そのうえで60fpsを安定的に超えられる感覚は安心感につながります。
「よし、これなら大丈夫だ」と自然と笑みがこぼれる瞬間があるんですよ。
設定を突き詰める作業は面倒だ、と感じる人も多いと思います。
正直、私も昔はそうでした。
その感覚に気づいたとき「なんだ、こんなことで変わるのか」と思わず声に出してしまったくらいです。
リフレクションやライティングを少し落とすだけでも余裕が出てきて、急にゲーム世界が遊びやすい場所に変わる。
美しさを求める気持ちと、遊びやすさを失わないための調整。
その二つをどうまとめるかが5070を活かす鍵になります。
実体験で忘れられないのは、ある有名タイトルをウルトラ設定、レイトレーシング最高で挑んだときのこと。
平均で60fpsすら割り込んでしまい、正直がっかりしました。
「ここまで投資したのにこれかよ」という感情が込み上げてきました。
でも、DLSSをパフォーマンス寄りに変え、シャドウをひとつ落としたら70fps以上を安定して維持できたんです。
劇的な変化に「これぞ最適化の凄みだ」と鳥肌が立ちましたね。
これこそRTX50世代のカードが持つ柔軟さで、ただ性能が高いだけではなくプレイヤーに調整できる余裕を与えてくれるんです。
大きな進化です。
私が強く感じているのは、ゲームをする上で全部を犠牲にする必要はないということです。
「ここだけは譲らない」という軸を残しながら、他を調整する。
それでこそ納得できる環境が作れます。
ラグが勝敗を決める場面でストレスを感じない、それだけで勝率が変わることすらある。
やはり実戦重視、そういう割り切りも時には大切だと痛感してきました。
一方で最近のゲームは映画のような作り込みを誇ります。
フレームレートが落ちればせっかくの美しい映像も台無しです。
そこで目安として私が大切にしているのは最低でも80fpsを維持すること。
このラインを守れば映像の迫力を保ちながらも快適な操作感を確保できます。
ゲーム中のストレスを大幅に減らせるので、集中力も途切れません。
先日、BTOショップを回ったときの光景は印象的でした。
RTX5070搭載モデルがガラスケース越しに並んで、まるで主役のように輝いていたんです。
システムメモリも32GBが当たり前になり、全体として余裕のあるスペックで構成されている。
正直「これなら買い替え時かもしれない」と心が揺れました。
頼もしさを感じる瞬間でしたね。
ただし、性能ばかり追い求めるのは危険です。
GPUの消費電力と発熱は見過ごせないですし、静音性を無視した環境ではどんなに高性能なパーツを積んでもストレスにつながります。
ケース内部のエアフローや冷却設計、CPUクーラーの選び方も軽視できません。
だからこそ私は声を大にして言いたい。
私としてのまとめはこうです。
RTX5070で4Kゲーミングを狙うなら、美しく描画したい気持ちを持ちながらも、影や反射、一部ライティングをバランスよく抑え、DLSSを積極的に使う。
この戦略がもっとも現実的で、長く楽しめる落としどころです。
欲張る気持ちは理解できますが、そこに飲み込まれたら楽しさそのものを削いでしまう。
だから私は断言します。
バランスをうまく捉えたときにこそ、本当の意味での快適なゲーム体験が手に入るのです。
納得の最適解。
――機械の性能と自分の感覚、その間を何度も調整しながら答えを探す時間。
DLSSやレイトレーシングを無理なく使う工夫
RTX5070を4K環境で使ってみてまず痛感したのは、単純に「性能がいいからすべて最大設定で楽しめる」と思うのは大きな勘違いだということでした。
どんなに高性能なカードでも、無理に最高設定を突き詰めれば負荷は一気に跳ね上がり、結局映像は綺麗でも動作が重くなってしまいます。
私が実際に試行錯誤して分かったのは、力任せではなくバランス調整こそが一番のカギだということです。
正直に言えば、最適解を探す過程は少し泥臭く面倒でもありましたが、その分だけ自分なりの納得感にたどり着けました。
まず頼りになったのはDLSSでした。
DLSSを適切に活用すれば、ただ解像度を落とさずに軽量化できるだけでなく、ゲーム体験全体の質が明らかに底上げされるのです。
特にDLSS 4を使ったときの自然さには驚かされました。
最初は「フレーム生成って機械的に見えるのでは」と半信半疑でしたが、実際に使ってみれば滑らかさは十分で、ほとんど気にならないどころか快適そのものでした。
一方でレイトレーシングです。
やはりすべてを最高値にすると映像は美しいのですが、私にとって実用的ではありませんでした。
光や影の描写がリアルになる代わりに、フレームレートは見て分かるほど落ちる。
そのせいでアクションのテンポが崩れ、ゲームの面白さそのものを損なってしまったのです。
そこで私は割り切ることにしました。
リフレクションや影といった、プレイしながら強く目に入る部分にだけレイトレーシングを絞り、その他は中程度にとどめる。
この調整を取り入れることで、映像のリアルさと動きの軽快さをどちらも維持できたのです。
あるときTPSを遊んでいて、思い切って全設定を最高にしました。
スクリーンショットを撮れば垂涎ものの映像が映し出され、「やっぱり凄い」と最初は興奮しました。
しかし実際に動かすとガクガクでテンポが乱れる。
私はその時に強く学びました。
「最高設定=正解」ではない、と。
少し控えめに設定を下げてみたら、120Hzモニターとバランスが取れて、むしろプレイ体験は格段に良くなったのです。
身の丈に合った調整こそが現実の答えでした。
最近の大作ゲームは、DLSSやレイトレーシング前提で設計されているケースが多くなりました。
逆に言えば、それらを活用してこそ本来の映像美を楽しめるように作られているのだと思います。
私自身、シャドウやテッセレーションを高くし過ぎてGPUのリソース不足に悩んだ経験がありましたが、きちんとDLSSを土台に据えてから設定を組み立てると、格段に安定する。
その瞬間の変化は、数字のベンチマーク以上にプレイしていて体で実感できるものでした。
映像の迫力とプレイの気持ちよさ、その両方が一段上に引き上げられるのです。
設定を詰めていく中で感じたのは、順序の大切さでした。
まずDLSSでフレームを安定させ、そのうえで余裕がある範囲にレイトレーシングを足す。
この流れで調整すれば、全体に破綻が出ないんです。
逆に最初からレイトレーシングをすべてオンにして、あとでDLSSに頼ろうとしても改善はごくわずかで満足できません。
やはり基本を作ってから積み重ねることが肝なのだと、実体験でよく分かりました。
例外もあります。
最近のオープンワールド作品は公式プリセットの完成度が高く、初期設定のままでも驚くほど自然で引っかかりのないプレイを楽しめました。
作り手が想定した環境には、やはり意味がありますよね。
最初から妙に背伸びせず、その土台を活かして微調整した方がはるかに楽でした。
RTX5070はスペック上はミドルハイの位置づけですが、DLSS 4を活用すれば間違いなくハイエンドに迫る体験が実現できます。
けれども「とりあえず全部最高」に設定する時代はもう終わったと私は思います。
本当に効き目のある部分に的を絞って調整することが、最も楽しいプレイにつながるのです。
それはベンチマークの数値ではなく、実際に遊んでいるときに「楽しい」と素直に思えるかどうかで決まります。
私の結論はこうです。
このバランスを守ることこそ、4Kでも快適に遊べる秘訣でした。
余分に背伸びすれば快適さを失い、削りすぎれば美しさを損なう。
だから両立点を探す努力が何より大切になるのです。
安心感が違います。
最終的に私は、RTX5070は工夫次第で想像以上の力を発揮してくれる頼もしい一枚だと確信しました。
モニターの前に座るたびに、滑らかさと映像美が共存する画面が広がる。
その瞬間に「この調整は正解だったな」と嬉しくなるのです。
あぁ、やっぱり遊びはこうでなくちゃ。
CPUやメモリの組み合わせで変わる体感パフォーマンス
RTX5070を軸に4Kゲーミングの環境を考えるなら、私はまず「GPUだけで完結する世界ではない」と強く伝えたいと思います。
確かにGPUは花形の存在ですし、誰もが大事だと口をそろえる部分です。
しかし、何度も試行錯誤を重ねた私の実感としては、CPUとメモリがしっかりしていなければ、せっかくのGPUは力を出し切れない。
高価な投資をしたのに肩透かしを食らうようなものです。
この現実を痛感してから、私はゲーム用PCの組み方をガラリと変えました。
ゲームのプレイ中「なんとなく引っかかるな」と感じたことはありませんか。
あれ、案外GPUではなくCPUが原因なことが多いんです。
特に大量の敵がわっと出てきた瞬間や、リアルタイムで計算が必要な場面。
そこが中途半端なCPUだと一気に処理落ちする。
私も何度もやられました。
正直あの瞬間は思わず「なんだよこれ」と口にしたほどです。
だからRTX5070を本気で動かすなら、Core Ultra 7クラス以上を前提にした方がいい。
これは断言できます。
GPUのポテンシャルを殺さないために。
メモリもまた見過ごせない存在です。
量を増やせば万全、という単純な話ではない。
実際に私は帯域の広さを軽視して後悔しました。
せっかくの映像が急にカクつく。
まるで流れるはずの水が細いホースに押し込まれて詰まるような感じです。
だから今ならDDR5-5600で32GBが一番安心できる。
これ未満だと、データ転送が追いつかず結果としてGPUを遊ばせてしまう。
この経験は胸に刻まれました。
私は以前、Core Ultra 5と16GBメモリで組んだ環境を試して、正直「これがあの最新GPUか?」と疑ったほどです。
高画質設定にすると場面が切り替わるごとにカクつきが出る。
楽しいはずのゲームでストレスしか残らない。
ところがCPUをCore Ultra 7に、メモリを32GBに強化したら、別次元でした。
そうか、結局は土台なんだ、としみじみ実感したのを今でも覚えています。
大事なのは、GPUだけを疑ってはいけないということです。
なぜか人はフレーム落ちや違和感を感じた瞬間、真っ先にGPUを疑うんですよね。
でも本当の原因はCPUやメモリに隠れている。
そしてそれを見逃せば、高価なGPUはただの飾りになってしまう。
これほどもったいないことはありません。
だから私は強く「CPUとメモリを軽視しないでほしい」と言いたいのです。
長時間プレイをしてもそれは明らかです。
GPUの温度対策を入念にしても、なぜか安定しないことがある。
そのときの真犯人は、CPUのコア数不足やクロック限界。
裏で処理しきれないタスクが蓄積されているのが透けて見える瞬間、没入感は一瞬にして消え去ります。
「ああ、やってしまったな」という失望感。
楽しいはずの時間がストレスに変わる。
だから私は二度と妥協した構成は選ばないと固く心に誓いました。
メモリについても同じです。
今の感覚では32GBがスタンダード。
でも趣味のゲーミング用途なら、多くの場合32GBで十分です。
逆に16GBだと、たとえ割安でもGPUの実力を削いでしまう。
結果的に「安物買いの銭失い」になるわけです。
私自身16GBでの挫折を体験して、もう二度と戻れないと痛感しました。
先日、RTX5070にRyzen 7 9800X3Dと32GBメモリ、さらにGen.4のSSDという環境で試したのですが、ようやく理想的な構成にたどり着いたと感じました。
映像負荷の大きなシネマティックシーンでもFPSが60を下回ることはほとんどなく、DLSSを加えると信じられないほど滑らかな動きになる。
思わず「これこそ4Kゲーム体験の完成形だ」と声に出してしまいました。
ゲームの世界に入り込むあの感覚は、本当に格別でした。
最高の没入感。
私が出した結論は明確です。
RTX5070を活かすには、Core Ultra 7やRyzen 7といった堅実なCPUを選び、メモリはDDR5-5600の32GBを搭載する。
それが最低条件。
そうすることでやっとGPUの真価を引き出せる。
その時「投資してよかった」と心から思えるのです。
私はこの構成こそ、誰にでも胸を張って勧められると断言できます。
最終的に振り返って思うのは、機械の数値ではなく「体感の質」が全てだということです。
カタログスペックの並びを追うよりも、自分が実際にどんなプレイ感を望むかを具体的に思い描いて構成を考える。
その視点があるかどうかで雲泥の差になる。
私自身はその考え方に救われました。
だからこそ今後も、私はCPUとメモリに一切妥協しない。
それが私の答えです。
最新CPU性能一覧
| 型番 | コア数 | スレッド数 | 定格クロック | 最大クロック | Cineスコア Multi |
Cineスコア Single |
公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 9 285K | 24 | 24 | 3.20GHz | 5.70GHz | 43230 | 2437 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 42982 | 2243 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X3D | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 42009 | 2234 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900K | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.00GHz | 41300 | 2331 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X | 16 | 32 | 4.50GHz | 5.70GHz | 38757 | 2054 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X3D | 16 | 32 | 4.20GHz | 5.70GHz | 38681 | 2026 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265K | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37442 | 2329 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265KF | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37442 | 2329 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 9 285 | 24 | 24 | 2.50GHz | 5.60GHz | 35805 | 2172 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700K | 20 | 28 | 3.40GHz | 5.60GHz | 35664 | 2209 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900 | 24 | 32 | 2.00GHz | 5.80GHz | 33907 | 2183 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.60GHz | 33045 | 2212 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700 | 20 | 28 | 2.10GHz | 5.40GHz | 32676 | 2078 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X3D | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.50GHz | 32565 | 2168 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7900X | 12 | 24 | 4.70GHz | 5.60GHz | 29382 | 2017 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265 | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28665 | 2132 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265F | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28665 | 2132 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245K | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25561 | 0 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245KF | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25561 | 2150 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9700X | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.50GHz | 23187 | 2187 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9800X3D | 8 | 16 | 4.70GHz | 5.40GHz | 23175 | 2068 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 235 | 14 | 14 | 3.40GHz | 5.00GHz | 20946 | 1838 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7700 | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.30GHz | 19590 | 1915 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7800X3D | 8 | 16 | 4.50GHz | 5.40GHz | 17808 | 1795 | 公式 | 価格 |
| Core i5-14400 | 10 | 16 | 2.50GHz | 4.70GHz | 16115 | 1758 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 5 7600X | 6 | 12 | 4.70GHz | 5.30GHz | 15354 | 1959 | 公式 | 価格 |
RTX5070と相性の良いPCパーツ構成を考える
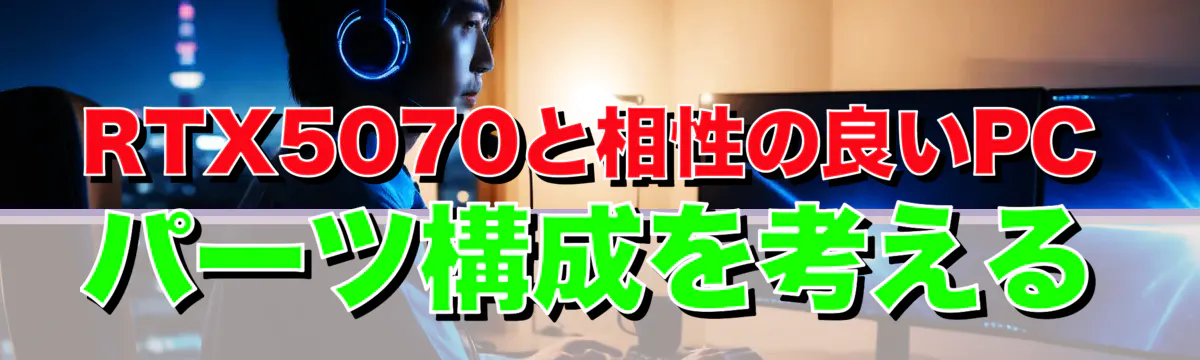
CPU選び――Core UltraかRyzenか、実際の使いやすさ
ハイエンドのGPUを導入するときに、私が一番頭を悩ませるのはいつもCPUの選び方です。
どれだけ優秀なGPUを揃えたとしても、適切なCPUを組み合わせなければ本来の力を引き出せない。
昔、自分がその落とし穴にはまったとき、本当に歯がゆい思いをしました。
だからこそ声を大にして伝えたいのです。
RTX5070を4Kで最大限に活用したいなら、CPUの選定こそがすべてを決める分岐点になります。
3D V-Cacheの恩恵によって処理の一貫性が際立っており、フレームの滑らかさが数字以上に体感で伝わってくるのです。
長時間FPSを遊んでいてもマップ切り替え時のわずかな遅延が目立たない。
GPUの力を遮らずにそのまま画面に投影してくれるような心地よさで、「やっぱりこれだ」と納得せざるを得ませんでした。
実際にプレイ中にふと笑みがこぼれる、そんな瞬間があったことをはっきり覚えています。
一方で、Core Ultra 7 265Kも私にとっては侮れない存在でした。
特に仕事や趣味を並行して行うような日常では、このCPUの頼もしさが光るのです。
私の場合、ゲームを遊びながら同時に動画のエンコードを走らせ、さらにリアルタイムで字幕処理を試したことがあります。
そのとき驚いたのは、リソースを食う重たい処理が重なってもシステムが引きずられず、むしろスムーズに裏方が動き続けていたことでした。
まるで縁の下から強く支えられている安心感に、思わずうなってしまったくらいです。
ただし両者の差を最終的に分けるポイントは、電力効率と発熱の扱いやすさでした。
Core Ultraは高負荷になると一気に温度が上昇する傾向が強く、ときには空冷で無理を感じたことがあります。
静音性を優先したい私は、水冷に思い切って切り替えました。
正直その費用が余計にかかったのは悩ましいところ。
しかし切り替え後は気持ちがすっきりし、集中度も段違いでした。
一方でRyzenは温度変化が穏やかで空冷一本でも安定。
夜通しのプレイでも大きなストレスを感じなかった経験があります。
数字に頼りきるのは危険です。
私も昔、ベンチマークの数値だけを見て「よしこれで大丈夫」と判断したことがありました。
でも実際に使ってみると別物で、ゲーム三昧の日と仕事寄りの日とで、はっきり快適さが違っていたのです。
理論上の性能と現場のリアルの溝に苦笑したこともありました。
そんな瞬間、机上の数字より自分の生活リズムや使い方に寄り添うかどうかのほうがよほど大切だと痛感したものです。
私の結論ははっきりしています。
RTX5070を4Kで存分に楽しむことだけを目的とするならRyzen 7 9800X3Dです。
フレームの安定感や描画の伸び方が自然で、GPUの解放感をそのまま味わえる。
それに比べてマルチタスク前提で仕事や配信を組み込みたいならCore Ultra 7 265Kの方が現実的に役立ちます。
要は軸足がどこにあるか。
それを見極めれば、おのずと答えは出てくるのです。
最も避けるべきなのはせっかく投資したRTX5070がCPUのせいで走りきれないという悲劇です。
GPU使用率が頭打ちになり、画面にカクつきが見えるたびに、私は「もっと伸びるはずなのに」と悔しさでため息を漏らしました。
これを避ける唯一の方法は、最初の選定で妥協しないこと。
深夜、暗い画面を見つめながら「この投資に何の意味があったのか」と落胆したのを今でも思い出します。
その悔しさがあるからこそ、いま同じように迷っている人に本気で伝えたいのです。
二度と自分と同じ後悔を味わってほしくないと。
結局、どちらが自分に合うのかを最後に決めるのは、自分がPCとどう付き合いたいかに尽きます。
自宅でのんびり好きなゲームを心行くまで楽しむなら間違いなくRyzenでしょう。
しかし日常で在宅ワークや配信、加えてAI処理を回す習慣があるならCore Ultraが光ります。
自分の生活にどちらがなじむのか。
それが境界線になるのです。
時間をかけて悩むことは無駄ではありません。
むしろ、そこにしっかり向き合うことこそが後悔のないPC環境を作る第一歩なのです。
単に遊ぶための道具を組むのではなく、仕事も趣味も含めて自分を支える相棒を選ぶ感覚でCPUを選んでほしい。
その視点があればRTX5070への投資が生き、日常を支える力強い基盤に変わります。
忘れられない気持ちがあります。
振り返ると、CPU選びは高性能かどうか以上に、日々を支える使い勝手の良さに直結していました。
数値だけでは伝わらない快適さを繰り返し味わったからこそ、私は妥協するなと強く言いたいのです。
せっかくRTX5070を選んだのなら、その力を抑え込まない最高のパートナーを選んでください。
DDR5メモリは32GBで足りる?それとも64GBを積んだ方が安心?
ただ同時に、ゲーム目的に絞るのであれば32GBで十分に快適に楽しめる現実もある。
ここは声を大にして伝えたい。
メモリの容量をどう構成するかは、単純に多ければ安心というだけではなく、自分の使い方をどう想定しているか次第なのです。
私はRTX5070を組み合わせたPCで何度も検証してきましたが、純粋にゲームを遊ぶだけなら32GBで何も困らなかったのが正直な感想です。
AAAタイトルの最新作であっても、4K環境でストレスなく動いてくれる。
フレームレートが大きく落ち込んでしまうこともなく、敵の動きや演出に集中できる。
ゲーム好きにとって、これ以上の安心感はそうそうないと思うんですよね。
正直、遊んでいる最中に「あれ、もう少しメモリがほしいな」と思ったことはありませんでした。
ところが、私自身ゲームだけをして終わる日は少ないのです。
配信を並行して立ち上げたり、裏で動画をエンコードしながら遊んだりする光景は、今や日常そのもの。
そんなときに32GBではちょっと余裕がなくなり、「今なんか重くなったぞ?」と戸惑う場面に出くわす。
しかも最近のゲームはテクスチャが膨大で、ただのロードですら気を抜くと時間を食います。
64GBまで積んでいるとこの不安がすっと消えて、快適さと安心感が背中を押してくれるんです。
実際に最新のオープンワールドを最高設定で配信環境込みで試したとき、使用メモリはあっさり40GBを超えました。
その時は思わず「おいおい、もう足りなくなってるじゃないか」と笑ってしまったほどです。
仕事の場面になると、その差はさらに歴然とします。
動画編集で複数のクリップを同時に扱ったり、3D制作で高解像度テクスチャを何枚も読み込んだりするときに、容量不足がもたらすストレスは想像以上です。
一回のページングで失う時間は数秒でも、その積み重ねで作業効率が一日単位でごっそり削られる。
32GBから64GBへ乗り換えた瞬間の快適さといったら「天と地ほどの違いだ」と思いました。
余裕のありがたさを身をもって知った経験です。
とはいえ、すべての人が64GBを必要とするわけではありません。
実際、私のサブ機は今も32GBですが、『Valorant』や『Apex Legends』のような競技系タイトルなら4K解像度でも100fps前後を叩き出して快適に遊べます。
軽い配信を横で走らせても処理落ちが目立たず、驚くほど滑らかな感覚があるんです。
ですから、コストを抑えつつ十分楽しみたい方にとって32GBは依然として強力な選択肢です。
ただ最近は、生成AIをゲーミング環境に取り入れる人が増えました。
背景をAIに生成させるモッドを導入したり、制作作業を手伝うツールを裏で回したりすると、意外とじわじわとメモリを食い尽くしていく。
見かけ上は軽い処理でも油断できないのです。
以前、32GBで十分だったはずの環境で、裏でAIを走らせた瞬間に「止まりはしないが妙に心もとないな」とヒヤリとした経験があり、やはり余裕の64GBが精神的にも助けになると痛感しました。
加えて見逃せないのが、アップデートによる要求スペックの上昇です。
最新の大作はリリース後の追加パックや高解像度テクスチャで、どんどん要求メモリが増していく傾向があります。
その時に思ったのです。
「長く構成を維持するつもりなら、迷わず64GBだ」と。
それでもやはり最終的な選択はシンプルです。
RTX5070と組み合わせて、純然たるゲーミング用途なら32GBで楽しく快適に遊ぶことができる。
でも配信やAIツールを同時に使いたい方、またこれから数年先を見越した重いタイトルに臨みたい方には64GBがしっかりと応えてくれる。
その分の安心感。
これが大きい。
私の答えはこうです。
コストを意識して、必要最低限で済ませたいなら32GB。
それで十分に働きます。
でも余裕を重視して、将来に渡って快適さを確実に維持したいなら64GBが最良です。
そして忘れてはいけないのは「自分がそのPCで何をしたいのか」を冷静に見極めること。
その視点があれば、どちらを選んでも後悔しないはずです。
私はそれが最も大事だと思っています。
それだけの違いが日々の満足感につながるのです。
GeForce RTX5070 搭載ゲーミングPC おすすめ5選
パソコンショップSEVEN ZEFT Z57U

| 【ZEFT Z57U スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra9 285 24コア/24スレッド 5.60GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | CoolerMaster MasterFrame 600 Black |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | intel Z890 チップセット ASRock製 Z890 Steel Legend WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R62L

| 【ZEFT R62L スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R61GI

| 【ZEFT R61GI スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 DIGITAL WH |
| マザーボード | AMD X870 チップセット GIGABYTE製 X870M AORUS ELITE WIFI7 ICE |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55HH

| 【ZEFT Z55HH スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra9 285 24コア/24スレッド 5.60GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S100 TG |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Pro |
パソコンショップSEVEN EFFA G09B

| 【EFFA G09B スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 9900X 12コア/24スレッド 5.60GHz(ブースト)/4.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ブラック |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
Gen4 SSDとGen5 SSDを比べてみた体感の違い
映像の美しさやフレームレートの安定性はほとんどグラフィックボードの力に依存しますし、ストレージが直接勝敗を分けるような場面はそう多くはありません。
ただし、ロード時間の短縮やデータの展開速度といった部分は確かに変わります。
例えばオープンワールドゲームを遊んでいるとき、大きなマップを移動する瞬間の切り替えや、高解像度テクスチャが大量に使われる場面では「おっ、違うな」と実感できるのです。
こうした細かい快適さは、遊んでいる時間が長い人ほど効いてくる。
ただし、これはあくまで環境全体のバランスあってこそです。
CPUやメモリの性能が追いつかなければ、いくら最新のSSDに投資しても実力を発揮できません。
RTX5070ならDLSS4を活用することで映像は驚くほど洗練されますが、その分、ボトルネックがCPUやストレージに移ってくるのを感じました。
Gen5 SSDは公称値で14,000MB/sくらい出ると言われていますが、実際には「読み込み画面が半分になった!」なんて劇的な変化はありません。
体感的には、確かに短くなったけれどそれほど大きなインパクトではなく、「まあ少し早いかな」という程度です。
私が自分の環境でテストしたときには、OSの起動時間がGen4からGen5に変えてもわずか2~3秒縮んだ程度でした。
ただ、ゲーム中のマップ切り替えでは大きく違いました。
待ち時間が減ってスムーズに移れるようになり、ちょっとした苛立ちが減るのです。
この細かな快適さこそが長時間遊ぶゲーマーにじわじわ効いてきます。
4K解像度で遊んでいるとどうしてもテクスチャ読み込みや瞬間的なカクつきに神経質になってしまいますが、Gen5にするとその心配がふっと軽くなる。
ほんの少しだけれど気持ちに余裕が生まれるのです。
その余裕こそが、プレイ体験全体を左右する要素だと私は感じました。
とはいえ、Gen5を導入して初めて直面する問題があります。
発熱です。
最近のGen5 SSDは巨大なヒートシンクや冷却ファンを備えるものが多く、パーツ単体で見れば頼もしいのですが、そこまでして投資する意味があるのか立ち止まってしまう瞬間があります。
逆にGen4 SSDであれば冷却も小型ヒートシンクで十分に対応でき、取り回しも快適です。
作業スペースに余計な負担を抱える必要がなく、私はそちらの安心感を重視するほうでした。
安定した動作が欲しいならこちらです、と言いたくなるくらい。
最近はBTOパソコンでも標準がGen4、オプションでGen5という形がよく見られるようになりました。
そこで悩むのはコストです。
追加費用を支払ってまでGen5に切り替えるほどの価値があるのかと考えると、私の感覚では答えは「限定的」です。
確かに動画編集や8K映像編集のような重労働では秒単位での差が積み上がって大きな恩恵になっていきます。
でもRTX5070で4Kゲームを楽しむ、という前提で考えるなら話は別で、正直なところGen4で十分やれるのです。
ではGen5は不要なのかと考えると、それも極端な結論です。
今すぐの快適さだけを追うならGen4で問題はありません。
しかし数年先も同じマシンで快適性を維持したいなら、あえてGen5へ投資しておく選択肢も見えてきます。
今この瞬間では「誤差程度」と思える差も、将来の新作ゲームが登場したときに違いとなって表れる。
その可能性を考えると、一概に切り捨ててしまうのももったいないのです。
要は今を重視するか、未来を重視するか。
実際に私はGen5 SSDを1か月ほど日常的に使いました。
そのときに強く感じた課題は消費電力と発熱でした。
冷却用にファンを高速で回し続ける必要があり、静音性を犠牲にせざるを得ませんでした。
せっかくゲームの世界に没入したいのに、耳に残るファンの音がどうしても気になる。
集中しきれずに「これは少し違うな」と思った瞬間がありました。
些細なことのように見えても、長時間使えば不満に積み重なるのです。
そして最終的にはGen4の使いやすさを懐かしく思う場面もありました。
正直に言います、あのバランスの良さは魅力です。
RTX5070を活かすのに必要なのは、リッチなグラフィック表現と安定したフレームレートを両立させることであり、それを支えるストレージはバランスが重要です。
コストや発熱を考えると現時点での最適解はGen4だと私は思っています。
4Kで遊ぶ分には不足する部分はほとんどありませんし、導入コストも無理がなく現実的です。
Gen5は未来への投資として意味がある。
しかし「今すぐ必須」という位置づけではありません。
私はそういう判断に落ち着きました。
快適性。
現実的な選択肢。
これが自分の手で組み、実際に使い比べた私の実感です。
1500文字を超えて語ってしまいましたが、あえて短くまとめるなら「今のRTX5070ならGen4で十分」という一言に尽きるのです。
SSD規格一覧
| ストレージ規格 | 最大速度MBs | 接続方法 | URL_価格 |
|---|---|---|---|
| SSD nVMe Gen5 | 16000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD nVMe Gen4 | 8000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD nVMe Gen3 | 4000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD SATA3 | 600 | SATAケーブル | 価格 |
| HDD SATA3 | 200 | SATAケーブル | 価格 |
4Kゲーミングを見据えた冷却とケースの選び方
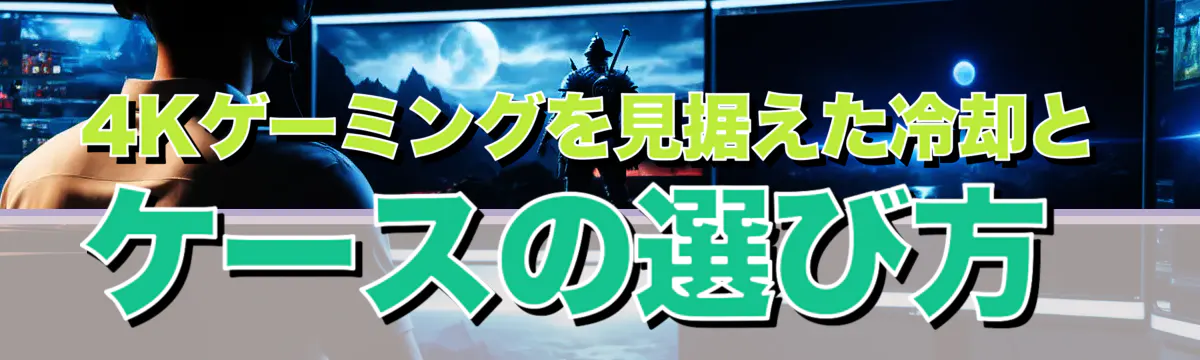
空冷と水冷、悩んだときに考えるポイント
高性能なRTX5070を活用してPCを組もうとする時、多くの人がまず悩むのが冷却方式の選択だと思います。
私も散々迷って両方を経験してきましたが、率直に言えば今の自分なら空冷を選びます。
理由は単純で、安定して長く付き合える安心感があるからです。
どれだけ見た目が華やかであっても、毎日使う道具に必要なのは「壊れにくさ」と「信頼感」ではないでしょうか。
疲れて帰宅して電源を入れる時に、余計な不安を持たずに済むこと。
これが私にとって何より大事なんです。
たとえば大きめのヒートシンクを備えた空冷クーラーなら、一度しっかり取り付ければ数年以上は黙々と働いてくれるんです。
私は以前、Core Ultra 7とRTX5070を組み合わせ、空冷で4Kゲームを何時間もプレイしたことがあります。
CPU温度は常に80度前後で収まり、ファンの音も気になるほどうるさくなかった。
これは、「ああ、信頼できるな」と素直に思えた瞬間でした。
ただ、水冷の魅力も無視できません。
水冷は静かで、特に夏場は長時間稼働でも差が出やすい。
さらにケース内がスッキリして、RGBライティングと組み合わせれば雰囲気は段違いです。
展示会で見た水冷PCに心が躍った時のことは今でも忘れられません。
「これこそ理想のゲーミングPCだ」と心から憧れました。
あの見た目の迫力に興奮しましたね。
でも現実問題、水冷にはリスクがつきまといます。
ポンプが止まれば一発で冷却不能になり、液漏れなんて起きたらPC自体に大きなダメージが及びます。
それほど頻発するトラブルではないにせよ、発生した時のショックは計り知れません。
さらにメンテナンスの手間もかかる。
「もしもの時」を常に意識しながら使うのは、どうしても心細い。
これが私が水冷を選べない一番の理由です。
最近はピラーレスの強化ガラスケースが流行していますが、これも少しやっかいです。
見た目はとても美しい反面、ラジエーターの設置に制約が増え、空気の流れが損なわれがちです。
その結果、本来の冷却性能が期待ほど発揮されない場合があるんです。
結局はその二択を突きつけられるような気持ちになります。
一方で、空冷はそうした迷いを生みません。
コストも抑えられる上に、何年も置きっぱなしで動き続けてくれる。
私にとってはこの「放っておける気楽さ」が非常に大きな価値なんです。
正直に言えば、多少の見た目の派手さよりも、ゲームや作業に集中できる時間の方が大切です。
だから「信頼性」で考えれば空冷という結論になります。
納得感があります。
とはいえ、人によって優先する価値は違うものです。
SNSに映える美しいデスク環境を作りたいなら、水冷は最強の手段でしょう。
実際に20代の頃の私なら、迷わずそちらを選んでいたと思います。
「カスタマイズを楽しむのが正解だ」と言っていたはずです。
でも40代になった今は欲しいものが違います。
仕事で疲れ切った後に余計な心配をせず、ただ快適にゲームを楽しめる環境。
水冷は華。
空冷は実。
そう言い切ってもいいかもしれません。
RTX5070ほどの性能を持つGPUであっても、必ずしも水冷が必要というわけではありません。
これは実際に私が体験して確かめた事実です。
そして水冷はある意味「贅沢」であり「上乗せの楽しみ」ですが、空冷はあくまで「基盤」だと思います。
落ち着きのある強さを持っているんです。
もちろん人によって答えは変わるでしょう。
けれども安定して長くPCに向き合いたいと本気で思うのであれば、やはり空冷を選ぶのが賢明だと感じています。
私が自分の選択に後悔しないのは、この実感があるからです。
「これで良かった」と心から言える。
それが空冷を選んだ理由でした。
最終的には、派手さを取るか信頼を取るか。
高発熱GPUを安定させるためのエアフロー設計の工夫
どんなに最新のGPUを積んでも、熱が溜まれば性能はガクッと落ちてしまいますし、結果としてゲームに集中できなくなるんです。
要するに、パーツの魅力を100%引き出すには、見えない冷却設計こそが安心の土台になるんだと私は思っています。
私には苦い経験があります。
数年前、ケース内のエアフローをたいして考えず、とりあえずファンを付けておけばいいだろうと高を括っていました。
ところが実際に使ってみるとGPUが常に80度前後。
ファンの音は街中の工事現場さながらで、正直言ってゲームどころではなかったんです。
「これじゃ趣味じゃなくて騒音との戦いじゃないか」と自虐したのを、今もはっきり覚えています。
あのときの落胆は本当に大きかった。
その失敗をきっかけに、ケース選びから配置を徹底的に見直しました。
正面からの吸気を確保し、上部と背面に排気ファンを追加して流れをシンプルにする。
こうした見直しをしたときの変化は劇的でした。
同じゲームでも温度は10度以上も下がり、ファンの音は信じられないほど静かになったのです。
思わず「こんなに違うのか」と声が出てしまいました。
ただし、冷却ファンを増やすだけが解決策ではありません。
むしろ空気の流れを分かりやすく直線的にしてやること。
空気の動きが渦巻くと、結果は逆効果になりかねません。
そのときはパーツに申し訳なさすら感じましたよ。
今は見た目が美しいガラスケースが人気です。
確かに見栄えは抜群で、部屋に置いたらインテリアとして映えます。
私も正直その誘惑に負け、デザイン重視で選んでしまったことがあります。
でも実際に使ってみると吸気が不足し、ケース内部がサウナ状態。
見た目にうっとりしても、PCが熱を持ちすぎては元も子もありません。
結局「格好良さと快適さを天秤にかけるなら、私は快適さを選ぶ」と心から思うようになりました。
忘れがちですが、熱に弱いのはGPUだけじゃないんです。
最新のGen.5 SSDなどは注目されがちですが、その発熱は想像以上。
冷えが足りない環境ではすぐに性能低下を起こすのを目の当たりにして、本当にがっかりしたことがあります。
CPUクーラーや周辺パーツの位置まで含め、風の動き全体を俯瞰しないと、どこかにしわ寄せが出てしまうのです。
これが現実です。
私は車好きでもあるのですが、高性能エンジンでも空気抵抗をきちんと処理しないと力を出しきれないという事実と、PC内部の冷却問題が酷似しているように感じます。
通気の流れを考えずにハードを積んでも、力を発揮するどころか性能を殺してしまう。
私のおすすめは明快です。
ケースは正面からの吸気がしっかり取れるタイプを選ぶこと。
そして上部と背面に排気用ファンを確保し、空気が一方通行で流れるようにすること。
パーツの配置も丁寧に調整して、SSDやGPU、CPUクーラーが互いに邪魔をしないように気を配ること。
この三つの基本を守れば、冷却も静音性も両立し、4Kゲームでも長時間安定稼働が実現できます。
静かな時間。
これが何より嬉しいんです。
スイッチを入れた瞬間、余計な心配なく画面の世界に飛び込める。
汗をかきながら格闘していた頃を思い出すと、この快適さがどれほど貴重かわかります。
パーツをいじり倒し、試行錯誤を繰り返した日々が、この「肩の力を抜いたプレイ感」に変わったんだと実感できるのです。
RTX5070の実力をしっかり楽しめる冷却環境こそ、努力の成果と言えるでしょう。
私は思います。
4Kゲーミングを本当に楽しめるのは、冷却に本気で取り組んだ人だけだと。
対して、きちんと風の通り道を整えた環境であれば、長期にわたって安定と安心が約束されます。
そしてその安心感が、何より大切なのです。
熱を制する者が、4Kゲーミングを制する。
最新グラフィックボード(VGA)性能一覧
| GPU型番 | VRAM | 3DMarkスコア TimeSpy |
3DMarkスコア FireStrike |
TGP | 公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | 32GB | 48879 | 100725 | 575W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5080 | 16GB | 32275 | 77147 | 360W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9070 XT | 16GB | 30269 | 65968 | 304W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7900 XTX | 24GB | 30192 | 72554 | 355W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5070 Ti | 16GB | 27268 | 68111 | 300W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9070 | 16GB | 26609 | 59524 | 220W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5070 | 12GB | 22035 | 56127 | 250W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7800 XT | 16GB | 19996 | 49884 | 263W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 16GB | 16625 | 38905 | 145W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 16GB | 16056 | 37747 | 180W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 8GB | 15918 | 37526 | 180W | 公式 | 価格 |
| Arc B580 | 12GB | 14696 | 34506 | 190W | 公式 | 価格 |
| Arc B570 | 10GB | 13796 | 30493 | 150W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 | 8GB | 13254 | 31977 | 145W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7600 | 8GB | 10864 | 31366 | 165W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 4060 | 8GB | 10692 | 28246 | 115W | 公式 | 価格 |
デザインと冷却性能を両立できるケース選び
RTX5070を搭載したゲーミングPCで長時間4Kプレイを快適に楽しみたいと思うなら、私が一番に伝えたいのは「ケース選びを甘く見てはいけない」ということです。
CPUやGPUの性能ばかりに目を奪われがちですが、ケースの冷却設計が悪ければ宝の持ち腐れになってしまいます。
ケースはただの入れ物ではなく、熱をいかに逃がし、部品の安定性を守るか、その舞台を整える重要な存在なのです。
これは軽い話ではありません。
私は過去に、見た目の格好良さを優先してガラスパネルで覆われたケースを買ったことがありました。
光る部品が映えて最高だと胸を張っていたのも束の間、RTXクラスのGPUを積んだ瞬間に熱がこもってクロックダウン。
ゲーム中に処理が落ちるたび、ため息しか出ませんでした。
あの時の悔しさといったらないですよ。
その後、慌ててフロントをメッシュタイプに変え、冷却ファンを追加したら嘘みたいに改善しました。
自分自身で「環境を整えることこそ最大の投資だ」と痛感した瞬間でしたね。
ケースには冷却性能と整備のしやすさ、この二つが欠かせません。
RTX5070は最新のGDDR7メモリを載せていて、かなりの発熱があります。
そのためケース内部の空気がスムーズに流れる構造が求められるのです。
そして単なる空気の流れだけでなく、裏配線スペースの広さや埃掃除のしやすさひとつで使い勝手は大きく変わる。
これを軽視すると、結局自分自身がメンテナンスに追われてストレスをためる羽目になります。
だから、購入前に確認しておくべきだと強く思います。
最近はケースのデザインも実に多彩で、木材やアルミを組み込んだものや、RGBライティングで派手に演出するモデルも増えてきました。
私は展示会で木目調のパネルを備えたケースを触ったのですが、その温もりある質感に思わず感嘆しました。
ただ、一時的な流行に飲み込まれるのではなく、自分が毎日使う空間の雰囲気とどう調和するかを冷静に考えることが大切だとも気づきました。
デザインは心を動かす力があります。
でも流されてはいけませんね。
そして忘れてはならないのが、ケースはインテリアではなく機能部品でもあるということです。
RTX5070単体の発熱でも相当ですが、CPUやSSDもまたしっかりした熱源になります。
そのためケース全体としてフロントで空気を取り込み、GPU周辺を抜け、リアやトップから熱を出す一連の流れを確保しなければなりません。
これは4Kで長時間ゲームを楽しむうえでの必須条件なのです。
これがあるからこそ安心してハードにプレイできる。
本当にそう思います。
加えて静音性も重要です。
ケースの素材が分厚くて防音性があるか、吸音パネルを備えているか、さらにファンコントロールの余裕があるか。
こうした点は一見地味ですが実際の集中力に直結します。
私も在宅勤務のときにPCの轟音が気になって仕方がなかった経験があり、以来必ず静音性のあるケースを買っています。
静かさこそ集中の源です。
組み立てのしやすさも侮れません。
裏配線がぎちぎちだと、コードが熱を持ちトラブルの原因になります。
だからこそ見た目や冷却だけでなく、後々の扱いやすさを検討しておく必要があるのです。
この数年でいくつもケースを触ってきて心底思うのは「完璧は存在しない」という現実です。
冷却を追えばデザインが犠牲になり、デザインに走ればメンテ性を諦めることになる。
けれどその中で自分なりの納得の落としどころを探し、ここなら大丈夫と自分で腹をくくれるかどうかが大事なのです。
迷いはある。
でも、それがまた楽しいんです。
要点をまとめると、RTX5070の力をしっかり活かしながら静かに安定して動作し、さらに普段の生活空間になじむケースを選ぶことが最優先になります。
私はこの条件を押さえることこそが失敗のない選択だと思います。
デザインの美しさを感じながらも十分なエアフローを備え、長時間でも安心して4Kゲームに没頭できる。
それこそが理想のケースです。
ケースというのは、派手さばかりに目が奪われて忘れられがちですが、実は真の主役だと私は声を大にして言いたい。
全体を支え土台を支える存在。
忘れないでください。
RTX5070搭載ゲーミングPCを賢く使いこなす方法
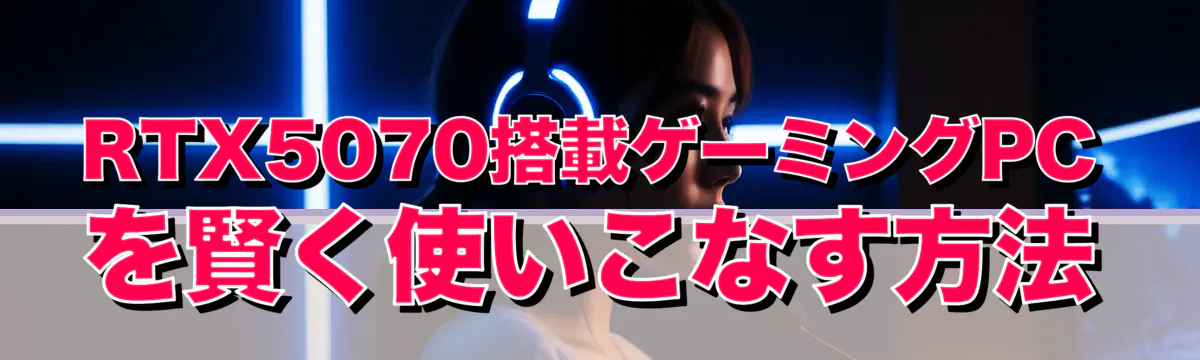
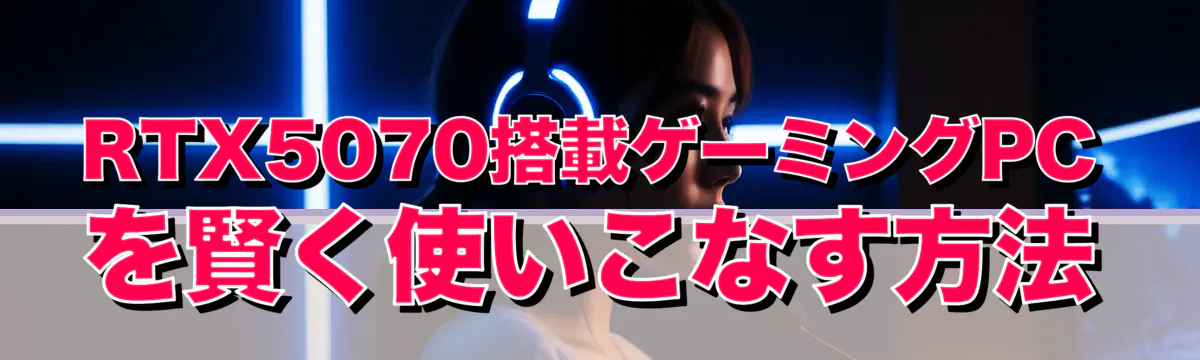
144Hzモニターをしっかり活かすための設定調整
性能を余すことなく引き出せるかどうかは、結局どれだけ基本を大事にできるかで決まってしまう。
仕事においても同じことが言えますが、派手な部分ばかりに気を取られて基盤を疎かにすると、必ずどこかで歪みが出るという経験を私は何度もしてきました。
私がこの点を痛感するようになったのは、自分の失敗がきっかけでした。
ある休日、気分転換にゲームをしていたのですが、どうにも動きがぎこちなくカクカクしてしまう。
高性能なグラフィックカードを入れているのにおかしいぞと首をかしげ、メモリを増設したり設定を片っ端から触ったりしましたが、改善しない。
悩んだ末に調べたところ、なんとOSのリフレッシュレートが初期値のままだったことが発覚。
144Hzモニターをつないでいるのに、ずっと60Hzで動かしていたわけです。
「なんて無駄なことをしていたんだ」と。
当時を思い出すと、数か月ものゲーム時間をふいにしたようで情けなく、笑うしかありませんでした。
だからこそまず確認すべきはOSの画面設定です。
ここを怠れば、どれだけ良いGPUを積んでいても本来の滑らかさは絶対に得られません。
派手なチューニングや無理なアップグレードに走るのではなく、こうした基礎がものを言う。
これは社会人としても同じで、資料や演出に凝っても中身が伴わなければ意味を持たないのと似ていますね。
次に重要になるのが、NVIDIAコントロールパネルでの動作設定です。
特にG-SYNCを有効化することで映像がモニターとしっかり同期され、カクつきが大幅に減ります。
さらに低遅延モード、特にReflexを有効にした効果には正直驚かされました。
敵の動きに反応してから画面に反映されるまでのごく短い遅延が縮まっただけで、プレイの感覚がまるで違う。
撃ち合いの勝率すら目に見えて変わった時には、「設定ひとつでここまで変わるのか」と本気で感心しました。
こういう経験があると、もう設定を軽んじなくなりますね。
ゲーム内のグラフィック設定でも同じです。
プリセットで高画質を選んでしまうと、一見美しい景色は楽しめますがフレームレートは安定せず、結果として144Hzモニターの良さを打ち消してしまう。
実務で言えばプレゼン資料に凝りすぎて、結局相手に何一つ伝わらないという状態に近い。
そして最新のDLSSを取り入れる。
結局のところ大切なのは、妥協の加減をどう見極めるか。
そこに経験値が出ると実感しています。
そして忘れてはいけないのがCPUやメモリです。
GPUに任せても処理を受けるCPUが弱ければ結果は頭打ち。
私なら現行世代のCore Ultra 7やRyzen 7ほどを選ぶ。
この辺りを整えておくことで、初めてGPUが本来の力を解き放てる。
システム構築を仕事にしてきた経験から言えるのは、全体のバランスを外すと、必ずどこかで無駄な負荷とストレスが積み重なるということ。
後から悔やむ羽目になります。
私が初めて144Hzモニターを導入した瞬間、その映像の滑らかさには息をのむほど驚きました。
本当にゲーム世界に入り込んだようで、思わず叫んでしまったのです。
「これだ!」って。
40代になった今もその時の衝撃は色褪せていません。
240Hz以上のモニターも出ていますが、コストや安定性を含めて考えれば144Hzがちょうどよい落とし所だと思います。
欲を言い出せば際限がありませんが、RTX5070との相性を考えると、このバランスが最適解だと断言できるのです。
ただ気をつけるべき点が一つ。
冷却です。
ケース内のエアフローを軽視すると熱が溜まり、クロックが抑制されて結局性能が出なくなる。
だから私はケースファンの配置を細かく考えるようになりました。
たかがファン、されどファンです。
冷却は軽視できません。
さらに意外と盲点になるのが日常使いの場面です。
そうなると「どうも重いぞ」と違和感を抱え続けることになります。
だから私は普段から確認を怠らない。
それが安心につながるからです。
振り返ると、RTX5070と144Hzモニターの組み合わせが真に価値を放つのは、調整と確認のひと手間を惜しまないからこそです。
性能と安定性とコスト、そのバランスに支えられて初めて快適な体験が得られる。
高価なパーツに頼るのではなく、むしろ当たり前の確認を徹底することが真の差を生む。
そう心から思います。
だから私は自信を持って言います。
144Hzを最大限に活かすための最適化こそが、ゲーマーにとっての唯一の正解だと。
最高の体験は、細部への気配りから生まれるのです。
GeForce RTX5070 搭載ゲーミングPC おすすめ5選
パソコンショップSEVEN ZEFT R63S


| 【ZEFT R63S スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 7700 8コア/16スレッド 5.30GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | CoolerMaster MasterFrame 600 Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット GIGABYTE製 B850 AORUS ELITE WIFI7 |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55XC


| 【ZEFT Z55XC スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265F 20コア/20スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R61GK


| 【ZEFT R61GK スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 DIGITAL WH |
| マザーボード | AMD X870 チップセット GIGABYTE製 X870M AORUS ELITE WIFI7 ICE |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R61G


| 【ZEFT R61G スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ブラック |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55IR


| 【ZEFT Z55IR スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra5 245KF 14コア/14スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.20GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ブラック |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
配信や動画編集とゲームを同時にこなすときの工夫
配信やゲーム、さらに動画編集まで同時に進めたいと思ったときに大事なのは、派手な数字やカタログスペックに飛びつくことではなく、全体のバランスを整えることだと私は強く感じています。
実際にRTX5070を導入したとき、確かに性能は圧倒的に頼もしかったのですが、その一方でCPUやメモリに余裕がないと全体がぎこちなくなる瞬間が必ず出てきました。
たとえば映像は滑らかに出ているのにソフトの操作がもたつくとか、一度に複数の処理を走らせたときに引っ掛かりが目立つといった具合です。
私は今、Core Ultra 7と組み合わせて配信していますが、この安定感は数字以上の価値があります。
以前の私は、GPU性能を信じすぎてOBS上で配信した際、フレームレートのわずかなブレにストレスを抱えました。
ちょっとした違和感が積もると「やっぱりGPU任せじゃダメか」とうなだれる。
けれどCPUに余裕があれば、その不安はきれいに解消されるのです。
単なるテスト結果ではなく、長時間の利用で安心できるかどうか、それが本当に大切なんだと感じます。
メモリについても同じです。
32GBから64GBに増設したときの違いは、数字以上に気持ちの面で大きかった。
最初は32GBで回していましたが、配信しながらブラウザで資料を開き、さらにPremiereを立ち上げた瞬間に「あ、これは厳しいな」と体感しました。
64GBにしてからはそのストレスが一気に払拭され、快適さの質がまるで変わったのです。
もう戻れません。
ストレージは、私は思い切ってNVMe Gen4の2TBを導入しました。
動画編集をしていると、数十GB単位のデータを何度も読み書きすることになります。
待ち時間が減るだけで驚くほど集中力を保てるのです。
「ストレージは外付けでもいい」という考え方もありますが、私にとっては内蔵の余裕が精神的な余白に直結しました。
たとえば数秒とはいえ待たされるとその間に集中が切れてしまうんです。
職場の作業効率と同じで、やっぱり些細な手間が積み重なるかどうかで大きな差が生まれます。
配信方式に関しても、定石どおり1つに決め打ちするのは危険だと思います。
RTX5070のNVENCは確かに優秀で、GPUエンコードなら負荷をほとんど感じさせません。
ただし同時進行で動画編集をするとなるとCPUに任せた方がうまく回る場合もある。
私は何度も試行錯誤しましたが、結局その場その場で柔軟に切り替えるのが一番でした。
「これ一択でいい」と決めつけない姿勢ですね。
大人の余裕って結局そういうものでしょう。
OBSのシーン切り替えやエフェクトも、最初は見栄えを求めてどんどん盛り込んでいました。
しかし、いざ本番でカクつきを目の当たりにしたときに、視聴者目線で考えるようになったんです。
演出の派手さよりも、滑らかに見てもらえることの方が大事。
だから今では必要最小限に抑えてシンプルな構成にしています。
結果的に処理負荷が軽くなり、私自身も気楽に続けられる環境になりました。
これが一番です。
冷却も見過ごせません。
私は大型の空冷クーラーを選びましたが、その判断にはかなり満足しています。
水冷はパワフルですが、ポンプ音が耳に触るのが気になったのです。
静けさが自分のリズムを守ってくれる。
これは意外に大きな差でした。
ケースのエアフローも重要で、見た目に惹かれてガラスケースを使ったときは、本当に後悔しました。
熱がこもり、GPU温度が急激に上がり、不安定な挙動を繰り返すという悪循環。
そこでファンの配置を徹底的に見直したところ、内部温度が5度下がり、安定性は劇的に改善しました。
そのとき実感しました。
競技性のあるゲームを遊ぶと、その違いはもっとシビアに現れます。
フォートナイトやAPEXのように瞬発力が勝敗を左右する場面では、1フレームの遅延すら致命的です。
RTX5070のReflex 2対応を初めて体感したとき、本当に鳥肌が立ちました。
マウス操作が指先に吸いつくように反映される。
言い過ぎではなく、配信をしながらでも勝負に集中できる余裕をくれるのです。
この快適さは、使う人にしかわからない実感だと思います。
だからこそ、私が辿り着いた答えはこうです。
GPUの力だけに依存せず、CPUとメモリ、ストレージ、さらに冷却とケースの設計にまで心を配ること。
それらを全てバランスさせることが、配信も編集もゲームも同時に満足できる環境をつくる道でした。
RTX5070の性能は確かに強力で軸にはなるけれど、それに寄りかかりすぎると歪みが出る。
むしろ地味に思える構成要素の調和こそが、本当の快適さを支えるのです。
派手な話ではありません。
でも現場で試行錯誤してきた今だから言える。
最強パーツを買えば解決するわけではない。
私はそう信じています。
数字に踊らされず、地道に環境を詰めていく。
そのプロセスこそが配信者として、ゲーマーとして本当に長く楽しむために欠かせないものなのです。
タイトルごとのプリセット調整と細かいチューニング
RTX5070で4Kゲームを最大限に楽しむには、見た目の綺麗さに惹かれてすべての設定を「ウルトラ」にするのはあまり賢い選択ではありません。
最初のうちは派手な映像に感動するのですが、少し長めに遊んでみると細かいフレーム落ちが気になり始めるんです。
私はまさにその罠にはまり、「せっかくのGPUだから最高画質にするしかない」と意気込んで始めたものの、30分ほど経つと妙にカクつく場面にいら立ちを覚えてしまい、結局設定を見直しました。
やっぱり美しさ以上に安定感が大切。
ゲームは眺めるものではなく自分の意思で操作するものですからね。
私が優先して調整するのはレイトレーシングとシャドウ品質です。
この二つを控えると一気にフレームが安定するのを体感しました。
さらにDLSS4を組み合わせると、負荷が軽くなるのに映像の見た目は思いのほか綺麗なまま。
気づけばフレームレートは90近くをキープしており、思わず「お、これなら安心だな」と声に出してしまったほどです。
厄介なのは、ゲームごとに求められる正解が違うこと。
広大なフィールドを探索するオープンワールド系だと木々や遠景の描写がとにかく重い。
一方FPSや対戦ゲームでは映像よりも操作の反応速度がほぼすべてです。
だからReflex2といった機能が効いてくる。
入力遅延を削れるだけで「自分の動きに直結している」と実感できる瞬間があります。
私も一度eスポーツ系を試したとき、画質を犠牲にしてフレームを稼ぐ選択をしたのですが、それが勝敗に響いた感覚は忘れられません。
CPUも無視できません。
私はRyzen 7 9700Xの環境で試したのですが、GPUのパワーだけを信じていたところ、動画編集ソフトを裏で開いたままプレイして処理が急に落ち込み、「しまった」と苦笑いした経験があります。
万能のように見えるゲーミングPCでも、用途を同時進行すれば限界が出る。
これを肌で感じ、タスク管理の大事さを痛感しました。
メモリやストレージの影響も小さくないです。
32GBのDDR5-5600を積んでいれば困ることは少ないですが、テクスチャの大量読み込みでSSDが追いつかず、一瞬だけ止まる感覚が出ることがあるのです。
私は当初Gen4のSSDを使っていましたが、たびたび細かい引っ掛かりに腹立たしさを覚えました。
その後にGen5へ変えたら、正直なところ笑ってしまうくらいスムーズになり「これが本物の快適さなんだな」と納得しました。
ストレージを侮ってはいけない。
グラフィック設定については、遠景描写やポストプロセス効果も効果的な調整ポイント。
例えば遠くの山や街並みをどこまで鮮明に描くかは、気分の問題に近いところがある。
しかしそこにリソースを取られると結局フレームがブレて集中できない。
だからある程度割り切りが必要です。
そして小さな調整の積み重ねが、長く遊んだときに本当に差を生み出す。
印象に残っているのはサイバーパンク系のゲームを遊んだとき。
レイトレーシングで描かれる光と反射が作品の雰囲気を作っていたのでそこは残しましたが、シャドウやリフレクションは少しだけ下げました。
その調整だけで体感は大きく変わった。
80fps前後で安定しながら映像の迫力は失わないバランスが実現した瞬間、心の底から「これだ」と思ったのを覚えています。
小さな工夫で極上の没入感に包まれる、この満足感こそ調整をする意義だと思います。
冷却性能も重要です。
過去にガラスパネル多めのケースを使った際、熱がこもってクロックが下がり結局は設定を落とさざるを得ない経験をしました。
そのときは正直ショックでしたね。
だから今は迷わずエアフロー優先のケースを選んでいます。
冷却と性能は切っても切れない関係にある。
空気の流れが整うだけでパーツが本来の力を出せるようになるわけで、この違いを身をもって知ったことは大きい学びでした。
ここまで色々語りましたが、最終的に確信しているのは「RTX5070で4Kを遊ぶなら、ウルトラ設定に固執しないこと」です。
タイトルごとの特徴を理解し、無駄に重い処理をそぎ落とし、DLSSやReflexといった機能を適切に組み合わせる。
それによって映像の満足感とスムーズな動作を両立できるのです。
少し面倒に感じるかもしれませんが、細かく調整を繰り返して掴んだ快適さは、ただ観賞用に眺める映像では味わえない特別な価値を持っています。
快適なゲーム体験を求めて試行錯誤を重ねた末に辿り着く感覚は格別です。
何となく遊ぶ時間が、かけがえのない楽しみに変わる。
私はそう信じています。
RTX5070に関するよくある疑問と答え
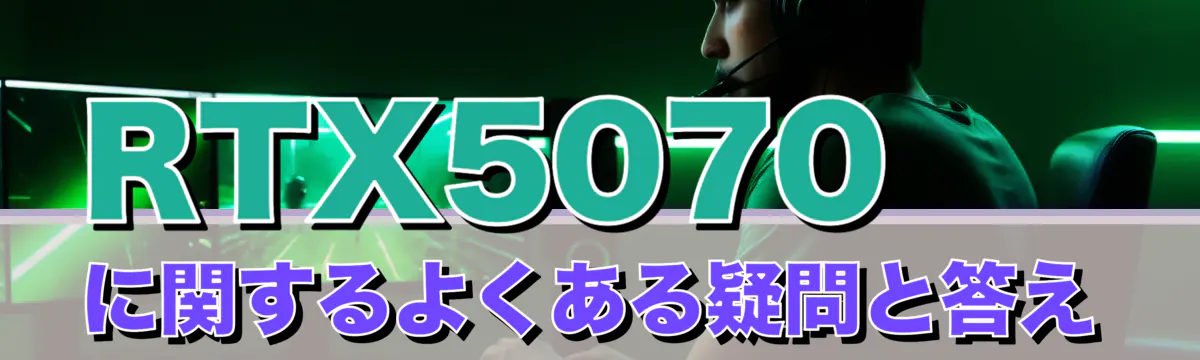
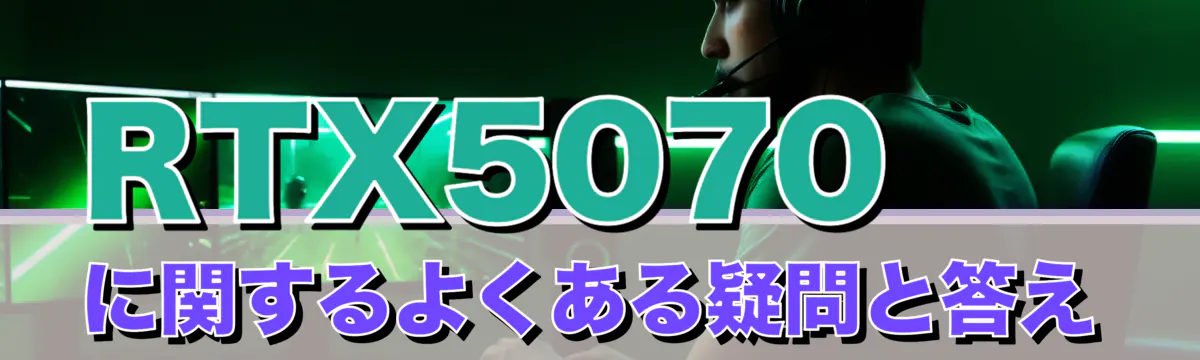
RTX5070で4K144Hzはどこまで現実的?
RTX5070を実際に手にして使い込んでみて、私が率直に思ったのは「4K解像度で144Hzを目指すのは完全に夢物語ではない」ということでした。
もちろんタイトルを選んだり、設定を最適化したりといった配慮は欠かせませんが、それでも現実的に実行できるレベルにまで技術が進んできたのだと感心しました。
特にDLSS4をオンにした瞬間の映像のなめらかさには強い印象を受け、思わず「お、これはいけるな」と一人で口にしてしまったこともよく覚えています。
単なるベンチマークの数値以上に、自分の目と感覚で体験する映像の質が確かに変わったと実感できたのです。
とはいえ現実は理想通りにはいきません。
特に重量級のタイトルでレイトレーシングをふんだんに使ったとき、光の表現が美しすぎて思わず見入ってしまったものの、その直後にフレームレートが60fps台まで下がり「これは厳しいな」と思わず苦笑したこともありました。
やはり技術の進歩と同時に、負荷の高さもまた進化しているのだと痛感させられます。
そんなときDLSS4を有効にすると空気が一変します。
平均120fpsを超えるまで数字が戻ってきて、映像が再びスムーズさを取り戻す。
その瞬間には「これだよ、これなんだよ」とうなずきながらコントローラーを握り直しました。
アップスケーリング特有の少し硬い印象も最初はありましたが、数分プレイしているうちに自然に馴染んでしまい、違和感はすぐに薄れていきました。
つまりDLSSは見た目の美しさと快適な操作感の橋渡し役であり、その恩恵は絶大だと身をもって感じています。
一方、eスポーツ系タイトルや最適化が進んでいる軽量なゲームでは状況は一気に楽になります。
RTX5070単体でも4Kで100fpsを軽く超え、DLSSを組み合わせれば144Hzでのプレイが狙えるのです。
実際に試してみたとき、その滑らかさは本当に衝撃的で思わず「これはすごい」と口に出してしまったほどでした。
G-SYNC対応のモニターをつなぐとさらに違いが際立ち、110fps前後しか出ていない状態でもカクつきが吸収され、滑らかさが維持されます。
さらに重要なのは設定の工夫です。
影や反射の品質を少し控える。
ボリューメトリックの効果をオフにしてみる。
アンチエイリアスはDLSSに委ねる。
こういった一見地味な調整が、画質と滑らかさを両立させる現実的な道筋になります。
昔のように「画質を取るか、フレームレートを取るか」の二者択一に悩む時代は終わったなと感じました。
今は数分の調整で環境を一変できる。
これはユーザーにとって安心できる力強い要素ですし、「自分で最適解を導ける」という実感を持てるのは大きな強みだと思います。
私の試験環境はCPUにCore Ultra 7 265Kを搭載したマシンでした。
CPUがボトルネックとならず、GPUの実力を存分に発揮できる環境が整っている。
これがどれほど快適さにつながるかは、ゲームを長時間続けてみるとすぐにわかります。
「CPUをケチらなくてよかった」と心底思った瞬間でした。
もちろんどんなタイトルでも完全なネイティブ4K144Hzを維持するのは、まだ難しいのも事実です。
最新の重量級タイトルでは特に顕著で、選択と工夫が不可欠になります。
しかしDLSS4を中心とする技術が助けてくれるおかげで、もはや実用域に達しているというのが私の実感です。
過去世代と比較すると映像体験の質は明らかに次元が違い、4Kの迫力と144Hzのなめらかさを同時に手に入れられるこの状況は、ゲーマーにとって夢のようです。
なにより感情を動かされたのは、体験そのものの豊かさでした。
以前の私は「解像度か、滑らかさか」と必ずどこかで譲歩するしかありませんでした。
しかし、RTX5070を手にしてからはその壁を乗り越えられることに驚きと喜びを覚えています。
多少の調整は必要ですが、結果的に144Hzの快適さと4Kの美しさを同時に味わえる。
極上の映像体験。
そう呼びたくなるほどです。
私にとって、これは単なるハードの性能評価を超えた手触りのある体験でした。
このカードを基盤にした環境なら、重量級のタイトルも軽量なeスポーツも幅広くカバーできる。
だからこそ私は「RTX5070で4K144Hzは十分現実的だ」と自信を持って言えます。
それこそが私の結論です。
モニター側の最新技術とも噛み合えば、快適さはさらに高まり、プレイするたびに新鮮な喜びを与えてくれます。
これほどまでに機材選びが直接的に体験を変えるものかと改めて痛感しました。
技術の進歩。
私が長年追いかけてきたPCゲーミングの世界では、夢だったことが次第に現実に変わっていきます。
だからこそ、これから先に試せる新しい環境に胸が高鳴って仕方がありません。
挑戦する楽しみ。
冷却強化は本当に必要?空冷でも安心できるか
この点については多くの方が気になると思います。
私も購入を検討していた頃には同じ不安を抱えていました。
高性能になった分、きっと冷却も今まで以上に気を使わなければならないのではないか。
ですが結論から言えば、空冷でも十分に安定した環境は作れます。
無理に水冷にこだわる必要はありません。
最初に実測したときは拍子抜けしましたよ。
「これなら何の不安もないじゃないか」と思わず声が出ました。
正直に言えば、冷却を強化しようと水冷まで導入するよりも、ケースの空気の流れを整えることの方が現実的で有効でした。
これが私にとっての大きな気づきです。
水冷を悪く言うつもりはありません。
その静音性や見た目のスタイリッシュさは確かに魅力的です。
ガラスパネルのケースなんて、そこに水冷を組み合わせれば、まるで展示品のような格好良さになる。
それは一つの完成形です。
ただメンテナンスや取り付けの手間を考えると、誰にでも気軽にすすめられるものではありません。
堅実な構成。
私が心からそう感じた場面がいくつもあります。
たとえば重量級タイトルを配信しながら同時に動画編集まで走らせたときです。
GPUもCPUも常時高回転の状況でしたが、それでも空冷とファンの配置だけで温度は安定。
むしろ「空冷ってここまで戦えるのか」と感心したほどです。
この驚きは今でも鮮明に残っています。
確かにSSDのような別の部品を考えると、高速化したPCIe Gen.5 SSDなどは専用の冷却が必要になるケースもあります。
しかしこれは例外的な話であって、ことGPUやCPUに関しては世代を重ねるごとに電力効率も改善されてきました。
それなのに冷却への過度な不安ばかりが膨らんで、一人歩きしてしまっているようにも思えるのです。
私の体感として、最も効果的に温度を安定させたのはフロントからきちんと空気を吸い込み、リアやトップからきれいに吐き出すというごく当たり前の工夫でした。
技術雑誌に載っている定石かもしれませんが、実際に自分のマシンで試してみるとびっくりするほど効果が出ました。
そのときは思わず「なるほど、冷却って理屈より実践だな」と唸りましたよ。
ある日の体験は忘れられません。
BTOショップで購入した標準仕様のPCを引き取ってきて、半信半疑で4Kゲームを数時間プレイしてみたときのことです。
てっきり温度が跳ね上がると思っていました。
ところがGPU温度は最後まで安定。
拍子抜けどころか、今までの自分の不安が過剰だったと気づかされました。
その瞬間に「水冷じゃなきゃダメ」という固定観念が崩れたのです。
実際の体験でしか得られない納得感がありました。
最近のガラスパネルケースの流行についても考えさせられました。
見た目は本当に格好良い。
デスクに置いて仕事場を彩るにも最適です。
ただ空気の抜けが悪くて熱がこもりやすいのが難点なんですよね。
そこで追加のファンを数基つけただけでGPUの発熱問題は大きく改善しました。
小さなコストと時間で得られる変化が、ここまで大きいとは予想していませんでした。
この事実は私の考えをはっきり変えてくれましたね。
時々、「どうせなら最初から水冷でいこう」と割り切る人もいます。
その潔さも理解できます。
ですが少なくとも冷却性能に限って言うなら、空冷環境で十分。
それに水冷のポンプやチューブの寿命を考えると、管理コストの面でも空冷の方が安心できます。
長く付き合うパートナーとして考えれば、無理のない選択こそ結果的に賢い判断になるのです。
落ち着いた運用。
RTX5070の性能を活かすために、大げさな冷却を必須と思い込む必要はありません。
きちんとした空冷クーラーと適切なファン配置。
その実感があるからこそ、私は水冷を「冷却のために必須」と考える必要はないと断言できます。
最終的に大事なのは、合理性です。
冷却にだけ目を奪われすぎず、全体をバランスよく構成すること。
静音性や外観重視なら水冷を選べばいい。
ただ冷却性能そのものに関しては、空冷こそが実用的で堅実な答えです。
私は胸を張ってそう言えます。
無駄を省き、安心と安定を両立する。
それがRTX5070を使う最も現実的な構築方法だと確信しています。
GeForce RTX5070 搭載ゲーミングPC おすすめ5選
パソコンショップSEVEN ZEFT R66J


| 【ZEFT R66J スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 7700 8コア/16スレッド 5.30GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | DeepCool CH170 PLUS Black |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R62L


| 【ZEFT R62L スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z59Q


| 【ZEFT Z59Q スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265K 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Corsair FRAME 4000D RS ARGB Black |
| CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ Corsair製 水冷CPUクーラー NAUTILUS 360 RS ARGB Black |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 1000W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Corsair製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60YL


| 【ZEFT R60YL スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen5 8500G 6コア/12スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.50GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55IG


| 【ZEFT Z55IG スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265F 20コア/20スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
これから買うならBTOと自作、どっちがコスパ良い?
RTX5070を中心にゲーミングPCを考えたとき、私はやはり現状ではBTOの完成品を選ぶほうが費用対効果に優れていると感じています。
単純にパーツを個別に揃えて組み上げようとすると、どうしても総額が膨らみますし、メーカーや販売店が大口仕入れで得る価格には太刀打ちできません。
そのうえ保証やサポートまで付随するのですから、冷静にコストと安心感を秤にかけると、BTOの選択は非常に合理的なのです。
特に仕事の忙しさで時間が限られている人にとっては、購入してすぐに安定的に稼働するというメリットがありがたいものです。
とはいえ、私は過去に何度も自作をしてきた経験があり、パーツを吟味しながら一つずつ組み立てる工程の楽しさや、完成した瞬間の達成感を知っている人間です。
だからこそ、自作の魅力を簡単に切り捨てる気にはなれません。
実際にRTX5070をベースに構成を考えた際、BTOではメモリの容量が固定されていたり、SSDの規格が限られていたりと、自由度に物足りなさを感じました。
一方で自作なら、自分の用途に応じてMicron製のDDR5メモリを積み、発熱対策として次世代のSSDに放熱性能の高いヒートシンクを取り付けることができる。
そうした一つひとつの選択が快適な環境につながるので、その自由度自体が大きな価値に思えて仕方ないのです。
やっぱり心が踊るんですよ。
ただ、BTOにも十分な魅力があるのは確かです。
私は以前、RTX5070を搭載したBTOモデルを購入したことがあります。
価格も納得できるもので、実際の使用感も悪くありませんでした。
ところが使っていく中で、ケースがやや簡素でガラスパネルの排熱性が弱く、「長時間のゲームプレイで温度が上がるんじゃないか」と不安になったのも事実です。
その経験から、冷却効率という視点では自作による工夫の余地が大きいと痛感しました。
だからこそ、コストと設計の自由度をどちらに比重を置くかは、利用者それぞれの考え方に尽きます。
悩ましい選択です。
多くても1万円ほどの差であれば、自分の意志で組み上げた分の満足感が得られる。
これは単なる機械的な価格の比較に収まらない部分です。
苦労も含めて楽しいと感じられるのが自作の魅力で、それはアウトドアやキャンプにも似ています。
準備や片付けが面倒でも、その過程を経ることで思い出深い体験になる。
自作PCも同じで、工程そのものが自分の中に刻まれるんです。
この実感は、お金に換算しにくい豊かさだと思います。
もちろん性能を重視して冷静に見れば、BTOの完成度は高いです。
RTX5070にRyzen 7やCore Ultra 7を組み合わせ、32GBメモリと1TBのNVMe SSDが標準で実装された製品が普通に流通している以上、買ったその日から4K解像度での最新ゲームも快適に楽しめる。
迷う必要がないというのは大きなメリットですね。
そして何か問題が発生した場合に保証やサポートを頼れる安心感。
これは家庭で長期的に一台を維持したい人にとって非常に心強いと思います。
私はそこにBTOの大きな強みを感じています。
一方で、自作を選ぶ意味合いが一番強く出てくるのは、拡張性や将来性だと考えています。
RTX5070を起点としながらも、数年後にRTX5070Tiやさらに新しい世代のGPUに差し替えることを想定して、余裕のある電源ユニットや広いケースを準備しておく。
これは自作だからこそできる計画です。
BTOだと購入した時点で仕様が固定されてしまいやすく、後からアップグレードしたくなった時に電源容量が足りないとか、ケースに物理的に収まらないといった問題が発生しやすいのです。
私はここで自作に軍配を上げます。
未来への余裕を最初から仕込んでおける安心感は大きいものです。
最近では、PCをあえてインテリアとして楽しむ潮流も見えます。
これも自作ならではですね。
部屋に置いたときに「ああ、自分のこだわりがこの空間に溶け込んでいる」と実感できる。
万人受けを狙ったBTOには難しい部分です。
見せる楽しみ。
これは大きい。
結局のところ、短期的にコストと性能を両立させたいならBTOを選んだほうが合理的でしょう。
逆に、数年先までの拡張やカスタムを楽しみたい人間にとっては自作が有効な答えになります。
私自身は次にRTX5070を基盤に組むとしたら、まずは効率的にBTOで環境を揃え、数年先にアップデートを見据えるタイミングで自作に切り替える可能性を考えています。
その併用こそが、私にとって現実的で長く楽しめる最適解です。
どちらかに固執しすぎず、目的や時期に応じて柔軟に選ぶ。
この発想が大事だと強く感じているのです。
自分の時間の使い方、生き方そのものが反映される。
ゲーム用SSDは何TBくらいあると不安がないか
特にRTX5070クラスで4Kプレイを狙うなら、1TBではどうにもならない。
最近のゲームタイトルは平気で100GBを超え、その上で追加のアップデートや高解像度のテクスチャを入れると、あっという間に空き容量は消えてなくなります。
私も過去に1TBで済むかと甘く考えて組んだことがありましたが、結局インストールと削除を繰り返す羽目になって、そのたびにイライラが募りました。
これは決して大げさではなく、2TBあれば大型タイトルを複数同時にインストールしておいて、なおかつ録画やスクリーンショットも保存できる余裕が生まれます。
余裕というのは不思議なもので、ただのストレージ容量の話以上に、プレイしているときの安心感につながるんですよね。
「ゲームを消さないと新作を入れられない」という小さなストレスがないこと、これがどれほど快適か。
こうした余裕を持つことこそが、自作PCの醍醐味なんだと私はつくづく感じます。
一方で1TBはどう考えても今では試し撃ちレベルです。
小規模タイトル中心に遊ぶならギリギリ成立するかもしれませんが、本気でRTX5070を活かして遊ぶとなれば窮屈すぎる。
容量計算を気にしながらゲームするのは本来の楽しさを損なうと思います。
正直、私はもう二度と1TBでは組まないと心に決めてますね。
さらに踏み込むなら、動画編集や配信を見据えている人は4TBも選択肢に入れるべきです。
私自身、以前2TBで配信アーカイブや録画ファイルを残していたときに限界を迎え、泣く泣く外付けHDDに逃したことがありました。
あのときは本当にストレスで、データをどこに置くかで時間を無駄にする自分に腹が立ちました。
その後思い切って4TBを積んだら、ようやく肩の力を抜いて作業もプレイもできるようになったんです。
あの解放感、忘れられません。
ストレージはもちろん容量だけではありません。
速度も大事です。
私はPCIe Gen4のSSDを愛用していますが、正直これで十分です。
ロード時間が短縮されることによって、ゲームに入るまでの待ち時間がほぼストレスフリーになります。
Gen5は確かに桁外れの速度ですが、発熱がすさまじい。
私も実際に試したとき、大きなヒートシンクや補助ファンが必要になり、ケース内は騒がしくなるし見た目もごつくなるしで、正直やりすぎ感がありました。
だから私は、今はまだGen4でいいと考えています。
また、大容量なら「あとから増設すればいい」と軽く考えてしまうことが多いですが、それが落とし穴です。
いざケースを開けてみると、M.2スロットが埋まっている、グラボと干渉して物理的に取り付けられない、ケーブルの取り回しが厄介で熱対策も難しい。
こうした制約は必ず出てきます。
だからこそ最初から余裕ある容量を積むほうが、あとで頭を抱えずに済むんです。
この考えに至るまでに、私は何度も苦い経験をしました。
市場の傾向を見ても、多くの人が行きつく答えは同じです。
主流は2TB、次いで1TB、さらに余裕を考えて4TB。
裏を返せば、人々は実際に「1TBでは足りない」という現実を体験し、それをもとに判断しているということです。
私もその一人です。
RTX5070で4Kゲームを楽しむなら最低でも2TB、さらに配信や制作も見据えるなら4TB。
これが最も後悔しない選び方です。
本来はゲームそのものを楽しむために組むPCですからね。
余計な心配はしないでいい。
好きなときに好きなゲームを始められる。
これがゲーミングPCの最大の魅力なんだと思います。
そしてその幸せを左右するのが、意外にもSSD容量なんです。
だから私はこれからも、2TBを基準に、必要なら迷わず4TBを選びます。
それが一番自然で、一番快適で、一番幸せになれる道だと信じてます。
安心感。
この感覚には代えがたい価値があります。
だからこそ、もし「どの容量にしようか」と悩んでいる方がいれば、私は強くこう伝えたいです。
迷うくらいなら余裕を持っておいたほうが絶対にいい。
これが私が何度も実感してきた揺るぎない結論です。
RTX5070Tiとの違いが購入判断に与える影響
パソコンのパーツを選ぶときに一番迷うのは、結局どれくらい先を見据えて投資するかという点だと、私はいつも感じています。
結果から言うと、5070を選べば日常的な使い方や多くのゲームプレイでは十分満足できるのですが、4Kや数年先のタイトルまで見据えるなら5070Tiにも確実な魅力があります。
つまり自分が何を重視するかで最終判断は変わるということです。
5070が搭載している12GBのVRAMは、いま主流となっているフルHDからWQHDまでの解像度ではほとんど困ることがありません。
正直、最初に使ってみたときは「おっ、これでいいじゃないか」と肩の力が抜けるほど快適でした。
大作タイトルでも、DLSSを使えば違和感のない映像でサクサク動いてしまうのです。
この瞬間はちょっと感動しましたね。
ただ、興味本位で4K設定に変えてみたときに現実を思い知らされました。
街並みやキャラクターが多く登場する場面では負荷が一気に高まり、描画が不安定になる。
数値で見ればフレームレートが安定している、という冷たい表現になりますが、実際には「遊んでいてストレスがないかどうか」という温度感のある違いになって表れる。
まさに安心感の差。
5070Tiの16GBのVRAMには、この安心感を買う価値があると強く感じました。
長時間プレイで少しのカクつきが気持ちを削ぎ、没入感まで奪ってしまうことを考えると、安定した描画環境が欲しい。
この気持ちは、ゲームという趣味にどれだけ腰を据えて付き合うのかを自問させてきます。
とはいえ価格を考えれば話は変わります。
5070であれば性能とコストの釣り合いがかなり良い。
余った予算をCPUやメモリに回すことで、システム全体の快適性をさらに伸ばすことができます。
これが現実的なバランス感覚だと実感しています。
昨年注目を集めたAAAタイトルを例にすれば、5070でも高設定+DLSSを使えば平均80fps前後を叩き出します。
一方で5070Tiならネイティブ寄りの設定で100fps付近を維持できます。
もし配信や動画撮影も兼ねて遊ぶスタイルであれば、この差は大きな価値になります。
ただ、自分一人で遊ぶだけなら80fpsでまったく不満は感じませんでした。
基準って人によって本当に変わるものだな、とそこで気づかされたわけです。
CPUやメモリとの兼ね合いも忘れられません。
5070Tiの性能を存分に引き出すには、Core UltraやRyzen 7クラス以上のCPUが必須で、メモリも32GBは欲しくなります。
さらに電源容量や冷却性能、ケース内部のエアフローまで考える必要が出てくる。
正直、気軽には踏み込めない領域です。
私の気持ちを整理すると、普段の使い方からすれば5070でほぼ間違いなく満足できます。
けれども「将来を見据えて今から余裕を持っておく」という考えも無視できません。
人間らしい矛盾、ですね。
堅実さか、将来性か。
この二択が常に頭を離れません。
5070を選んで浮いた予算はデスクやモニター環境に回せて、仕事にも生活にも恩恵がある。
だから実用的に考えるなら5070がベストバランスの答えになる。
けれど、心のどこかで「いつか限界を感じるのではないか?」という不安がつきまとうのです。
5070Tiという選択は、その不安を先回りして解決してくれる保険のようなもの。
もし後悔したくないなら、自分がゲームをどう楽しむのかを具体的にイメージすることが大事だと、この比較を通じて痛感しました。
そうすると自然に「自分にはどちらが合うか」が見えてきます。
最終的な答えを言えば今の私には5070がちょうどいい。
でも、余裕を買いたいと考える人にとって5070Tiは強力な選択肢です。
二つのカードが示すのは単なる性能差ではなく、自分の価値観と考え方の投影。
その事実を今回あらためて学びました。
悩ましい二択。
人気PCゲームタイトル一覧
| ゲームタイトル | 発売日 | 推奨スペック | 公式 URL |
Steam URL |
|---|---|---|---|---|
| Street Fighter 6 / ストリートファイター6 | 2023/06/02 | プロセッサー: Core i7 8700 / Ryzen 5 3600
グラフィック: RTX2070 / Radeon RX 5700XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Monster Hunter Wilds
/ モンスターハンターワイルズ |
2025/02/28 | プロセッサー:Core i5-11600K / Ryzen 5 3600X
グラフィック: GeForce RTX 2070/ RTX 4060 / Radeon RX 6700XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Apex Legends
/ エーペックスレジェンズ |
2020/11/05 | プロセッサー: Ryzen 5 / Core i5
グラフィック: Radeon R9 290/ GeForce GTX 970 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| ロマンシング サガ2
リベンジオブザセブン |
2024/10/25 | プロセッサー: Core i5-6400 / Ryzen 5 1400
グラフィック:GeForce GTX 1060 / Radeon RX 570 メモリ: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| 黒神話:悟空 | 2024/08/20 | プロセッサー: Core i7-9700 / Ryzen 5 5500
グラフィック: GeForce RTX 2060 / Radeon RX 5700 XT / Arc A750 |
公式 | steam |
| メタファー:リファンタジオ | 2024/10/11 | プロセッサー: Core i5-7600 / Ryzen 5 2600
グラフィック:GeForce GTX 970 / Radeon RX 480 / Arc A380 メモリ: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| Call of Duty: Black Ops 6 | 2024/10/25 | プロセッサー:Core i7-6700K / Ryzen 5 1600X
グラフィック: GeForce RTX 3060 / GTX 1080Ti / Radeon RX 6600XT メモリー: 12 GB RAM |
公式 | steam |
| ドラゴンボール Sparking! ZERO | 2024/10/11 | プロセッサー: Core i7-9700K / Ryzen 5 3600
グラフィック:GeForce RTX 2060 / Radeon RX Vega 64 メモリ: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE | 2024/06/21 | プロセッサー: Core i7-8700K / Ryzen 5 3600X
グラフィック: GeForce GTX 1070 / RADEON RX VEGA 56 メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ファイナルファンタジーXIV
黄金のレガシー |
2024/07/02 | プロセッサー: Core i7-9700
グラフィック: GeForce RTX 2060 / Radeon RX 5600 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Cities: Skylines II | 2023/10/25 | プロセッサー:Core i5-12600K / Ryzen 7 5800X
グラフィック: GeForce RTX 3080 | RadeonRX 6800 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ドラゴンズドグマ 2 | 2024/03/21 | プロセッサー: Core i7-10700 / Ryzen 5 3600X
グラフィック GeForce RTX 2080 / Radeon RX 6700 メモリー: 16 GB |
公式 | steam |
| サイバーパンク2077:仮初めの自由 | 2023/09/26 | プロセッサー: Core i7-12700 / Ryzen 7 7800X3D
グラフィック: GeForce RTX 2060 SUPER / Radeon RX 5700 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ホグワーツ・レガシー | 2023/02/11 | プロセッサー: Core i7-8700 / Ryzen 5 3600
グラフィック: GeForce 1080 Ti / Radeon RX 5700 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| TEKKEN 8 / 鉄拳8 | 2024/01/26 | プロセッサー: Core i7-7700K / Ryzen 5 2600
グラフィック: GeForce RTX 2070/ Radeon RX 5700 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Palworld / パルワールド | 2024/01/19 | プロセッサー: Core i9-9900K
グラフィック: GeForce RTX 2070 メモリー: 32 GB RAM |
公式 | steam |
| オーバーウォッチ 2 | 2023/08/11 | プロセッサー:Core i7 / Ryzen 5
グラフィック: GeForce GTX 1060 / Radeon RX 6400 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| Monster Hunter RISE: Sunbreak
/ モンスターハンターライズ:サンブレイク |
2022/01/13 | プロセッサー:Core i5-4460 / AMD FX-8300
グラフィック: GeForce GTX 1060 / Radeon RX 570 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| BIOHAZARD RE:4 | 2023/03/24 | プロセッサー: Ryzen 5 3600 / Core i7 8700
グラフィック: Radeon RX 5700 / GeForce GTX 1070 メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| デッドバイデイライト | 2016/06/15 | プロセッサー: Core i3 / AMD FX-8300
グラフィック: 4GB VRAM以上 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| Forza Horizon 5 | 2021/11/09 | プロセッサー: Core i5-8400 / Ryzen 5 1500X
グラフィック: GTX 1070 / Radeon RX 590 メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |