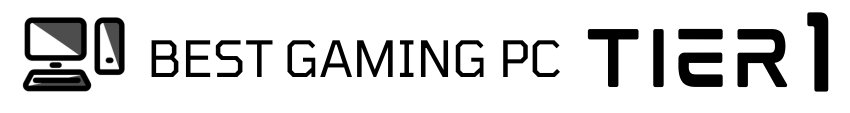Apex Legends を快適に遊ぶためのゲーミングPC推奨スペックまとめ

フルHDで遊ぶときに気をつけたいCPU選びのポイント
Apex LegendsをフルHDで気持ちよくプレイしたいなら、正直に言って「CPUは軽視できない」と心から思っています。
GPUの性能が重要なのは言うまでもありませんが、それだけではどうにもならない場面があるという現実を、私は何度も体験してきました。
高リフレッシュレートを本気で狙うなら、CPUの処理力がものを言う。
その差が勝負を決める瞬間に直結するのです。
多くの人がフルHDならGPU性能がすべて、と考えがちですが、Apex Legendsはゲーム画面を描くだけでなくサーバーとの同期や物理計算、想定外の一時的な処理負荷といった複雑な要素が絡んできます。
そのため、CPUにはシングルコアの瞬発力もマルチコアの並列処理力も求められる。
GPUが優秀でもCPUがついてこないと、フレームタイムが乱れて一瞬カクっと止まるわけです。
その一瞬が命取り。
FPSではそれで負けが決まってしまうことだってあるのです。
私はかつてRyzen 5からRyzen 7に切り替えた経験がありますが、あのときは本当に驚きました。
GPUは変えていないのに、敵の動きが格段に追いやすく、撃ち合いの精度がはっきりと上がった。
買い替えの翌日にはすぐに成果が出たんです。
あの時の高揚感は今も忘れていません。
大人数が入り乱れる戦闘やスキルエフェクトが重なる状況でも、以前のようなもたつきが消え、スムーズに動き続ける。
今の世代で言えば、IntelならCore Ultra 5やAMDのRyzen 5でも動かせなくはありません。
ですが、私の実感としてはそれらの「中位モデル」ではどうしても大事な場面で乱れが出やすいと感じます。
Apexは負荷が急に上振れするゲームですから、ワンランク上げてCore Ultra 7 265KやRyzen 7 9700Xクラスを選んでおいた方がいい。
240Hzモニターを本気で使い切りたいのであれば、迷わずそうした方が賢明です。
勝ちたいならここは妥協してはいけない。
もちろんGPUとの組み合わせも忘れてはいけません。
もしCPUが足を引っ張れば、GPUは力を出し切れない。
せっかくの高性能GPUが宝の持ち腐れになる。
私も過去にこのミスマッチをやらかして、思いきり後悔しました。
痛恨の経験でしたね。
それだけではなく、冷却環境も非常に重要です。
どれだけ性能の良いCPUを選んでも、温度が上がればクロックダウンして力を出せなくなる。
私は以前、手頃な空冷クーラーで十分だろうと考えていました。
でも真夏の夜、長時間遊んでいると突然フレームが不安定になり、モヤモヤ感が残ることが増えたのです。
疑問に思ってクーラーを上位の水冷モデルに替えたら、まるで別のマシンかと思うほどの安定感。
これでやっと本来の性能が引き出せるのかと実感しました。
温度管理を侮ってはいけない。
144Hzモニターなら多少の落ち込みはカバーできますが、240Hzモニターを狙うなら冷却強化は必須だと確信しています。
240mmクラスの簡易水冷や実績ある大型空冷ファンを用意することで、長時間の高負荷プレイにも安心して臨めます。
FPSは一瞬のラグが戦局を左右する世界。
冷却は単なる静音や寿命対策ではなく、勝利のための投資なのです。
Apex LegendsをフルHDで長期間快適に楽しむためには、「もう少し背伸びしたCPU選び」が正解だということです。
ミドルレンジではなく、ミドルハイクラス。
例えばCore Ultra 7 265KやRyzen 7 9700Xを選んでおけば、高リフレッシュレートのゲームプレイを現実的に支えてくれますし、数年先まで使い続けられる安心感がある。
GPUとCPU両方をバランス良く揃えることが、ゲーム体験のクオリティを一段引き上げてくれるわけです。
私はこれまでの経験を振り返って、CPUを「影の存在」だとはもう思いません。
確かに見た目は地味で、GPUのような派手さもない。
それでもゲーム全体を底から支える縁の下の力持ち。
CPUの選び方ひとつで、フレームレートの安定感も勝率も変わってしまう。
だからあえて強い言葉を使います。
CPU選びを甘く見るな。
GPUだけで判断するのは危険です。
そう願うなら、CPUに本気で投資するべきです。
これは単なる理屈ではなく、私自身が積み重ねてきた体験から導き出した答えです。
CPUが土台。
GPUが華。
最新CPU性能一覧
| 型番 | コア数 | スレッド数 | 定格クロック | 最大クロック | Cineスコア Multi |
Cineスコア Single |
公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 9 285K | 24 | 24 | 3.20GHz | 5.70GHz | 43230 | 2437 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 42982 | 2243 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X3D | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 42009 | 2234 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900K | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.00GHz | 41300 | 2331 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X | 16 | 32 | 4.50GHz | 5.70GHz | 38757 | 2054 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X3D | 16 | 32 | 4.20GHz | 5.70GHz | 38681 | 2026 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265K | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37442 | 2329 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265KF | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37442 | 2329 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 9 285 | 24 | 24 | 2.50GHz | 5.60GHz | 35805 | 2172 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700K | 20 | 28 | 3.40GHz | 5.60GHz | 35664 | 2209 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900 | 24 | 32 | 2.00GHz | 5.80GHz | 33907 | 2183 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.60GHz | 33045 | 2212 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700 | 20 | 28 | 2.10GHz | 5.40GHz | 32676 | 2078 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X3D | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.50GHz | 32565 | 2168 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7900X | 12 | 24 | 4.70GHz | 5.60GHz | 29382 | 2017 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265 | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28665 | 2132 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265F | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28665 | 2132 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245K | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25561 | 0 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245KF | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25561 | 2150 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9700X | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.50GHz | 23187 | 2187 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9800X3D | 8 | 16 | 4.70GHz | 5.40GHz | 23175 | 2068 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 235 | 14 | 14 | 3.40GHz | 5.00GHz | 20946 | 1838 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7700 | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.30GHz | 19590 | 1915 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7800X3D | 8 | 16 | 4.50GHz | 5.40GHz | 17808 | 1795 | 公式 | 価格 |
| Core i5-14400 | 10 | 16 | 2.50GHz | 4.70GHz | 16115 | 1758 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 5 7600X | 6 | 12 | 4.70GHz | 5.30GHz | 15354 | 1959 | 公式 | 価格 |
144Hz以上を出したい人向けのグラボ選び比較
Apex Legendsを高リフレッシュレート環境で遊ぶ際に本当に差を生むのは、やはりグラフィックボードです。
CPUやメモリがどれほど高性能でも、最終的に画面へ映像を出力しているのはGPUですから、ここで不足があればフレームレートは必ず頭打ちになります。
ゲームの快適さを決める分岐点はこの一点にあると、私は強く感じています。
私自身がまず人に薦めたいモデルはRTX5060Tiです。
フルHD環境で144Hzを狙ううえで、コストパフォーマンスの良さと安定感が両立している点は大きな魅力ですし、実際に一日中ランクマッチを回しても温度が上がりすぎることなく、電源に余計な負荷もかからなかったのは安心材料でした。
特に撃ち合いの場面でマウスの入力が即座に反映される瞬間は格別で、「よし、勝負に集中できる」と思えたのを、今でも鮮明に覚えています。
ただ、解像度をWQHDに広げ、なおかつ144Hzを安定的に確保したいとなるとRTX5070やRadeon RX9070XTといった一段上のクラスが現実的です。
実際に大会映像を見ても、240Hzモニターを前提にした選手構成が当たり前になっている場面も多く、やはり勝負の世界では「GPUこそ盤石さの象徴なんだ」と痛感させられます。
激しい描画負荷でもfpsが崩れないかどうか、その信頼性を選手たちは頼みにしているわけです。
さらに上を目指して240Hz環境を作るなら、RTX5070Tiを選ぶことになります。
Reflex 2の効果による入力遅延の削減は無視できず、撃ち合いの勝敗をコンマ数秒で決めるApexにおいては、価格差以上の大きな武器になります。
「ここぞという場面で少しでも優位に立ちたい」この欲求は、決してスペック表や宣伝文では伝わらない部分です。
プレイヤーとしてその場に立っていると、投資の意味がはっきりと見えるのです。
とはいえ現実的な選択肢として、画質をやや落とせばRTX5060Tiでも144Hz環境は成立します。
しかし最終安置の混戦やエフェクトが集中する瞬間、フレームが落ち込むことの怖さは想像以上で、たとえ一瞬でも動きに鈍さを感じれば勝負を落としかねません。
だからこそ「リスクを避けるために多少贅沢をする」ことが合理的に思えてしまう。
安心を買うかどうか、その差が実感の大きな違いです。
Radeonにも好感触を得た経験があります。
RX9060XTを短期間レンタルで試した際、以前は気になっていたドライバ面の不安定さが改良されているのを体感しました。
FSR4のアップスケーリングもなめらかに効き、1080p環境では「この価格でここまでできるなら十分だな」と素直に思いました。
レイトレーシング性能などはやや控えめですが、Apexをプレイする限り不要な贅沢というだけで、ネックにはならなかったのです。
落ち着き。
もしWQHDや240Hzといった上位環境を目指すなら、現実的な落とし所はやはりRTX5070やRX9070XTです。
もちろん4Kやさらにハイエンドの環境を望むなら別のクラスが必要ですが、144Hzをゲームの基準に据えるならこの辺りが分岐点になります。
性能と価格の折り合いが取れるのはここまでだと、実際に構成を考えたとき私も納得しました。
となると最終的な答えはシンプルです。
フルHDで144HzだけならRTX5060Ti。
一方でWQHD以上での144HzならRTX5070。
そして240Hzクラスを求めるならRTX5070Ti。
これが私の判断です。
もちろん「もっと上を」と考え出すとキリがありません。
でも、自分がどの解像度を基準にするか、そしてどこまで勝負にこだわるか、その軸をはっきりさせれば最適な選択肢は自然と見えてきます。
妥協するのか投資するのか、自分にとっての優先順位が浮き彫りになっていくのです。
パソコンは単なる道具ではなく、勝負の緊張感を支えてくれる支柱です。
だからこそ、信じることができるパーツを選んでおく。
それがプレイヤーにとって最大の準備になるのだと思います。
最新グラフィックボード(VGA)性能一覧
| GPU型番 | VRAM | 3DMarkスコア TimeSpy |
3DMarkスコア FireStrike |
TGP | 公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | 32GB | 48879 | 100725 | 575W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5080 | 16GB | 32275 | 77147 | 360W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9070 XT | 16GB | 30269 | 65968 | 304W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7900 XTX | 24GB | 30192 | 72554 | 355W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5070 Ti | 16GB | 27268 | 68111 | 300W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9070 | 16GB | 26609 | 59524 | 220W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5070 | 12GB | 22035 | 56127 | 250W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7800 XT | 16GB | 19996 | 49884 | 263W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 16GB | 16625 | 38905 | 145W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 16GB | 16056 | 37747 | 180W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 8GB | 15918 | 37526 | 180W | 公式 | 価格 |
| Arc B580 | 12GB | 14696 | 34506 | 190W | 公式 | 価格 |
| Arc B570 | 10GB | 13796 | 30493 | 150W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 | 8GB | 13254 | 31977 | 145W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7600 | 8GB | 10864 | 31366 | 165W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 4060 | 8GB | 10692 | 28246 | 115W | 公式 | 価格 |
メモリは16GBか32GBか、実際どっちが使いやすい?
Apexを本気で遊ぶ人にとって、メモリを16GBにするか32GBにするかはかなり悩ましい選択になります。
私自身いろいろ試してきましたが、今なら迷わず32GBを勧めたい。
実際、16GBで遊んでいた頃も一応動いてはいましたが、少し余計な作業を同時にすると途端に重くなる。
ゲーム中に固まるたびに「またかよ」と小さく舌打ちしたものでした。
そんな経験を経て32GBに変えた瞬間、空気が澄んだように操作が軽くなり、やっと心置きなく遊べるようになったのです。
16GBだとフルHD解像度で遊んでいるぶんには大きな問題を感じないでしょう。
画面がカクつくと集中が途切れてしまい、ストレスが蓄積して楽しさが半分以下になる。
この「小さな苛立ち」が積もるのが地味に痛いのです。
やるなら快適にやりたい。
32GBに増設すると、その苛立ちがほぼなくなるのが大きい。
アプリを同時にいくつも起動させても余裕があり、長時間プレイしても疲れ方が違う。
単なる数値の余裕ではなく、気持ちの余裕につながるのです。
私の環境ではBTOパソコンにCrucial製のDDR5を入れています。
以前は16GB×2枚の構成でしたが、正直不安定でした。
夜中に録画配信をしていて、いきなり音声が途切れる。
映像が止まる。
せっかく時間をかけて楽しんでいたのに、その瞬間すべてが台無しになる。
何度も悔しい思いをしました。
けれど32GBにしてから、そのトラブルが一度も起きなくなったんです。
録画が朝まで途切れず続く。
それに消費電力や発熱への不安もありましたが、実際には大きく変わらない。
むしろ余裕がある分、スワップが減ってCPUやSSDへの負担が減り、結果的に全体の処理が落ち着くのを感じます。
長時間プレイ後でも、以前のような「なんだかカリカリ動いている」感じが消えて、安定した空調の下にいるようでした。
これは理屈ではなく、肌感覚での実感です。
ゲーム以外のシーンでも差は歴然と出ます。
ブラウザを閉じずにタブを大量に開いても問題なく、リモート会議をしながら複数の資料を並べ、さらに動画編集ソフトまで走らせることができる。
昔だったらすぐに処理落ちして、「ちょっと待って」と同僚に声をかけていたはずが、いまではスムーズに進められる。
仕事でも趣味でも、自由度の広がりが心に余裕を与えてくれます。
昔なら「16GBで十分動くし、余計な投資なんて不要だ」と思ったでしょう。
けれど、限られた自由時間で趣味を中途半端に味わうのはもったいない。
快適さに投資する価値があると経験から実感しました。
そこでストレスを抱えるなんて、考えるだけで惜しい。
コスト重視ならそれも正解です。
でも、ゲームはアップデートを重ねて必ず重くなっていく。
追加のエフェクトや高品質なテクスチャで要求スペックが上がるのは目に見えています。
必要に迫られてから買い替えるより、余裕を持って備える方がずっと建設的。
慌てて買い替えて出費に頭を抱えるより、前もって選んでおけば精神的にもゆとりが生まれます。
安心感がある。
持続力がある。
価格差以上の満足感があります。
特にApexを本気で楽しみたい人、配信や録画を同時にこなしたい人、これから出る重量級タイトルに備えておきたい人にとって、16GBを選ぶ理由は薄れていくばかり。
私も過去の自分に言いたい。
「あのときから迷わず32GBを選んでおけ」と。
最適な答えはシンプルです。
迷ったら32GBで間違いないと、心から断言できます。
Apex Legends 向けの最新グラボ事情と選び方

NVIDIA RTX 50シリーズとRadeon RX 90シリーズの違いを整理
Apex Legendsをやり込んでいくうちに痛感したのは、やはりグラフィックボード選びがプレイ体験の質や勝ち負けを左右する大きな要素だということです。
昔から自作PCをいじっては組み替え、思うようにフレームが出なかったり熱暴走に悩まされたり、そのたびに頭を抱えてきました。
その経験から言えるのは、結局RTXかRadeonか、この二択にたどり着くというシンプルな話です。
高フレームレート重視ならRTX、画質や安定性の重視ならRadeon、この図式が今の世代では一番自然な答えだと私は実感しています。
特にDLSS 4によるフレーム生成を初めて試したときの驚きは、今でも記憶に残っています。
144Hzを超えるモニター環境で動かした瞬間、エイムを合わせて撃った弾が、ほとんどラグを感じさせずに敵に届くのです。
弾幕の中で「あとほんの少し間に合えば勝てたのに」という場面を、確実に拾ってくれる。
競技感覚を求めたい人には、このレスポンスの鋭さが何よりの武器になると感じます。
まさに速さが命。
RDNA 4世代で強化された点ももちろんありますが、最も大きいのはVRAMの余裕感です。
RX 9070XTで16GBや20GBといった容量を確保できるのはかなり強みで、シーンによってはRTXの同価格帯よりも明確に伸び伸びと動くのを体感します。
私が以前RTX 4070を使っていたとき、特にテクスチャを高設定にするとメモリ不足でカクつく場面が多発しました。
その安心感ときたら「もう余計なことを気にせずゲームを楽しめる」という解放感に近いものでした。
私が使い分けた実体験を整理すると、RTXの魅力は即応性、Radeonの強みは粘り強さ。
たとえばRTX 5070Tiを使ったとき、フルHD環境でも240Hzを狙える安定性があり、いざ撃ち合いの最中に「ここしかない」と感じる瞬間に、映像がしっかりついてきてくれる。
そのときの胸の高鳴りは、勝負にこだわる人にしか分からない特別なものです。
逆に、WQHD環境でRX 9070XTを使っていたときは、少々強気な画質設定にしても落ち込みがほとんどなく長時間快適でした。
冷却ファンも静かで、耳障りなノイズに邪魔されることなく夢中でプレイできる。
リラックスしながら深い没入感を得られるのは、Radeonならではの味です。
もう一つ見逃せないのがインターフェース周りの対応力です。
RTXはDisplayPort 2.1bをしっかり抑えていて、次世代の8K出力にも抜かりがない。
新しい規格を早い段階で取り入れてくるこの姿勢は、NVIDIAの強い信頼材料だと思います。
一方でRadeonはDisplayPort 2.1aやHDMI 2.1bに幅広く対応し、複数モニターで環境を組むときに柔軟性がある。
相性の懐の深さ、ここも選択理由になりますね。
そして避けて通れないのが消費電力と発熱問題。
RTXは性能を追い込んだ分だけ冷却に手をかける必要があります。
上位モデルなら水冷を選ばざるを得ないこともあり、コストもかさみます。
私はそこでケチって痛い目を見たことがあります。
「ここはケチるな」というのは身をもって学んだ教訓です。
一方、Radeonは比較的消費電力が抑えられており、空冷で十分に運用できるケースが多い。
導入コストや日々の電気代、さらには静音性まで含めて、長く使うほど差が効いてくる。
この点は見過ごせません。
最終的に私が行き着いた結論は、勝ち筋を追うならRTX、快適で豊かな環境を楽しみたいならRadeon。
この二択です。
フルHDからWQHDの範囲で勝ちへの執念を優先するならRTX 5060Tiや5070Ti。
一方で4Kで迫力ある映像体験を楽しみたいならRX 9060XTや9070XT。
どちらを選ぶかは、自分が「どんな時間を過ごしたいか」で答えが変わります。
迷ったときに一番大事なのは、自分に正直になることだと思います。
勝ちにこだわりたいのか、没入できるゲーム体験そのものを求めるのか。
あるいはそのどちらも欲しいのか。
そう考えることで、自分なりの答えは意外と早く浮かび上がってくるはずです。
未来に見据える選択肢。
RTXとRadeon、どちらも今世代は確実に大きな進化を積み重ねており、Apexを遊ぶ私たちにとっては間違いなく恵まれた環境です。
だからこそ悩むのだと思います。
ですがその悩む時間も含めて楽しいと感じられることが、ゲームの面白さを支えているのかもしれません。
私はそう感じています。
コスパ目線だとRTX 5060Tiや5070が候補になりやすい
Apex Legendsを快適にプレイするために、私が現実的だと考えているグラフィックボードはRTX 5060TiかRTX 5070の二つです。
正直なところ、もっと上位のモデルに行けば確実に性能は伸びますし、カタログスペックを見れば誰だって心を揺さぶられると思います。
ですが、実際に遊んでみて必要十分な環境が揃うのなら、それ以上を求めても結局のところは自己満足に近い。
だから私は「ちょうど良さ」にこそ価値があると実感しています。
フルHD環境なら5060Ti、WQHD環境を本気で楽しむなら5070。
この二つが、現実と欲望のバランスが取れた選択肢だと考えています。
以前、BTOショップに立ち寄った際、5060Tiを搭載した試用機でApexを触った経験があります。
240Hzモニターに繋いで影やアンビエントオクルージョンを少し調整しただけで、驚くほど滑らかに動いてくれました。
最新のDLSSが効いていることもあって、体感はもうワンランク上の製品に触れているかのようでした。
正直なところ、競技寄りにApexを楽しむ人にも「これなら十分やれる」と言いたくなる完成度でした。
一方でWQHD環境で144Hz以上を安定して出したい人にとっては、5070以外の選択肢はないと感じています。
実際にプレイしてみると余裕が違うんです。
フレームレートだけでなく、映像表現が重たいタイトルも難なくこなせる安心感がありました。
中でもレイトレーシングを有効にしたゲームで、景色や光の反射が自然に表現されるのを見た時には、「ここまで来たか」と思わず息をのむほどでした。
自宅で本気のゲーム環境を揃えるなら、5070を軸に組むのが理想的だろうと今は考えています。
この世代のGPUは、性能面だけでなく電力効率や発熱の低さも大きな魅力です。
大げさな水冷を導入しなくても静音性は確保され、長時間のゲームでも耳障りな音がほとんど気にならない。
それどころか、仕事中でも快適に使えるレベルなのが実にありがたいと感じました。
扱いやすさ。
まさにこれが肝なのだと思います。
とはいえ、価格面を見ると5060Tiと5070には大きな差があります。
この差額をどうとらえるか。
BTOパソコンの構成を考える際、メモリを16GBから32GBに増やすことと同等の負担になる場合もあり、単に「少し上げれば済む」という話ではありません。
私はよく「解像度をどこまで追求するのか、そしてフレームレートをどこまで重視するのか」を天秤にかけます。
これを基準に考えていくと、自分にとって最適な答えが自然と見えてくるんです。
また、GPU単体では快適さを語れないというのも現実だと思います。
SSDは1TB以上のPCIe Gen.4を積んでおきたいし、ケースはエアフローがちゃんと考えられている構造を選ぶべきでしょう。
私自身、強化ガラスパネル付きのケースを試したことがありますが、冷却設計が整っていればまったく問題なく使えました。
内部の空気がこもらず抜けが良いと、安心感が違うんです。
改めて感じたのは、PC全体はグラボ一枚ではなく総合力で成り立っているという事実でした。
最近では5060Tiにも16GB版が出ました。
正直今のところVRAM 8GBで困る場面はほとんどありません。
しかし、数年先を考えるとテクスチャの要求はどんどん重たくなる。
私は長く使う前提であれば、余裕を持たせたVRAM容量を選んだほうが後悔は少ないと思っています。
5070をメインにしてVRAM12GB以上を確保し、サブ機には8GB版の5060Tiを回す。
そうすれば「無理のない二本立て」が組めると考えています。
考えてみれば、そもそも「安心して楽しめる環境」とはどこを基準にするのか、ここが一番難しいのだと思います。
最高のフレームを極限まで求める人であれば、当然のように上位モデルに手を出すべきなのでしょう。
ただ私にとっては、毎日のように遊んでも快適で、目と耳に負担がなく、満足感を得られることが最優先です。
だからこそ、無駄に上を追わない選択に価値を感じています。
Apex LegendsをフルHDでやり込みたいユーザーは5060Ti、WQHDで高リフレッシュ環境を求めるユーザーは5070。
私はこの選択が現状の答えだと確信しています。
投資であると同時に趣味でもあるゲーミングPCの選定において、40代の私の目線では、この二択こそ効率と満足度のちょうど真ん中だと思えてならないんです。
最後に、やはりPC選びは「自分がどう遊びたいのか」を見つめ直す時間そのものなのだと思います。
そのちょうどいい落としどころを探す作業こそ、本当の楽しみなのだと私は感じています。
ゲーミングPC おすすめモデル5選
パソコンショップSEVEN ZEFT R60BY

| 【ZEFT R60BY スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 7700 8コア/16スレッド 5.30GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | Radeon RX 7800XT (VRAM:16GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (8GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | ASUS ROG Hyperion GR701 ホワイト |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B650 チップセット ASUS製 TUF GAMING B650-PLUS WIFI |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55DU

| 【ZEFT Z55DU スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | Radeon RX 7800XT (VRAM:16GB) |
| メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7400Gbps/7000Gbps Crucial製) |
| ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R53JA

鮮烈ゲーミングPC、スーペリアバジェットで至高の体験を
優れたVGAと高性能CPU、メモリが調和したスペックの極致
コンパクトなキューブケース、洗練されたホワイトで空間に映えるマシン
最新Ryzen 7が魅せる、驚異的な処理能力のゲーミングモデル
| 【ZEFT R53JA スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 7800X3D 8コア/16スレッド 5.00GHz(ブースト)/4.20GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (8GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B650 チップセット MSI製 PRO B650M-A WIFI |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55AC

| 【ZEFT Z55AC スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265 20コア/20スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | NZXT H9 Elite ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
4Kで遊ぶときに必要になるグラボ性能
フルHDやWQHDであればミドルクラスのGPUでも十分に動作しますが、4Kに設定を切り替えると一気に負荷が跳ね上がるのです。
CPUやメモリが最新スペックでも、グラフィックボードの性能が追いつかなければ映像がカクつき、勝負の流れすら崩れてしまいます。
結局のところグラボの力が勝敗を決めるのです。
私も最初は「推奨環境を満たしていれば大丈夫」と気楽に考えていました。
確かに映像は息を呑むほど鮮明になります。
ただ操作は重く、敵の素早い動きに反応しづらい。
正直「これはやってられない」と独り言が漏れたほどです。
しかしRTX 5080に変えてからの変化は驚きでした。
フレームが安定し、遊んでいて余計な不安を感じなくなった。
あの安心感は本当に特別でした。
Apexは比較的軽量なゲームエンジンを使っていますが、それでも4Kまで解像度を引き上げると様子が変わります。
推奨環境クリアでは十分とは言えず、「どの水準で快適に遊べるか」が重要なのです。
実際、RTX 5070でも設定を調整すればプレイ可能です。
ところが激しい場面でフレームが60を割り、敵の動きがぎこちなく映ることがある。
その一瞬で集中が切れる。
勝負どころで大きな差になる。
私自身、悔しさを噛みしめた経験があります。
そこで問題になるのがVRAMです。
8GBではあっという間に限界です。
VRAMは「余裕があるに越したことはない」ではなく、「余裕がなければ成立しない」存在です。
高リフレッシュレートのモニタを組み合わせると驚くほど快適になります。
100fps前後を安定して出せる環境は、ただ映像が滑らかなだけではなく、試合中の判断すら的確にしてくれる。
勝負に挑むなら、4Kでもそこを追い求める気持ちが強くなります。
ミドルクラスで妥協すると「映るだけ。
でも勝てない」という環境になる。
それでは心から楽しめないのです。
電源と冷却。
忘れがちですが、これも大切です。
最新世代の上位GPUは発熱も消費電力も大きく、ケース内のエアフローが不足すれば簡単にfpsが落ちてしまう。
せっかく高いパーツを揃えても、それでは宝の持ち腐れです。
私は850W以上の電源と冷却設計を強化したケースを組み合わせたことで、本当にパフォーマンスが一変するのを体験しました。
基礎を整えるだけで安心して没頭できる。
その差は想像以上に大きいものです。
確かに補助的な意味では力がありますが、根本的な性能が不足していると決して快適とは言えません。
「もう一工夫で中級GPUでも4K高設定いけるかも」と思った時期もあるのですが、現実はそうはいきません。
結局、体感して理解しました。
選択肢は二つだけです。
この答えを裏付けてくれたのが、先日の国際大会でした。
観客から自然に歓声が上がり、その瞬間の熱気と映像が一体となって心を揺さぶりました。
トップ環境の持つ力を、私は肌で感じました。
最終的な選択はシンプルです。
4KでApexを本気で楽しみたいなら、RTX 5080やRadeon RX 9070 XTを選び、VRAMは16GBを意識し、電源と冷却を整える。
その三本柱だと断言します。
コストは確かに重い。
しかし投資に見合う体験は確実に得られる。
半端な構成で後悔するくらいなら、思い切って環境を整える方がはるかに満足できるのです。
「ハイエンドGPUで挑め」と。
準備を整えた瞬間に広がる景色は、ただのゲームを超えて鮮烈な体験そのものになります。
そこには悔しさも苛立ちもなく、純粋に熱中できる時間だけが広がっている。
本物の舞台。
夢中になれる環境。
それを求めるなら、迷わず選択すべき答えは一つなのです。
Apex Legends 用ゲーミングPCに搭載したいCPU比較
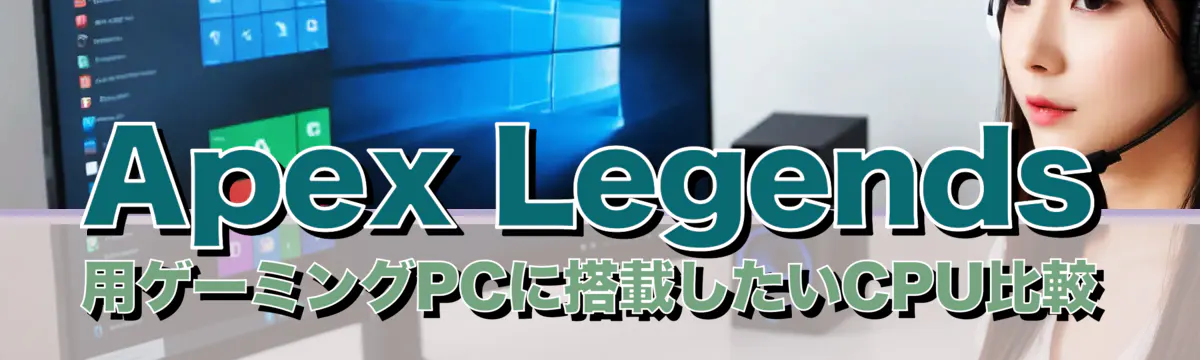
Intel Core UltraとAMD Ryzen 9000の特徴をざっくり紹介
Apex Legendsを快適に遊ぶためにPCを選ぶとき、多くの人が最初に迷うのはCPUだと思います。
実際に私もそういう後悔をしたことがありますから、同じ轍は踏んでほしくないのです。
Intel Core Ultraの魅力は、何と言っても一瞬の反応が必要な局面で発揮される瞬発力です。
フルHDやWQHDで高リフレッシュレートのモニタを使う人にとっては、これ以上ない強みとなるでしょう。
特に打ち合いでわずかな遅延が生死を分ける場面では、Core Ultraの真価を感じます。
正直に言えば、AI処理用のNPUに関しては私のゲーム用途ではまだありがたみが薄いのですが、発熱が控えめで空冷クーラーでも十分に性能を発揮できる点はとても実用的だと感じています。
冷却に工夫を凝らさずとも快適に遊べるのは、自作歴が長い私としては思わず「助かるな」と声に出してしまったほどです。
頼もしさを感じる瞬間ですね。
一方で、AMD Ryzen 9000は安定性が売りです。
Zen5アーキテクチャとX3Dモデルの大容量キャッシュによって、解像度が上がるほど強さを発揮します。
WQHDや4Kの環境でフレームの揺らぎがほとんどなく、長時間プレイしても画面が乱れないのは実に快適でした。
Ryzen 7 9800X3Dを初めて導入したとき、リフレッシュレートがモニタとピタリと噛み合い、フレームドロップに悩まされない爽快感に思わず「これだよ、これ」と心の中で叫んでしまったくらいです。
さらに、Ryzen 9000の大きな安心要素は拡張性です。
私は「この余裕があるつくりなら数年は十分戦える」と感じました。
投資だからこそ、安心できる土台が必要だと実感しています。
もちろんIntel Core Ultraが劣っているわけではありません。
むしろ、私が日常業務で使うCore Ultra搭載PCではExcelや動画編集の処理速度の速さに感心しました。
同じ人間が使っているからこそ、ゲームではRyzenの分かりやすい強みを感じ、仕事ではCore Ultraの快適さに驚くのです。
要は使い道が明確ならば答えも自然と導き出せるものです。
Ryzen 9000の小さな安心といえば、統合GPUの存在です。
これは予想以上にありがたいものでした。
以前、外付けGPUが突然動かなくなり画面が真っ黒になったことがあります。
締め切り直前の出来事で冷や汗をかき、原因を切り分けるのにとても苦労しました。
その経験以来、「保険として内蔵GPUがあった方がいい」と心から思うようになったのです。
実際に使ってみてこそ分かる安心感です。
ゲーム用PC選びで見落としがちなのは、CPU単体だけを見てしまうことです。
CPUは大事ですが、グラフィックカードやメモリ、ストレージ、モニタとの組み合わせで初めて性能が生きてきます。
私自身が他人にすすめるならこうです。
逆に、WQHDや4K、あるいは複数年先まで視野に入れた安定的な環境を求めるならRyzen 9000の方が適しています。
自分がどの環境で遊びたいのか、どういう快適さを手に入れたいのか、それを具体的に想像することこそが最も大切です。
数字のスペック表をにらみながら悩むのも一つの楽しみではあります。
しかし最終的に大切なのは、実際にそのPCを前にしてどんな気持ちで遊びたいか、どんな安心感を得たいか、そういった具体的な「体験のイメージ」だと私は思います。
私は両方を自分なりに経験したからこそ、買う前に胸に手を当てて考える時間の尊さを知りました。
私にとっての答えははっきりしています。
自分の環境とプレイスタイルを見極め、その上で選んだPCが「納得の一台」として長くそばにいること。
それこそが失敗しない秘訣なのだと確信しています。
そして私は40代のひとりのゲーマーとして、後輩たちや同じ趣味仲間にこう伝えたいのです。
「スペックの数字よりも、自分が納得できるかどうかを大事にしよう」と。
安心できる選択。
それが私の結論です。
ざっくり言えば、Intelの瞬発力かRyzenの安定性か。
その二択を、自分の未来の遊び方に照らして選ぶ。
これ以上でもこれ以下でもない。
その答えに気づいた今だからこそ、声を大にして伝えたいのです。
長くPCと付き合ってきた人間として、失敗しない選び方をしてほしいと。
納得の判断。
ゲーム中心ならCore Ultra 7かRyzen 7が実用的
Apex Legendsを快適に遊ぶために、結局はCore Ultra 7やRyzen 7のクラスが最も現実的ではないか。
私はそう考えています。
確かに世の中にはUltra 9やRyzen 9といった高性能なCPUが堂々と並んでいます。
しかし実際にApexをプレイしてみると、その圧倒的な差を体感できる場面はほとんどありません。
むしろ重要なのはGPUとの組み合わせや全体バランスであって、CPUだけを飛び抜けて強化しても意味が薄い。
これが私のリアルな実感です。
数か月間、私はCore Ultra 7 265Kを実際の環境で使い込んできました。
フルHDの画面で200fps前後を維持するのに不安を覚えたことはなく、何百試合と重ねる中でも「あれ、カクついたな」と気づく場面はほとんどなかったんです。
Ryzen 7 9700Xも試しましたが、165Hzのモニタと組み合わせても十分な滑らかさを保てました。
率直に言って、両者の差を日常的なプレイで意識することはありませんでした。
一方で、欲が出る気持ちは誰にでもあります。
「せっかくなら最上位を」と思ってUltra 9やRyzen 9に手を伸ばした時期が、私にもありました。
その結果どうなったか。
消費電力は跳ね上がり、冷却のために大げさなファンや水冷を導入せざるを得なくなった。
しかもゲームの体感はそれほど変わらない。
正直、投資効果が見合わないと痛感しました。
贅沢をしたつもりが、結局は余計なコストと手間に苦しむ。
そうした現実を私は身をもって学びました。
もちろん、最上位のCPUがまったく不要だとは言いません。
動画編集をしつつAI処理や配信まで同時に回すような場面では確実に力を発揮します。
しかしApexだけにフォーカスするのであれば答えは単純です。
Core Ultra 7かRyzen 7で十分。
私はこの結論を何度も試行錯誤の末に繰り返し確認しました。
無駄をなくす意味でもこの選択が一番自然だと感じています。
実際、大会会場で行われたeスポーツイベントでも同じことが証明されていました。
舞台には華々しい環境が並んでいましたが、使われているCPUはやはりこのクラス。
選手も予想外の不具合に振り回されることなく集中できます。
豪華に揃えたハードウェアよりも、安定した選択こそが現場では大切にされていた。
その光景を私は目の前で見ました。
興味深いのは、これからのCPUがただの演算速度競争だけでなく、NPUによるAI支援を積極的に取り込んでいる点です。
ゲーム外のシーンでその力を実感することが増えるでしょう。
例えば録画や配信を同時に行うとき、映像変換の処理が驚くほどスムーズに流れる。
それを初めて試した私は「これは自分の常識が変わるな」と思わず声に出してしまいました。
技術の進化を体で感じた瞬間でした。
私なりに思い描く理想の環境は、Core Ultra 7 265KかRyzen 7 9800X3Dを中心に据え、GPUはRTX 5070やRadeon RX 9070 XTクラス。
それにDDR5の32GBを積む。
数年先までは余裕を持ってプレイできる仕様です。
特にVRAMが多いGPUの安心感は大きく、マップの大幅な更新や、グラフィック強化が行われるタイミングでも「準備不足だった」と焦らずに済みます。
私はそこに強い価値を見出しました。
CPUのグレード選びでも少し面白い経験をしました。
同じCore Ultra 7でも「K付き」か「非K」で性格がまったく違うのです。
当初は「オーバークロックなんてしない」と割り切って非Kを選びました。
静かさは気に入っていました。
ですが、ある時誘惑に負けてK付きにしたところ、その伸びに驚かされた。
後悔と満足。
その入り混じった感覚はいまでも記憶に残っています。
昔、私は分不相応に高いモデルを買ってしまい、そのときに余計な電力や熱に頭を抱えました。
その経験があったからこそ、今は胸を張って「このクラスで十分ですよ」と伝えられる。
余分な心配ごとをなくし、集中力を勝負に全力投球できる。
これこそが快適に楽しむために必要な選択肢だと、私は確信しています。
安心感。
納得感。
そして何より、自分の体験を通して得た実感は「計算の上で選んでも、最後に残るのは使ってみた手応え」でした。
だから私は、同じようにApexを楽しみたい仲間にこう伝えたいのです。
迷って上位CPUに投資する必要はない。
身の丈に合った現実的な構成を組めば、それだけで十分に戦える。
人の声や広告よりも、自分の体験に耳を澄ませる。
その選択が、遊びを一番豊かにしてくれると私は思います。

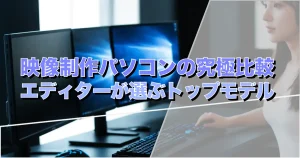
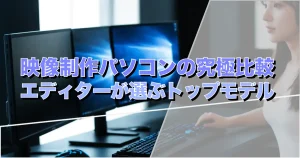
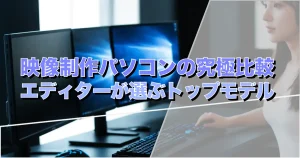
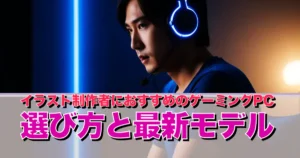
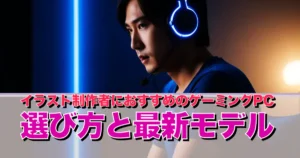
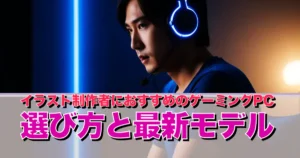



配信しながら高フレームレートも狙えるCPUはどれか
Apex Legendsを配信しながら気持ちよく遊びたい。
その思いで色々試してきたのですが、はっきり言って8コア以上のCPUを選ばないと安定した環境は作れない、と痛感しました。
画面が一瞬止まり音声も途切れる、その瞬間に自分も視聴者もテンションが下がる。
正直、あの気まずさはもう味わいたくないと思ったのです。
だから私は実際に財布を痛めつつ複数のCPUを自分の環境で試しました。
試したのはCore Ultra 7 265KとRyzen 7 9800X3Dでした。
数値としてのベンチマークではそこまで差が見えないのですが、配信を立ち上げてプレイすると「差はここにあるのか」と驚かされました。
Ryzen 7 9800X3Dを使ったとき、いつも見に来てくれている視聴者から「今日はやけに安定してるね」と言われた瞬間、思わず心の中でガッツポーズ。
数値ではなく実感に裏打ちされた安心感こそ、自分が求めていたものだったと気付かされました。
あの小さな一言が大きなご褒美のように感じられましたね。
ただしIntelも軽視できません。
シングルスレッドのキレ味はやはり鋭く、キャラ操作のレスポンスが小気味よい。
特にWQHD以上で配信しようとするとCore Ultraシリーズの強みが光ります。
発熱についても想像していたより扱いやすく、簡易水冷を使えば連続配信でも怖さがない。
正直、この取り回しやすさは実務的にもメリットが大きい。
気を使う要素が一つ減るだけで、気持ちのゆとりが違うのです。
フレームレートについての発見も忘れられません。
240fpsを目指すとなると当然GPUがフル稼働します。
しかし配信を絡めた瞬間にCPUがボトルネックとなり、伸びるはずのフレームが頭打ちになる場面が出てきたのです。
最初は「GPU余ってるのになぜ?」と疑問に思い、設定を見直しても変わらず、原因はCPUの限界でした。
快適な動作の裏にCPUがどれだけ影響するのかを、身をもって思い知らされました。
やはり避けては通れない部分なのです。
では最終的にどう選ぶのが正解か。
私なりの答えは、Ryzen 7 9800X3DかCore Ultra 7 265K以上を選ぶことでした。
この二つなら配信とゲームを両立させつつ、録画や編集も十分にこなしてくれます。
安心感がある。
私は試合後によく録画を切り出してSNSに上げますが、そのときの処理が速いかどうかは、時間の問題にとどまらず「気持ちの疲れ具合」にも直結します。
短時間で終わると不思議なほど気分が楽になり、逆に待たされると疲弊してしまう。
だから性能は単なる数値以上に、自分の意欲を守る投資だと感じました。
配信を続けていると「体力的にも精神的にももう無理」と感じて引退する人がいます。
私自身ニュースでそうした話を耳にするたびに、もっと環境が整えば少しは楽になるのではないかと思うことがあります。
不安定な配信環境は小さなストレスを積み重ね、そのストレスが配信者の気力を蝕む。
だからこそ最初の段階でCPUをしっかり選ぶことが肝心だと強く言いたい。
節約を優先して性能に妥協した結果、後で不満が爆発するのは目に見えています。
本当にそうなんです。
最終的に私は、Ryzen 7 9800X3DかCore Ultra 7 265Kのどちらかを選んでおけば確実に後悔はしないと考えています。
高フレームレートを維持したまま配信も安定させ、さらに動画編集まで手を広げることができる余裕。
この余剰性能がもたらす広がりは単なる快適さを超え、気持ちの面での支えにもなります。
結果としてコスト以上の価値があるのです。
Apex Legendsを本気で楽しみたい。
そのために投資すべきはここしかないでしょう。
これを選べばフレーム落ちへの不安から解放され、余裕を持ってプレイし、安心して配信が続けられる。
環境が整えば人とのやり取りも自然と明るくなり、ゲーム体験全体が格段に豊かになります。
これが私なりの答えであり、実際に体験して腑に落ちた結論です。
環境次第。
Apex Legends を快適に動かすためのストレージと冷却の考え方


Gen4 SSDとGen5 SSD、実際に選ぶならどっち?
なぜかといえば、最新のGen5 SSDが持つ数字上の速さは確かに魅力的ですが、それを実際のプレイ環境で実感できる場面はほとんどないからです。
ベンチマークを眺めると確かにGen5は圧倒的に見えます。
しかし蓋を開けてみれば、起動もロードも体感は変わらない。
あの肩透かしを食らった感覚は、今でも忘れられません。
ところがいざ使い始めてみると、ゲーム自体はGen4とほぼ変化なし。
それどころか、発熱や騒音という非常にやっかいなオマケがついてきました。
ケース内部に熱がこもってしまって、ゲームどころじゃない。
冷却ファンを追加したり内部のエアフローに悩んだり、時間も手間もかかってしまい「これは余計な投資をしたな」と我に返りました。
正直、がっかりでしたね。
一方のGen4 SSDは、安定していて扱いやすい。
私にとっては、この「気楽さ」が実はとても重要でした。
ゲームを始める前に余計な心配が増えることほどストレスなものはない。
安心感がある。
さらに無視できないのが価格です。
Gen5はまだ高い。
容量1TBで見てもGen4の1.5倍から2倍、それ以上になるケースもあります。
そのお金を、グラフィックカードや高リフレッシュレートのモニター購入に回す方が、よほどゲームの満足度は高まります。
Apexを毎日のようにプレイしていて感じるのは、ロードが一秒縮んでも勝敗は左右されないということです。
もちろん将来性という観点でGen5を選ぶ人もいるでしょう。
数年を見据えれば、AI処理やデータ負荷の重たいゲームが普及して、Gen5が標準になっていくことも考えられます。
ただ、それはまだ未来の話です。
今、この瞬間にApexを快適に遊ぶという目的を考えるなら、Gen4で不足は一切ありません。
たとえるなら、スマホの端子をLightningからUSB-Cに切り替えるタイミングを焦っているようなものです。
今の機種で支障なく使えているなら、慌てる必要はないし、そのままでも十分生活できる。
それと同じことです。
それからもうひとつ重要なのが容量でした。
Apexはシーズン更新のたびに容量が増え続けます。
気がつけば数百GBにまで膨れ上がっている。
それでも半年もすれば半分以上埋まっているんです。
ゲームクリップや動画を保存するならなおさら。
ここを甘く見ると後から必ず困ります。
外付けを増設するのは正直面倒ですし、管理も複雑になる。
だからこそ最初から容量に余裕を持たせることが肝心。
これは自分で失敗して気づいたことでした。
数字上の性能が魅力的に見えるのは当然だと思います。
私もパーツ選びのときはどうしても性能表やベンチに目が奪われてしまいました。
スペックを語る自己満足だけでなく、本当に自分が欲しい体験は何かを考えること。
ここを勘違いすると、せっかく高いお金を出してもストレスが残るだけです。
正直な話、私はGen5を試したときに初めて、本当に必要なのは「数字ではなく体験の質」だと実感しました。
大人になってからの買い物は、見栄より実利です。
これは仕事もゲームも同じで、余計なトラブルがないことほどありがたいものはありません。
そう考えると、今の答えは実にシンプルです。
Apexを快適に遊ぶならGen4 SSDを選ぶべきです。
そのバランスの良さが、コスト効率と静音性、そしてストレスなく遊べる安心感を与えてくれる。
技術的な最先端を追いかける喜びも理解しますが、今必要なのは「快適にプレイできること」であり、その期待に最も応えてくれるのはGen4だと私は確信しています。
最終的に選ぶ基準は人それぞれですが、私の答えは明白です。
今を楽しむためなら迷わずGen4。
未来に備えたくても、その未来はまだ来ていない。
だから、この瞬間にApexを思い切り楽しみたい人にこそ、Gen4 SSDをお勧めしたいのです。
SSD規格一覧
| ストレージ規格 | 最大速度MBs | 接続方法 | URL_価格 |
|---|---|---|---|
| SSD nVMe Gen5 | 16000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD nVMe Gen4 | 8000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD nVMe Gen3 | 4000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD SATA3 | 600 | SATAケーブル | 価格 |
| HDD SATA3 | 200 | SATAケーブル | 価格 |
ゲーミングPC おすすめモデル4選
パソコンショップSEVEN ZEFT Z54HS


| 【ZEFT Z54HS スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra5 245KF 14コア/14スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.20GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P10 FLUX |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R53FC


力強いパフォーマンス、コンパクトに凝縮。プレミアムゲーミングPCへの入門モデル
バランスの極みを実現、32GBメモリと1TB SSDの速さが光るスペック
スリムで洗猿、省スペースながらもスタイルにこだわったPCケース
最新のRyzen 7パワー、躍動する3Dタスクを前にしても余裕のマシン
| 【ZEFT R53FC スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 7800X3D 8コア/16スレッド 5.00GHz(ブースト)/4.20GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | INWIN A1 PRIME ピンク |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B650 チップセット MSI製 B650I EDGE WIFI |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z54ATC


| 【ZEFT Z54ATC スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | Radeon RX 7800XT (VRAM:16GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake Versa H26 |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R57GD


| 【ZEFT R57GD スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 7900X 12コア/24スレッド 5.60GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (8GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7300Gbps/6300Gbps WD製) |
| ケース | CoolerMaster NR200P MAX |
| マザーボード | AMD B650 チップセット MSI製 B650I EDGE WIFI |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R61K


| 【ZEFT R61K スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 7950X3D 16コア/32スレッド 5.70GHz(ブースト)/4.20GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7300Gbps/6300Gbps WD製) |
| ケース | Fractal Design Pop XL Air RGB TG |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B650 チップセット ASUS製 TUF GAMING B650-PLUS WIFI |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
空冷と水冷の違い、それぞれの長所と注意点
冷却に関しては無理に人の意見をなぞっても仕方ない。
空冷の利点は、やはり扱いやすさに凝縮されています。
取り付けはスムーズで、運用も比較的シンプル。
ホコリをエアダスターで軽く吹いて、ファンの回転に異常がないか確かめるだけ。
これは安心材料になります。
ところが、ゲーム配信を深夜に数時間続けていると、ファンノイズが少しずつ気になり始める時があります。
ある日も音が録音に乗り始め、「ああ、ついに限界か」と苦くつぶやきました。
この時ばかりは、空冷の弱点を実感させられました。
一方で水冷は圧倒的な冷却力を誇ります。
特に大型のラジエーターを組み込めるなら、CPUを高負荷で走らせ続けても温度は穏やかに安定してくれる。
正直な話、初めて導入してゲームを立ち上げた瞬間、私は心底驚きました。
「え、こんなに静かで冷えるのか」と思わず声が出たほどです。
144Hz以上の高リフレッシュ環境でFPSを回しても耳疲れせず、長時間の集中を助けてくれる。
水冷の恩恵は数字よりも、その体感の差にあります。
ポンプが故障すれば一発アウト。
希に液漏れのトラブルも起きる。
さらに管理を誤ると寿命は短くなる。
これを思うと「絶対安全」とは言い切れないんです。
だから私は、自分で定期的にチェックする習慣を受け入れられるなら水冷を薦めるけれど、そうでなければ空冷で十分だとも感じます。
安心して長く使いたいなら、無理は禁物。
これが正直な思いです。
ケースとの相性も忘れてはいけません。
空冷クーラーはサイズが合わなければ物理的に入らない。
ケース内の風の流れが滞ればパフォーマンスが落ちる。
水冷なら、ラジエーターを天井に配置するのか前面にするのかで冷却効率が変化します。
そしてガラス張りケースでは見た目重視と実用性との葛藤が起こる。
見栄えを取るか、安定を取るか。
悩みは尽きません。
私自身が配信環境を整えた時は、最初は空冷で粘っていました。
しかし数週間後、ファンノイズがマイクに入り込み、リスナーからも指摘が出ました。
その瞬間に「これはもう限界だな」と悟りました。
結局、思い切って簡易水冷へ交換。
結果は想像以上でした。
ケース内の熱はすっと引き、配信時の音も気にならなくなった。
まるで部屋自体が落ち着いた空気をまとったようで、正直ちょっと感動しました。
確かに導入コストは上がった。
けれど、自分の環境にとっては必要不可欠な投資だったと胸を張って言えます。
ゲーミングに求められる冷却は、一瞬の最高性能よりも安定した持久力です。
3時間、4時間と続くプレイでフレームレートが落ちず、音も邪魔にならない。
それが「快適さ」になります。
だからフルHDで気軽に遊ぶなら空冷で十分。
ただしWQHDや4Kで同時に配信や録画を行うなら、水冷の強みは格段に輝く。
どちらが正しいというより、どんな使い方をするかが答えを決めるのです。
私は空冷も水冷も両方経験しました。
最終的には「これがベストだ」と一つに決めることはできません。
生活パターンやプレイスタイルが変われば、最適な冷却方法も変わる。
それを素直に受け入れることが、快適なゲームライフに直結すると身をもって学びました。
だから「空冷派」か「水冷派」かを議論するより、「自分の今の状況にはどちらが合うのか」を見極めることこそ肝心だと確信しています。
要は冷却を軽視してはいけない。
プレイの質を支えているのは、CPUやGPUの性能だけではなく、緻密に守られた温度環境なんです。
冷却次第でゲーム体験は良くも悪くも変わる。
私はそう信じています。
冷却こそが鍵なんです。
静かで快適に過ごすための相棒。
結局、自分の選択をどう受け止めるかにかかっています。
投資と管理の手間に見合った見返りを冷却がくれるのか、その答えを冷静に考え抜いた先に、自分だけの最適解が見えてくるはずです。
エアフローを重視しつつデザインも妥協しないケース選び
これは仕事にも似たところがあり、優秀なメンバーを集めても環境が整っていなければ実力を発揮できないのと同じです。
特にApex Legendsのような一瞬の判断や反応が勝負を決めるゲームでは、ほんの数度の熱が原因で処理落ちしたりフレームレートが不安定になったりすることさえあります。
だから私はケースを買うときに、まず冷却性能を真っ先に確認する習慣がついています。
正直、ここを外せば何を積んでも宝の持ち腐れです。
しかしそうは言っても、デザイン面を完全に無視することもできないんですよね。
毎日目にするものですから、気に入らない見た目だとそのたびに微妙な気持ちになる。
ここが本当に悩ましいポイントです。
その間で何度頭を抱えたことか。
冷却性能という観点で言うなら、フロントがしっかりメッシュ構造になっているケースは本当に頼れる存在です。
その差は数値となってはっきり現れます。
最近のGPUはRTX 4070やRadeon RX 7900シリーズのように性能が飛び抜けている分、発熱も相応にあります。
冷却が追いつかないとクロックダウンが起き、パフォーマンスが落ちる。
いや、これは本当に悔しい。
ただ、ファンをただ闇雲に増設すれば良いかと言うと、そうではありません。
吸気と排気のバランスが崩れると、むしろ熱がこもる。
ケース内部のケーブルが風を塞ぐだけでも温度は上がります。
さらに使い続けるなかでホコリが溜まれば、あっという間に効率は落ちる。
私は以前、掃除を怠っていて夏場にGPUの温度が90度近くまで上がったことがありました。
その時の焦りは今も忘れられません。
「なんであのとき掃除をサボったんだ?」と後悔しましたね。
そういう経験から、私はケースを選ぶときに整備性を非常に重視するようになりました。
フィルターの着脱や掃除のしやすさ、ケーブルの配線の自由度。
長く使うならここを外してはいけないと痛感しています。
どれだけ高性能なPCも、ホコリだらけでは話にならない。
安心して遊べる環境を維持するための条件です。
私はこれまで、いくつかのケースを実際に使い比べてきました。
フロントメッシュタイプと強化ガラスタイプ。
その差は思った以上に大きかったです。
メッシュケースでは真夏でも動作が安定し、ゲームに集中できました。
一方でガラスケースは、見た目の高級感は抜群ですが、熱がこもりがち。
ある晩、ゲーム中にGPUのクロックが落ちてしまい「これではダメだ」と強いストレスを感じました。
そのとき感じた気持ちは、部下に任せたプロジェクトが環境のせいで失敗したときのようなやるせなさに近かったですね。
それでもデザイン性を求めたい気持ちも理解できます。
特に最近は木目調のフロントパネルや支柱を減らしたピラーレスデザインなど、部屋にしっくり馴染むケースが続々と登場しています。
私の家族もPCの見た目について意外と敏感で、リビングに置いても違和感のないデザインだと受け入れやすい様子をみせます。
やはり家庭で暮らす以上、自分だけ良ければいいわけじゃないんですよね。
ただ、一番声を大にして言いたいのは「見た目だけでは絶対に後悔する」ということです。
派手なRGBライティングが施されたモデルが格好良くとも、本当に必要なのは冷却性能です。
実際、私はケースを変えただけでGPU温度が7度下がった経験があります。
この差は大きい。
真夏の暑い部屋でゲームを続けられるか、突然不安定になるか、その境目になります。
だから私は光より風を優先する。
最近はメッシュとガラスを組み合わせたハイブリッドタイプも出ています。
外から見える美しさと冷却力を両立する工夫には感心しますね。
それに水冷ラジエーターを無理なく設置できるかどうかも重要で、対応しているケースとそうでないケースでは将来の拡張性に大きな差が出ます。
私にとってケースはもう「箱」ではなく「冷却システムの一部」。
ここまで来るとその存在感は無視できません。
私の考えはシンプルです。
冷却を一番に考えたうえで、次に気持ちよく眺められるデザインを選ぶ。
その順序を守れば後悔は少ない。
たとえばフロントメッシュと側面ガラスを組み合わせた形や、木目調の外観としっかりした風の通りを両立させた形。
そういうバランス感覚が大事なんです。
カッコよく見えて、ちゃんと冷える。
理想。
最終的な判断基準も明確です。
それだけ。
ゲームを心から楽しめる環境を維持できるかどうか、そこに尽きます。
そのうえで気に入ったデザインなら、長く愛着を持って使い続けられる。
後悔はしたくない。
だからこそ私は冷却を最優先に置きながら、自分が日々気持ちよく過ごせる見た目を最後に選びます。
Apex Legends ゲーミングPC購入のポイント【2025年版】


BTOで買うときにチェックしておきたいメーカー
Apex Legendsを快適に楽しみたいと考えるとき、私が大切にしているのはBTOメーカーの選び方です。
それが長く付き合ううえでの満足度を大きく左右します。
私はこれまでに何度もBTOパソコンを購入してきましたが、その中で「これにして良かった」と振り返れる買い物と「あぁ、選び方を間違えた」と後悔した買い物とがありました。
違いはスペックでも価格でもなく、むしろメーカーの姿勢にあったと今では感じています。
ラインナップの幅広さが印象的で、仕事にもゲームにもどちらにも対応できるモデルを探すとき、私にとって頼れる選択肢でした。
数年前、仕事で資料を扱いながら夜はApex Legendsを楽しみたいという欲張りな環境を整えようとしたとき、最終的にここで購入しましたが、正直「助かった」というのが本音です。
手続きの流れが非常にスムーズで、検討から注文、そして到着までがスピード感を持って終わってしまった。
それだけではなく、サポート窓口での説明が分かりやすく、平日の仕事終わりで疲れていても、余計に消耗することなく解決へ進めたのをよく覚えています。
次に触れたいのはマウスコンピューターです。
ここには落ち着いた安心感があります。
BTOメーカーと聞くと「遊び」のイメージが強い方もいると思いますが、この会社は元々法人向けの機器を長年扱ってきているため、製品づくりに実直さが漂っています。
そして何よりも記憶に残っているのは、ある深夜にどうしようもない不具合が起きたときのことです。
藁にもすがるような気持ちで電話をかけると、24時間対応のサポートが即座に応じてくれて、大きな安心を得られました。
あのときは本当に救われました。
「困ったとき頼れる」この一点があるかどうかで、気持ちの余裕はまるで違います。
だから私は今でも人にマウスコンピューターをおすすめできるんです。
そしてパソコンショップSEVEN。
正直、最初は知る人ぞ知る存在でした。
しかし近年ではカスタマイズの自由度から注目を集めるようになり、その人気には納得させられます。
CPUクーラーの種類やPCケースの細部まで、ここまで選ばせてくれるのかと驚きました。
自作をしたことがある人なら分かると思いますが、自由である一方で細部を追うのは不安もあるものです。
ところがSEVENはパーツの型番まで公開しており、情報を調べながら納得して構成を決められる。
私も一度、グラフィックボードの冷却性能を気にして決めかねていた時期がありましたが、このショップでは不安を減らし、納得したうえで注文できた。
購入前に抱く心理的な重荷が消えていくのを実感できるのは大きな価値です。
SEVENのもう一つの強みは、ゲームメーカーとの協賛経験です。
Apex Legendsのような人気タイトルで動作検証済みのモデルがあると、安心感も大きく違います。
スペック表だけを眺めて「大丈夫かな」と悩むのと、実際に動作保証があるのとでは天と地ほどの差です。
プレイヤーにとって、これは評価すべき要素だと私は考えています。
安心感。
では、どのメーカーを選べば良いのか。
コストを可能な限り抑えてなお快適さを確保したいならパソコン工房です。
信頼できるサポートを求め、長期間安心して使いたいならマウスコンピューターです。
どちらが優れているかという比較ではなく、どんな価値観を重視するかで道が変わる。
それがBTOメーカー選びの本質だと思います。
忘れてはならないのは、BTOパソコンは「買ったら終わり」という買い物ではないことです。
製品保証や修理対応の有無で、後々の安心感が決まる。
私は過去に価格だけで判断し、安さに惹かれて買ったモデルで痛い目を見ました。
1年も経たないうちに電源が故障し、夜中にうんともすんとも言わなくなった。
途方に暮れてサポートセンターに電話しても時間外で繋がらず、数日間仕事に差し支えるほどの事態になりました。
正直、あのときの焦りと後悔は今思い返すだけで胃が痛くなります。
それ以来、メーカー選びにおけるサポートの大切さを人に話さずにはいられなくなりました。
私たちはパソコンを選ぶとき、つい目の前の価格差に意識を引っ張られがちです。
しかし毎日の利用を考えると、不具合時の対応や構成の自由度こそが本当の安心につながる。
安さや名の知れたブランドだけで選んでしまうと、後から満足できずに後悔を抱えることがある。
逆に慎重に選んで納得のいく1台を手にできたとき、その後の日々はとても快適になります。
これは実際に失敗と成功の両方を経験してきたからこその実感です。
最後に整理して言います。
長期間安心とサポートを重視するならマウスコンピューター。
細部までカスタマイズして理想を詰めたい人はSEVEN。
失敗しない選び方です。
PC環境は、ゲームを楽しむうえでの土台そのものです。
だからこそ、これから本気で遊びたいと考えるなら、メーカー選びの時間だけは惜しまずに丁寧に取り組むことをおすすめします。
私はその経験を踏まえ、今でも人にそう伝えています。
将来的なアップグレードを見据えた構成の考え方
Apex Legendsを快適に遊ぶためのゲーミングPCを選ぶなら、私が強く伝えたいのは「いま快適なだけではなく、数年後も安心して使える構成を考えること」です。
ゲームが軽いと評されることもありますが、解像度を上げたり、高フレームレートを求めたりすれば、想像以上にGPUが悲鳴をあげます。
加えてアップデートごとに必要なVRAMはじわじわ増え、結局のところ数年先を見越した設計が必要になります。
実際に私が過去に痛い経験をしたからこそ、声を大にして言いたいのです。
財布にずしんと響きましたし、当時の悔しさはいまでも忘れられません。
「もっと考えておけばよかったのに」と、自分を責めましたよ。
電源やケースに妥協したことがあの失敗につながったのです。
やはり余裕を残す設計こそが一番の保険だと、あの体験で身に刻みました。
以前650Wの電源を使っていたのですが、GPUをアップグレードした瞬間に挙動が怪しくなり、フリーズや再起動に悩まされました。
正直、作業中に突然止まったときには、怒りすら覚えました。
その経験以降は電源に余裕を持たせるようにしています。
さらにゴールド認証ならなおさら安心です。
余裕があることが精神的な安定につながる。
これは単なる数字の話ではなく、日常のストレスを減らすことに直結します。
ストレージも同じです。
最初は1TBを入れて「これでいける」と思っていました。
しかし、動画編集や配信ソフトを追加すると、数か月でストレージは真っ赤に。
外付けを慌てて買ったものの、結局後から2TBへ換装し直す羽目になりました。
この作業の面倒さと追加出費を考えると胃が痛くなるレベルです。
結果論ですが、最初から余裕を組み込むことこそ、快適さと財布の両方を守る正解だったのです。
CPUも同じく軽視できません。
Apexなどのゲームだけならミドルクラスでも十分動きますが、実際に私は配信ソフトを同時に動かしたことで、大きなストレスを感じました。
バックグラウンドで複数のアプリを走らせたとき、「あれ?こんなに重いのか」と愕然としました。
少し余裕のあるCPUにしておけばよかったと痛感しましたよ。
特にマルチスレッドへの対応力は後々効いてきます。
短期的には無駄な出費に見えても、長期的に見れば安定と快適を買う投資なんです。
冷却についても後悔があります。
昔、見た目重視で小型ケースと簡単な空冷クーラーを選んだときのこと。
常にファンは全力で回転し、うるさくて集中できませんでした。
深夜の静かな時間にゲームをしていても、ファン音が頭に響き、気が休まらない。
ケースを大型に変更し、本格的なクーラーを導入した瞬間、まるで別世界の静けさを得られました。
この快適さを最初から知っていれば、余計な回り道をしなくて済んだのにと、強く悔やみました。
ケースは土台です。
ここを軽視すると後々の選択肢が狭まります。
内部の広さ、ケーブルの取り回し、冷却やストレージを増設する余地、それらを無視してデザインだけで選んだ結果、大失敗したことがあります。
「見た目は気に入ったのに、中が狭すぎて手も入らない」と、後悔しました。
今思えば、広さと余裕こそすべてを救う最強の要素だと断言できます。
私の考えとしては、スペックを盛りすぎる必要はありません。
ただし「これで十分」という水準では数年先に困ることが目に見えています。
これこそが長年安心してPCを使い続けるための秘訣です。
冷静に考える余裕。
将来を見据える視点。
これらが最終的にはコストを抑える最短ルートになります。
私はこれまでの失敗の積み重ねから、二度と「目先だけで満足する」選択をしないと心に決めました。
PC選びは単に性能を追うだけではなく、自分のこれからの働き方や余暇の過ごし方を支える基盤になるもの。
その基盤に余裕があるかどうかで、日常の気持ちまでも変わってきます。
派手さは要りません。
大切なのは余裕と安心。
その二つさえあれば、ゲーミングPCは長い時間をともにできる最高の相棒になるのです。
安心感。
信頼できる土台。
私にとって、この二つがゲーミングPC選びのすべてを語る言葉です。
ゲーミングPC おすすめモデル4選
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55H


| 【ZEFT Z55H スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra5 235 14コア/14スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (8GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | LianLi O11D EVO RGB Black 特別仕様 |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47AH


力強いパフォーマンスとハイクオリティな体験を兼ね備えたリファインドミドルグレードゲーミングPC
64GBの大容量メモリ、先進のプロセッシング能力、均整の取れた究極体験を叶える
透明パネルが映し出す、内部のRGB幻想世界。Corsair 5000Xでスタイルを際立たせる
Core i7 14700Fが魅せる処理速度、プロフェッショナル領域の仕事も遊びも完全サポート
| 【ZEFT Z47AH スペック】 | |
| CPU | Intel Core i7 14700F 20コア/28スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.10GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | LianLi O11D EVO RGB Black |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60BV


| 【ZEFT R60BV スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 9900X 12コア/24スレッド 5.60GHz(ブースト)/4.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | Radeon RX 7800XT (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | LianLi O11D EVO RGB Black 特別仕様 |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B650 チップセット ASUS製 TUF GAMING B650-PLUS WIFI |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R44CG


高速な実行力で極限のゲーム体験を支えるゲーミングモデル
直感的プレイが可能、16GBメモリと1TB SSDでゲームも作業もスムーズに
コンパクトなキューブケースで場所を取らず、スタイリッシュなホワイトが魅力
Ryzen 9 7900X搭載で、臨場感あふれるゲームプレイを実現
| 【ZEFT R44CG スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 7900X 12コア/24スレッド 5.60GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (8GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B650 チップセット MSI製 PRO B650M-A WIFI |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
予算ごとのおすすめ構成例(フルHD・WQHD・4K)
こう書くと堅苦しく感じるかもしれませんが、要するに最初に方向性を決めてしまえば後のパーツ選びは自然と決まっていくものなのです。
フルHDで気楽にかつ真剣に遊ぶのか、WQHDで画質と快適性のバランスを取るのか、それとも4Kの圧倒的な没入感に振り切るのか。
これまでに自分が組んできたPCや試してきた環境の記憶を振り返りながら、その現実的な構成について包み隠さず話したいと思います。
まずはフルHDの環境です。
正直に言ってしまうと、財布に優しい構成でも十分勝負できるのがこの解像度の強みです。
もちろんハイリフレッシュレートのモニターを選ぶならGPUには相応のものを組み合わせる必要がありますが、CPUはそこまで無理に上のグレードを選ばなくても動きます。
私が昔BTO案件で組んだときは、Core Ultra 5クラスのCPUとRTX 5060Tiを組み合わせ、240fpsを安定して出せていました。
そのときのプレイフィールは、指の動きとゲーム内のキャラクターの挙動がまるで一体化したかのように感じられて、本当に楽しかったんです。
軽快で、スムーズで、心地良い。
この「ちょうどよさ」こそがフルHDの魅力です。
だから私はフルHD環境を「手堅さと実用性の両立」と捉えています。
次にWQHDに目を向けると、ここからが別次元です。
描画負荷が一気に増し、GPUはどうしてもワンランク上が必要になります。
RTX 5070やRX 9070XTといったクラス、CPUならCore Ultra 7やRyzen 7あたりが無難なところでしょう。
私が初めてWQHDのモニターを仕事帰りに触ったとき、建物の窓枠や遠方の地形のディテールまで見えて、思わず声が出ました。
解像度の違いが戦略の幅を広げるんですよ。
没入感という言葉で片付けるにはもったいないレベルです。
しかも144Hz以上を保てる環境なら、まさに操作性と視認性が一気に跳ね上がる。
私はWQHDこそが、ある意味で「最適解」に一番近いと感じています。
そして最後に4K。
誰にでもすすめられるものではありません。
ただ、実際に経験してしまうと簡単には戻れない。
それが4Kです。
RTX 5080クラスやRX 7900XTX、そこにCore Ultra 7 265K以上やRyzen 7 9800X3DといったCPUを組み合わせ、水冷クーラーや850W以上の電源ユニットを整える。
そしてモニターに4K最高画質を表示させた瞬間、滑らかで生々しい描画に思わず言葉を失いました。
ゲーム内のキャラクターの表情や銃の質感、光の差し込み方まで鮮明に映り込み、手汗をかくほど没頭してしまったんです。
正直に言うと、贅沢の極み。
でも圧巻。
体験してしまった自分としては、もうフルHDやWQHDには完全には戻れません。
これぞ特権の世界。
面白いのは、この数年でハイエンドGPUの価格や入手性が以前ほど手の届かない存在ではなくなってきたことです。
昔は「一部の愛好家だけの領域」だったのに、今では頑張れば一般ユーザーでも揃えられる。
ちょうどスマートフォン市場と同じです。
中堅機でも十分便利なのに、フラッグシップ機は圧倒的に突き抜ける。
その構造がPCパーツ市場にも重なって見えるんです。
ただし、ここで大事な注意点があります。
どの解像度を選ぶにしても、「最低限ギリギリ回ればいい」程度の構成にしてしまうと、案外早く限界がやってきます。
その度に「もう一歩余裕が欲しかった」と後悔するんです。
残酷なくらいシビアな世界ですから、ほんのわずかなフレームレートの落ち込みが勝敗を分ける場面なんて珍しくありません。
メモリの容量やSSDの空き、VRAMの余裕。
こうした一見地味な要素が、実際には快適さを左右する大きなカギになるんです。
まとめるとこうです。
フルHDで競技に集中したいならCore Ultra 5とRTX 5060Ti。
WQHDを狙うならCore Ultra 7やRyzen 7とRTX 5070かRX 9070XT。
そして4Kを夢見るならRTX 5080やRX 7900XTXに水冷を組み合わせた構成。
これが私の中で「三本柱」です。
最後に私が一番伝えたいのは、この選択はただのスペックの話ではなく、「自分の遊び方への投資の覚悟」だという点です。
最高の体験を求めるのか。
あるいはコストを抑えて気楽に楽しむのか。
その判断を下せるのは、結局のところあなた自身なんです。
どこまで本気で遊びたいか。
それが答えです。



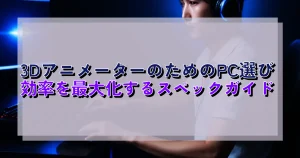
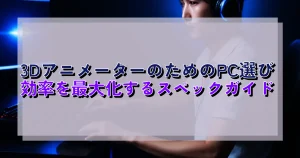
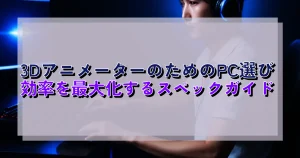






FAQ よくある疑問と答え
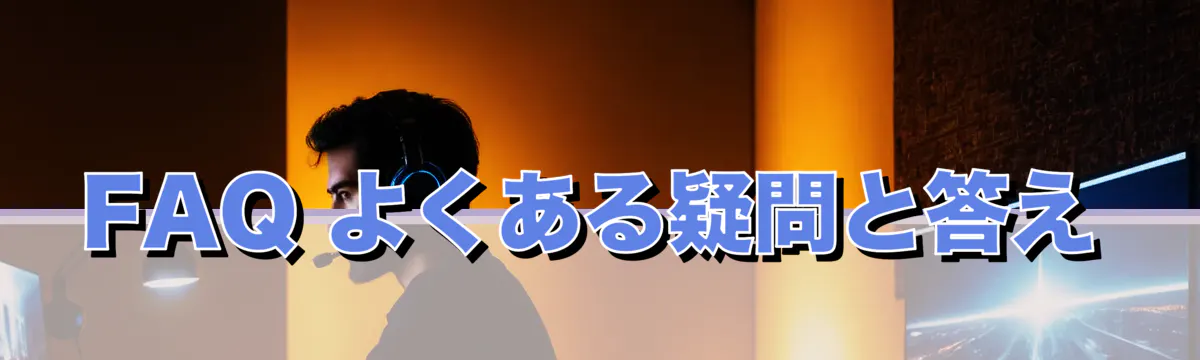
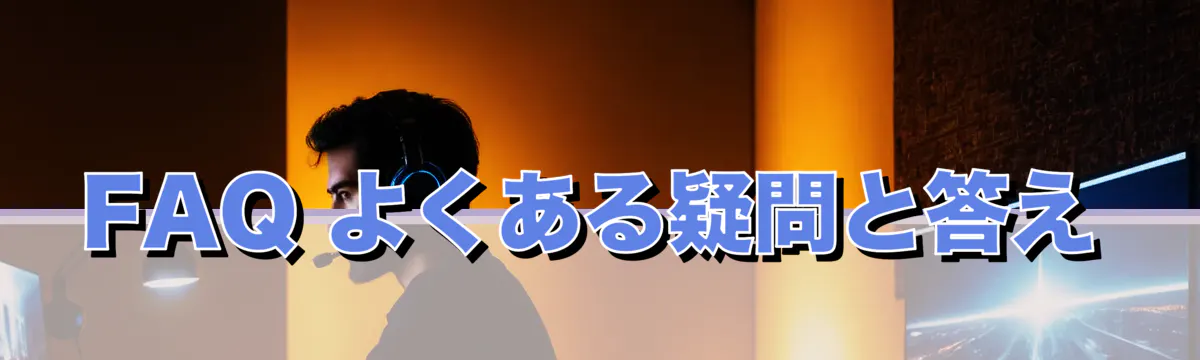
Apex Legendsはメモリ16GBでも十分?
Apex Legendsを快適にプレイするために必要なメモリ容量が16GBで十分なのか、それとも32GBを選ぶべきか。
これはゲーマー同士でよく持ち上がる話題で、私も過去に悩んできた内容です。
率直に言えば、ゲーム単体を動かすだけなら16GBでほとんど問題は感じませんでした。
ただし、それで満足できるかは人それぞれですし、私自身の体験ではゆとりを持たせた32GB環境の方が安心して楽しめました。
後から「やっぱり増設すればよかった」と悔やまずに済むので、結局は32GBを選んだほうが賢いやり方だと考えています。
昔、まだBTOの初心者だった頃に16GBを積んだPCを組んだことがあります。
その構成でフルHD環境なら快適に遊べて、仲間と深夜までプレイしていても不満など特にありませんでした。
メモリの使用量も12GB前後で収まっていましたし、その時は「もうこれで十分だな」という気分だったのです。
ところが思わぬ落とし穴が待っていました。
試合後にスプレッドシートで記録をまとめようとしたり、Discordで会話しながらブラウザを何枚も開いたりすると、急に重くなって焦る瞬間があったのです。
あの時のがっかり感、今でも忘れられません。
その経験があってからは気持ちが揺れました。
でも快適さや未来を考えたら16GBでは不安。
あるとき配信や録画に挑戦するようになったのですが、16GB環境ではどうしても動作が苦しく、同時進行が成り立たなかったのです。
我慢を重ねた末に32GBへ換装しました。
その瞬間、「最初からやっておけばよかったな」という言葉が自然に口を突いて出ました。
今にして思うと、それは単なるスペックの話だけではありません。
心の余裕の話でもあったのです。
16GBだと「足りるかな」といつも気にかけてしまい、小さなストレスを感じ続ける。
ゲームも作業も、安心して取り組める。
気分まで軽くなるんですよね。
とは言っても誰もが32GBを選ぶ必要があるかと言えば、そうでもありません。
配信や録画を全くしない場合、ただApexを遊ぶだけなら16GBで十分な環境は作れると思います。
むしろフルHDで高リフレッシュレートを求めるなら、GPUの性能を優先する方が効果は大きい。
メモリに余裕があっても、肝心のGPUが足りなければ意味は薄いです。
ですからプレイスタイルによって答えは違うものになります。
ただ興味深い事実もあります。
16GBと32GBで平均fpsはそこまで変わらないのに、負荷の高い瞬間には差が出ます。
一方32GB環境ではそうした場面が滑らかに処理される。
わずかな差に見えても、一瞬の反応が勝敗を決めるゲームでは無視できないことです。
私はその現実を身を持って体感しました。
さらに最近ではメモリ市場の事情も変わりました。
DDR5へ移行する中で32GBキットが思いのほか手ごろに買えるようになったのです。
数年前は憧れの価格帯で、手が届かずに「いつか余裕が出たら」と思っていたもの。
でも今では少しの予算追加で現実的に購入できる。
店頭で見た時に心から驚きました。
「え、ここまで安くなったのか」と。
そういう流れもあり、今は32GBに乗り換えるハードルがかなり下がっているのです。
私なりの結論を整理するとこうです。
Apex Legendsだけを純粋に楽しむなら16GBでも困りません。
しかし配信や録画、並行作業を考えるなら16GBは窮屈です。
余裕を求めるのであれば32GBを選ぶ価値は十分にありますし、将来的にも安心です。
仕事の合間にゲームを遊ぶ立場としても、余計な不安が頭をよぎらないだけでも気持ちよく過ごせますから。
だからこそ、これから新しくPCを組む人には自分の体験を伝えたいと思います。
「少しの投資が、長く快適に遊べる安心に変わる」これが私の正直な感覚です。
忘れたくない大切なこと。
私は32GBを選びます。
静かな納得。
積み重ねの価値。
数値以上に大切な心の余裕。
人気PCゲームタイトル一覧
| ゲームタイトル | 発売日 | 推奨スペック | 公式 URL |
Steam URL |
|---|---|---|---|---|
| Street Fighter 6 / ストリートファイター6 | 2023/06/02 | プロセッサー: Core i7 8700 / Ryzen 5 3600
グラフィック: RTX2070 / Radeon RX 5700XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Monster Hunter Wilds
/ モンスターハンターワイルズ |
2025/02/28 | プロセッサー:Core i5-11600K / Ryzen 5 3600X
グラフィック: GeForce RTX 2070/ RTX 4060 / Radeon RX 6700XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Apex Legends
/ エーペックスレジェンズ |
2020/11/05 | プロセッサー: Ryzen 5 / Core i5
グラフィック: Radeon R9 290/ GeForce GTX 970 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| ロマンシング サガ2
リベンジオブザセブン |
2024/10/25 | プロセッサー: Core i5-6400 / Ryzen 5 1400
グラフィック:GeForce GTX 1060 / Radeon RX 570 メモリ: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| 黒神話:悟空 | 2024/08/20 | プロセッサー: Core i7-9700 / Ryzen 5 5500
グラフィック: GeForce RTX 2060 / Radeon RX 5700 XT / Arc A750 |
公式 | steam |
| メタファー:リファンタジオ | 2024/10/11 | プロセッサー: Core i5-7600 / Ryzen 5 2600
グラフィック:GeForce GTX 970 / Radeon RX 480 / Arc A380 メモリ: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| Call of Duty: Black Ops 6 | 2024/10/25 | プロセッサー:Core i7-6700K / Ryzen 5 1600X
グラフィック: GeForce RTX 3060 / GTX 1080Ti / Radeon RX 6600XT メモリー: 12 GB RAM |
公式 | steam |
| ドラゴンボール Sparking! ZERO | 2024/10/11 | プロセッサー: Core i7-9700K / Ryzen 5 3600
グラフィック:GeForce RTX 2060 / Radeon RX Vega 64 メモリ: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE | 2024/06/21 | プロセッサー: Core i7-8700K / Ryzen 5 3600X
グラフィック: GeForce GTX 1070 / RADEON RX VEGA 56 メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ファイナルファンタジーXIV
黄金のレガシー |
2024/07/02 | プロセッサー: Core i7-9700
グラフィック: GeForce RTX 2060 / Radeon RX 5600 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Cities: Skylines II | 2023/10/25 | プロセッサー:Core i5-12600K / Ryzen 7 5800X
グラフィック: GeForce RTX 3080 | RadeonRX 6800 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ドラゴンズドグマ 2 | 2024/03/21 | プロセッサー: Core i7-10700 / Ryzen 5 3600X
グラフィック GeForce RTX 2080 / Radeon RX 6700 メモリー: 16 GB |
公式 | steam |
| サイバーパンク2077:仮初めの自由 | 2023/09/26 | プロセッサー: Core i7-12700 / Ryzen 7 7800X3D
グラフィック: GeForce RTX 2060 SUPER / Radeon RX 5700 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ホグワーツ・レガシー | 2023/02/11 | プロセッサー: Core i7-8700 / Ryzen 5 3600
グラフィック: GeForce 1080 Ti / Radeon RX 5700 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| TEKKEN 8 / 鉄拳8 | 2024/01/26 | プロセッサー: Core i7-7700K / Ryzen 5 2600
グラフィック: GeForce RTX 2070/ Radeon RX 5700 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Palworld / パルワールド | 2024/01/19 | プロセッサー: Core i9-9900K
グラフィック: GeForce RTX 2070 メモリー: 32 GB RAM |
公式 | steam |
| オーバーウォッチ 2 | 2023/08/11 | プロセッサー:Core i7 / Ryzen 5
グラフィック: GeForce GTX 1060 / Radeon RX 6400 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| Monster Hunter RISE: Sunbreak
/ モンスターハンターライズ:サンブレイク |
2022/01/13 | プロセッサー:Core i5-4460 / AMD FX-8300
グラフィック: GeForce GTX 1060 / Radeon RX 570 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| BIOHAZARD RE:4 | 2023/03/24 | プロセッサー: Ryzen 5 3600 / Core i7 8700
グラフィック: Radeon RX 5700 / GeForce GTX 1070 メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| デッドバイデイライト | 2016/06/15 | プロセッサー: Core i3 / AMD FX-8300
グラフィック: 4GB VRAM以上 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| Forza Horizon 5 | 2021/11/09 | プロセッサー: Core i5-8400 / Ryzen 5 1500X
グラフィック: GTX 1070 / Radeon RX 590 メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
RTX 5060TiとRX 9060XT、性能的にはどっちが有利?
Apex Legendsを快適に楽しむために、グラフィックカード選びは避けて通れないテーマだと私は感じています。
私自身が試してきた経験から言えば、もし本気で高フレームレートと快適さを追求するなら、RTX 5060Tiの方が一枚上を行くと思います。
理由は明確で、NVIDIAのReflexやDLSSといった独自の機能が競技性の高い場面において実用的に効いてくるからです。
特に大会シーンやスクリムのようにフレームレートが一瞬の判断に影響するような状況では、確かなアドバンテージになると実感しました。
実際、設定を極限まで落としフレームレートを優先したプレイをしたとき、わずかな差が勝敗に響く場面が何度もありました。
やっぱりここは無視できませんね。
一方で、RX 9060XTを軽んじるのはもったいないと感じます。
価格帯を踏まえるとむしろ非常に魅力的で、コストパフォーマンスの観点から見ればこちらが正解になる場合も多いからです。
FSRによるフレーム生成も安定しており、普段遊ぶ分には全く不満を感じません。
私は以前、BTOパソコンでRXシリーズを導入したことがあるのですが、そのときに感じたのは電気代の安さと発熱の少なさによる快適さでした。
長い時間プレイすると小さな差が積み重なって、最終的には大きな違いになるんだと痛感しました。
静かに効いてくる安心感。
それを改めて覚えました。
Apexの場合、CPUの依存度が比較的低いため、性能を左右するのはGPUとVRAMになります。
RTX 5060TiではGDDR7メモリが高い帯域を確保しており、高リフレッシュレートのモニターを使った環境でも安定感が出ます。
例えば、激しい銃撃戦が続くシーンでも極端なフレーム落ちが少なく、滑らかさが持続してくれるのです。
それに対してRX 9060XTも大容量のVRAMを積んでおり、追加コンテンツのマップや高精細なテクスチャ表示にも強さを感じました。
実際に「お、このカード、思った以上に持ちこたえるな」と声を漏らした瞬間もありましたから、正直に驚かされました。
中長期の視点になると、RTXの強みはやはりDLSSやAIベースの処理機能にあります。
新しいタイトルや機能拡張が出るたびに、その余裕を感じさせてくれるのは未来志向の安心に繋がります。
対するRXはFSRが改善されてきたとはいえ、場面によって出来にムラを感じることもあるのが惜しい点です。
「安定は正義。
」その想いを持つ私としてはどうしても気になる部分でした。
具体的にパフォーマンス差を挙げると、RTX 5060Tiと240Hzモニターの組み合わせでは200fps前後を維持するシーンが多く、勝負どころでしっかり踏ん張ってくれます。
その余力があることで、攻める時の判断に迷いが減るんですよね。
逆にRX 9060XTでは160?180fpsの範囲で動くことが多い印象ですが、価格を抑えながらこの数字を出すのは十分に立派です。
さらに静音性や電力効率に目を向けるとRXの魅力が際立ちます。
私はリビングに小型ケースを置いて生活の中で使ったことがあったのですが、そのときの静かさや熱の少なさが家族の日常を変えました。
騒音がないだけで妻からの苦情が減り、心地よくゲームができる時間が確保されたのです。
私にとっては性能以上に価値が感じられた瞬間でした。
やっぱり、家庭環境での快適さの影響は大きいです。
こうやって改めて並べてみると、多くの人が気になる「どちらが正しい選択か」という問いは本当はナンセンスに近いのだと思います。
競技志向でフレームレートや遅延を優先するならRTX 5060Tiが適していますし、電力効率や静音性を含め、日常的でコスト意識の高い人にはRX 9060XTが向いています。
結局パソコンパーツにおいては、製品単体での優劣よりも、自分のライフスタイルとの相性がすべてなのだと感じます。
環境とスタイル。
この2つをどう考えるかに尽きるのです。
勝率を上げたいならRTXを選びますし、のんびりやりつつ電気代やコストを抑えたいならRXに軍配を上げます。
そのどちらを選んだとしても、きっと満足できる部分はあって、製品を通じて学びも得られる。
無理に一方を切り捨てて優劣をつける必要はないのだと思います。
最後に伝えたいのは、スペック表を眺めても本当の答えは見えてこないということです。
必要なのは、あくまで自分自身の使い方や生活に馴染むかどうか。
数字や比較表よりも、そこで得られる快適さや安心感に耳を傾けるべきだと私は考えています。
BTOと自作、Apex Legends向けにはどちらが現実的?
理由はシンプルで、市場のパーツ価格があまりにも不安定だからです。
グラフィックボードやCPUは数か月ごとに新製品が出て、少し判断を誤っただけでとんでもなく割高な買い物をさせられる。
正直、そこに振り回されるのはもう疲れました。
仕事の後にゲーム時間を気持ちよく楽しむために、必要なのは安定。
BTOの魅力は、すでに全体のバランスが調整されていることです。
ショップ側がある程度の最適解を組んでくれている。
私はこれを「余計な不安に時間を奪われず、純粋に遊べる安心感」だと考えています。
こういう時間の質、その価値を今さらながら痛感しました。
もちろん、自作を軽んじるつもりはありません。
私自身、20代30代のころは毎週末のように秋葉原へ通って、ケース一つでさえ何時間も迷っていました。
机いっぱいにパーツを並べて、ああでもないこうでもないと考えながら組む感覚。
そこには確かに興奮があった。
完成して電源を入れた瞬間に胸が熱くなったのを今でも思い出します。
これは間違いなく自作ならではの醍醐味です。
でも、冷静に言えばApexに必要な快適さはGPU性能に大きく依存している。
究極のCPUやメモリに凝っても、かけた手間に比べて得られる差は驚くほど小さい。
現実はそんなものなんです。
私は失敗も経験しています。
数年前、新しいGPUが話題になったとき、熱に浮かされたように市場を追いかけました。
最初は「今度こそ理想の環境だ」と心が躍っていたのですが、数週間で市場価格が乱高下し、気が付いたら完全にタイミングを外していました。
結局、考えていた倍近い金額で購入する羽目になり、その時の悔しさは今でも鮮明に覚えています。
あのとき思いました。
「最初からBTOを選んでおけば…」と。
安心を買うべき場面を見誤った、典型的な例ですね。
これは私の痛い教訓です。
ただし、BTOにも注意点があります。
電源や冷却への配慮を軽視すると痛い目を見るのです。
私の知人も価格だけを見て選んだ結果、電源がギリギリしか積まれていないモデルを手にしてしまいました。
その結果、高負荷がかかるとフリーズを繰り返す始末。
修理に出し、ゲームもできず、ただただ時間だけが過ぎる。
本人は本当に悔しがっていました。
電源と冷却。
ここは妥協したら絶対に後悔すると断言します。
一方で自作にしかない楽しさも健在です。
たとえばケースの多様さ。
最近はクリアパネルで魅せるデザインや、木材を取り入れたユニークな外観も増えていて、インテリア感覚で部屋に置けるPCも多い。
特に「見た目にこだわりたい」「静音性を徹底したい」と考えるなら、間違いなく自作が有利だと感じます。
ただ、Apexで結果を出すという一点に絞ったとき、この要素は趣味でしかない。
私にとって勝負を左右するのはfpsの安定以外にないから、どうしても自作よりBTOに気持ちが傾いていくのです。
見た目より実利。
これが正直な心境です。
また意外に大きな差を生むのが、サポートと保証です。
Apexはアップデートで環境が変わることが多く、突然ドライバやOSとの相性不具合が出ることがあります。
自作だと、この原因探しが本当にしんどい。
夜中にログをにらみながら試行錯誤し、気がつけば朝を迎え、翌日の仕事でぐったり……そんな失敗を私は何度か経験しました。
その点BTOは故障やトラブル時にメーカーの保証と修理にすぐ頼れる。
これは本当に安心です。
助けてくれる相手がいる。
それだけで気持ちがどれほど楽になるか、身をもって知りました。
だからといって、自作を切り捨てたいわけじゃありません。
夢中でパーツを探し、自分だけの一台を組む過程そのものが報酬になる。
映像編集やAIを活用した重い作業など、用途を拡張したい人には自作の柔軟さが光ります。
私自身、PCに求める役割が広がったときには再び自作へ戻る可能性がゼロではない。
自由に組み替えられる余白、そこに人を惹きつける力があるのは確かです。
ただ、現実的な答えは明確です。
Apexを快適に楽しむためだけを考えるなら、BTOです。
コストと安定性のバランスという意味で、これ以上の選択肢はない。
自作は挑戦であり趣味、BTOは安心であり現実解。
この線引きを頭の中で整理すれば、自ずと方向は見えてきます。
安定が勝利を呼ぶんです。
だから私は、同じようにApexを真剣に楽しみたい仲間には迷わずBTOを勧めます。