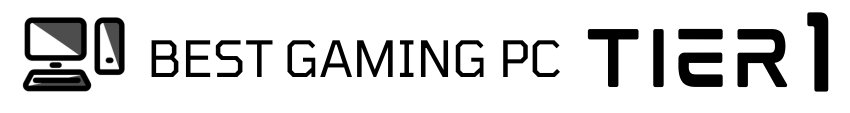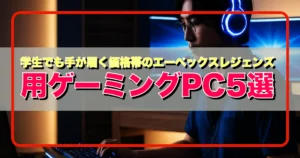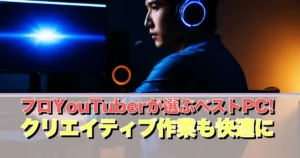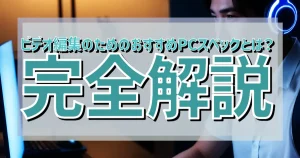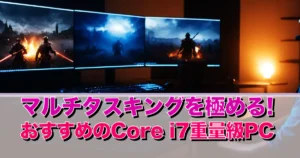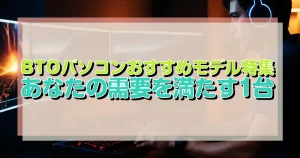Apex Legendsを快適に遊ぶためのPCスペックをわかりやすく解説
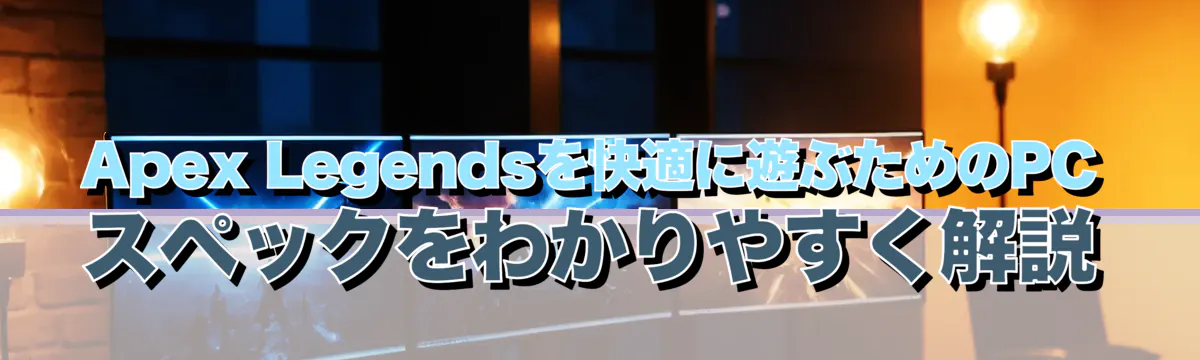
CPU選び CoreシリーズとRyzenシリーズ、実際に使って違いを感じるのはどこ?
それを突き詰めて考えていくと、やはりCPUの存在感が頭をもたげてきます。
ですが、CPUが安定していなければ結局はカクつきや遅延が生じ、いざというときに足を引っ張られる。
私はその現実を何度となく味わってきました。
数値だけ見ればGPUを優先させたくなるでしょう。
それでも最後の最後、勝負の場面で頼りになるのはCPUの処理力と安定感なんです。
私自身、Core UltraとRyzen 9000シリーズを行き来させながらプレイした経験を持っています。
数値上のベンチマークだけを眺めていると「そんなに違いはないのでは?」と安易に考えがちですが、実際に何時間もプレイし続けるとその感触に思わず頷かされるタイミングが出てくるのです。
そこで「よし、これなら作業が途切れない」と胸をなで下ろす安心感があります。
逆にRyzenのX3Dモデルでは、画面が混雑したシーンで妙な頼もしさを見せるんですよね。
特に移動中のフレーム落ちが軽く済み、緊張感が切れない。
あの踏ん張りを味わうと「やっぱりこれはゲーマーを分かっている作りだな」と唸らされます。
体感の差というのは面白いもので、フレームレートを定量的に測定すればどちらも十分に優秀です。
しかし手元に伝わるリズムや映像の滑らかさは、没入感に直結する。
新幹線と在来線を比較するようなものです。
最終的に着く場所は同じですが、揺れを感じるかどうかでその道のりの印象が全く違う。
これは数字では表せない大きな差です。
だからこそ、ある瞬間に「やっぱりこちらを選んで良かった」と安心できるかどうかがプレイヤーにとって重要なんでしょう。
もう一つ外せないのが発熱と騒音です。
正直、数年前までは深夜にゲームをしているとファンの音で気が散ることがありました。
しかし今は違います。
大型の空冷クーラーでも十分に冷却でき、音も静かになりました。
静音性がここまで向上していると、配信マイクが雑音を拾わなくなるのも大きな改善です。
一見小さな一歩のようですが、長時間のプレイを続ける者にとっては欠かせない進化でした。
私が率直に思うのは、扱いやすさを求めるならCore Ultra 7 265Kという選択がもっとも安心できる、ということです。
性能に癖がなく、電力効率も高く、オーバークロック耐性もあり、まさに相棒と呼びたくなるような安定感があります。
一方で「絶対に競技で勝ち抜きたい」と覚悟を持つならRyzen 7 9800X3Dの存在が浮上してきます。
膨大なキャッシュによる独特の粘りは、勝負の最後の場面で光ります。
本気で結果を求めたい人にとっては、この一枚が命運を握ることになるかもしれません。
そのとき私はきっぱりとこう答えます。
「配信と作業の安定を大事にしたいならCoreを選んだほうがいい。
もし勝負強さが第一ならRyzenを選ぶべきだ」と。
ここで曖昧な答えをすると、かえって相手を迷わせる。
明確に線を引くことが、パソコン選びのサポートには必要だと感じています。
つまり選択肢はシンプルなんです。
CoreかRyzenか。
その二択に尽きる。
どちらが優秀かではなく、自分がどこに重きを置くかが答えを決めるのだと思います。
これが理解できると、迷いよりもむしろ気持ちが晴れてくる。
シンプルゆえに難しい。
でも決断すれば迷いはない。
ここ数年のCPUの進化を追いかけてきた身としては、今後の新しい技術にもワクワクしています。
AIが組み込まれて、CPUが状況に応じて自動で負荷を最適化する時代。
そんな未来は決して夢物語ではなくなってきました。
まさに新しい当たり前になる。
その時を待ち望んでいます。
だから今の段階でApex Legends用にPCを選ぶなら、未来も見据えた決断が必要です。
配信と作業をバランスよく進めたい私はCore Ultra 7 265Kを推します。
けれど一瞬のブレも許さず、勝敗に命を懸けたい方にとってはRyzen 7 9800X3Dこそ唯一の答えとなる。
両者の違いを理解したうえでこそ、その決断に揺るぎがなくなるのです。
迷ったままでは前に進めません。
だからこそ選ぶこと。
PC選びというのはスペックを比べる作業のようでいて、実は自分の価値観を反映させる鏡のような時間です。
ただ性能を追いかけるのではなく、自分がゲームをどんな姿勢で楽しみたいのか。
そこに自分の意思を映し出すものだと私は思っています。
CPUひとつを決める行為でも、それは自分が大切にしたいスタイルそのものです。
そう考えると、決して単なる買い物ではない。
自分の歩みを選び取る、そんな誇らしい瞬間になっていくのだと強く信じています。
最新CPU性能一覧
| 型番 | コア数 | スレッド数 | 定格クロック | 最大クロック | Cineスコア Multi |
Cineスコア Single |
公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 9 285K | 24 | 24 | 3.20GHz | 5.70GHz | 43230 | 2437 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 42982 | 2243 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X3D | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 42009 | 2234 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900K | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.00GHz | 41300 | 2331 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X | 16 | 32 | 4.50GHz | 5.70GHz | 38757 | 2054 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X3D | 16 | 32 | 4.20GHz | 5.70GHz | 38681 | 2026 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265K | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37442 | 2329 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265KF | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37442 | 2329 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 9 285 | 24 | 24 | 2.50GHz | 5.60GHz | 35805 | 2172 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700K | 20 | 28 | 3.40GHz | 5.60GHz | 35664 | 2209 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900 | 24 | 32 | 2.00GHz | 5.80GHz | 33907 | 2183 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.60GHz | 33045 | 2212 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700 | 20 | 28 | 2.10GHz | 5.40GHz | 32676 | 2078 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X3D | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.50GHz | 32565 | 2168 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7900X | 12 | 24 | 4.70GHz | 5.60GHz | 29382 | 2017 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265 | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28665 | 2132 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265F | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28665 | 2132 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245K | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25561 | 0 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245KF | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25561 | 2150 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9700X | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.50GHz | 23187 | 2187 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9800X3D | 8 | 16 | 4.70GHz | 5.40GHz | 23175 | 2068 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 235 | 14 | 14 | 3.40GHz | 5.00GHz | 20946 | 1838 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7700 | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.30GHz | 19590 | 1915 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7800X3D | 8 | 16 | 4.50GHz | 5.40GHz | 17808 | 1795 | 公式 | 価格 |
| Core i5-14400 | 10 | 16 | 2.50GHz | 4.70GHz | 16115 | 1758 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 5 7600X | 6 | 12 | 4.70GHz | 5.30GHz | 15354 | 1959 | 公式 | 価格 |
人気GPUのRTX4070TiとRX7900XTを実際のゲーム体験で比べてみた
この実感は、私が実際に両方のカードを使い込んだうえで得た率直な結論です。
確かに数値上での性能比較はいくらでも表にまとめられますが、一晩中ゲームに没頭していると、紙の上では見えない「安定性の差」がはっきり気になってくるものなんです。
仕事の疲れを引きずった夜にお気に入りのApexを起動しても、設定の細かい調整や不安定なフレームに悩まされることなくサッと遊びたい。
それが本音ですよ。
そんなとき、私はRTX4070Tiの安定ぶりと取り回しの良さに何度も助けられました。
RTX4070TiをフルHD・240Hzのモニターと組み合わせたとき、フレームレートは180から240fpsを安定して維持してくれる。
重いエフェクトや爆発シーンが重なったときでも、急激にフレームが落ちこむことは少なく、その安心感が快適さを生むんです。
FPSのような一瞬の判断が勝敗を分ける場面では、この落ち着いた動作が精神的にも効いてくるんですよね。
変に肩肘張らずに自然と試合に集中できる。
逆にRX7900XTを同じ条件で試したとき、平均値では引けを取らないどころか優秀な瞬間もありましたが、フレームの波がどうにも荒い。
「あれ、今なんで落ちた?」と首をひねることが度々あり、体感を重視する私にとっては不安定さが気になりました。
ただし、解像度を4Kに切り替えるとゲームの様子は一変します。
RTX4070Tiでは映像負荷に押される場面が確かに出てきて、快適さはやや削がれる印象です。
一方でRX7900XTは大容量のVRAMが効いて、高テクスチャ設定でもロードが速く、描画もなめらか。
3時間以上遊んでみてもフレームが崩れにくく、「そうそう、これが余裕ってやつだ」と感じる瞬間が何度もありました。
腰を据えて大画面の迫力を堪能したい場面ではRX7900XTに軍配が上がるのは確かで、私はこの差をまざまざと体験しました。
次に、配信環境での違いです。
RTX4070Tiは映像エンコードの支援が本当に安定していて、私は週末にフレンドとボイスチャットを繋ぎながらOBSで何時間も配信したのですが、裏でアプリを立ち上げても映像が乱れにくかった。
「やっぱりNVIDIAはこういうところが強いな」とそのとき独り言が出たほどです。
RX7900XTも配信自体はもちろん問題なく可能なのですが、高解像度に設定すると唐突にカクっとした場面が増えました。
もし配信を軸に考える人なら、そこは頭に入れておいた方がいい。
価格面について触れると、これはもう時期とショップ次第で大きく変動します。
秋葉原を巡ったときにRTX4070Tiが思った以上に下がっていて、つい「これは即決でしょ」と声に出してしまったことがあります。
ところが別の日にオンラインで見ればRX7900XTが驚くほど安い。
価格の乱高下に一喜一憂するのも、自作PCという趣味の醍醐味かもしれません。
それから意外に侮れないのがドライバの進化です。
対してRadeonのドライバは、ある日突然劇的な伸びを見せることがある。
FSRや最適化次第でフレームが目に見えて変わり、「昨日までと全然違うじゃないか」と心底驚いた経験もあります。
だからこそ、単純にスペック表だけで結論を出すのは危険だと実感したんです。
要するに、フルHDやWQHD環境で安定さを重視し、さらに配信も絡めたいならRTX4070Tiが最有力です。
一方、休日に腰を据えて大型モニターで4Kの美しさを楽しみたいならRX7900XTに勝る選択肢はないでしょう。
私は両方を実際に使い込んで、そういう住み分けを見出しました。
突き詰めれば、自分がどんな遊び方を大切にしたいのか、そのスタイルこそが選ぶ基準になるのです。
仕事帰りに短時間でサクッと気分転換をしたいのか、それとも休日にどっぷり非日常の映像世界に浸りたいのか。
そこさえはっきりさせれば、迷いは意外と少なくなるはずですよ。
答えは、求める体験の中にあるんです。
最新グラフィックボード(VGA)性能一覧
| GPU型番 | VRAM | 3DMarkスコア TimeSpy |
3DMarkスコア FireStrike |
TGP | 公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | 32GB | 48879 | 100725 | 575W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5080 | 16GB | 32275 | 77147 | 360W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9070 XT | 16GB | 30269 | 65968 | 304W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7900 XTX | 24GB | 30192 | 72554 | 355W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5070 Ti | 16GB | 27268 | 68111 | 300W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9070 | 16GB | 26609 | 59524 | 220W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5070 | 12GB | 22035 | 56127 | 250W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7800 XT | 16GB | 19996 | 49884 | 263W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 16GB | 16625 | 38905 | 145W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 16GB | 16056 | 37747 | 180W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 8GB | 15918 | 37526 | 180W | 公式 | 価格 |
| Arc B580 | 12GB | 14696 | 34506 | 190W | 公式 | 価格 |
| Arc B570 | 10GB | 13796 | 30493 | 150W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 | 8GB | 13254 | 31977 | 145W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7600 | 8GB | 10864 | 31366 | 165W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 4060 | 8GB | 10692 | 28246 | 115W | 公式 | 価格 |
メモリ16GBで足りるか?32GBにするとどう変わるか実使用感から考える
しかし私自身、ある時から配信に挑戦しようと思い立ち、DiscordやOBSを同時に立ち上げて試合を重ねてみると、途端に足を引っ張られる感覚を覚えました。
そういう経験を重ねたことで「これはもう増設するしかない」と自分の中で覚悟が決まったのです。
16GBでのプレイ自体は、正直なところゲーム単体だけであればそこまで大きな問題は出ません。
ただ、試合に没頭しているときに限って裏でブラウザのタブが増えていたり、仲間と通話していたり、さらにOBSで配信まで走らせたりすると、一気に環境が窮屈になるんですよね。
そのせいでカーソルの反応がワンテンポ遅くなり、「今の一瞬が命取りだったのに!」と頭を抱えそうになる。
負け試合の原因が自分の技術ではなく機材のせいだと思った瞬間ほどやりきれないものはありません。
実際私は16GBの時に長めのマッチを配信していたのですが、残り数分の盛り上がりどころでカクつきが起こり、大事な場面を逃してしまったことが何度もありました。
気付いたらそのストレスでプレイそのものが楽しめなくなっていた。
裏でアプリを複数走らせても不安定にならないため、安心してゲームに集中できる。
例えば配信中にコメントを返したり、試合の合間に戦績を調べたりしても動作が止まらずに済むというのは、地味だけれど非常に大きな支えになってくれています。
肩の力が抜けて、自然にプレイへ気持ちが向かっていく。
視聴者の立場から見ても32GBへの移行は大きな意味がありました。
それまで配信を見てくれていた人から「途中で映像が止まってたよ」と言われた時は本当に情けなかったんです。
ですが新しい環境に変えてからは、そうした報告がぱったり消えた。
私自身も「これで余計な不安を感じずに試合に臨める」と思えて、自然と声のトーンまで明るくなったことを今でも覚えています。
最近新しく購入したBTOパソコンを開封した際、標準で32GBが搭載されていました。
もう当たり前のようにその容量が用意されているんだなと知り、少し時代の移り変わりを実感しました。
それが今や、32GBこそが「最低限の快適さ」を担保するラインに変わった。
周囲の仲間でも「とりあえず32GBで組む」という言葉を口にする人が増え続けています。
この流れの速さに、正直驚かされました。
一方で「それじゃ64GBはどうなの?」という問いもよく耳にします。
私も気になって試してみましたが、少なくともApexを中心に遊ぶ分にはオーバースペックでした。
確かに動画編集や高度な作業に踏み込む人なら必要かもしれません。
しかし配信を交えてゲームを楽しむ程度なら32GBで十分すぎる、これが率直な実感です。
むしろ64GBは使いこなす機会が少なく「自己満足」でしかないようにさえ思えてしまいました。
私は32GBの環境へ移してから、安心して長時間の配信ができるようになりました。
プレイヤーとして集中力が続きやすくなり、大事な場面での判断力も鈍らない。
ここまでくると「なぜもっと早く導入しなかったんだ」と自分でも少し後悔するほどです。
もちろん予算の問題は誰にとっても悩むポイントです。
しかし振り返るとメモリ価格は以前のような高嶺の花ではなくなりました。
それを知ってしまうと、16GBで環境を維持し続ける方がかえって損をしている気すらしてきます。
実際私も購入をためらっていた時期がありましたが、思い切って環境を整えた後は、確実に満足度が費用を上回りました。
もし後輩や知人に相談されたら、私は迷わずこう言うでしょう。
「Apexを本気で楽しみたいなら、迷わず32GBを選んだ方がいい」と。
あれこれ複雑に説明する必要はない。
シンプルですが、それが一番確実な解だと思うんです。
だって実際に経験したから。
16GBはもう過去の基準。
身も蓋もない表現かもしれませんが、この切り替えこそが本当に快適な環境を手に入れるための要です。
無理なく遊び、視聴者が快適に見て、そして自分も余裕を持って楽しむ。
そのすべてを支えているのは32GBのメモリなのです。
安心感。
私にとってはそれが、何よりの価値なのだと実感しています。
配信しながらプレイするならどの程度の安定動作を見ておくべきか
配信をしながらApex Legendsを快適に楽しむためには、単純に高いフレームレートが出ているだけでは足りないと私は痛感しています。
数字が良ければ問題ないだろうと軽く考えていた時期もありましたが、実際にはフレームレートが安定しないだけで視聴者のコメント欄には不満がにじみ出てきますし、こちらの集中力もすぐ途切れてしまうんです。
結局のところ、大事なのはブレない安定感だと思います。
配信ソフトの処理がCPUやGPUに予想以上の負荷をかけるので、余裕のあるマシン構成を組むことは「ぜいたく」ではなく「必須条件」だと身にしみてわかりました。
油断して適当に済ませると、画面がひっかかったり映像がカクカクしたりして、それまでの努力が無意味になってしまう。
だから私は余力を持ったパソコンを選ぶことを強くおすすめします。
私が経験から学んだことを率直に書くと、フルHDで配信を前提にするなら、CPUはCore Ultra 5やRyzen 5の上位モデル以上でなければ安心できません。
昔は「そこまで高性能じゃなくても十分だろう」と思って安めのモデルを使っていたのですが、実際には配信を続けるうちに処理が遅くなり、気づけばゲーム画面が止まりかけ、そのたびに視聴者とのやりとりもぎこちなくなってしまいました。
そのとき初めて「CPUはケチっちゃいけない」と思い知らされましたね。
GPUについても同じで、ゲームだけ遊べればいいという発想では不十分です。
Apex自体はある程度軽いゲームと見られていますが、配信をかけ合わせると急激に負荷が増します。
私がRTX5060Tiに切り替えたとき、「ああ、ようやく肩の荷がおりた」と素直に感じました。
楽になったんです。
そしてメモリ。
ここが地獄だった。
最初は16GBでいいだろうと高をくくっていたのですが、数時間経つと途端に重くなり、配信ソフトやチャットアプリがもたついてプレイどころの話ではなくなりました。
その後32GBへ増設した瞬間、肩の凝りが取れたような解放感が訪れました。
メモリって単なる数字ではなく、余裕を持つことで気持ちが落ち着くんです。
これは数字以上の安心を与えてくれる部分でした。
さらに重要なのはストレージです。
実は軽視しやすいのですが、ここが遅いと細かいストレスがズシッと心に積もります。
以前SATA SSDを使っていたときは、ゲームのロードや配信ソフトの立ち上げに妙な待ち時間があり、その数秒が地味にイライラを募らせるんですよね。
そこで思い切ってPCIe Gen4のNVMe SSDに変えたときの衝撃は忘れません。
ロードが実質ゼロに近づき、すぐに操作できる感覚が配信全体を明るくしたんです。
気持ちまで前向きになりましたね。
そして冷却。
ここを甘く見てしまうと本当に痛い目に遭います。
画面の向こう側の沈黙がこちらまで突き刺さってきて、冷や汗が止まりませんでした。
その経験から冷却に投資するようになり、大型の空冷と簡易水冷を導入しました。
冷却が足りないと全体が不安定になり、どれだけ性能の高いCPUやGPUを積んでいても意味をなさないんです。
ケースについても皆さんなめがちですが、私はケースで失敗した身です。
古いケースを使っていたとき、どうしても熱がこもってファンの音も大きくなり、集中しにくい環境が続いていました。
そこでしっかりエアフローが取れるメッシュケースに替えたら、静かさも快適さも桁違いに良くなったんです。
そのとき、「見た目や値段だけじゃなく、ケースは心地よさを決める最後のピースなんだ」と素直に思いました。
まとめると、配信をしながらApex Legendsを快適にプレイするには、強力なGPU、余裕あるCPU、32GB以上のメモリ、高速ストレージ、冷却環境、この五つが必須です。
そして最後にケースまで手を抜かないことが、配信環境を安定させるために欠かせない条件です。
これらを揃えるのは正直簡単ではありませんし、コストもかかります。
Apex Legends向けゲーミングPC 予算ごとのオススメ構成

エントリーモデルでも十分遊べる実用的な構成例
実際、ここ数年はミドルクラス寄りのPC環境でプレイしていますが、驚くほど快適に動いてくれているのです。
フルHDで遊ぶ前提なら、十分に勝負できる性能があるし、正直に言えば「もっとお金をかけないとダメだろう」と考えていた自分の昔の思い込みが笑えるほどです。
私の現在の環境は、Core Ultra 5とGeForce RTX 5060 Tiを組み合わせたものです。
描画を標準にしておけば、150fps前後で安定してプレイでき、撃ち合いの際に遅延を不安に感じたことがありません。
昔は「重たいゲームなんだから、最新かつ最上位が必須だ」と思い込んでいたのですが、その根拠はまったくの幻想でした。
体験してみれば分かります。
十分なんです。
さらにメモリは16GBのDDR5を積んでいます。
これがなかなか快適で、Discordで仲間と通話しながらブラウザで攻略情報を調べつつ遊んでも、特にカクつきを感じることがない。
仕事上で培ったマルチタスクの癖がゲームにも出てしまう私には、この余裕がありがたい。
ストレージは1TBのNVMe SSDにしました。
これが大正解。
最近はアップデートや追加コンテンツの容量が膨れ上がっているので、容量が足りなくなるたびに古いデータを削除するなんて面倒でやってられない。
仕事帰りの貴重な時間を、そんな細かい作業に使いたくないんですよ。
楽しむ時間は何より大事だから。
電源は650W。
正直、少し余裕を見ました。
でもこの余裕が安心に繋がります。
GPUをフルで回しても電力不足を心配せず使えるし、将来的に上位のグラフィックカードに入れ替える可能性を考えても、この選択は無駄にならない。
「今を楽しみつつ先も見据える」なんて、仕事に通じるものがありますよね。
安いモデルに見えるかもしれないけれど、今のエントリーモデルやミドルレンジの性能って昔のハイエンドに迫るものがあるんです。
これは本当にありがたい時代だと思います。
だから私は声を大にして言いたい。
無理して上を目指す必要はないんだ、と。
背伸びはほどほどでいい。
ケースのデザインについても思っていた以上に日常に影響しました。
私が購入したBTOパソコンにはピラーレスデザインのケースが採用されていて、ガラス面から内部のライティングが見える仕様です。
買う前は「ケースなんて機能を守る入れ物でしかない」と思っていたのですが、実際に自宅の部屋でその光景を見ると気持ちが変わります。
仕事終わりにPCを起動した瞬間、ちょっとした高揚感がありますし、それが小さなご褒美のようになっているんです。
冷却性能も予想以上で、空冷でも安定した温度を維持できています。
正直、ありがたい驚きでした。
水冷を導入しなくても、Core Ultra 5やRyzen 5クラスであれば空冷で十分。
これを実感するのは長時間遊んだ時です。
ファンの音が気にならないように静音性にこだわったおかげで、配信しながらでも騒音の指摘をもらったことが一度もない。
気兼ねなく遊べる。
これがいいんですよ。
モニターやネットワーク環境も侮れません。
例えば240Hz対応のモニターを導入したとき、その滑らかさの違いはすぐに体で理解できます。
144Hzとの差は驚くほど。
特にApexの場合、エイム力に直結するので、投資した価値を体感します。
有線LANで2.5GbE接続をしてから、撃ち合い中に通信が詰まる不安が消え、プレイの集中力が高まりました。
本体だけをグレードアップさせても体験の質は伸び悩む。
周辺環境を含めて整えることが本当の快適さにつながるのです。
私が推す構成はシンプルです。
Core Ultra 5かRyzen 5 9600、そこにGeForce RTX 5060 TiかRadeon RX 9060 XTを合わせた構成。
メモリはDDR5で16GB、ストレージは1TBのNVMe SSD、電源は650W。
これで画質を中設定にすれば150fps以上を安定して出せて、配信だって余裕を持って行えます。
この構成ならばしばらく買い替えを考えずに済みます。
コストとパフォーマンスの両立がしっかり取れているからです。
毎回PCを起動するたび、「良い買い物をしたな」と心から思える。
小さな満足。
だけど積み重なれば大きな支えです。
人は誰でも、無理のない範囲で少し背伸びしたい。
趣味だからこそ、そのバランスが心地よいんだと実感しています。
ミドルクラスならではのコスパ重視ポイント
Apex Legendsを快適に遊びたいと思ったとき、私は「高いモデルを買えば間違いない」とは思わないんです。
なぜかというと、極端に高価なハイエンド機を用意しなくても、実際に必要な性能は十分に確保できるからです。
体感としては、フルHDやWQHDで遊ぶ環境なら、価格とのバランスがちょうどいい位置に落ち着くのがミドルクラスだというのが率直な印象ですね。
必要十分で、不足を感じない。
ここに尽きます。
私が実際に組んでみた構成では、Core Ultra 7とRTX 5070を選びました。
結果は予想以上に快適で、Apexを高フレームレートで動かしながら、配信ソフトを同時に実行しても不満を覚えるシーンはありませんでした。
そのとき心の中で「なんだ、これで十分じゃないか」と思わされたんです。
肝心になるのはやはりグラフィックボード。
私はこれを選び間違えると後悔の入口になると思っています。
たとえばRTX 5060TiやRadeon RX 9060XTなら、そこそこ手に入れやすい価格なのに描画の安定感はしっかりしていて、144Hzモニターにもしっかり対応できます。
正直、この辺りの性能で多くの人の環境には十分応えてくれるはず。
でも、「あと少し余裕が欲しい」と思うなら、RTX 5070やRX 9070あたりが安心感を与えてくれるクラスになるでしょうね。
200fps近いフレームを狙えるなら、競技性を重視した遊び方でも納得できます。
逆にケチって失敗すると、「しまった、もっと上にしておくべきだった」とハッキリ悔やむ場面が見えてくる。
買い替えの二度手間ほど無駄なものはない、と私は声を大にして言いたいんです。
そして忘れがちなのが電源と冷却。
地味ですが、ここを軽視すると安定性を失って、せっかくのスペックが台無しになります。
電源に関しては650W以上、できれば80PLUS Goldくらいは押さえた方が安心です。
長時間ランクマッチに集中していても耳障りにならず、集中が途切れなかったんです。
水冷が豪華に映ることもあるのですが、実際はミドルクラスなら空冷で十分。
冷却に求めるのは派手さではなく、落ち着いた信頼感だと思っています。
ストレージの選択も悩ましいのですが、今なら最低ラインは1TBのNVMe SSDにすべきでしょうね。
最近のゲームは数十GB単位で更新され、知らないうちに容量が一気に減っていくものです。
2TBにしておけばより余裕を持てますし、心理的な安心感も増します。
私も過去に「HDDで十分だろう」と安易に決めたことがありました。
でも起動の遅さにうんざりし、何度もPC前でイライラしました。
SSDに切り替えたとき、立ち上がりの速さに「もう戻れない」と心から思いましたよ。
これは本当に大きい違いなんです。
PCケースについても触れておきたいです。
あまり優先度を高く感じない人もいますが、エアフローの効率や掃除のしやすさは想像以上に効いてきます。
私は以前、派手なRGBライティングのケースを見た目だけで選びました。
ところが使ううちに、意外にも内部設計が丁寧でメンテナンス性が高く、パーツ交換のしやすさに助けられたのです。
「見た目で選んだはずなのに、結果的には使いやすさで得をしたな」と後で気づきました。
結局、ケースは単なる箱ではなく、安定感を支える土台。
ここを軽く見ると後で痛い目を見るというのが実感です。
メモリに関しても、思った以上に後悔しやすい部分です。
現状16GBでもゲーム自体は動きますが、配信やブラウザを同時に扱うと急に足りなくなる。
その瞬間「やっちまったな」と思わされます。
私も16GBで配信に挑戦したことがありましたが、動きが遅れて舌打ちする自分がいました。
そうなりたくないなら、32GB。
使わない分があっても邪魔にはならないし、逆に持て余すくらいが快適さにつながるんです。
余裕大事。
こうして考えると、私がベストだと感じる構成はだいたい固まってきました。
CPUならCore Ultra 5かRyzen 7。
グラフィックならRTX 5060TiかRadeon RX 9060XT以上。
メモリは32GB。
ストレージは少なくとも1TBのSSD。
電源は650Wクラスにして、冷却は空冷。
ケースはシンプルで扱いやすいもの。
突き詰めていけばこの組み合わせが一番現実的なんです。
余計な見栄や派手さには走らず、堅実で長持ちする構成。
それが結果的に私たちにとって一番満足感をもたらすと思います。
もちろん、ハイエンドで夢を追うのも一つの楽しみではあります。
ただ40代になった今の私には、価格と性能の釣り合いを見ながら、冷静に長く付き合える相棒を選ぶことにこそ価値を感じます。
振り返ると、結局ミドルクラスこそが一番バランスが良い、というところに落ち着くんです。
最後にもう一度だけ言います。
無理しないミドルクラスへの投資。
それこそが、後悔しない賢い選び方だと私は信じています。
これが私の答えです。
ゲーミングPC おすすめモデル5選
パソコンショップSEVEN ZEFT Z56R

| 【ZEFT Z56R スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra9 285K 24コア/24スレッド 5.70GHz(ブースト)/3.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z59E

| 【ZEFT Z59E スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | DeepCool CH160 PLUS Black |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z54ARV

| 【ZEFT Z54ARV スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | INWIN A1 PRIME ピンク |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860I WiFi |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z52BC

| 【ZEFT Z52BC スペック】 | |
| CPU | Intel Core i7 14700KF 20コア/28スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S100 TG |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
ハイエンド構成なら4K配信も安心できるパワー
圧倒的な解像度でプレイできる満足感も確かにありますが、それ以上に「安定した配信を届けられる」という安心感が一番大きい。
配信中にカクついたり映像が荒れたりすると、それだけで空気が一気に冷めてしまうんですよ。
だから私は、まず「安定性ありき」で構成を考えるようになりました。
以前使っていたPCはWQHDであれば特に困ることなく快適に遊べていました。
ただ、そこで配信を重ね始めると途端に弱点が浮き彫りになったんです。
特に激しい戦闘シーンでは画質が破綻しがちで、その瞬間にコメントで「今のカクついたよ」と指摘を受けた時、心底情けない思いをしました。
あの一言は背筋が冷えるような感覚でしたね。
やはり高解像度で配信を考えるなら、それなりの覚悟を持ったスペックが必要だと痛感しました。
その時の悔しさが、私をハイエンド環境に踏み切らせる決め手になったんです。
環境を見直すにあたって、私がまず重視したのはGPUでした。
私はRTX 5080を選びましたが、正直この金額を一気に投じるのは胃が痛む買い物でした。
それでもApexのようなGPU依存度の高いタイトルでは、ここに投資するかどうかで結果がはっきり変わります。
配信と同時処理になると映像の滑らかさに直結しますし、帯域を強引に食い潰すような負荷がかかっても、このクラスなら余裕で捌いてくる。
安心感が違いました。
CPUにはRyzen 7 9800X3Dを組み合わせていますが、X3Dキャッシュの効き目なのか、大人数が入り乱れる局面でもフレームが崩れることがない。
プレイ中に「今日の動きはやけに快適だな」とふと実感できた時、胸の奥がじんわりと満たされるんです。
さらにメモリは32GB DDR5を必須ラインと決めました。
16GBでもやれないことはありませんが、ブラウザを複数開いただけで挙動が怪しくなる。
その頼りなさは何度味わっても耐えられない悔しさでした。
だからこそ、余裕を持たせた構成が結果的にストレスをなくすんですよね。
音楽を流しながら配信しても、裏で資料を整理してもビクともしない。
ストレージには2TB NVMe SSDを搭載しましたが、これは正解でした。
ゲームの大型マップも動画素材も余裕をもって保存でき、いちいち空きを気にするストレスから解放されたのは大きいです。
温度管理の重要性も再認識しました。
配信は数時間に及ぶこともあるため、負荷がかかり続ければ当然温度が上がります。
その結果、CPUもGPUも70度あたりで安定してくれる。
ファンの音に邪魔されてゲーム音がかき消されることもなくなり、正直かなり救われました。
以前の空冷では配信後半になるにつれて轟音になり、正直「もうやめようか」とまで思った瞬間もありました。
騒音に悩まされなくなった今、その快適さのありがたみをしみじみ感じています。
これらの準備を整えると、目の前のプレイと配信の見え方がまるで変わります。
このご時世、SNSで切り抜き動画をポンと載せる人も多い。
そこでは映像の品質が直接「この人は上手そう」とか「見やすい配信だ」といった評価に繋がります。
つまり妥協した配信環境では、せっかくのプレイ内容に見合わない印象を与えてしまう可能性すらあるんです。
だから私は迷うことなく「配信環境に妥協は絶対にすべきじゃない」と断言します。
実のところ、私は昨年に性能不足な構成で4K配信へ挑んで大きく失敗しました。
思い出すと苦笑いしか出ません。
映像はガタガタ、戦闘シーンではフリーズの嵐で、まさに「見苦しい」という言葉がピッタリのものでした。
でもその経験から一つの確信を得ました。
快適さはプレイヤーの自己満足に留まらず、視聴者の体験そのものを形作る大きな要素だということです。
こちらが楽しそうにプレイしている姿を真っ直ぐに伝えるには、滑らかで美しい映像がどうしても不可欠なんです。
もちろん、ハイエンド構成は決して安い買い物ではありません。
私自身、正直なところ財布の紐を何度も締め直しながら考えました。
それでも冷静に未来を見据えれば答えははっきり出ます。
今後数年先のアップデートや新作FPSの要求スペックを考えると、初めから基盤を固めておく方が長い目では結局コスパが良いんです。
AIベースのフレーム生成やアップスケーリングの進歩もあり、4Kでもなめらかで120Hz級の体感が得られる。
ただ数年前には考えられなかったような進歩を享受できることを思えば、この投資には十分な意義があります。
気づいてみれば、私は4K配信を負担と感じなくなりました。
むしろ「楽しめる領域」に変わったんです。
自然と声にも余裕が出て、プレイも伸び伸びしてくる。
視聴者に伝わる雰囲気も確実に変わっていく。
本当にプラスしかありません。
だから私は断言します。
Apexを4Kで配信するなら、迷わずハイエンド構成を選ぶべきだ。
そこにこそ安定性、画質、そして自分の楽しさを守る鍵があるんです。
最終的にこの選択こそが唯一の解だと、自信をもって言い切れます。
結局のところ──答えは明快なんですよ。
Apex Legendsの配信を快適にするためのPC構成ポイント

CPUとGPUの組み合わせ次第で変わる配信の画質と安定度
Apex Legendsを安定して配信したいと思うなら、CPUとGPUの相性をきちんと考えることが何より大事だと私は強く感じています。
片方だけをとにかく高性能にしても、いざ配信で動かすと映像がガクつき、フレームが乱れ、心底がっかりした悔しい記憶がいまだに消えません。
私も昔はそう思っていた一人ですが、実際にはそう単純なものではありません。
エンコード処理はCPUにのしかかるからです。
CPUの並列処理が弱ければ、せっかく良いGPUを載せていても結果はお世辞にも安定とは言えません。
私はそれで何度も「やってしまった」と後悔しました。
思わずため息をついた夜もありました。
その結果は本当に鮮明で、前者は複数の配信ソースを扱っても動きが軽やかだったのに対し、後者はGPUを活かす場面で強さを発揮するイメージでした。
もう野球チームの監督とエースの関係そのもので、監督の采配次第でエースの力も変わると実感しました。
痛烈な気付きでした。
GPUの性能そのものも、もちろん無視できません。
RTX 5070やRadeon RX 9070XTクラスであれば、ソロプレイで200fps近い描画も余裕でこなします。
ただし、いざ配信を始めるとその余裕は一気に目減りするんです。
CPUが踏ん張れなければ急にフレームが落ち込む。
こればかりは現場で体験するまで想像できませんでしたね。
ソフトウェアエンコードを選ぶならCPUの強さがものを言いますし、GPUエンコードならRTX 5060Ti以上かRadeon RX 9060XTクラスが安心です。
Ryzen 9800X3Dの大容量キャッシュが絶妙に効いて、バランスを整えやすかったのが印象的でした。
設計の妙というやつです。
冷却と電源を甘く見ると痛い目を見ます。
これは私の苦い経験です。
以前、簡易水冷をフロントに付けていたのですが、高負荷テストで温度が80度近くまで跳ね上がり、配信中の画質が一気に荒れるという最悪の結果を招きました。
そのショックから空冷に変更し、ケース全体のエアフローを根本的に見直すとどうなったか。
温度が60度程度で安定し、フレームの落ち込みも止まりました。
つまり、冷却ひとつでゲーム配信の質まで直結する。
これには鳥肌が立ちました。
油断大敵です。
CPUとGPUの役割分担をあらかじめ明確にすること。
どちらでエンコードするかを最初から決めて設計すること。
これさえ守れば、冷却と電源をきちんと整えるだけで高負荷時もスムーズに動き続けます。
さらに最近のパーツはAI処理が組み込まれており、思っていた以上に余裕を確保できるのが特徴です。
ここを見極めて世代ごとの特性を踏まえて選ぶのが本当に大切だと痛感しました。
性能競争ではなく、設計競争。
私はそう理解するに至りました。
要点は3つです。
CPUとGPUの世代を揃えること。
エンコードを任せる相手を最初に決めること。
そして冷却と電源に徹底して気を配ること。
この3つを守れば、配信の安定度は驚くほど変わります。
これは机上の空論ではありません。
私が実際に体感して得た結論です。
静かな安心感。
このふたつを軽く見ることはできません。
PCは毎日長時間と向き合う道具であり、仕事にも遊びにも関わりますから、ちょっとした不具合がモチベーションさえ削ります。
一方で、安定した環境を整えた時の充実感は、どこまでも安心して楽しめる日常を与えてくれるのです。
結局のところ、配信環境作りは数字より実体験を積み重ねる作業。
スペック表だけでは絶対に見抜けない落とし穴と、小さな工夫の積み重ね。
この過程を経て初めて、自分にとっての最適解に辿り着くのだと、私は胸を張って言えます。
NVMe SSDがゲーム起動や録画・配信に与える影響
Apex Legendsを本気でやり込みながら配信まで楽しみたいのなら、私の経験上、NVMe SSDは単なる選択肢ではなく「必須」と言ってしまっていいと思っています。
いくらCPUやGPUにお金をかけても、ストレージを軽視してしまうと、その効果を十分に発揮できません。
結局のところ、起動の速さや配信中の安定感という点で、NVMe SSDなしには快適な環境は実現できないと強く感じました。
私が最初に大きな違いを実感したのは起動やロード時間でした。
昔はHDDを使っていたので、Apexのロードがやたらと長く、仲間はすでに戦場に出ているのに自分だけ取り残されている、そんな場面が何度もありました。
SATA SSDに変えても多少は改善しましたが、NVMe SSDに乗り換えてみると世界が変わったように感じました。
ロード画面があっという間に終わり、試合開始直後の立ち回りで大きな差をつけられるようになったのです。
数秒の差がこんなにも影響するのか、と衝撃でした。
ほんの数秒。
その数秒で勝敗が動くのです。
さらに大きな発見は録画や配信との相性でした。
私はよくプレイ動画を残したりライブ配信をしたりするのですが、以前は映像がカクつくことがありました。
最初は理由が分からなくて悩みましたが、原因がストレージにあると分かった時は少し驚きましたね。
NVMe SSDに変えた途端、録画中のプレイが嘘みたいに滑らかで、もう「これが正解か」と思わず口にしました。
安心感につながる。
実際、私はWD製のGen4 SSDからCrucialのGen5 SSDに乗り換えた経験があります。
とても嬉しかったです。
ただ、そのときに突きつけられたのが「発熱」という現実でした。
性能だけなら最高クラスでも、冷却をおろそかにすると本来の力を出し切れません。
ヒートシンクの強化は必須。
仕事でも、机上のプランだけでは良い成果が出せないのと同じで、環境全体を見て対策を施さなければ実力が現れないことを思い知らされました。
まさに経験からの学びです。
容量についても甘く見てはいけません。
Apexはアップデートのたびにサイズが膨らむし、配信アーカイブを数時間分保存すれば、一気に数十GBなど当たり前です。
以前私は1TBで十分だと思っていました。
けれど、大会の配信データを保存したら一瞬で容量が埋まり、慌てて外付けに逃がしたことがあります。
そのときの焦りはもう嫌でしたね。
それ以来、私は2TB以上が当たり前だと考えるようになりました。
余裕がもたらす心のゆとり。
そして強く勧めたいのが、録画用とシステム用のSSDを分けることです。
一つのドライブにゲーム、OS、録画を全部詰め込むと、どうしても競合してパフォーマンスが落ちます。
あのときの感動は今でも鮮明です。
「やっと本来のプレイができる」と小さく声を上げたのを覚えています。
価格面では、今ではGen4 SSDが標準的で、しかもお手頃になってきました。
私や同世代の仲間は、派手さよりも安定を重視するので、大容量のGen4を選ぶ傾向があります。
冷却環境をきちんと整えられるならGen5も選択肢ですが、コスパを考えればやはりGen4が現実的でしょう。
配信用なら2TBを1本用意することで、ほとんどの悩みは解消します。
価格と性能、そのバランスを冷静に考えて投資することが大事です。
ゲームは娯楽でありながら、真剣に取り組めば取り組むほど準備の大切さを痛感させられます。
仕事で大事な会議の資料を入念に仕上げるときと同じように、プレイ環境を整えることは結果を大きく左右します。
PCは嘘をつかない。
だからこそ、自分のやる気を裏切らない環境を整えなければならないのです。
私の結論は明快です。
2TB以上のNVMe SSDをGen4以上で導入し、録画専用にもう1本揃える。
これさえ実行すれば、配信とゲームプレイの両立がスムーズになり、余計なトラブルにわずらわされず本来の楽しさを味わえます。
案外、ゲーミングPCの要ともいえるのは目立たないSSDだったというのが私の実感です。
仲間と同じタイミングで戦場に立てる喜び。
滑らかにプレイしながら録画を続けられる安心感。
これらが積み重なってこそ、日々のプレイがさらに充実していく。
私は今もその思いを強く抱きながらプレイを続けています。
SSD規格一覧
| ストレージ規格 | 最大速度MBs | 接続方法 | URL_価格 |
|---|---|---|---|
| SSD nVMe Gen5 | 16000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD nVMe Gen4 | 8000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD nVMe Gen3 | 4000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD SATA3 | 600 | SATAケーブル | 価格 |
| HDD SATA3 | 200 | SATAケーブル | 価格 |
静かで冷えるPCにするためのCPUクーラー選びのコツ
Apex Legendsを配信しながら快適に遊ぶためには、CPUクーラーの選択が実は大きな鍵を握っていると私は思っています。
冷却が甘いと処理性能が落ちてしまい、映像がカクつく。
せっかく盛り上がる場面でも視聴者にうまく伝わらず、「なんだかもったいないな」と自分でガッカリした経験もあります。
その一方で、冷却に予算を突っ込み過ぎると他のパーツに回せなくなる。
私自身も過去に静音性を軽視して後悔したことがあります。
数年前、海外のレビューで評価が高かった大型空冷クーラーを意気揚々と導入したんです。
ところが実際に使ってみると、アイドル時ですらファンの音が耳につき、気になって仕方がなかった。
「これじゃ落ち着いて使えないじゃないか」と思い、泣く泣く外す羽目になりました。
性能だけでは安心できない。
そこでようやく、静音性の大切さを痛いほど実感しました。
最近のCPUは世代が進むごとに効率が上がっており、正直そこまで消費電力を心配しなくても済む場面が増えています。
私が普段使うCore Ultra 7やRyzen 7程度なら、大型空冷でも十分に安定して動かせる構成が作れます。
特に120mmや140mmファンを積んだヒートシンクだと、配信中でも落ち着いた温度を維持してくれる。
しかも取り回しも簡単で手入れがラクなんです。
水冷は見た目が洗練されていて性能も良いですが、数年後のメンテナンスを想像すると「やっぱり空冷の手軽さってありがたいな」と思う瞬間が多いんですよね。
とはいえ、水冷を選んで正解だと感じることがあるのも事実です。
ケースの内部をすっきりと見せたいときや、GPUまで含めて発熱を効率的に流したいときには、やはり水冷の方に分があります。
実際、昨年配信用に組んだPCでは240mmラジエーター付きの簡易水冷を前面に設置しました。
そのときはファンノイズがぐっと小さくなり、真夏に数時間配信しても熱で不安になることは一切なかった。
見た目もスタイリッシュでしたし、一石二鳥の感覚でした。
忘れちゃいけないのがケースとの相性です。
デザインを優先して流行りのピラーレスケースを選んだら、見た目は最高でもエアフローがイマイチで結局温度が下がらない、なんてこともよく耳にします。
意外とそれだけで安定するんです。
高額なクーラーに頼らなくても解決できる場合もありますから、ここは無知で損をしやすい部分だと思います。
静音性の重要さ。
これを軽く見てはいけません。
「視聴者に集中してもらいたいのはゲームの戦いなのに、背後でブーンって音が混ざっちゃうのか」とがっかりしてしまう瞬間が過去に何度もありました。
多少の静音材で誤魔化す方法もありますが、それより上質なファンを最初から導入したほうが結局安心です。
静圧型のファンを低回転で回す設定は王道中の王道で、試したときには「こんなに静かに冷やせるのか」と驚かされました。
さらに最近では、ファン制御の自由度が格段に上がっています。
マザーボードのBIOSや専用ユーティリティで細かく調整して、アイドル時は極力静かに保ち、ゲーム中など負荷が高い場面でだけしっかり回す。
昔なら静音と冷却のどちらかを犠牲にするしかなかった。
それが今は両立できるのですから、技術の進歩を肌で感じます。
だから私の結論としては、配信用PCに向いているのは大型空冷もしくは240mmクラス以上の簡易水冷です。
コストや扱いやすさを大切にするなら空冷。
見た目や絶対的な冷却性能で勝負したいなら水冷。
方向性を最初に決めれば迷いは減ります。
特に配信は映像と音で魅せるものですから、この選択が配信全体のクオリティを握っているといっても言い過ぎではありません。
冷却不足でカクついた配信ほどつらいものはありません。
視聴者にとってはストレスで、配信する自分にとっても大きな負担になる。
だから最初から冷却と静音を意識して選ぶことが重要です。
そこを抑えておけば、プレイも会話も快適になり余計なストレスから解放される。
だから私は強く言いたい、「CPUクーラーは軽視しないほうがいい」です。
最終的に、私が大切にしているのは快適さです。
決して派手なパーツ選びではありませんが、その一手間が「滑らかで静かな配信」につながっていきます。
私にとってCPUクーラーの選択は、単なる部品選びではなく、配信そのものの品質を左右する大事なテーマなんです。
Apex Legends用ゲーミングPCを買うときに注意したいこと


ケース選び 冷却性能を優先するか、見た目を重視するか
どれほど美しいデザインのケースを手に入れても、熱がこもって処理が落ちてしまえば台無しです。
特にApex Legendsのように長時間かつ高負荷のゲームを快適に遊びたいなら、確実に冷却を優先することが欠かせません。
これは経験から断言できます。
なぜなら、安定性がゲームの楽しさそのものを支えているからです。
ただ人間ですから、機能性だけでは心が動きません。
ふと目に入ったガラスパネルやライティングに魅了されて、「やっぱり見た目も捨てがたいな」と思う瞬間がある。
頭で理解していても、心は別方向に引っ張る。
正直、葛藤です。
メッシュフロントケースは冷却の観点ではほぼ間違いない選択肢です。
特に真夏の蒸し暑い日に何時間も配信をしながらプレイしていると、その効果がよく分かります。
内部の熱がしっかり逃げてくれるおかげでパフォーマンスが維持され、フレーム落ちも少なく済む。
私は何度もそれを実感しました。
あの安定感こそ、縁の下の力持ちだと心から思わされました。
だから私は声を大にして言いたいんです。
冷却は軽視できない、と。
かつて私は黒一色のスチールケースを使い続けていました。
ガラスパネル越しに見えるカラフルなライティング、水冷のチューブを流れる冷却液の輝き、光るパーツ群。
それを見た瞬間、羨望のような感情が湧き上がり、「こういう世界もいいな」と思わず呟いたのです。
正直に言って、心を撃ち抜かれました。
その後リビングに三面ガラスのケースを置いたとき、妻から「これなら家具としても見栄えがいい」と褒められた場面があります。
あの一言が妙に嬉しかった。
単なるゲーム機じゃなく生活の一部として価値がある。
これが新しい視点でした。
流れが悪くなれば高温で動作が不安定になるのは目に見えています。
特に配信を兼ねてプレイしていると、CPUもGPUもかなりの負荷を受けるので油断できません。
温度管理を甘くしたら結果は火を見るより明らかです。
木材を取り入れたユニークなケースを見たときは驚きました。
正直最初は冗談に思えましたが、実際見れば上質で温かみがあり、リビングの棚にあっても違和感がない。
ゲーム機というより家具に近い感覚。
こうしたアプローチは、生活と趣味の折り合いを考える40代にとってすごくありがたい方向性です。
私は水冷に挑戦もしました。
ガラスケースに簡易水冷を入れると、少し不安もあったのですが、結果的に長時間のプレイでも安定してくれました。
数時間の配信でも温度が一定に収まり、GPUも落ち着いて動作する。
これこそ投資の価値あり、と感じた瞬間です。
最終的な選択を考えると、やはり私の答えは「冷却性能を最優先し、そのうえでデザインを楽しむ」というものです。
熱に悩まされてゲームが途切れるくらいなら、派手さは後回しでいい。
まずは機能。
そして自分なりに気持ちが晴れるデザインを選ぶ。
この順番こそ安心して遊び続けられる秘訣です。
PCはただの道具に留まりません。
毎日目に入り、触れて、時には仕事にも遊びにも寄り添う存在です。
だから私は思います。
無骨でも派手でも構わない。
長く信じて一緒に過ごせる相棒であること。
それが何よりも重要です。
安心感は大きい。
信頼できる相棒。
数字には出にくくても確実に心に効くものがあります。
40代になってようやく分かる感覚かもしれません。
スペックや効率性を重視する気持ちは変わりませんが、そこに快適さや日々の暮らしとの調和が乗ると、選び方が変わってくるんです。
華やかさより堅実。
でも堅実さの中に少しの遊び心。
それを追い求めるのは、大人の楽しみ方じゃないでしょうか。
結局のところ、ゲーミングPC選びは冷却とデザインの間でどれだけ自分を納得させられるかです。
人によって大切にするものは違うでしょう。
しかし私は胸を張って言えます。
冷却性能を土台にしたうえで、自分の感性に響くケースを選べば後悔はしない、と。
ゲーミングPC おすすめモデル4選
パソコンショップSEVEN ZEFT R67M


| 【ZEFT R67M スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9700X 8コア/16スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Corsair FRAME 4000D RS ARGB Black |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60FW


| 【ZEFT R60FW スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 9900X 12コア/24スレッド 5.60GHz(ブースト)/4.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | Radeon RX 9060XT (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 DIGITAL WH |
| マザーボード | AMD X870 チップセット GIGABYTE製 X870M AORUS ELITE WIFI7 ICE |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R61FA


| 【ZEFT R61FA スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | INWIN A1 PRIME ピンク |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850I Lightning WiFi |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60FL


| 【ZEFT R60FL スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9700X 8コア/16スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | Radeon RX 9060XT (VRAM:16GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 DIGITAL WH |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60BS


| 【ZEFT R60BS スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | Radeon RX 7800XT (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | NZXT H9 FLOW RGB ホワイト |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II White |
| マザーボード | AMD X870 チップセット GIGABYTE製 X870M AORUS ELITE WIFI7 ICE |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
電源ユニットの容量不足がパフォーマンス低下につながる理由
ゲーム環境を快適に整えたいと本気で考えるなら、まずは電源ユニットの選び方をおろそかにしてはいけないと私は感じています。
CPUやGPUの性能ばかりに注目してしまいがちですが、根本となる電力供給が不安定では結局そのポテンシャルは十分に発揮されません。
むしろ電源が追いつかないと、不安定な動作や突然のクラッシュという厄介なトラブルにつながってしまい、せっかくの楽しみが水の泡になってしまいます。
実際に私は過去、自分の環境でその現実を痛いほど体験しました。
印象的だったのは、GPUを新しくして「これで理想のプレイ環境に近づくぞ」と胸を躍らせていた頃のことです。
ところが実際にゲームを始めてみると瞬間的にカクついたり、フレームが乱れることが続きました。
ドライバやネットワークを疑ってあれこれ調べましたが、最終的に突き止めた原因は電源の容量不足。
瞬間的に高い電力を要求される場面で電源が踏ん張り切れず、クロックダウンが起こっていたのです。
派手に壊れるわけではなく、じわじわと快適さを削っていくこの不具合は本当にやっかいでした。
電源ユニットは定格出力の数字を満たしていればいい、という単純な話ではありません。
そこを軽く見て「動いているから大丈夫だろう」と自己判断してしまうと、後で痛い目を見るリスクが高まります。
特にApex LegendsのようなゲームではCPUとGPUが同時に全力を出し、さらに配信ソフトによるエンコード処理も重なるので一時的な電力の波が激しくなります。
やっかいなのは、電源不足の症状が分かりにくいことです。
映像のカクつきやマウスの反応遅延を経験しても、多くの人は「ネット回線かな」とか「グラボのドライバを更新したら改善するだろう」と考えてしまうでしょう。
でも実際には裏で電源が悲鳴をあげている。
私もそのことに気づくまで時間がかかりました。
だからこそ今では人に会うたびに「電源ユニットこそが性能の根幹なんだ」と伝えずにはいられないのです。
高額なRTXシリーズを購入しても、電源が貧弱では真価を発揮できません。
補助電源規格の変化や12VHPWRケーブルの安定供給が必須になり、従来650Wで足りていた環境が750W、さらには850W以上が推奨される状況になっています。
実際に私も世代交代を経験し、思わず「いつからこんなに要求が高くなったんだ」と声を漏らしました。
技術進化は喜ばしい反面、電源周りの投資が欠かせなくなっていることを肌で感じています。
もうひとつ大事なのは寿命です。
電源を定格ぎりぎりで動かし続ければ、内部のコンデンサや回路に常に無理を強いることになり、結果として寿命を大幅に縮めるリスクを抱えることになります。
私自身、かつてぎりぎりの電源構成で夏場を迎え、不安定になった経験があります。
以来、余裕ある容量の電源を選ぶことを徹底しています。
750Wや850Wを積んだからといって使い切れない無駄ではありません。
長期的な安定を買っている。
配信を伴うプレイなら、なおさら電源の重要性は高まります。
Apex Legends自体の負荷に加え、OBSなどの配信ソフトはCPU処理を容赦なく奪い、同時に消費電力も一気に跳ね上がります。
この複合負荷を安定して支えるには「余裕が必ず必要」なのです。
私の場合、余裕を持った電源を導入することで「放送中に突然映像が止まらない」という安心感を得られるようになりました。
最近はBTOパソコンの中でも80PLUS Gold以上の高効率電源を標準で備えるモデルが目立つようになりました。
表向きは十分なスペックに見えても、実際のプレイで突然クラッシュしたり予期せず終了してしまうケースが報告されています。
掘り下げて調べてみると、やはり多くは電源不足。
つまりコストのしわ寄せが電源に現れているのです。
昔の私は電源の重要性を信じてはいませんでした。
「そんなもので性能が変わるのか」と鼻で笑っていたくらいです。
でも今では胸を張って「電源がすべてを左右する」と言えます。
快適さを壊すのも電源なら、それを守るのも電源。
違いは大きいですよ、本当に。
どう選ぶのが最善か。
答えは明白です。
推奨構成ぎりぎりではなく、常にワンランク上を選ぶことに尽きます。
その余裕があるからこそ安心でき、真夏の高温時や負荷が急に跳ね上がる瞬間でもシステムが揺らがない。
結果としてGPUやCPUが本来の性能を解放できるのです。
それは単なる部品選びではなく、自分の時間を守る選択です。
安定性。
私は今後も折に触れて同じことを伝えていくと思います。
同じようなトラブルで大事な時間を無駄にしてほしくないからです。
仕事に追われながらようやく確保できる貴重なゲーム時間を支えるのは、華やかなパーツではなく、静かにケースの底で動き続ける電源ユニットなのだと。
40代になった今の私だからこそ、なおさら強くそう思っています。
BTOで後悔しない構成を選ぶときにチェックすべき点
正直、ここをいい加減にするとどれだけ他のパーツにお金をかけても「しまったな」と感じる瞬間が必ず来るのです。
フルHDで240fpsを安定させたいのか、それともWQHDで滑らかさと映像美を両立させたいのか、自分がどんなプレイ体験を求めるのかによって必要なGPUは全く変わってきます。
私はそういう基準を持たずに選んだ結果、後悔する人を何度も見てきました。
たとえばRTX 5070クラスなら、ほとんどのプレイヤーにとって満足できる快適さを届けてくれるし、大会に近い感覚のスムーズさが味わえます。
Apexは急に描画負荷が跳ね上がる瞬間があって、その時に映像が一瞬でもカクついたら全てが台無しになる。
悔しさだけが残ります。
だから私はGPU選びだけは妥協しないようにと後輩にもいつも伝えています。
妥協は禁物。
これは確信です。
CPUについては「最上位を選べば間違いない」と思っている人もいます。
でも実際はそうではありません。
私がCore Ultra 7 265Kを使った時、配信しながらでも144Hzを維持できた体験は衝撃でした。
そのうえ、ファンの音も耳障りではなく静かに回ってくれる。
数時間プレイしても全くイライラしませんでした。
一方でRyzen 7 9800X3Dも評判がよく、特に反応の速さに強みがあると言われます。
両方とも安心して使える実力があり、選択肢が複数あることそのものが救いになるのです。
どちらを買っても後悔はないはずです。
メモリについては、16GBで最低限は足ります。
ただし実使用では32GBを選んだほうが安心できます。
余裕がある方が気持ちにも余裕が持てます。
ストレージの容量を甘く見る人もいますが、これも危険です。
最初は1TBで十分だろうと思っていた私も、動画編集を始めたらあっという間にSSDが埋まってしまいました。
録画データは容量を食います。
結果として「しまった」と焦って、急いで2TBに換装することに。
あのとき心底思ったんですよ。
先を見据えて選ばないと後悔する、と。
余裕があるストレージは安心感に直結します。
これは経験談だからこそ強く言いたいです。
性能ばかりに目を向けると冷却が疎かになりがちですが、実際には冷やし方で結果が大きく変わります。
クロックが下がって思ったほど力を発揮できないこともあるし、もし冷却が不十分なら「ブオーッ」というファンの音ばかりが耳に残って、プレイに集中できなくなります。
私は以前そういう失敗をしたので、静音性と冷却性能にこだわるようになりました。
最近は空冷でもかなり性能が良いモデルが多く、無理に水冷にしなくても十分に戦える時代です。
冷えるし静か。
それだけで環境は随分と良くなりますよ。
格好だけで選ぶと痛い目を見る。
私は若い頃、見た目だけで選んだ結果、通気性が悪くて熱がこもり、GPUが落ちるという事態に遭遇しました。
その経験があったから、今はケース内部の作り、振動の少なさ、配信時の音漏れまで気にしています。
ケースはただの箱じゃない。
最終的に私がたどり着いた構成の基準を挙げるなら、こうなります。
GPUはRTX 5070クラス以上。
CPUはCore Ultra 7 265KかRyzen 7 9800X3D。
メモリは32GB。
ストレージは2TB以上のGen4 SSD。
そして冷却は高性能空冷か240mm水冷。
少なくともこのラインを押さえておけば、大きく外すことはありません。
どれかをケチって「あの時こうしておけば」と悔やむくらいなら、最初から堅実に組む方が精神的にも財布的にも健全だと私は思います。
迷ったらこの構成を基準に考えればよいと思っています。
正直、それだけでも安心材料になります。
ゲームも配信も、不安なく楽しめる。
それこそがBTOパソコンを選ぶ本当の価値だと私は信じています。
安心感。
信頼性。
この2つが揃ったとき、人はようやくゲームに全力で没頭できるのです。
Apex Legends向けゲーミングPCに関するよくある疑問
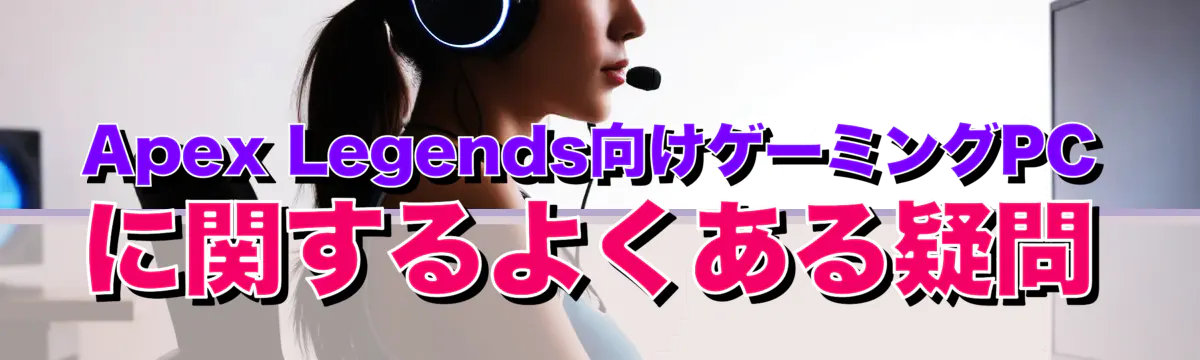
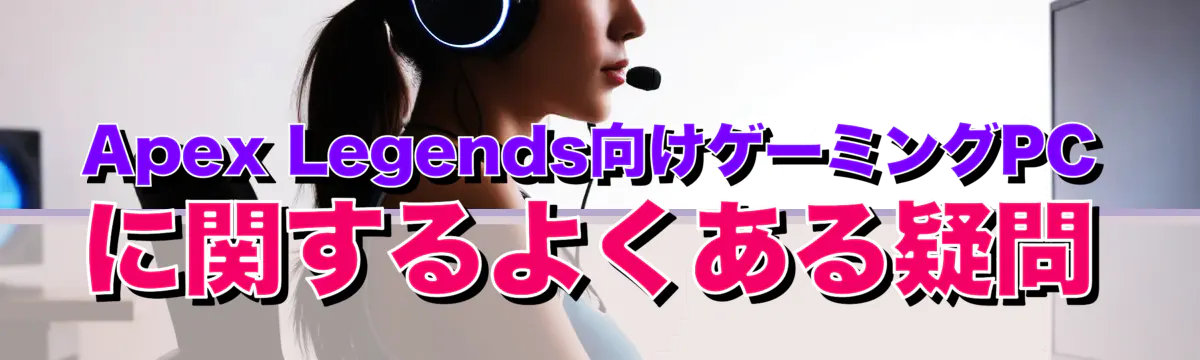
Apex Legendsを快適に遊ぶための最低限のスペックはどの程度?
ゲームは娯楽ですが、時に真剣勝負になるからこそ、細部の快適さが大事になるのだと思います。
特にメモリに関しては、公式に「6GBでも動作可能」と書かれているものの、実際にプレイをすると意味のない数字にしか思えません。
容量が足りなければカクつきやフリーズが頻発して、真剣な場面で一瞬固まったときの悔しさといったら、本当に忘れられません。
私は16GBから32GBに増設したときの変化を今でも鮮明に思い出します。
試合中の急な止まりがなくなり、「ああ、これでようやく安心できるな」と心から感じました。
余裕を持ったメモリは心理的な安定にもつながりますよ。
安心感。
CPUも見落とされがちですが、これも軽く考えてはいけません。
確かに「GPUさえ強ければどうにかなる」と言う人は多いですが、それはあくまでも表面的な話です。
私は以前Core Ultra 5で組んで、ソロプレイでは問題なかったのですが、同時配信をしようとした瞬間に映像がカクついて視聴者から苦情が来ました。
そのときの焦りと落胆を味わってから、「これはもうCore Ultra 7クラス以上でないと駄目だ」と悟りました。
配信という要素を加えただけでCPUの力不足が一気に露わになる。
この実感が、スペックに投資する意味を教えてくれたんです。
「遊ぶ」だけと「遊びながら伝える」では求められるものが本当に違います。
一方で、グラフィック性能に関してはもっとシビアだとすら思います。
60fps程度で楽しむだけなら安価なGPUでも誤魔化せるんです。
しかし、144Hzモニタを用意すると、もうまるで別物の体験になります。
私は一度安いグラフィックカードでごまかそうとして、集団戦で一瞬フレームが止まり、その刹那に撃ち負けました。
悔しすぎてコントローラーを投げ出しそうになったのを覚えています。
結局RTX5060Tiクラスに変更して初めて、「そうそう、この滑らかさだよ!」と心から納得できました。
勝敗を分けるのは一瞬。
その一瞬のためにどれだけ準備できるかが勝負どころだと痛感しました。
ストレージも地味に重要な要素です。
実際にはアップデートのたびに容量が膨らんでいき、それに加えて録画データや別のゲームであっという間にいっぱいになります。
私も以前500GBのSSDを使っていましたが、録画を続けていたらすぐに容量が限界に達しました。
仕方なく1TB NVMeに更新し、さらには2TBへ拡張しましたが、そのおかげでストレスは格段に減りました。
特にGen.4 NVMeの読み込み速度によるテンポの良さは、試合ごとのテンポをまったく変えてくれるんです。
ロード時間が短いだけで、なんだか自分が優先されているような快感すら覚えました。
気持ちの余裕。
冷却やケース選びの失敗も実際に経験しました。
デザインに惹かれて木製パネルのケースを買ったのですが、夏場に熱がこもってフレームがボロボロに落ちてしまい、そのときばかりは後悔しか残りませんでした。
せっかくの高性能パーツも熱が逃げなければ意味がない。
泣く泣くケースを買い直し、「次からは絶対に冷却を優先するぞ」と誓いました。
あれほど自分の判断を悔やんだことはありません。
結局、どんなに見た目が良くても、安定性の前では無力なんです。
空冷や水冷の選択も含め、冷却に対して妥協してはいけないのだと実感しました。
総じて言えることは、Apex Legendsにおいて「最低限動けばOK」という基準は存在していないということです。
大事なのは「勝負できる環境を作れているかどうか」。
だからこそ私は、メモリ16GB以上、CPUはCore Ultra 7やRyzen 7クラス、GPUは現行ミドルレンジ以上、ストレージは1TB以上のGen.4 NVMe SSDを用意することを前提とすべきだと考えています。
これらはもはやオプションではなく、必要条件です。
妥協すれば動くことは動きます。
しかしそれで得られるのは中途半端な満足だけ。
プレイしていても常に「ここが足りないんじゃないか」と心のどこかに引っかかる気持ちが残ってしまいます。
逆に最初から余裕を持った環境を整えておけば、その後長く安心して付き合える。
しかも性能が余っていればコスト効率だって悪くありません。
だからこそ私は「どうせやるならしっかり準備する」派なんです。
答えは簡単です。
本気で楽しみたいなら現行世代の中堅以上を構えること。
ゲームは楽しむものですが、勝負で結果を残した瞬間にこそ、本当に投資してよかったと心から思えるんです。
配信や動画編集もやりたい場合、どういうPCを選べばいい?
実際に配信や動画編集を考えるとき、私はいつも「どうせなら最初から少し余裕ある構成で組んでおいた方が後悔しない」と思っています。
理由は単純で、ゲームだけなら快適でも、同時に配信ソフトや編集ソフトを立ち上げた瞬間に一気に動作が重くなり、結局後から買い直す羽目になるからです。
あの出費と手間を思い返すと、最初の判断次第で時間もお金もかなり変わるのだと強く痛感します。
最優先で考えるべきはCPUの性能です。
だから今なら迷わずRyzen 7やCore i7クラスを選びます。
ほんの一段スペックを上げるだけで、安定感が天と地ほど違うのです。
そしてGPU。
Apex自体は重すぎるゲームではありません。
でも録画や配信を組み合わせると、映像処理はあっという間に限界に近づきます。
私はかつてRTX4060で頑張ったことがありますが、録画を見返したらコマ落ちの連続で愕然としました。
取り直すしかないあの徒労感。
もう嫌だ。
だから今ではRTX 4070以上、できれば5070クラスがおすすめです。
単に映像がきれいになるだけじゃなく、配信の安定度が格段に増します。
メモリの甘さも忘れられません。
最初に16GBで挑んだとき、ブラウザで攻略サイトを開いただけで重くなり、Premiere Proを同時に走らせるなんて到底ムリでした。
でも32GBに増設してからは別世界。
録画、編集、ブラウジングを同時にしてもストレスを感じないのです。
もっと早くそうしておけばよかった、と心から悔やみました。
Apexはアップデートのたびに肥大化し、編集する動画ファイルは一本で数十GBなんて普通です。
以前の私の環境は1TB。
常に容量が赤ランプで、録画した直後に整理整頓ばかりしていました。
正直、ゲームや編集を楽しむ前に片付け作業に疲れてしまった。
2TBにしてからは気持ちが本当に楽になり、制作そのものに集中できます。
心の余裕がまるで違う。
冷却性能についても大きな学びがありました。
デザインに惹かれてガラス張りケースを使っていたときは、長時間配信で内部が熱を持ち、ファンの騒音で耳が疲れてしまったのです。
それで泣く泣く通気重視のケースへ買い替えたのですが、結果的に静かで安定感も増し、ようやく快適になりました。
やっぱり見た目よりも機能。
ここは譲れないと悟りました。
配信に必要な三本柱は、処理能力、映像性能、安定性です。
具体的に言うなら、CPUはCore i7-14700KかRyzen 7 7700X、GPUはRTX 4070以上、メモリは32GB、ストレージは2TB NVMe SSD、そして確実な冷却を意識した構成、これが理想的な組み合わせだと私は考えています。
一見オーバースペックに見えても、実際に編集や配信を同時にやるとちょうど良いのです。
私は以前、ギリギリの構成で始めてつまずきました。
その時の焦りと悔しさは今でもよく覚えています。
ただ、その失敗があったからこそ、今のPC構成にとても満足しています。
おかげで「配信しながら遊んで、そのまま編集へ」という流れをストレスなくこなせています。
つまり、一段余裕のあるスペックを選ぶことが、結果的に正解なのです。
気持ちが楽になります。
前者ならミドルスペックで大丈夫ですが、後者は余力を前提に選ぶべきで、それがストレスから解放される唯一の方法です。
その選択が「後悔しないための鍵」になるのだと私は信じています。
私も何度も痛感しましたが、結局長く使えばわかる答えはシンプルです。
余裕のある構成は安心につながるし、安心があるからこそ配信や編集を楽しむ余地が生まれます。
パソコンはただの道具ではなく、自分の時間をどう過ごすかを左右する基盤なのだと感じています。
そしてこれから挑もうとしている方には「どうせなら最初から少し背伸びして選んでください」と伝えたい。
楽になりますよ、その方が。
ゲーミングPC おすすめモデル4選
パソコンショップSEVEN ZEFT R60GV


| 【ZEFT R60GV スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 9950X 16コア/32スレッド 5.70GHz(ブースト)/4.30GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | NZXT H9 FLOW RGB ホワイト |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II White |
| マザーボード | AMD X870 チップセット GIGABYTE製 X870M AORUS ELITE WIFI7 ICE |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55GD


| 【ZEFT Z55GD スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra5 245KF 14コア/14スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.20GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ブラック |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R61BK


| 【ZEFT R61BK スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 9950X3D 16コア/32スレッド 5.70GHz(ブースト)/4.30GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | AMD B850 チップセット MSI製 PRO B850M-A WIFI |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R44CG


高速な実行力で極限のゲーム体験を支えるゲーミングモデル
直感的プレイが可能、16GBメモリと1TB SSDでゲームも作業もスムーズに
コンパクトなキューブケースで場所を取らず、スタイリッシュなホワイトが魅力
Ryzen 9 7900X搭載で、臨場感あふれるゲームプレイを実現
| 【ZEFT R44CG スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 7900X 12コア/24スレッド 5.60GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (8GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B650 チップセット MSI製 PRO B650M-A WIFI |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
SSDはGen4とGen5のどちらを選ぶのが実用的?
ゲーム用のストレージを選ぶときは、最終的に実用性を基準にした方が満足度が高い、と私は強く思っています。
正直に言ってしまうと、派手な数値や最新世代の響きに心を動かされる場面はありますが、冷静に振り返ると「その投資がどこまで実感につながるのか」が一番のポイントになるんですよね。
Apex Legendsを快適に遊ぶことを考えれば、現時点で一番扱いやすく、コストとのバランスが取れているのは間違いなくGen4 SSDです。
なぜなら、Gen5が見せてくる速度の大台はたしかに見栄えがしますが、実際問題として体感できるほどの差は少ないからです。
ゲームのロード時間を冷静に比べてみました。
フルHDだろうとWQHDだろうと、Gen4とGen5の差はせいぜい数秒。
数万円の投資をして得られるものがそのわずか数秒。
私は「これは本当に必要な差なのか」と戸惑いました。
発熱の厄介さ。
大きなヒートシンクや小型ファンを用意して、ケースのエアフローまで気を配らなければならない。
見た目のスマートさを求めている私にとっては、この手間がとにかく煩わしかったです。
さらに追い打ちをかけるのが価格の高さです。
SSDにそこまで予算を割くと、GPUや冷却システムなど他の重要なパーツに回す資金が削られてしまう。
ここが一番痛いのです。
Apexは頻繁に大型アップデートがあり、そのたびに数十GB単位で容量が奪われていきます。
ある日気付けば残り容量がほとんどなくなっていて、仕方なく不要なゲームを消す羽目になったことも何度もありました。
だからこそ、現実的な解としてはGen4の1TBか2TBを確保する方が快適なのです。
容量に余裕があるというだけで、プレイ環境に安心が生まれます。
地味ですが、これが長く楽しむために非常に大きな意味を持ちます。
実際に私はGen5を試しました。
そのときは「これでロードが圧倒的に短くなるはずだ」と期待に胸を膨らませていました。
しかし、いざ使ってみると拍子抜け。
思っていたほど差がなかったのです。
数秒の違い程度では感動は生まれませんし、複数の大作ゲームを切り替えて遊ぶときはむしろCPUやGPUの初期読み込みに時間を取られることが多く、SSDの世代差なんてすぐにかすんでしまうのです。
「あれ、これで終わり?」と心の中で呟いてしまった瞬間を今も覚えています。
ただ、将来的にはGen5の強みが活きる瞬間が来る可能性はあると思います。
例えば、高解像度の大容量テクスチャが当たり前になる時代や、新しいゲームエンジンがプリロードをフルに要求する時代が来れば、14,000MB/sという速度は本当に意味を持つはずです。
もし既にGen5対応のマザーボードを持っていたり、未来への投資として最先端を揃えておきたいと考えるのであれば、その選択は否定しません。
けれど、それはあくまでも投資であり、現段階で日常的な快適さを求める選択とは違う領域だと思います。
ゲーム環境というのは結局のところ総合力で決まります。
SSDへの期待も分かりますが、本当に体験を大きく左右するのは別の部分です。
GPUのパワーや高リフレッシュレートのモニタ、そして安定したネット回線。
これらの要素が素直に「快適さ」を生み出します。
SSD世代の違いが大逆転をもたらすことはほとんどありません。
その現実を見誤らない方が、結局は長く満足できる環境につながると私は考えます。
私が行き着いた結論は明快です。
Apexを快適に遊ぶ前提ならGen4 SSDが最適解だということです。
そのうえで余った予算をCPUやGPUなどのパフォーマンスを底上げする方向に割いた方が、体験全体の質は格段に上がっていきますし、大容量のストレージを初めから押さえておけば、度重なるアップデートで容量が逼迫し、ストレスを抱えることもなくなります。
これは私の実体験からも断言できます。
最終的に、買う人の価値観や優先順位で答えは違うと思います。
しかし、冷静に「どこにお金を注ぐべきか」を考えること。
ここを外さなければ失敗しないでしょう。
私はGen4を選んで堅実に構成し、今も後悔は一切ありません。
安心して長く楽しめるからです。
要は現実路線でいく。
これが私の選択なんです。
初めてゲーミングPCを買う・組むときに避けたい失敗ポイント
これを外すと後で高くつきます。
その結果、夏場にまともに動かなくなり、泣く泣く再購入する羽目になりました。
自分の過去の失敗を思い返せば、声を大にして言えることはただ一つ。
目的を軸に性能を組み立てることが、後悔しないための一番の近道です。
まず真っ先に考えてほしいのはGPUの選択です。
数字の比較や「なんとなく高いモデルがいい」という気持ちで決めると多くの人が損をします。
しかし同じ環境をRTX5060Tiに変えてみても、144Hzのモニターでは違和感がなくスムーズに楽しめたんです。
この体験から学んだのは、「欲しい解像度とフレームレート」を基準に選ぶべきだということ。
そうしないと、不必要にお金だけが飛んでいきます。
CPUも罠があります。
ところが実際にCore Ultra 9で組んだときと、Core Ultra 7の構成で比べたとき、フレームレートがほとんど変わらないことに驚きました。
思わず「何のためにあの金額を…」と頭を抱えましたよ。
結局のところ、多くのゲームはGPUに依存度が高く、CPUは中位から上位で十分。
これが私なりの結論です。
そして地味だけれども重要なのが冷却です。
私は一度木目調のケースを選んで後悔しました。
見た目はおしゃれでしたが、エアフローが弱くてすぐに高温になり、動作が不安定に。
まさに「カッコよさに振り回された無駄遣い」でした。
ストレージも忘れてはいけません。
Apexのようなゲームはアップデートが容赦なく大きく、あっという間に容量を食います。
初めは「1TBもあれば余裕」と思っていた私ですが、他のソフトやゲームも重なって気づけば容量不足。
容量は余裕があって困ることはないですから。
メモリについても同じです。
当時の私は「ゲームだけなら16GBで十分」と判断しました。
でも配信を始めたり、Discordを同時に立ち上げたりすると一気に足りなくなり、ゲームがガクガクしたことを今でも覚えています。
16GBで苦しんだ自分を振り返りながら、「なぜ最初から32GBにしておかなかったのか」と本気で悔いました。
余裕のある構成はストレスを確実に減らしてくれます。
空冷派と水冷派の議論をよく耳にしますが、使う環境がすべてです。
私の場合、夏場に室温が高い部屋で空冷を使ったらファンがフル稼働し、あまりのうるささに集中できなかったことがありました。
その後240mmの簡易水冷に替えると、温度が安定し静音性も大幅に改善。
これには心底ほっとしました。
静かな環境はパフォーマンス以上に快適さを与えてくれます。
電源も軽視できません。
私は一度、750Wの電源で間に合わせようとした結果、ゲーム中に突然PCが落ちて青くなりました。
あのときの焦りは、二度と味わいたくないものです。
それからは余裕を持った出力、せめてゴールド認証以上の電源を必ず選ぶようにしています。
電源は縁の下の力持ち。
ここをケチるのは自爆行為です。
見た目の好みは誰しも大事にしたい部分です。
RGBで華やかにしたいとか、ガラスケースで内部を見せたいとか、私自身その気持ちは強く分かります。
ただし性能を犠牲にしてまで見た目を優先するのは危険です。
せめて冷却に強いケースを選び、その中で照明や演出を楽しむ。
これこそが遊び心と実用の両立だと思いますね。
大人の趣味としても、その方が心から楽しめます。
結局のところ、私が失敗から学んだのはとてもシンプルな話です。
GPUとCPUのバランスを間違えない。
冷却性能を軽く見ない。
ストレージとメモリは余裕をもって選ぶ。
そして電源は安定性を意識して投資する。
これらを徹底するだけで、長く快適に遊べる環境は手に入ります。
私は自分の過去の失敗を糧にしてきました。
だからこそ今声を大にして言いたいのです。
解像度とフレームレートを基準にGPUを選び、CPUはほどほどに。
この判断こそが、後悔しないゲーミングPC選びにつながります。
これに尽きます。
人気PCゲームタイトル一覧
| ゲームタイトル | 発売日 | 推奨スペック | 公式 URL |
Steam URL |
|---|---|---|---|---|
| Street Fighter 6 / ストリートファイター6 | 2023/06/02 | プロセッサー: Core i7 8700 / Ryzen 5 3600
グラフィック: RTX2070 / Radeon RX 5700XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Monster Hunter Wilds
/ モンスターハンターワイルズ |
2025/02/28 | プロセッサー:Core i5-11600K / Ryzen 5 3600X
グラフィック: GeForce RTX 2070/ RTX 4060 / Radeon RX 6700XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Apex Legends
/ エーペックスレジェンズ |
2020/11/05 | プロセッサー: Ryzen 5 / Core i5
グラフィック: Radeon R9 290/ GeForce GTX 970 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| ロマンシング サガ2
リベンジオブザセブン |
2024/10/25 | プロセッサー: Core i5-6400 / Ryzen 5 1400
グラフィック:GeForce GTX 1060 / Radeon RX 570 メモリ: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| 黒神話:悟空 | 2024/08/20 | プロセッサー: Core i7-9700 / Ryzen 5 5500
グラフィック: GeForce RTX 2060 / Radeon RX 5700 XT / Arc A750 |
公式 | steam |
| メタファー:リファンタジオ | 2024/10/11 | プロセッサー: Core i5-7600 / Ryzen 5 2600
グラフィック:GeForce GTX 970 / Radeon RX 480 / Arc A380 メモリ: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| Call of Duty: Black Ops 6 | 2024/10/25 | プロセッサー:Core i7-6700K / Ryzen 5 1600X
グラフィック: GeForce RTX 3060 / GTX 1080Ti / Radeon RX 6600XT メモリー: 12 GB RAM |
公式 | steam |
| ドラゴンボール Sparking! ZERO | 2024/10/11 | プロセッサー: Core i7-9700K / Ryzen 5 3600
グラフィック:GeForce RTX 2060 / Radeon RX Vega 64 メモリ: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE | 2024/06/21 | プロセッサー: Core i7-8700K / Ryzen 5 3600X
グラフィック: GeForce GTX 1070 / RADEON RX VEGA 56 メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ファイナルファンタジーXIV
黄金のレガシー |
2024/07/02 | プロセッサー: Core i7-9700
グラフィック: GeForce RTX 2060 / Radeon RX 5600 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Cities: Skylines II | 2023/10/25 | プロセッサー:Core i5-12600K / Ryzen 7 5800X
グラフィック: GeForce RTX 3080 | RadeonRX 6800 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ドラゴンズドグマ 2 | 2024/03/21 | プロセッサー: Core i7-10700 / Ryzen 5 3600X
グラフィック GeForce RTX 2080 / Radeon RX 6700 メモリー: 16 GB |
公式 | steam |
| サイバーパンク2077:仮初めの自由 | 2023/09/26 | プロセッサー: Core i7-12700 / Ryzen 7 7800X3D
グラフィック: GeForce RTX 2060 SUPER / Radeon RX 5700 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ホグワーツ・レガシー | 2023/02/11 | プロセッサー: Core i7-8700 / Ryzen 5 3600
グラフィック: GeForce 1080 Ti / Radeon RX 5700 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| TEKKEN 8 / 鉄拳8 | 2024/01/26 | プロセッサー: Core i7-7700K / Ryzen 5 2600
グラフィック: GeForce RTX 2070/ Radeon RX 5700 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Palworld / パルワールド | 2024/01/19 | プロセッサー: Core i9-9900K
グラフィック: GeForce RTX 2070 メモリー: 32 GB RAM |
公式 | steam |
| オーバーウォッチ 2 | 2023/08/11 | プロセッサー:Core i7 / Ryzen 5
グラフィック: GeForce GTX 1060 / Radeon RX 6400 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| Monster Hunter RISE: Sunbreak
/ モンスターハンターライズ:サンブレイク |
2022/01/13 | プロセッサー:Core i5-4460 / AMD FX-8300
グラフィック: GeForce GTX 1060 / Radeon RX 570 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| BIOHAZARD RE:4 | 2023/03/24 | プロセッサー: Ryzen 5 3600 / Core i7 8700
グラフィック: Radeon RX 5700 / GeForce GTX 1070 メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| デッドバイデイライト | 2016/06/15 | プロセッサー: Core i3 / AMD FX-8300
グラフィック: 4GB VRAM以上 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| Forza Horizon 5 | 2021/11/09 | プロセッサー: Core i5-8400 / Ryzen 5 1500X
グラフィック: GTX 1070 / Radeon RX 590 メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |