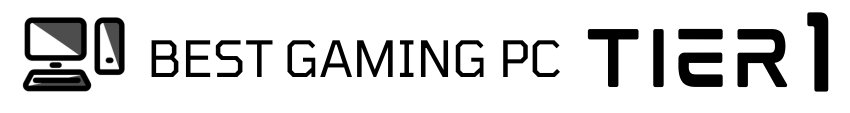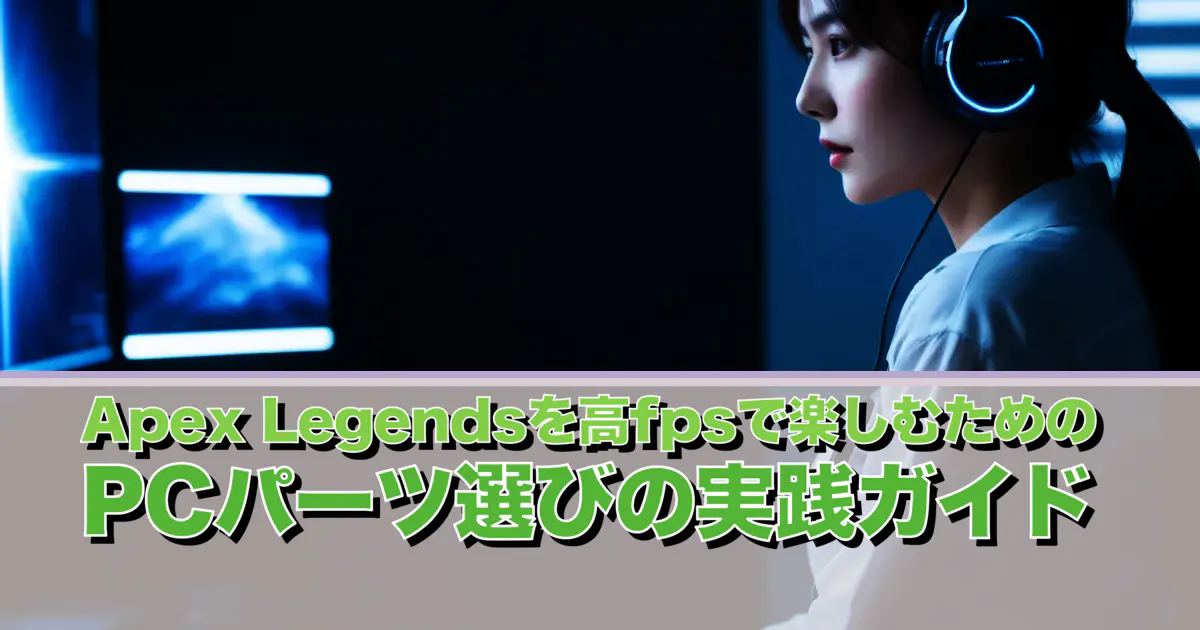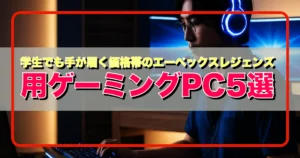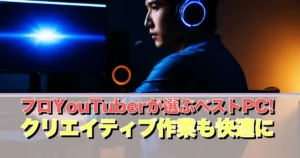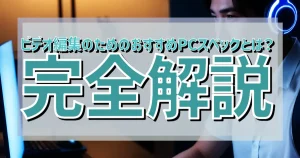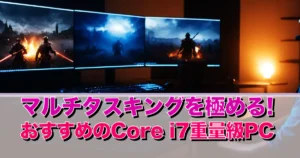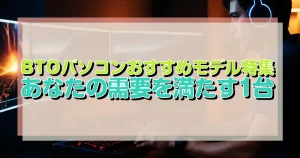Apex Legends向けゲーミングPC|CPUの選び方を現実的に考える
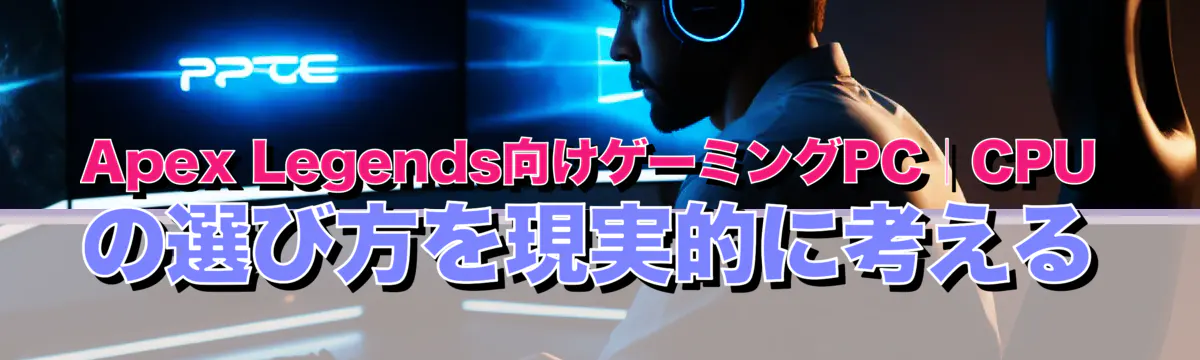
Core UltraかRyzenか――高fpsを狙うならどっちが有利?
Apex Legendsのように、一瞬の判断や操作が勝敗を分けるゲームをプレイする時、CPUの選び方は単なるスペック比較に留まらないと痛感しています。
私が感じてきたのは、フレームの安定性や処理落ちの有無が、そのままプレイヤーの満足度や勝率につながるという現実です。
端的に言えば、限界までパフォーマンスを求めるならCore Ultra、配信や長時間利用を含めた実用性や安心感を優先するならRyzen、そういう棲み分けになると私は考えています。
実際、Apexの世界では激戦区での銃撃戦や、派手なエフェクトが重なる瞬間に顕著な差が出ます。
Core Ultraは高クロックで動作し、シングルスレッド性能とキャッシュ効率によって、複雑な場面でもfpsを保ちやすい。
何度か私自身も、入力に対する応答がスッと返ってくる感覚に鳥肌が立ちました。
「これが勝負の分かれ目か」と思った瞬間です。
ただ、144Hz以上で安定して映像を維持しながら録画や配信までしたいとなると、話は違ってきます。
例えばRyzen 7 9800X3Dを使った時、同時に配信ソフトを動かしてもfpsが崩れにくく、長時間のプレイでも滑らかで快適でした。
あの安定感。
派手さではなく、確かな安心が得られる選択肢だと心から感じました。
Core Ultraのもう一つの特徴としてAI処理を意識したNPUの統合があります。
正直なところ、現状のApexでfpsに直結するわけではないんです。
ただ、最近は生成AIを使った映像処理やテクスチャ最適化の研究が増えてきており、将来的にゲームのアップデートで突然AI支援技術が導入されるかもしれません。
その時にCore Ultraが一歩先を行く可能性は十分にありそうです。
私はふと、「次のシーズンで何か仕掛けてくるんじゃないか」と想像してしまいます。
その未来志向な余地に、期待半分、不安半分といったところです。
一方、Ryzenが持つ魅力はもっと現実的で、使い続ける安心感です。
特に消費電力と発熱が安定している点は見逃せません。
ケースの冷却を工夫すれば空冷で十分抑えられ、夏場でも突然の熱暴走を心配せずに済む。
私のように仕事用と遊び用を兼ねるPCでは、その安定性がありがたいですね。
わざわざ大型の水冷を組まなくても成り立つのは大きなメリットだと思います。
気楽さが違います。
fps特化の性能で言うならCore Ultraの優位性は確かに存在します。
そしてそれを狙う人もいます。
その点、Ryzenは環境全体の負荷を抑えつつ、バランス良く長時間快適に使える。
ここに「どちらを選ぶか」の分かれ道がある気がします。
最近ではマップ自体の負荷も増しており、Ryzenのキャッシュ効率が体感で効いてくる場面がますます増えてきました。
私なら迷わずRyzenと答えます。
コスト面でも差が出ます。
同じ価格帯の製品を比べた場合、Ryzenは冷却や電源に余分な投資をしなくても済むケースが多い。
その分のお金をGPUに回した方が、結果的にシステム全体の快適さが底上げされるんです。
PCはCPU単独で完結するものではありません。
バランスを大切にしなければ、全体として満足できるゲーム体験にはなりません。
「CPUだけ速くても意味がない」ということです。
最終的に、選び方は目的次第です。
240Hzの高リフレッシュレート環境で、瞬間的な反応速度に賭けたい人はCore Ultraでしょう。
一方で、配信やマルチタスクを同時にこなしたいならRyzen一択です。
特徴が明確に分かれているからこそシンプルに結論を出しやすい。
迷う余地が少ないとも言えるかもしれません。
私は夜遅くに友人とApexをしていた時、Ryzenで組んだPCが安定して動き続けたことにほっとしました。
あの「熱で落ちるかもしれない」という不安がない安心こそ、社会人ゲーマーにとってはありがたいんです。
対して競技を目指す友人はCore Ultraに惚れ込み、「ここで耐えられるのはデカい」と興奮気味に語っていました。
両方の意見を聞き、なるほど人によって価値基準は本当に違うのだと実感しました。
私は40代のビジネスパーソンとして、時間とコストの配分を常に気にしています。
その立場からすれば今の自分なら迷わずRyzenを選びます。
どちらか一方が正解というよりも、自分のスタイルに合う選択をすること。
その一点が、結局は一番大切なのだと思います。
配信や録画を並行する場合に効いてくるマルチコア性能
ただフレームレートを稼げるだけでは足りません。
配信をオンにした途端に画面がカクついたり音がズレたりすると、せっかくの楽しい時間が一瞬で壊れてしまうんですよね。
私自身、何度かそういう失敗を経験してきました。
だからこそ「余剰コアをしっかり確保すること」が、安定した環境づくりの第一歩になると強く思っています。
144fpsを目指しつつ録画まで同時に走らせたんですが、結果は散々で……。
プレイ中の映像はガタガタ、録画を確認すると二度と見たくないようなカクつきの連続。
あの時は正直、机に頭を抱えました。
そこで思い切ってCore Ultra 7に買い替えたんです。
するとどうでしょう。
OBSの処理が格段に安定し、ゲームのフレームもきれいに維持されている。
あの安堵感は忘れられません。
パソコンの性能に疑いを抱かず、純粋にプレイと配信を楽しめる安心感。
私は「こうでないとダメだ」と心から思いました。
AMDのRyzen 7 9800X3Dを触った時も鮮烈でした。
3D V-Cacheの効果なんでしょう、録画を同時に走らせても動作が乱れません。
配信用のOBSに常時録画をのせていてもまったく負担を感じないんです。
その余裕感に触れて「ああ、ようやく肩の力を抜いて楽しめる」と思いましたね。
録画や配信という楽しみを気軽に加えられる、その支えになっているのが余剰性能だと気づいた瞬間でした。
滑らかで安定した応答、それが一番大事な安心材料なんです。
もちろん、Ryzen 9のようなさらに上位なら鉄壁でしょう。
ただ私としてはRyzen 7のコストバランスで十分納得できた。
配信文化自体が大きく変わったと感じます。
TwitchやYouTubeを見れば、当たり前のように高解像度で滑らかな映像が流れています。
そこに慣れた視聴者は「カクカクしていても仕方ないね」と許してはくれません。
特にeスポーツの現場を覗くと、映像の品質は選手の実力と同じくらい大事に扱われています。
美しい映像が前提の時代に突入している。
だからこそ、個人配信者といえども一定以上のPC環境を整えておかねば取り残されるなと痛感します。
あの熱量に触れると、人ごとではないと本気で思うんです。
もちろん配信用とプレイ用にPCを分けるやり方もあります。
ただ、フルタワーを2台も設置し、電源も電気代も余計に抱え込むとなれば現実的ではない。
多くの場合そんな余裕はありません。
だからこそ1台で完結させる。
そこで頼れるのがマルチコアCPUです。
近年は冷却技術も上がっていますが、長時間配信となると負荷は蓄積します。
空冷の高性能ファンにするのか、240mm級の簡易水冷を導入するのか。
これも悩みどころ。
ただ、静かな冷却環境を整えると集中力が全然違うんですよ。
ファンの轟音にイライラしながら配信を続けるなんてナンセンスだと私は思います。
最終的に見えてきた答えは驚くほどシンプルでした。
高解像度で配信や録画を同時に行いたいなら8コア以上は絶対に欲しい。
さらに突き詰めて安定を重視するなら12コアクラスを積む。
シングル性能が高ければ十分だと信じている人も少なくないですが、実際には配信と録画の負荷がかかると限界が見えてくるんです。
本当に大切なのは、余剰性能。
私は痛感しました。
では、どこで線を引くべきなのか。
コストを抑えつつバランスを求めるならCore Ultra 7かRyzen 7。
もう一段の余裕を持ちたいならCore Ultra 9かRyzen 9。
これだけの選び方で、大きく失敗することはないと確信しています。
というのも、戦闘シーンでフレームが一切落ちない快感や、録画した映像が綺麗に残っている満足感を一度体験すると、もう妥協できないんです。
戻りたくない領域に入ってしまう。
だから私は同じように悩む人へ声を大にして伝えたい。
「余裕をケチるな」と。
滑らかなプレイができる喜び。
美しい映像が残せる満足感。
その両立なしにApex Legendsを心から味わう環境は完成しません。
私はこの数年の試行錯誤でそう学びましたし、これから取り組む人には同じ遠回りをしてほしくない。
もう、その一点に尽きるんです。
最新CPU性能一覧
| 型番 | コア数 | スレッド数 | 定格クロック | 最大クロック | Cineスコア Multi |
Cineスコア Single |
公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 9 285K | 24 | 24 | 3.20GHz | 5.70GHz | 43230 | 2437 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 42982 | 2243 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X3D | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 42009 | 2234 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900K | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.00GHz | 41300 | 2331 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X | 16 | 32 | 4.50GHz | 5.70GHz | 38757 | 2054 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X3D | 16 | 32 | 4.20GHz | 5.70GHz | 38681 | 2026 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265K | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37442 | 2329 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265KF | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37442 | 2329 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 9 285 | 24 | 24 | 2.50GHz | 5.60GHz | 35805 | 2172 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700K | 20 | 28 | 3.40GHz | 5.60GHz | 35664 | 2209 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900 | 24 | 32 | 2.00GHz | 5.80GHz | 33907 | 2183 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.60GHz | 33045 | 2212 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700 | 20 | 28 | 2.10GHz | 5.40GHz | 32676 | 2078 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X3D | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.50GHz | 32565 | 2168 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7900X | 12 | 24 | 4.70GHz | 5.60GHz | 29382 | 2017 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265 | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28665 | 2132 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265F | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28665 | 2132 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245K | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25561 | 0 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245KF | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25561 | 2150 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9700X | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.50GHz | 23187 | 2187 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9800X3D | 8 | 16 | 4.70GHz | 5.40GHz | 23175 | 2068 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 235 | 14 | 14 | 3.40GHz | 5.00GHz | 20946 | 1838 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7700 | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.30GHz | 19590 | 1915 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7800X3D | 8 | 16 | 4.50GHz | 5.40GHz | 17808 | 1795 | 公式 | 価格 |
| Core i5-14400 | 10 | 16 | 2.50GHz | 4.70GHz | 16115 | 1758 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 5 7600X | 6 | 12 | 4.70GHz | 5.30GHz | 15354 | 1959 | 公式 | 価格 |
コスパ重視で狙いたいミドルクラスCPUの候補
値段の張る最上位モデルを求めたくなる気持ちはわかりますが、実際に試してみるとその投資に見合う体感を得られる場面は意外と限られていて、むしろ価格と性能の釣り合いが取れたミドルクラスを選ぶほうが、はるかに賢い選択なのだと痛感したのです。
高すぎもせず、安すぎもしない。
ちょうどその中間にこそ答えがある、と今では強く言い切れます。
私自身、初めてCore Ultra 5を導入したときのことをいまだに覚えています。
正直、最初は不安でした。
本当にこの価格帯で満足できるのだろうか、と。
しかし、いざベンチマークを回してみれば200fps近い数字が画面に出てきて、思わず声を出して笑ってしまったものです。
あの瞬間は純粋な驚きと嬉しさが入り混じり、「これで十分すぎる」と心から納得していました。
候補に挙げたいCPUとしては、インテルならCore Ultra 5 245Kや235、AMDならRyzen 5 9600あたりが堅実だと私は考えます。
本当に。
Apexだけを念頭に置くなら不足を感じるシーンなんてめったにありませんし、余計な出費を抑えられる分でGPUや周辺機器に回すこともできます。
もちろん、配信や動画編集といった並行作業に重きを置くのであればRyzen 7にステップアップしてもいいでしょうが、それはあくまで用途次第。
境界線を自分の生活スタイルに照らしてどう引くかが大事で、そこを誤ると、後で「あんなに出したのに持て余してる」と悔しい思いをする可能性大です。
このテーマを語るうえで、CPUとGPUの関係性を車に例える話をよく耳にしますが、実際に自作を重ねた身からすればその比喩はあまりに的確でした。
エンジンだけ高出力でも、タイヤが追いつかなければ路面を空転するだけ。
ゲーム用のPCでも構図はまるで同じで、CPUに偏って投資しても、GPUが抑えられているとフレームレートが伸び悩む状況に直面します。
そのときに「やってしまったな」と頭を抱える。
だからこそ両者の釣り合いが決定的に重要だと、私は骨身に染みて思い知りました。
個人的に思い出深いのはCore Ultra 5 235Fを組んだときのことです。
想像以上に静音性が高く、夜中に作業をしていてもファンの音が耳障りにならない。
ヘッドセットを外しても、かすかな風の音しか聞こえないほどで、ふと「これなら夜更かししても家族に迷惑がかからないな」と独り言を漏らしてしまいました。
PCは性能だけでなく暮らしに馴染むかどうかも大切で、静音性や冷却性能は快適さを大きく左右する。
毎日触れるものだからこそ実感する大切な要素ですね。
また、WQHD環境や配信・マルチタスクを伴う用途を意識するなら、Core Ultra 7 265KやRyzen 7 9700Xといった少し上のクラスに進む価値はあると考えます。
なぜなら、ゲームと並行して編集ソフトや配信アプリを動かしたいときに安定感を確保できるからです。
私自身、友人にプレイを見せながら軽く編集作業を並行させた経験があるのですが、そのときにCPUの余裕があると安心できました。
そしてその選択が実は過剰ではなく、必要に応じた堅実な投資だったと後から感じられる瞬間がありました。
欲ばりにも見える組み合わせが、むしろ効率的だったというわけです。
CPUを選ぶとき、私が必ず意識しているのは三つです。
今の用途に必要十分かどうか。
将来的な拡張に応えられるか。
その三点です。
例えば、Apexを遊ぶだけなら8コアでもまだ余裕があります。
しかし数年先に登場する新作ゲームや配信への挑戦を見据えると、8コアにしておく安心感には確かな価値があります。
自分が一年後、二年後にどのようにPCを使いたいかを想像しながら選ぶと、大きく道を誤らずに済むのだと思います。
未来志向。
そうして構成を考えていく中で、否応なく大きな出費となるのがGPUです。
これはどうしようもない現実です。
だからこそ私は「CPUは中庸を貫け」と自分に言い聞かせています。
高すぎれば財布が痛み、安すぎれば数年後にストレスが溜まる。
間を選び抜くことこそ、CPU選びの核心なんだろうな、としみじみ思います。
だから、Apexを安定した高フレームレートで遊びたい方に強く伝えたいのです。
この組み合わせ以上に効率よく「現実的な落としどころ」を得る方法はありません。
最終的に戻ってくるのはこの単純な原理で、どんな構成を考えるときも揺らがない柱になっています。
私は無駄が嫌いです。
効率重視。
だからこそ、Apex用にPCを組むときも、私は少しの迷いなくミドルクラスCPUを選びます。
そしてそれを仲間や後輩に勧めても、何一つ恥ずかしさを感じません。
そこには経験に裏打ちされた確信があるからです。
結局、遠回りをせずにすむのが一番の得。
そういう納得に至った道のりそのものが、私にとっての財産なのだと思います。
Apex Legendsを快適に遊ぶために必要なグラボ性能とは

最新のRTX 50シリーズとRadeon RX 9000番台をざっくり比較
Apex Legendsのように一瞬の判断がすべてを左右するゲームでは、グラフィックボードの選択が大きな意味を持つのだと実感しています。
私自身感じているのは、最終的には「勝つために性能をとるのか」「映像をとことん楽しむのか」という自分自身の価値観に依存する、ということです。
RTX 50シリーズは反応速度と安定感が抜きん出ており、Radeon RX 9000番台は映像の美しさで人を惹きつける。
正反対の魅力を持つからこそ、どちらを選んでも後悔はないのだろうと考えています。
この違いそのものが面白い、と私は思うんです。
特にRTX 50シリーズは明確な進化を感じさせます。
敵がドアから一瞬のぞいたときに反応できるかどうか、その差は勝敗に直結します。
あの瞬間感じた心強さは忘れられません。
勝負に挑む勇気をもらえる体験でした。
一方で、Radeon RX 9000番台には違う意味での魅力があります。
RDNA4の思想を反映した設計は堅実で、FSR4によって幅広いGPUでもフレーム生成を可能にしています。
ただ、反応の遅さに敏感な人には厳しく映ることもあるかもしれません。
WQHDや4Kでプレイしていると、一つ一つの光源や影の質感に思わず見入ってしまい、まるで映画を観ているような錯覚に陥る瞬間があります。
ゲームを超えて「作品」として没入できるのがRadeonの魅力だと、私は心から感じました。
メモリ帯域を比較したとき、RTXがGDDR7で1.8TB/sという驚異的な数値を叩き出すのはやはり未来を意識した構成だと分かります。
RadeonはGDDR6ながらも効率的に設計されていて、FSR4を組み合わせることで不足をカバーする工夫を見せています。
ここで思うのは、私たちが実際にプレイする場面で重視すべき点は必ずしも最大フレームレートではないということ。
ApexをフルHDやWQHDで遊ぶ限りでは、フレーム数の高さよりも「安定して落ちない」ことの方が大きい意味を持ちます。
そう痛感しました。
実際、友人たちとRTX 5070とRadeon RX 9070XTを同環境で比較したことがあります。
フルHD、大会に近い負荷設定での平均フレーム数は大きな差が出ませんでした。
ただ、爆発や複数のエフェクトが一度に重なる激しい場面では、RTXの方が粘り強さを発揮する印象が強かった。
一方でRadeonは映像の鮮やかさや彩度の面で群を抜いている。
その場にいた皆で「これって性格の違いそのものだよね」と笑い合ったのが忘れられません。
まさに好みの問題、です。
私は、もし大会や競技を意識するのであればRTX 5060Tiや5070、5070Tiあたりを選ぶのが正解だと思います。
フレームの安定感と応答速度で裏切られることはないでしょう。
逆に、大画面で映像美を堪能しながらじっくりとプレイしたい人にとって、Radeon RX 9070XTの魅力は計り知れません。
プレイ中に思わず見惚れる瞬間があるのはRadeonならではの特徴で、それはゲーム体験そのものを豊かにしてくれる力になります。
どちらを優先するのかによって結論は自然と決まるはずです。
究極的に言ってしまえば、勝ちを狙うならRTX、映像を重視するならRadeon。
これに尽きます。
もちろん電力効率や発熱、価格といった要素を無視できないのも事実です。
しかし最後は「そのゲーム体験を自分がどう過ごしたいか」という問いに正直に答えれば、自ずと納得できる選択にたどり着きます。
そう、自分の時間の使い方を決めるのは自分。
私は今なお、どちらに最終的な答えを出すべきか悩んでいます。
競技の緊張感と結果を求めたい気持ちもある。
けれどもソファに座ってじっくり映像美に酔いしれたい思いもある。
その間で揺れ動きながらも調べ続けているのが正直なところです。
けれどたった一つだけ、確信できることがあります。
どちらのシリーズを選んだとしても、Apex Legendsを快適に動かす基準はすでに満たされているということ。
だからあとは自分が何を求めているかに耳を傾けるだけなんです。
安心感。
満足感。
その贅沢な悩みこそが、ゲームを続ける喜びでもある、と私は思います。
144fpsを安定させるために押さえるべきGPUパワー
CPUが関係ないとは言いませんが、Apex Legendsのように瞬間的な判断や正確さが問われるタイトルでは、描画パワーがあるかどうかで敵を追えるかどうかが変わってしまう。
これは大げさに聞こえるかもしれませんが、実際に勝敗を大きく左右します。
私自身、身をもって体感したことです。
私は実際にRTX 5070クラスを導入したとき、「これは別物だな…」と心の底から驚きました。
それが新GPUでは140台後半でピタッと安定するようになった。
敵が突然クリアに見えるようになり、これまで気付かなかった小さいズレが一気に消えてしまったのです。
環境が整えば、プレイそのものが楽しくなる。
そう感じました。
もちろん現実的な問題として、予算の壁は避けられません。
常に上位モデルをポンと選べれば楽ですが、社会人でも家庭を持っている場合や他に出費が多い時期だと簡単には手が出せません。
RTX 5060TiやRadeon RX 9060XTといったシリーズは、フルHDで144Hzを目指すなら十分なパフォーマンスを発揮する。
私の後輩から相談を受けた時にも、このあたりをおすすめしました。
必要以上に背伸びするよりも「ちょうどいい投資」を選ぶほうが、結果的に長く楽しめる。
VRAMの容量も無視できない要素です。
公式推奨が8GBだといっても、アップデートを重ねるごとに処理負荷は確実に上がっています。
私の環境では12GBを積んだ時、気持ちの余裕がぐっと変わりました。
一瞬のカクつきで試合を落とすほど悔しいことはありません。
GPUを1ランク上げるだけでリフレッシュレートが40%近く改善する、といった実験結果を目にしたとき、私は素直に「これは投資の価値があるな」と思いました。
もちろん数万円の価格差を簡単に決断できるわけではありません。
しかし、シューターで144fpsと100fpsの差はあまりに大きい。
敵を一瞬だけ早く視認できることが勝敗を決める場面は、本当に多いです。
負けた後に「あと少しだけ反応できていれば」と悔やむ経験は、私を含め多くの社会人ゲーマーが味わっているのではないでしょうか。
安心感が違います。
最近はDLSSやFSRのようなアップスケーリング技術が急速に進化しています。
これによりGPUの負担を減らしながらfpsを稼ぐことができるようになり、画質との両立も容易になってきました。
私の周囲でも「多少古いゲームでもこの恩恵は大きい」と語る人が多く、正直ここまで実感できるレベルになったのかと驚きます。
AI処理ユニットを活用する最新GPUは、一見オーバースペックに見えても数年後まで安心して使える性能を秘めている。
そう思うのです。
私は次世代のフレーム生成技術にも期待せずにはいられません。
テスト段階のディスプレイ映像を見せてもらったとき、その映像の滑らかさは本当に自然で、補間フレーム特有の違和感がほとんどなかった。
遅延もほぼ感じられず、「これなら競技シーンでも通用する」と確信できました。
こういう未来を思い描くと、胸が高鳴ってしまいます。
信じられない進化だ。
あらためて振り返ると、社会人で自宅の限られた時間に遊ぶゲームは本当に貴重です。
だからこそ環境に投資する価値を素直に認めたい。
フルHD・144Hzで遊ぶことだけを重視するならRTX 5060TiやRX 9060XTは抜群のコスパを誇りますし、「どうせなら数年は安心したい」と考えるなら、RTX 5070やRX 9070XTが安心できる選択肢になります。
結局は、今の自分の遊び方と今後のスタイルをどう想像するか、そこに尽きるのです。
私自身が出した結論はシンプルです。
144fpsを安定して出したいなら、性能で妥協すべきではない、ということ。
限られた時間で遊ぶからこそ快適な環境で思い切り集中できるのは何よりありがたい。
そのための出費は、ただの娯楽の贅沢ではなく、自分の生活をより心地よくしてくれる投資だと感じています。
GPU選びは、最終的に自分の価値観への正直さを試される場面です。
その選択が日々のプレイの満足感を決定づける。
私はそう考えています。
最新グラフィックボード(VGA)性能一覧
| GPU型番 | VRAM | 3DMarkスコア TimeSpy |
3DMarkスコア FireStrike |
TGP | 公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | 32GB | 48879 | 100725 | 575W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5080 | 16GB | 32275 | 77147 | 360W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9070 XT | 16GB | 30269 | 65968 | 304W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7900 XTX | 24GB | 30192 | 72554 | 355W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5070 Ti | 16GB | 27268 | 68111 | 300W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9070 | 16GB | 26609 | 59524 | 220W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5070 | 12GB | 22035 | 56127 | 250W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7800 XT | 16GB | 19996 | 49884 | 263W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 16GB | 16625 | 38905 | 145W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 16GB | 16056 | 37747 | 180W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 8GB | 15918 | 37526 | 180W | 公式 | 価格 |
| Arc B580 | 12GB | 14696 | 34506 | 190W | 公式 | 価格 |
| Arc B570 | 10GB | 13796 | 30493 | 150W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 | 8GB | 13254 | 31977 | 145W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7600 | 8GB | 10864 | 31366 | 165W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 4060 | 8GB | 10692 | 28246 | 115W | 公式 | 価格 |
ゲーミングPC おすすめモデル4選
パソコンショップSEVEN ZEFT R60GU

| 【ZEFT R60GU スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | AMD X870 チップセット GIGABYTE製 X870M AORUS ELITE WIFI7 ICE |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60CT

| 【ZEFT R60CT スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 9900X 12コア/24スレッド 5.60GHz(ブースト)/4.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Fractal Pop XL Silent Black Solid |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット GIGABYTE製 B850 AORUS ELITE WIFI7 |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R67H

| 【ZEFT R67H スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5000Gbps/3900Gbps KIOXIA製) |
| ケース | DeepCool CH160 PLUS Black |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60SM

| 【ZEFT R60SM スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 DIGITAL WH |
| マザーボード | AMD B850 チップセット MSI製 PRO B850M-A WIFI |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60CYA

| 【ZEFT R60CYA スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) SSD SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | NZXT H9 FLOW RGB ホワイト |
| CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 360 Core II White |
| マザーボード | AMD X870 チップセット GIGABYTE製 X870M AORUS ELITE WIFI7 ICE |
| 電源ユニット | 1000W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (アスロック製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
フルHD・WQHD・4K、それぞれの解像度に合うグラボ選び
社会人になると、自分のための時間はほんのわずかしかなく、その時間をストレスなく過ごせるかどうかは非常に大事な問題です。
だからこそ、解像度ごとに必要な性能をしっかり理解しておくことが、後悔しない買い物につながるのです。
かつて私は「まあこのくらいで十分だろう」と軽く考えて安価なモデルを選び、結局買い直すという痛い経験をしたので、この点は声を大にして伝えたいと思います。
たとえばRTX 4060 Tiくらいのクラスなら、価格と性能のバランスがちょうどよく、普段使いにも違和感がありません。
私はかつてRTX 4070を導入しました。
そのとき初めて、画面にスモークや派手なエフェクトが重なっても一切カクつかない滑らかさを体感しました。
これが本当に快適で、仕事終わりにプレイしていても変なストレスがなく、ただ楽しむことに集中できたのです。
大げさではなく、数字で測れない満足感がそこにありました。
次はWQHDです。
2560×1440の解像度で遊ぶと、映像の精細さに圧倒されます。
一度体感するとフルHDには戻れない。
まるで映像の布に包まれているような心地よさを覚えました。
ここではRTX 4070 TiやRadeon RX 7800 XTといったクラスがおすすめです。
144Hz以上の高リフレッシュレートを、安定して維持できる安心感があるからです。
私は以前、少し予算を抑えて廉価なカードを選びましたが、そのときは設定を上げるとすぐにフレームレートが落ちてしまう。
手応えある撃ち合いの最中に操作が遅れ、勝てたはずの勝負を落とした悔しさは今でも忘れられません。
性能を妥協することが、楽しみを削ることになると痛感した瞬間でした。
4Kになると話は変わります。
3840×2160の解像度は圧倒的に情報量が多く、RTX 4080やRadeon RX 7900 XTXといったクラスでなければ力不足です。
私は展示会で4K+120Hzの環境を目にしたことがありますが、その迫力はまさに次元が違いました。
吸い込まれる感覚。
言葉で説明するのは難しいほどです。
大事なのは、安定して60?120fpsを維持できること。
数値を突き詰めるよりも、圧倒的な映像美を存分に楽しむことに意味があると感じました。
ここで忘れてはならないのがVRAMの容量です。
これを軽視すると、後々本当に痛い目を見ます。
WQHDであれば12GBを下限とし、16GBあれば安心です。
そして4Kに挑むなら、16GB以上を強く推奨します。
私はある試合中、派手な演出が重なった瞬間に映像がガタッと止まり、再開したらすでに倒されていたことがありました。
力の抜けるような瞬間で、言葉にならない悔しさが残りました。
安定感の源だからです。
最近のGPUは性能だけでなく、冷却方式や基板設計の違いによっても寿命や長時間稼働の安定性が変わってきます。
同じシリーズでも、実際のユーザーの体験談を見て初めて「長時間だと熱で性能が落ちる」といった現実的な差が分かるのです。
だから私は、購入前には必ず口コミや使用動画を確認します。
経験者の声は無視できませんし、そこから得られる情報で投資の正しさが大きく変わると感じています。
整理してみれば、フルHDならミドルクラスで十分に快適、WQHDはワンランク上のカードが理想、そして4Kはフラッグシップ級が必要。
結局は「どの解像度とリフレッシュレートで遊びたいのか」を自分の中で明確にして、それに合わせたGPUを選ぶのがもっとも合理的で後悔のない選択になります。
私はそのプロセスを何度も繰り返して、ようやく自分に合った答えを見つけました。
けれども、自分の時間を豊かにするかどうかは環境で大きく左右されます。
だから私は、自分が納得できる選択をしてきたのです。
安心感。
信頼感。
これこそが私がGPUに最終的に求めるものであり、同じように自分の時間を大切にしたい人に伝えたい視点です。
Apex Legendsに適したメモリ容量と規格の考え方

DDR5メモリの速度は実際どこまで効果があるのか
数値的に見ればわずかな差に見える場面もありますが、実際のプレイ中にはその違いが体感としてはっきり現れるのです。
特に240Hz前後のモニタを用いて、とにかく一瞬の反応の速さが勝敗に直結するような環境なら、DDR5の存在が試合を左右することだってあります。
単なる理屈や数字の話ではなく、戦っている本人にとって分かりやすい差として現れるところが大きいのです。
CPUとGPUが同時にリソースを食い合うような状況で、DDR4の頃には感じていた一瞬の詰まりが薄れる。
この感覚は、机上の理論や比較サイトを眺めているだけではわかりません。
実際に銃声が鳴り響く激戦区に降り立ち、十人十色のプレイヤーが入り乱れる状況で「まだ抜けている」と実感できるのがDDR5です。
去年、私は思い切ってDDR5-5600の32GB構成に切り替えました。
それまでDDR4の環境で遊んでいた頃は、敵を追いかけながら視点を振った際にカクンと止まる場面があり、その瞬間に撃ち負けて画面を叩きたくなるような気持ちになることが多かったんです。
しかし新環境に移行してからは、そうした場面がぐっと減り、スムーズに敵の動きを追える。
最初に体験した瞬間には思わず、「ああ、これだよな」と声を漏らしました。
ゲームを続けてきて本当に良かったと思える出来事でした。
DDR5は手を出しやすい価格になりつつあるとはいえ、DDR4と比べればまだ割高です。
しかし私はこう考えました。
もし大会やランク戦の一番大事な場面で一瞬止まって負けたら、その悔しさはいつまでも残るだろう、と。
そこをなくせる可能性があるなら投資する価値は十分にある。
むしろCPUやGPUを新調しながらメモリを古いままで使い続ける方が、全体のバランスを崩してしまう危うさを感じます。
中途半端な投資ほどもったいない。
ただし勘違いしてはいけないのは、クロックをひたすら上げれば効果が得られるというものではないことです。
私自身、5600から6400まで上げて体感上の伸びを少し感じましたが、さらに7200以上にチャレンジする必要は薄いと感じました。
むしろシステム全体が不安定になるリスクまで見えてくる。
だから、等身大で程よいバランスの範囲を選んだ方が堅実なのです。
尖った選択を避けるのは若い頃には考えなかった発想ですが、今の私は安定を最優先しますね。
標準的なBTOでも5600を搭載したモデルが数多く見られるようになり、特別な選択ではなくなりました。
私自身は使ってみて安定性の面でCrucialに信頼を置いています。
一方で、仲の良い同僚はG.Skillを選び、高クロックで動かすこと自体を楽しんでいます。
その様子を見て、「なるほど、こだわる部分って人によって違うよな」と笑ってしまいました。
正解は一つではないということですね。
ゲーム用途に限らず、DDR5がもたらすメリットは日常の作業にも感じ取れます。
私は普段から複数ブラウザを開き、さらに録画や資料を置いたままゲームを起動するのですが、DDR4の時代には時折応答が遅れることがありました。
DDR5に換装してからはそうした遅れが一気に減り、マルチタスクの動作が滑らかになったのです。
配信をしながら複数のアプリケーションを動かすクリエイターやストリーマーにとっては、この余裕は間違いなく大きな意味を持ちます。
この用途では、もはや贅沢品ではなく必需品という感覚がふさわしい。
最終的に私が人に勧める組み合わせは32GB、DDR5-5600以上というラインです。
余裕があれば6400も悪くありませんが、私自身は7200までは不要だと考えます。
そこまでする必要はない。
それよりも安定した構成を選んでおくだけで、CPUやGPUが持つ力を十全に発揮できる。
実際に試合中の「一瞬のカクつきで負けた」という悔しさをぐっと減らせるのは大きな強みですし、その積み重ねが日々のモチベーションにつながります。
私は40歳を過ぎてもなおFPSをやめられません。
若い頃ほど反射神経には自信がありませんが、その代わりに環境を整えることが勝率や満足感に直結するのだと強く思うようになりました。
ほんの数秒の滑らかさが、自分を戦場で強くしてくれる。
だからDDR5はただの部品ではなく、自分に安心と余裕を与えてくれる存在なのです。
「環境を信じて戦える」という気持ちをくれるのがDDR5。
人数が増える終盤戦。
勝負どころの呼吸のリズム。
その時にプレイを支えるのは、結局のところ機材への信頼です。
私はこれからもDDR5を選び続けます。
CPUとGPUの力を存分に解き放ち、安心して戦場を駆け抜けるために。
16GBで十分?それとも32GB以上が安心?
Apex Legendsを快適に遊ぶために必要なメモリ容量について、私が感じている答えはシンプルです。
しかし配信をしながら遊んだり、裏で複数のアプリを同時に立ち上げたりするのであれば32GBは必要になります。
そしてさらに動画編集や3D制作まで手掛けたいのであれば64GBを選ぶことを強くおすすめします。
これは単なる数字の話ではなく、私自身が実際に経験してきたことの積み重ねから導いた実感なのです。
私は過去に16GBの環境で遊んでいた時期がありました。
フルHDで高いリフレッシュレートを狙っても平均で200fpsほど出ており、そのときは「これで十分だ」と安心していたのです。
ところがある日、配信をしながらDiscordで仲間と通話していたら、途端に動作がもたつき始めました。
ゲームが急に止まってしまい、友人に「おい、止まってるぞ」と笑われたときの悔しさは今でも鮮明に覚えています。
あのときの居たたまれなさは、もう二度と味わいたくない感情でした。
結局32GBに増設したのですが、その瞬間から世界が変わりました。
配信もゲームも快適、裏でいくつかアプリを立ち上げても心配はいらない。
息苦しさがなくなり、肩の力が抜けるような感覚になったのを今でも覚えています。
この経験をしてからは、私の中で「16GBで十分」という考え方は自然に消えていきました。
やっぱり余裕がある環境というのは心まで軽くするんだと強く感じました。
最近はWindows自体が昔よりも重くなっています。
便利な機能が増える一方で、そのぶんメモリを確実に食う。
ブラウザを数枚開いて、そこにチャットや動画が加われば、16GBではあっという間に窮屈になります。
DDR5規格の速さがあると言っても、長時間の安定感という点では不安を拭えません。
だからこそ32GBの安心感は大きいのです。
気持ちの余裕にまで繋がりますからね。
そして64GB。
これは正直、別世界です。
配信者仲間の中にはすでに64GBに移行した人もいますが、彼らが口を揃えて言うのは「もう戻れない」という一言です。
動画編集や複数ゲームを横断するような場面では、その余裕ぶりが圧倒的で、私も実際に試したときは鳥肌が立ちました。
32GBで充分だと考えていた自分が、64GBを経験した瞬間に「もう次はこれにする」と確信したほどです。
まさに解放感。
そう表現するのが一番しっくりきます。
最終的には予算の問題で32GBに落ち着いたのですが、実際に配信や同時作業をしていると「64GBにしておけばよかった」と思う瞬間が何度もありました。
そのたびに、小さな後悔が胸に浮かんできます。
結局のところ、私は数年以内に必ず64GBへ移行するだろうと、自分を納得させているのです。
あのときの選択は痛恨でした。
さらに重要なのは、全体的に最新のゲーム環境がどんどん重たくなっていることです。
Apexに限らず、多くのタイトルが高解像度のテクスチャを標準のように要求しています。
GPUからのデータやり取りが増える中で、システムメモリに負担がかかる未来は避けられません。
この変化を見据えれば、中長期で快適にゲームを楽しむためには、やはり余裕を持った選択が大切だと痛感します。
将来を考えるならなおさらです。
そして作業範囲をさらに広げるなら64GBが効いてくる。
この判断基準は私の体験にとどまらず、同じ環境で遊んでいる知人たちの実際の声とも重なります。
だからこそ確信が持てるのです。
最終的に整理すると、ゲームだけなら16GB、配信や作業を並行するなら32GB、さらに動画編集や大規模作業まで見込むなら64GB。
この基準が分かりやすい軸になります。
メモリ容量の選び方は、単に数値の問題ではなく、自分がどんなシーンで快適さを欲しているかに左右されます。
その判断軸をはっきりと持つことができれば、きっと後悔しない選択ができるはずです。
私はそう信じています。
安心感。
信頼性。
そして長く快適に遊びたいという気持ち。
配信や複数作業を踏まえた最適なメモリ容量の目安
でも少し負荷をかけるだけで途端に不穏な引っかかりが出てしまい、Discordで通話をしながらOBSを動かし、さらにChromeでタブをいくつも立ち上げていると、シーンを切り替えた瞬間に一拍置いたようなフリーズ感が走る。
これが地味にストレスを積み重ねて、試合の集中力を削るんですよね。
あの一瞬のラグが命取り。
それが私の痛感した現実でした。
だから32GB。
ここが最低限のラインだと身をもって学びました。
実際、32GBに変えてからは余裕がまるで違うんです。
以前は「タブをいくつ閉じるか」「仕事のアプリは落としておかないとダメか」といった面倒な心配を常にしていましたが、今はそういう小さな不安を抱かなくていい。
その安心感がゲームへの没入度を桁違いに高めてくれます。
余裕があるって本当に大切なんだな、としみじみ思いました。
安心感って大きい。
64GBについても私は一時期試しました。
検証が目的でしたが、その圧倒的な余裕は相当なものでした。
動画編集しながら配信をかけても、まったく不満を感じない。
動作が滞る場面もなく、想像を上回る快適さで「ここまで違うか」と驚いたことをはっきり覚えています。
しかし、率直に言ってそこまで必要な状況は滅多に訪れません。
プロの映像クリエイターや複雑な仮想環境を扱う方であれば投資する価値もあるでしょうが、大半のゲーマーや配信者にとってはオーバースペックです。
私自身も「贅沢すぎる」と結論づけました。
だから人に勧めるときはいつもこう伝えています。
「配信や同時作業を考えるなら32GBで十分。
それ以上は特別な用途がある人に限る」と。
64GBは価格も依然として高めですし、自己満足で買うと後から「ここまで使わなかったな…」と悔やむ可能性だってある。
現実的な判断としては、やはり32GBを基準に考えるのが一番だと確信しています。
必要十分。
その言葉がしっくりきます。
ここで改めて配信環境を具体的に想像してみてください。
OBSを立ち上げっ放し、ブラウザには動画サイトや複数のタブ、さらにチャットアプリが常駐。
音楽を流しながら友人と会話しつつ戦う場面は日常的です。
そうなると16GBではすぐに限界がやってきて、気づかないうちにスワップが発生。
結果として視聴者にカクつく映像が届いてしまう。
それはもったいないし、同時に信頼を落とす出来事にもつながります。
配信を観にきてくれた人に不快な印象を与えてしまうのは、私が一番避けたいものです。
だからこそ32GB。
これが持つ意味は、ただの数字以上に大きいんです。
WordやExcelを普通に開きっぱなしにして、その横でApexを立ち上げる。
閉じなくてもいいという心の余裕が思いのほか幸せなんです。
やりたいことを同時に走らせても問題ない環境だからこそ、ゲームをしているときもビジネス文書を扱っているときも安心できる。
何度も言いたくなります。
快適さはスペックに宿るんです。
一方で、64GBを体験したとき、心のどこかで「余裕はあればあるほどいい」と思った瞬間も正直ありました。
けれど冷静に振り返ると、配信を主目的とする人にとってはそこまでの投資は必要ないなと確信したんです。
大事なのは費用対効果。
だからこそ32GBを選択することが後悔しない判断になると思います。
信頼につながること。
Apexのように一瞬で勝敗が決まるゲームで、裏作業の不具合やメモリ不足による処理落ちで大事な場面を逃すと、言葉にできないほど悔しい。
小さな違和感、ほんの一瞬の止まりが敗因になり得る。
その現実を体験した私だからこそ言い切れます。
妥協は禁物なんです。
結局のところ、多くのプレイヤーや配信者にとって最適な答えは明確です。
32GB。
これ以上でもこれ以下でもない。
16GBはすでに時代遅れでストレスを抱える選択肢。
64GBは特別な用途のある人専用。
私自身が身をもって検証してきたからこそ、自信を持ってすすめられます。
32GBさえあれば配信も作業も並行しながら、安心して戦える。
その環境を自分のものにできるのです。
だから私は強く言いたい。
32GBがまさにベストな選択だと。
Apex Legendsを快適に動かすためのストレージ選びの勘所


Gen4とGen5 SSD――体感できる違いはある?
これは多くの人が気になるテーマですが、私が率直に感じた結論は「ゲームだけの用途ならGen4で十分」というものです。
プレイ中に劇的な差が出るのでは、と思っていたのですが、実際はロード時間が数秒縮まる程度。
本当にその差で勝敗が左右されるかといえば、全くそんなことはなかったのです。
そのとき私は、期待と現実のギャップに少々肩透かしを食らったような気分になりました。
もちろん、カタログスペックを見ればGen5の速さは圧倒的で、最大14,000MB/sを超える製品すらあるわけで、数値だけならGen4の倍近い性能を誇ります。
それを目にすると「これならマップロードなんて一瞬だろう」と思い込みたくなる気持ちは自然です。
けれどもゲームというのはCPUやGPUとの連携、そしてソフトの設計による制約も多いので、数字がそのまま体験に直結するわけではありません。
現実は冷静で、私が得た効果は起動からキャラクター選択までがほんの2秒ほど短くなった程度でした。
いやはや、派手さは皆無です。
ただし誤解してほしくないのは、Gen5の価値がゲームだけで判断されるものではないということです。
私は大きなアップデートが来るたび、数十GBのパッチ適用に時間を取られていたのですが、ここでは明確に違いを感じました。
加えて、録画をしながらプレイし、その裏で動画編集用のソフトも動かしていたとき、Gen4では「まだ処理が追いついてないのか」と溜め息をついていたのに、Gen5だと「おっと、もう進んでるな」と思える軽さが出てきたんです。
こういう瞬間には、財布を痛めてでも新しい世代に切り替えたことに意味があると実感しました。
作業効率の差。
一方で、Gen5には大きな落とし穴があります。
それは発熱。
ヒートシンクを取り付けるのは最低限としても、ケース内の風の流れが少しでも悪いとすぐに温度制御の警告が出てしまう。
最初の頃、私は冷却面を甘く見て「まあ大丈夫だろう」と軽い気持ちで設置したのですが、数分でサーマルスロットリングが発動してGen4以下の性能に落ち込むという最悪のパターンを経験しました。
笑えない。
まさに熱との戦いです。
この経験から私は「安心して使いたいならGen4の方が無難だ」と強く思うようになりました。
発熱に神経を使わなくても済むし、性能は必要十分。
コスト的にもGen4で組んだ方が遥かにバランスがいい。
もしゲームを中心に楽しみたいだけなら、むしろ余った予算をGPUやCPUに回した方が確実に満足度は高いと断言できます。
結局、性能のどこに重きを置くかで選び方が変わるんですよね。
納得感のある投資。
とはいえ、未来という観点で考えると見方は変わります。
思い出すのはスマホ回線が4Gから5Gへ移行したときの感覚です。
最初は誰もが「そこまで必要ない」と思っていたのに、1年もしないうちに「ああ、5G対応でよかった」と言える状況が増えていった。
変化とは往々にしてそんなふうに後から効いてくるものです。
PCパーツの進化も同じ道筋をたどるのだろうと私は考えています。
だから私は、今すぐ性能を使い切ることができなくても、Gen5対応のマザーボードを選んでしまいました。
将来「一歩先を踏み出しておいて良かった」と思える瞬間が必ず来ると信じたからです。
実際には冷却強化のために追加出費がかさみ、財布がかなり軽くなりましたが、それも自己投資として受け止めました。
正直「これは次に組むときの教訓にしないとな」と苦笑いもしたんですけどね。
最終的に重要なのは、自分がPCをどんなふうに使うのかをしっかり見極めることに尽きます。
Apexのように気軽に遊びたいだけならGen4で十分幸せになれるし、そこに余計なリスクや不安を持ち込みたくない人には最良の答えとなるでしょう。
一方で、動画編集やRAWデータの現像、大量データの圧縮や加工といった仕事にまでPCを使う方なら、Gen5の潜在力を確実に活かせる。
振り返れば、私がGen5を試したのは大人になってなお消えない「性能を追いかけたい」という好奇心のせいでした。
結果的に得られたのは速さそのものよりも、自分が何を大事にしているかを気づかせてくれるきっかけだった気がします。
快適さか、それとも将来性か。
選択の軸は人によって違います。
ただし自分の価値観を理解した上で選ぶことが何より大事です。
まとめると、ゲームを快適に遊ぶためだけならGen4で十分という答えになります。
逆に、作業効率や将来的な拡張を重視するならGen5を選ぶ意味は確かにある。
そしてその判断こそが、自分のスタイルを反映したPC作りにつながるのです。
結局のところ、どちらを選んでも致命的な失敗にはなりませんが、大事なのは納得して選ぶこと。
SSD規格一覧
| ストレージ規格 | 最大速度MBs | 接続方法 | URL_価格 |
|---|---|---|---|
| SSD nVMe Gen5 | 16000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD nVMe Gen4 | 8000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD nVMe Gen3 | 4000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD SATA3 | 600 | SATAケーブル | 価格 |
| HDD SATA3 | 200 | SATAケーブル | 価格 |
ゲーミングPC おすすめモデル4選
パソコンショップSEVEN ZEFT R60GV


| 【ZEFT R60GV スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 9950X 16コア/32スレッド 5.70GHz(ブースト)/4.30GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | NZXT H9 FLOW RGB ホワイト |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II White |
| マザーボード | AMD X870 チップセット GIGABYTE製 X870M AORUS ELITE WIFI7 ICE |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55GD


| 【ZEFT Z55GD スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra5 245KF 14コア/14スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.20GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ブラック |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R61BK


| 【ZEFT R61BK スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 9950X3D 16コア/32スレッド 5.70GHz(ブースト)/4.30GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | AMD B850 チップセット MSI製 PRO B850M-A WIFI |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R44CG


高速な実行力で極限のゲーム体験を支えるゲーミングモデル
直感的プレイが可能、16GBメモリと1TB SSDでゲームも作業もスムーズに
コンパクトなキューブケースで場所を取らず、スタイリッシュなホワイトが魅力
Ryzen 9 7900X搭載で、臨場感あふれるゲームプレイを実現
| 【ZEFT R44CG スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 7900X 12コア/24スレッド 5.60GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (8GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B650 チップセット MSI製 PRO B650M-A WIFI |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
ロード時間を縮めたい人に向いた容量の決め方
CPUやGPUにこだわるのも確かに大事なのですが、ロードが長引くだけで一気に気持ちが萎える。
仕事から帰って、ようやくリラックスできる時間にゲームを立ち上げたのに、肝心の試合開始までに何分も待たされると、「なんでこんな思いをしなきゃいけないんだ」と憤りを感じるんです。
そこで私は、容量の余裕こそが真のストレスフリーな体験を支える鍵だと悟りました。
昔、私は「500GBあれば十分だろう」と軽く考えていました。
実際、その時点ではApex Legendsと数本のタイトルを入れてもいけると思っていたんです。
しかし現実は違いました。
録画を少し溜めただけで残容量が警告表示になり、起動中にガタついて落ち込む羽目になる。
あの虚しさは今でも鮮明に覚えています。
「たったこれだけで不安定になるのか」と肩を落とし、何度も深いため息をつきました。
一方で、NVMe SSDへ換装したときの解放感はすごかった。
特に2TBを選んだ時は文字通り別世界で、起動からロードまでの流れがスムーズになり、あぁこれは間違いなく投資の価値がある、と胸の奥で納得しました。
理論値の改善とかそういう解説を聞くよりも、自分の体で感じる方がずっと説得力がありましたね。
本音を言えば、HDDに戻ろうとしたこともあります。
古い環境との比較をしたくて使ってみたのですが、数分で後悔しました。
あのもたつき、あの空回りするような感覚。
戻れるはずがないと強く実感しました。
二度と選ばない。
最近はGen5 SSDの話題も出ていますが、あれは正直、まだ現実的じゃありません。
発熱がすごいんです。
冷却ファンを調整して、ケースのエアフローまで考えて、温度管理をきっちりできる人なら選択肢に入るでしょう。
でも、仕事帰りにパッと電源を入れて遊びたい私のような人間にとっては、あまりに面倒。
だからこそ私はGen4を現実解として選んでいます。
十分速いし、容量面も2TBあればそう簡単には困りません。
安心感があります。
特に、SSDは容量の8割を超えると書き込み速度が落ちやすいというのは理論的に説明されますが、それを「体で理解した」と思えた瞬間がありました。
2TBに換装してから、余裕ある空き容量のおかげか挙動がひときわ安定する。
ロードが途切れなく進む。
その小さな違いが積み重なることで、ゲーム全体のテンポが明らかに良くなるんです。
ほんのわずかなズレでも、毎日触れるものだからこそ大きな差に育つ。
そういう肌感覚をようやく得られました。
たとえるなら、高級車を買ったのに渋滞でまったく進めないという状態に近い。
性能自体は高いのに、環境や条件次第で宝の持ち腐れになる。
SSD容量もまさにそうで、高速性能だけを追い求めても、本来の力を発揮できなければ意味がありません。
私は「速度だけでなく余裕を買っている」と考え直しました。
心が軽くなる発想かもしれませんが、これは実際に続けて遊ぶ上で非常に大きい。
それに、冷却のポイントも忘れてはいけません。
ヒートシンク付きのSSDは今では当たり前に選択肢にありますが、特にGen5を狙うなら追加の冷却管理は避けられません。
だから私は結局のところ、「余計な心配をせずに快適に遊べる環境」が欲しかった。
仕事の疲れを癒やすのに温度の数字と格闘するなんて御免でした。
以前は500GBでやりくりして、こまめに整理してゲームを切り替える生活をしていました。
しかしアップデートが肥大化し、録画やキャッシュが蓄積していく中ではそのやり方はもはや通用しません。
空き容量の確保に何時間も使って、結局遊ぶ時間を削られる。
ゲームを楽しむどころではなくメンテナンスが日課になる。
あれは最悪でしたね。
だから私は今、迷わず語れます。
1TB以上、ベストは2TB。
それ以上でももちろん構いませんが、生活に無理なく導入できるのはこの辺りが現実的な落としどころです。
ロードが短く、容量に悩む必要がないという要素は、想像以上に心を軽くしてくれます。
ロードが速くなる。
容量の心配がなくなる。
だからプレイに集中できるんです。
私の結論は明確です。
ロードの短縮を本気で望むなら、SSDの容量に妥協は禁物です。
2TBのGen4 NVMe SSDを選び、半分以上は常に余裕を残す。
それが最も安心でき、長続きする判断でした。
これなら、余計な神経をすり減らさなくていい。
何も考えずに腰を下ろし、パッと電源を入れて楽しめる。
ゲームのある生活を本当に豊かにするためには、この選択こそが必須なのだと、私は胸を張って言えます。
終わりに伝えたいのはただ一つ。
ヒートシンク付きSSDが熱対策に役立つ理由
高性能なパソコンを組むときに、多くの人がまず気にするのはCPUやGPUです。
ただ、今の私が強く実感していることは、パソコンを本当に快適に使うための鍵はストレージの安定性だということです。
とくにヒートシンク付きのSSDを選ぶかどうかで、その後の使い心地が大きく変わってしまいます。
だから今の私は胸を張って言いたいのです。
ゲームを長く安定して遊びたいなら、まずSSDの冷却に目を向けるべきだと。
私が初めてNVMe SSDのGen5モデルを導入したときの興奮は、今でも鮮明に覚えています。
最初にベンチマークを走らせた瞬間は「なんだ、この速さは!」と声が出るほど嬉しかったのです。
でもその喜びは長く続きませんでした。
実際にゲームを数時間連続で遊んでいると、温度がどんどん上がっていき、突然ロードが延々と終わらなくなった瞬間がありました。
戦闘シーンで急に動作がカクついたあの冷や汗。
心底「冷却なしではこの性能は守れない」と実感しました。
ヒートシンクの存在を軽く考えていた時期もありました。
正直に言えば「SSDは発熱で壊れることもないだろう」と思い込み、見た目や価格だけで選んでいました。
システム全体のリズムが狂うのです。
特にApex Legendsのようにアップデートサイズが数十GBに及ぶゲームでは、この違いがハッキリ出ます。
ロードやパッチ適用の待ち時間がうんざりするほど長く感じられ、少しずつ溜まるストレスに「やっぱり冷却って大事なんだな」と痛感したものです。
最近はBTOパソコンの多くが標準でヒートシンク付きSSDを搭載するようになってきました。
私はこれは自然な流れだと思っています。
PCIe Gen5のSSDは14,000MB/s以上の速度を誇るものもあり、こうなると冷却を意識しない設計ではせっかくの性能が生かしきれません。
私自身も大型のヒートシンク付きSSDに変えてからは、ストレスのない安定動作に感動しました。
長時間プレイでも温度が落ち着いていて、あの嫌なサーマルスロットリングが一切出なくなったとき、「これが本当の快適さか」と心の底から思いました。
安心感がある。
この言葉に尽きると思います。
パソコンは数字やスペックで語られやすいですが、安心して長時間遊べることほど価値のある要素はないです。
そんな当たり前のことが実はとても大きくて、日常の軽快さにつながるのです。
もちろんヒートシンクなら何でもいいという話ではありません。
材質や形状、SSDとの密着度で効果が大きく変わります。
ケース内部のエアフローも無視できません。
見た目は抜群に良かったのですが熱がこもりやすく、SSDの温度が安定しなくなったのです。
あのときは「どうして最初から冷却を考えなかったんだろう」と反省しました。
今は純正のヒートシンク一体型SSDを気に入って使っています。
メーカーが放熱設計までしっかり考えており、細部まで合理的に作られているのを感じます。
以前、安価な汎用品を試してみたこともありましたが、効果はいまひとつで苦笑いするしかありませんでした。
正直な話、SSDの冷却をおろそかにすると必ずツケが回ってきます。
特にApex Legendsのようにアップデートが多いゲームでは、一回ごとに負荷がかかる時間が長いです。
見えないところでSSDが必死に発熱と戦っていると考えると、「多少の工夫で寿命が延びるならやるべきだ」と自然に思えます。
これは単なるパフォーマンスの話ではなく、長期間安心して使うための投資だと私は捉えています。
どうしてもパソコンの宣伝ではCPUやGPUが主役になりがちで、SSDの存在は隅っこの扱いになるものです。
ロードの速さ、アップデートのストレスのなさ、そしてシステム全体の信頼性。
全部ここにかかってくる。
だから私はハッキリと言いたいのです。
Apex Legendsを心から楽しむなら、ヒートシンク付きSSDは必須だと。
それ以外の選択肢では、長期的に満足できる環境は整いません。
信頼できる選択。
これは大げさではなく、本当にそう思います。
両方を踏まえて強く言えるのは「後悔しない一歩を踏み出すなら、冷却を考えたSSDを選ぶのが正解だ」ということなのです。
Apex Legends用ゲーミングPC|冷却とケース設計の考え方


空冷と水冷――fpsを安定させやすいのは?
スペックの数字を追いかけることよりも、長くプレイしたときの安定感こそが重要なんです。
つまり、性能を支える舞台裏の部分ですね。
空冷と水冷、どちらを選ぶかは環境や目的によるのですが、私自身の経験ではどちらにも明確な優位性があり、その差を理解して選ぶことが失敗しない一番の近道だと思います。
私が最初に惹かれたのは空冷でした。
正直なところ特別な理由があったわけではなく、「シンプルで壊れにくい」という安心感が一番の決め手でした。
Core Ultra 7とRTX5070Tiを組み合わせ、フルHD・240Hzの設定で遊んだとき、CPU温度は70度前後で安定し、fpsも落ちません。
「集中できる」ってこういうことなんだよなぁと実感しました。
余計な心配をせずに遊ぶ。
それは思った以上に大事な価値でした。
もちろん、欲張りな自分もいます。
WQHDや4Kで試してみたいとなると、今度は話が変わります。
空冷だけでは安定しきれない場面が出てきて、水冷の強さを実感するんです。
初めて簡易水冷を導入する前は、正直「大げさじゃないか」と少し疑っていました。
でも実際に組んでみると違う。
fpsの揺れ幅が狭まり、最後までパフォーマンスを維持してくれるあの感触は忘れられません。
「ああ、これが水冷の力か」と心の底から納得しました。
とりわけ夏場は差が出ます。
真夏にエアコンを我慢しながら配信したとき、空冷ではどうも熱がこもってfpsが下がったんです。
あの瞬間のもどかしさは忘れられません。
大会を観ていても、後半になって明らかにフレームが落ちている選手を見たことがあり、これはまさしくクロックダウンの典型例だと感じました。
冷却を甘く見てはいけない。
勝ち負けに直結することだってあるんです。
水冷での体験も印象深いです。
プレイ後ログを見て思わず「これだ!」と声が出ました。
fpsの揺らぎがないと、操作の手応えそのものが澄んだように感じられます。
長年ゲームをやってきて、こういう感覚を得られたのはとても新鮮でした。
ただし、水冷も万能ではありません。
ポンプの故障や冷却液の劣化というリスクは確かに残りますし、設置にはそれなりのスペースも必要です。
しっかりしたトップクラスの空冷クーラーなら、ApexのようなGPU主体のゲームで不足を感じる場面はほとんどありません。
埃を時々掃除してやるだけで長く付き合える。
この堅実さ。
もっと言えば、自作好きには水冷を選びたくなる瞬間があります。
最近のケースは240mmや360mmラジエータの設置が前提になっていて、せっかくだから活用したいと思うこともある。
見栄えのために選ぶというのも決して悪くない。
自分がどういう環境を望み、どんなプレイスタイルを持っているか。
その価値観の問題です。
私の考えは明快です。
フルHDを中心に遊ぶなら空冷で十分、長時間の高負荷や4K環境で挑みたいなら水冷が安心。
要は「勝ちたいのか」「快適さを重視するのか」「見た目を楽しみたいのか」という選択にすぎません。
結局のところ、冷却を軽視すると途中で不満を抱えるのは間違いありません。
せっかく高価なGPUを買っても、その力を発揮できなければ意味がない。
投資が無駄になればがっかりですし、限られた時間で遊んでいる私のような年代には痛すぎるロスです。
だから声を大にして言います。
冷却は基礎体力。
ゲームを心から楽しむ土台です。
振り返ると、空冷か水冷かという二択は単純に見えて、その裏には生活スタイルや価値観が反映されています。
メンテナンスをシンプルに済ませるなら空冷。
性能を突き詰めてでも勝負に挑みたいなら水冷。
その選び方が、実は自分らしいプレイスタイルの象徴になっているのです。
迷う必要はありません。
どちらを選んだとしても価値がある。
空冷の良さ、水冷の良さ、それぞれに確かに存在しています。
その事実を理解したうえで選べば、仲間との雑談でも配信でも誇らしく語れるはずです。
高負荷時でもCPU温度を抑えるための工夫
あの悔しさを味わって以来、冷却を軽視してはいけないと深く心に刻みました。
描画処理だけでなく、裏で動く接続管理や同時処理の負荷が積み重なって常に高温になり続ける。
それが現実です。
だからこそ、CPUが安定して回り続けられるように支えてやる冷却設計こそ、ゲーム体験を左右するんだと痛感しています。
私の失敗談を挙げます。
以前、コストを抑えて中クラスの空冷クーラーを取り付けたことがあります。
当時は「それで十分だろう」なんて楽観視していました。
ところが実際にベンチテストを回すと、あっさり80度を越えてしまい、ゲーム中にファンが全力で回るたびにため息。
追い詰められた私は最終的に240mmの簡易水冷に切り替えました。
すると、嘘みたいに10度もCPU温度が下がったんです。
プレイ中もしっかり安定して70度台で収まる。
静かさも加わって、あの瞬間は心底「やって良かった」と思いました。
まさに別物でしたね。
しかし、クーラーを変えただけで全て解決するほど甘くありません。
ケース全体の空気の流れを整えなければ、根本的な安定は手に入りません。
前から入れて後ろと上から出す、この基本を崩すとほぼ失敗する。
確かに見栄えは最高でした。
でも熱がこもってしまって、気づけば筐体に触れると指先が温かくなっている。
もうゲームどころじゃない状態でした。
外見に心を奪われて冷却を疎かにしたあの時ほど、自分を責めたことはありません。
さらに設置環境でも差が出ます。
壁にピタリとくっつけたままでは吐き出した熱がこもり、まるで熱風機。
机の下に押し込んだときも同じで、ケース全体が熱気だまりになってしまいました。
ほんの少し背面に空間を作るだけでCPU温度が数度下がるのを目にして、シンプルな工夫が効果絶大だと実感しました。
小さいけれど馬鹿にならないんです。
これは生活の知恵に近い感覚でした。
ケーブル配置の乱れも見逃せません。
配線をまとめていないと空気の流れがせき止められて、結果として熱がこもります。
私は一度、丁寧にケーブルを整理してみたら、それだけでCPU温度が5度下がったことがありました。
作業はわずか数分。
それでこの違い。
思わず「なんで最初からやらなかったんだ」と悔しさを感じました。
怠慢を恥じましたね。
でもそこから、自分なりに配線管理にこだわるようになりました。
これらの経験を重ねてきて、私は冷却を「消極的な熱対策」とは考えなくなりました。
むしろ未来への投資だと感じるようになったのです。
最新の簡易水冷は扱いやすいですし、静音性も優れている。
昔は水冷と聞くと扱いが面倒でリスクも高い印象がありましたが、今ではBTOパソコンのオプションでも気軽に選べるレベルになっています。
いざ試してみると、「ここまで静かに保てるのか」と驚かされる。
環境が整えば集中力が変わる。
それはゲームの世界に深く入り込めるだけでなく、普段の作業にすらプラスになる。
そんな実感があります。
私は今では強く思っています。
冷却は徹底的にやりきるものだと。
空冷なら最高クラスを。
水冷なら240mm以上を妥協せずに選ぶ。
そしてケースは必ずエアフローを意識して設計し、排熱の流れを作る。
さらに配線を整え、設置環境に細心の注意を払う。
この一連の努力を積み上げることで、ようやく「これで安心だ」と心から言える環境ができ上がります。
安定。
熱対策。
これがすべての基盤だと思います。
Apexのような高速ゲームを高fpsで楽しむには、冷却と空気の流れ。
この二本柱を軽視して環境を語ることはできません。
40代になった今でも私はその価値を信じて疑いません。
何事も小さな工夫を積み上げ、丁寧に形にしていくこと。
その積み重ねがようやく信頼できるゲーミング環境をつくる。
ゲーミングPC おすすめモデル5選
パソコンショップSEVEN ZEFT R67C


| 【ZEFT R67C スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 7700 8コア/16スレッド 5.30GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5000Gbps/3900Gbps KIOXIA製) |
| ケース | DeepCool CH160 PLUS Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60SC


| 【ZEFT R60SC スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9700X 8コア/16スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S100 TG |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850I Lightning WiFi |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN EFFA G09U


| 【EFFA G09U スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 7700 8コア/16スレッド 5.30GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R53JA


鮮烈ゲーミングPC、スーペリアバジェットで至高の体験を
優れたVGAと高性能CPU、メモリが調和したスペックの極致
コンパクトなキューブケース、洗練されたホワイトで空間に映えるマシン
最新Ryzen 7が魅せる、驚異的な処理能力のゲーミングモデル
| 【ZEFT R53JA スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 7800X3D 8コア/16スレッド 5.00GHz(ブースト)/4.20GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (8GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 DIGITAL WH |
| マザーボード | AMD B650 チップセット ASRock製 B650M Pro X3D WiFi |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
ガラスパネルや木製ケースでエアフローはどう変わる?
Apex Legendsのように瞬間の判断で勝敗が変わるゲームを本当に安心して楽しむには、ケース内部の空気の流れを整えることが欠かせないと実感しています。
正直なところ、私も見た目の美しいケースに惹かれたことがあります。
ピカピカしたガラスに映えるLED、あるいは木材を使った高級感あるデザイン。
あの瞬間は「最高にかっこいいな」と心が動くんです。
しかし実際にゲームに使うと、冷却性能の不足がいかに大きなストレスになるかを思い知らされました。
だからこそ今の私の結論は、見た目と冷却性能が両立できるケースを選び、必要なときはファン増設などの工夫で最適化すること。
それが最も堅実で長く満足できる道だと考えています。
ショールームで見た瞬間のあの「これだ!」という高揚感はいまでも覚えています。
ところが夏、Apexを長時間プレイしているとGPUが80℃を超えてしまい、ファンが悲鳴を上げるように回転し続けました。
ブオーンという音が部屋に響き渡り、モニターの世界に没入したくても集中できない。
ガクッと来る感覚。
これは本当に耐えられませんでした。
そのときに初めて、自分は見た目に心を奪われるあまり、大切な安定性を犠牲にしてしまったんだと痛感しました。
見た目だけでは続かないんですよ。
そこから私はフロントメッシュ構造のケースに切り替えます。
吸気効率を最優先したものです。
すると驚くほどはっきりした違いが出ました。
同じ構成でも温度は5?8℃も下がり、フレームレートの乱れも消え去りました。
長時間のプレイでも音が気にならず、心から「これが本当の快適さなんだ」と実感できました。
思わず「こんなに違うのか…」と声が出たほどです。
最近では木目のフロントパネルを採用したケースもよく見ます。
家具のような高級感があり、リビングに置いても違和感がない。
確かに魅力的です。
けれど木という素材の性質上どうしても通気口が制限され、吸気が弱くなりがちです。
それでも「インテリアに合うから欲しい」と思う人は多いはず。
そういうとき、大切なのは考え方を少し切り替えることです。
例えばフロントの吸気が弱ければ、トップやリアにファンを増設して空気の流れを無理なく作ればいい。
手間はかかりますが、その一工夫で熱こもりが一気に解消されます。
私自身が試して実感した大切な学びです。
ガラスパネルも同じです。
ただ最近では、ガラスとメッシュを組み合わせたハイブリッド設計が出てきました。
見た目を保ちつつ、しっかり空気を取り込む構造です。
初めてそれを見たとき、私は思わず「お、やっと来たな」と声に出しました。
そう、ようやくバランスを本気で追及した製品が市場に現れたわけです。
現在私が使用しているのはフロントに木目デザインを採用しつつ、細かい通気スリットを複数備えたケースです。
外見はシックで部屋の雰囲気にしっかり溶け込みます。
性能面では、エアフロー調整とファンの追加によってGPUの温度は常に70℃台で安定。
Apexを200fps前後でプレイしても全く不安はありません。
以前は同じゲームで熱暴走に悩まされていたのですが、今は「同じゲームでも環境でここまで快適さが違うのか」と驚いています。
この違いは想像以上に大きい。
だから私は声を大にして言いたい。
見た目だけでPCケースを選ぶのはリスクが大きい。
外見がどれほど魅力的でも、冷却を欠くとハイエンドGPUも本来の性能を発揮できないのです。
それと同じです。
性能と快適さは環境によって決まります。
この視点を持つことが本当に重要なんです。
ゲームを最大限に楽しみたいなら、そしてパーツを長持ちさせたいなら、見た目と冷却性能の両輪をきちんと見極めることが絶対に必要です。
そこが揃ってこそ「本当に満足できるゲーミングPC」と呼べるものが完成します。
私はこのことをこれまでの試行錯誤から断言できます。
安定性。
それを得るためには、一瞬のかっこよさに惑わされず、自分が何を優先するべきかを冷静に判断する力を磨くこと。
ゲームも仕事も同じです。
その積み重ねこそが、40代を迎えた今の私にとって何よりの価値になっているのです。
FAQ|Apex Legends向けゲーミングPCに関するよくある質問
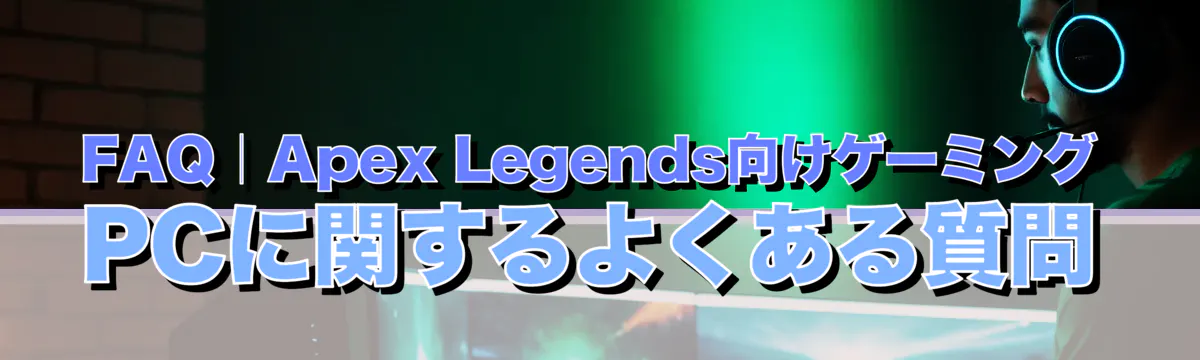
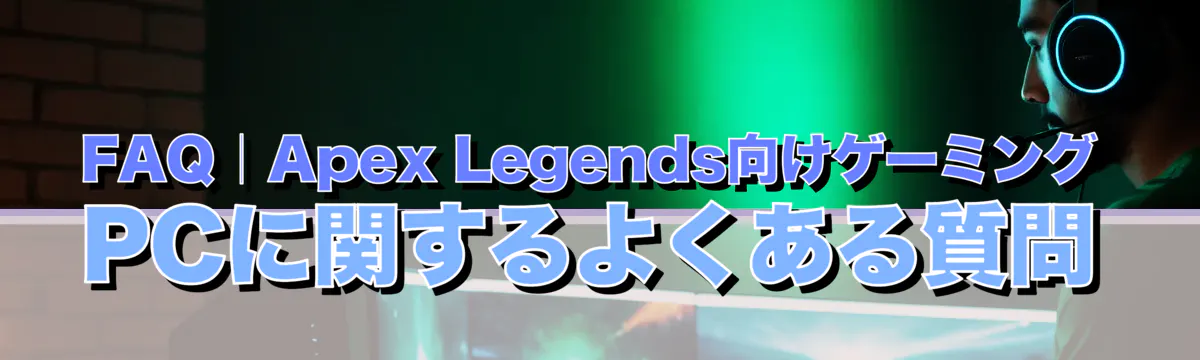
144fpsで遊ぶならどのグラボが現実的?
144fpsで快適に遊ぶために最も大切なのは、やはりグラフィックボードの性能だと感じています。
だからこそ、安定して144fpsを実現したいなら「どの製品を選ぶか」が核心になるのです。
私自身の考えでは、現時点ではGeForce RTX5070クラスやRadeon RX9070XTクラスが最も現実的な選択肢だと思っています。
特に5070Tiまで視野に入れれば、混戦時の描画落ち込みも防げますし、競技プレイに必要な安定性を手にできる。
逆に、RTX5060TiやRadeon RX9060XTはコスト面では魅力があるのですが、設定を落とさない限り144fpsを維持し続けるのは厳しい場面が正直多かったです。
負荷のかかる場面でフレームが沈み、あと一歩のところで悔しい思いをする瞬間がある。
この「惜しさ」をどう捉えるかで、そのグラボの評価も変わってくる気がします。
従来はRadeon RX9060XTを使っていたのですが、その差は自分の想像を超えていました。
特に撃ち合いの最中に「やばい」というシーンでもフレームが一切下がらず、操作に余裕が持てたことで思わず声を上げてしまったんです。
この時、なめらかに動き続ける環境がどれほど大切か、体感を通じて理解しました。
さらに印象的だったのはDLSS 4の存在です。
DLSSをオンにしたとき、fpsが高いまま操作の違和感がほとんどなかったのは衝撃でした。
もちろんRadeonのFSR 4も十分に頑張っていて、数値だけ見れば差は縮められます。
おそらくプレイスタイルや感度の好みによって評価は分かれそうですが、少なくとも「144fpsを安定させる要の仕組み」としてはかなり信頼できると確信しました。
ここで見落としてはいけないのは、グラボそのものの性能以外の要素です。
8GBで多くの場面は賄えますが、これから登場する高精細テクスチャを考えれば12GB以上が安心でしょう。
私は12GB搭載のモデルに変えたとき、大型イベントのシーンでも処理落ちをほとんど感じずに冷静に戦えた経験があり、その時に余裕のありがたみを噛み締めました。
余裕が結果を変える。
また、144fpsを維持しようとすると設定を「全部高」にしたくなる気持ちはあります。
私も以前はそうでした。
しかし影やエフェクトを少し抑えるだけでパフォーマンスが見違えるように改善されるんです。
派手さではなく視認性こそ競技シーンでは大事だと気付いた瞬間でした。
思えば、無駄な自己満足にこだわっていたんだなと苦笑いしました。
将来のアップデートやドライバの改善で、RTX5060TiやRadeon RX9060XTでも今より144fpsに近い環境が得られるかもしれません。
ですが、今まさに快適さを求められたら、答えははっきりしています。
5070クラス、あるいは9070XTクラスを選ぶことです。
結局のところ、私は144fpsで戦うためにはミドルハイ以上のグラボを選ぶことが唯一の正しい判断だと強く感じています。
理由は単純で、性能不足のせいで勝機を逃すという思いほど無駄なものはないからです。
勝つために努力し、時間を大切にするなら、環境に投資するのは決して贅沢ではなくむしろ必然です。
その投資は安定という形で必ず自分に戻ってきます。
そして選ぶべきラインは、やはり5070クラス。
これが最も納得できる答えだと私は言い切れます。
人気PCゲームタイトル一覧
| ゲームタイトル | 発売日 | 推奨スペック | 公式 URL |
Steam URL |
|---|---|---|---|---|
| Street Fighter 6 / ストリートファイター6 | 2023/06/02 | プロセッサー: Core i7 8700 / Ryzen 5 3600
グラフィック: RTX2070 / Radeon RX 5700XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Monster Hunter Wilds
/ モンスターハンターワイルズ |
2025/02/28 | プロセッサー:Core i5-11600K / Ryzen 5 3600X
グラフィック: GeForce RTX 2070/ RTX 4060 / Radeon RX 6700XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Apex Legends
/ エーペックスレジェンズ |
2020/11/05 | プロセッサー: Ryzen 5 / Core i5
グラフィック: Radeon R9 290/ GeForce GTX 970 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| ロマンシング サガ2
リベンジオブザセブン |
2024/10/25 | プロセッサー: Core i5-6400 / Ryzen 5 1400
グラフィック:GeForce GTX 1060 / Radeon RX 570 メモリ: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| 黒神話:悟空 | 2024/08/20 | プロセッサー: Core i7-9700 / Ryzen 5 5500
グラフィック: GeForce RTX 2060 / Radeon RX 5700 XT / Arc A750 |
公式 | steam |
| メタファー:リファンタジオ | 2024/10/11 | プロセッサー: Core i5-7600 / Ryzen 5 2600
グラフィック:GeForce GTX 970 / Radeon RX 480 / Arc A380 メモリ: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| Call of Duty: Black Ops 6 | 2024/10/25 | プロセッサー:Core i7-6700K / Ryzen 5 1600X
グラフィック: GeForce RTX 3060 / GTX 1080Ti / Radeon RX 6600XT メモリー: 12 GB RAM |
公式 | steam |
| ドラゴンボール Sparking! ZERO | 2024/10/11 | プロセッサー: Core i7-9700K / Ryzen 5 3600
グラフィック:GeForce RTX 2060 / Radeon RX Vega 64 メモリ: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE | 2024/06/21 | プロセッサー: Core i7-8700K / Ryzen 5 3600X
グラフィック: GeForce GTX 1070 / RADEON RX VEGA 56 メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ファイナルファンタジーXIV
黄金のレガシー |
2024/07/02 | プロセッサー: Core i7-9700
グラフィック: GeForce RTX 2060 / Radeon RX 5600 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Cities: Skylines II | 2023/10/25 | プロセッサー:Core i5-12600K / Ryzen 7 5800X
グラフィック: GeForce RTX 3080 | RadeonRX 6800 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ドラゴンズドグマ 2 | 2024/03/21 | プロセッサー: Core i7-10700 / Ryzen 5 3600X
グラフィック GeForce RTX 2080 / Radeon RX 6700 メモリー: 16 GB |
公式 | steam |
| サイバーパンク2077:仮初めの自由 | 2023/09/26 | プロセッサー: Core i7-12700 / Ryzen 7 7800X3D
グラフィック: GeForce RTX 2060 SUPER / Radeon RX 5700 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ホグワーツ・レガシー | 2023/02/11 | プロセッサー: Core i7-8700 / Ryzen 5 3600
グラフィック: GeForce 1080 Ti / Radeon RX 5700 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| TEKKEN 8 / 鉄拳8 | 2024/01/26 | プロセッサー: Core i7-7700K / Ryzen 5 2600
グラフィック: GeForce RTX 2070/ Radeon RX 5700 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Palworld / パルワールド | 2024/01/19 | プロセッサー: Core i9-9900K
グラフィック: GeForce RTX 2070 メモリー: 32 GB RAM |
公式 | steam |
| オーバーウォッチ 2 | 2023/08/11 | プロセッサー:Core i7 / Ryzen 5
グラフィック: GeForce GTX 1060 / Radeon RX 6400 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| Monster Hunter RISE: Sunbreak
/ モンスターハンターライズ:サンブレイク |
2022/01/13 | プロセッサー:Core i5-4460 / AMD FX-8300
グラフィック: GeForce GTX 1060 / Radeon RX 570 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| BIOHAZARD RE:4 | 2023/03/24 | プロセッサー: Ryzen 5 3600 / Core i7 8700
グラフィック: Radeon RX 5700 / GeForce GTX 1070 メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| デッドバイデイライト | 2016/06/15 | プロセッサー: Core i3 / AMD FX-8300
グラフィック: 4GB VRAM以上 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| Forza Horizon 5 | 2021/11/09 | プロセッサー: Core i5-8400 / Ryzen 5 1500X
グラフィック: GTX 1070 / Radeon RX 590 メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
予算20万円前後ならどんなPC構成が妥当?
これは昔からよく言われることですが、実際に自分で何度も組んできた経験からも痛感します。
Apex Legendsを高リフレッシュレートで快適に遊びたいと考えるなら、GPUにきちんと投資した上でCPUとの釣り合いを意識すべきです。
どちらかを軽視すると後で必ず後悔する状況になるからです。
私が考える理想的な構成は、グラフィックボードであればRTX 5070 TiやRadeon RX 9070 XTクラス、そしてCPUはCore Ultra 7 265KやRyzen 7 9700Xといったグレードが目安になります。
こうして組んでおけば、数年間は十分に安心して使えるだけでなく、拡張性を維持しながらも長く現役で戦えるマシンになります。
安定性。
逆にやってはいけないのは「とりあえずどちらもそこそこの性能で」という選択です。
以前の私もそうしてみたことがありますが、その結果は中途半端な性能に終わり、結局すぐに買い替えたくなってしまいました。
もう一歩踏み込んでGPUを良いものにすれば良かった、と強く感じましたね。
逆にGPUばかりに投資してCPUを軽視すると、映像が滑らかに出ているはずなのに微妙に引っかくような違和感が生じます。
ApexはCPU依存度が極めて高いわけではありませんが、実際にフレームの最低値や動きの自然さはCPUに大きく左右されます。
だからこそバランスが大事なんです。
20代や30代の頃は16GBで十分だろうと平気で思っていました。
ところが実際に仕事や遊びを同じPCでこなそうとすると、ブラウザにタブをたくさん開いた瞬間に重さを実感し、結果として作業効率ががくんと落ちていくのです。
そのストレスといったら本当に辛い。
ですから今の私は迷わず32GBをおすすめします。
ApexをしながらDiscordで通話し、配信ソフトを並行で動かすような環境では、16GBでは不安感が拭えない。
20万円を投資するならここは削らない方がいいです。
ストレージも人によって軽視しがちなポイントですが、とても大切です。
最低でも1TBのNVMe Gen4対応SSDは押さえておくべきです。
500GBなどではすぐにアップデートが入るたびに空き容量との戦いになり、本当に窮屈でイライラします。
私は現在2TBのSSDを利用していますが、複数のタイトルをインストールしていても空き容量を気にせずに済むというのは、とにかく気分が楽です。
実際の使い勝手に直結する部分だからこそ、ここでケチらない方が人生が楽になります。
冷却方式もよく議論になりますね。
水冷か空冷か。
昔、私も水冷に手を出したことがあるのですが、ある日突然ポンプが壊れて大慌てした苦い経験があります。
その一件以来、空冷派になりました。
やっぱり壊れにくさとメンテナンスの容易さは大事です。
最近のCPUは発熱性能が改善されているので、高品質な空冷で十分安定して使えます。
シンプルで手間がかからない分、長く安心して使いたい私のようなユーザーには空冷が合っているのだと思っています。
壊れにくい。
ケース選びも大人になるほどに重要さを思い知る部分です。
派手なRGBの光に魅力を感じなくもないですが、実際に体験してきた立場から言うと、一番のポイントはエアフローです。
しっかり風が通るケースを選ばないと、結局パフォーマンスが発揮されません。
以前エアフロー重視のケースに替えたとき、その静音性と快適さには正直驚かされました。
要は派手さより実益。
これが40代の私にはしっくりきます。
目先の数千円を節約して容量の小さいものを選ぶと、後でGPUを交換する際に制約が出て、本当に後悔する羽目になります。
650Wから750W程度、しかも80Plus Goldクラスを選んでおけば将来の拡張にも十分対応できます。
パソコンは拡張の余地を潰してしまった瞬間から「もったいない機械」になってしまう。
だからこそ未来の安心を先に買うつもりで選ぶべきなんです。
こうして振り返ってみると重要なパーツは限られています。
GPUとCPU。
それに32GBのメモリと1TB以上のSSD。
そしてしっかりとした空冷と良いケース、さらに余裕のある電源。
これさえ揃えて20万円前後で組めば、Apexを200fps前後で安定してプレイできる快適な環境が手に入ります。
そこでこそゲームの楽しさは本当に生きるのです。
私自身の結論は、「ミドルハイレンジを狙うのが最も満足度を高める近道」ということです。
逆に20万円前後でしっかり揃えれば、数年先まで余計な出費を避けながら快適さを維持できます。
それが大人の買い方だと私は思うのです。
最後に少しだけ個人的な考えをお話します。
30代までの私は「とにかく性能」と考えていましたが、40代となると視点が変わりました。
仕事に家庭にと忙しく、ゲームのために割ける時間は限られている。
だからこそパソコンは、起動したら確実に安定して動くことが一番大切です。
派手さは要りません。
必要なのは安心して電源ボタンを押せる気持ち。
その安心感が、何よりも価値のある投資だと私は感じています。
長く使うならストレージは何TBあれば安心?
私が伝えたいことはシンプルです。
ゲーミングPCを本気で長く快適に使いたいのなら、ストレージは最初から余裕を持たせておくべきだと実感しています。
特に私は40代になってから、後々の面倒や予想外の出費を避けるために最初の選択を間違えないことの大切さを痛感しました。
結局のところ、最低でも2TB、さらに将来の安心感を優先するのなら4TBは妥当な選択です。
私がこう断言できるのは、まさに自分自身の失敗による経験があるからです。
しかし、実際のところ半年も経たないうちにゲームのアップデートや動画ファイル、その他の重たいソフトたちでストレージはあっさりと埋まってしまったのです。
あの時の心境は「まさか、もう一杯になるなんて」。
完全に甘い見積もりでしたね。
あの後悔は、今でもよく覚えています。
最初から余裕を積んでおけば、これほど無駄な労力を払わずに済んだはずです。
手間をお金で買ったようなものです。
最近はGen4対応SSDが以前よりも手頃な価格で手に入るようになり、2TBモデルでもそこまで高価というわけではありません。
もちろん最新のGen5 SSDに惹かれる気持ちもあります。
カタログスペック上の速度は確かに魅力的です。
ベンチマークの数字よりも、実際の安定性と使いやすさこそ長く安心して使うために大切なんです。
大人の選び方とはそういうものだと思いますね。
例えば動画配信や録画を趣味にしている人ならなおさら容量は重要です。
ゲームのストリーミングを数時間高画質で撮影すると、一度の撮影で200GB近い容量を平気で消費します。
慌ただしく不要データを処分するか、外付けに移す作業で余計なストレスが増える。
これではせっかくの趣味の時間が台無しです。
だからこそ、最初から4TBという選択肢は大袈裟ではなく合理的なのです。
余裕のある環境がそのまま快適さに直結します。
だからこそ、私は積極的に4TBを選ぶべきだと言いたいのです。
私自身、平日は仕事に追われています。
だからこそ休日くらいはゲームや動画編集で気持ちを切り替えたいし、その限られた時間をファイル整理や容量不足の解決に振り回されるのは本末転倒です。
時間を充実させたいからこそ、余裕を持った投資で日常のストレスを回避するべきだと強く思います。
これは贅沢ではなく、効率を高めるための投資なんです。
同僚の中には「2TBで十分じゃないか」と言っていた人もいました。
体感する快適さが雲泥の差なんです。
やはり本体のストレージに余裕を積んでおくのが最も堅実なのだと私は確信しています。
短期視点なら最小構成で節約するのも一つですが、結局長期的に見れば余裕のない選択は割高になります。
最近のタイトルはアップデートが肥大化していますし、かつて数十GB規模だった追加データが今では100GBを超えることも珍しくありません。
この現状を見れば、ストレージは未来への「保険」と言えます。
余裕ある容量は確実に投資するに値するのです。
ですから私の結論は変わりません。
Apexを中心に遊ぶ人なら2TBは必須。
しかし録画や複数の大作タイトルを本気で楽しみたい人なら迷わず4TB。
結果として多少余ったとしても、それは安心を買ったにすぎないのです。
無理をせず、余裕を持つことこそが長く趣味を楽しむための鍵です。
余裕とは、ただの容量の多さを意味するだけではありません。
システムの安定や心の落ち着きに直結する大切な要素です。
いったんその快適さを体験してしまうと、もう「容量が足りなくて困る」状態には戻りたくないと心から思います。
だから声を大にして言います。
最初から余裕を買うべきなんだと。
気持ちの安定。
時間の余裕。
こういった小さな積み重ねが、毎日の暮らしを本当に豊かにしてくれるのです。
冷却不足が原因でfpsが下がることはある?
冷却不足がfps低下を招くかどうかについて、私の結論は一つです。
確実に下がります。
パソコンは見た目以上に熱に弱い機械なんですよ。
GPUやCPUが一定温度を超えると、自動的に動作クロックを落として熱を逃がそうとする仕組みが発動します。
この瞬間から処理速度が落ち、fpsもガタついてしまう。
私自身、幾度となくその現象に振り回されてきました。
どんなに性能の高いパーツを積んでいても、熱対策が甘ければ力を出し切れないのです。
高性能ランナーがスタート直後に重りをつけられて走らされるようなもの。
理屈ではなく体感で理解できる現象です。
特に負荷が高い環境で遊ぶ時ほど、冷却不足の影響は顕著になります。
解像度をWQHDや4Kに上げ、高リフレッシュレートのモニターでゲームを楽しもうとすると、GPUは猛烈に熱を持ちます。
95℃近い数字を見たときは、ちょっと背筋が冷えましたね。
fpsが安定するどころか、一瞬上がったり急に下がったりの繰り返しで、プレイに全然集中できない。
画質を落としても症状は収まりきらず、不快感ばかりが残りました。
fpsが急にストンと落ちて「あれ?」と振り返る瞬間が何度もありました。
ケースを思い切ってメッシュフロントに替えた途端、同じGPUでも温度がぐっと下がりfpsも劇的に安定。
あの時の感動は、まるで部屋にまとわりつく熱気が一気に消えたような爽快さでした。
ほんの些細な工夫が、これほど体験を変えるのかと驚かされたのです。
確かに省電力設計やAI処理の効率化でワットパフォーマンスは向上しています。
ただ実際に4K最高設定などで遊ぶと、発熱は避けられません。
むしろ性能が上がった分、その反動で生じる排熱も大きくなっている印象です。
だから冷却を軽視するのは本当に危険です。
空冷でも優秀なモデルは多数ありますが、長時間にわたり高fpsを安定的に求めるなら簡易水冷の導入を検討すべきです。
見落とされがちなのは、CPUやGPU以外のパーツへの熱対策です。
NVMe SSDは特に高速ですが、発熱も相応に大きい。
放置すると性能低下し、ゲームデータの読み込み速度まで影響してきます。
fpsに直結しないからこそ盲点になる部分です。
でもロードの遅れやデータ展開の遅延で没入感は確実に削がれる。
結局、体験全体を見ると冷却不足がもたらすダメージは計り知れないのです。
パーツ単体の性能ではなく、ケース内部の空気の流れという「見えにくい設計」がゲーミング体験を左右する。
これは実に面白い真実です。
さらに、それは単なる自作好きのこだわりで片づけられる範囲を超えています。
私は実際に、国際大会の配信で選手のPCが熱暴走しfpsが乱れた場面を見たことがあります。
会場のざわめきが一変し、その場の空気が冷え込んだ光景を今でもよく覚えています。
選手本人にとっては本当に悔しい出来事だったはずです。
つまり冷却は遊びではなく、時に競技の勝敗や観客の体験すら左右する要素となりえるということです。
では、どうすればよいのか。
答えは意外とシンプルです。
ケース内のエアフローをきちんと確保し、熱を効率的に排出できる構造にしてやる。
CPUとGPUがクロックダウンを起こさない状況を作る。
そのほんの少しの工夫で満足度が一気に変わります。
「100fps出れば文句なし」から「200fpsを安定的に維持」に変われるのですから。
反対に冷却をおろそかにしたPCは、せっかくのパーツを半分眠らせたままの状態で走らせているようなものなんですよ。
これほどもったいないことはありません。
冷却こそが核です。
fps低下の不安の大部分はそこを押さえれば解決できます。
だから私は声を大にして言いたいのです。
高性能なスピーカーをどれだけ揃えても、うるさい場所では音楽が台無しになるように。
最高のゲーム体験を得たいなら、まずは空気を澄ませることから始めるべきです。
それが本当に必要なことなんです。
信じられる一台。
だから私はこれからも冷却にこだわって、安心できるプレイ環境を作り続けたいと思っています。
BTOと自作PC、コストや利点を比べたときどちらが有利?
BTOと自作、ゲーミングPCをどちらで選ぶかと聞かれたなら、私の考えははっきりしています。
まず入り口としてはBTOの方が断然安心できるのです。
理由はいくつもありますが、一番大きいのは時間と安心感を同時に確保できるという点です。
仕事や家庭で毎日が慌ただしい中、自作に割ける時間はなかなか取れません。
仮にトラブルが起きたとしても、BTOであれば一つの窓口でまとめて対応してくれる。
それは、私のような年代にとっては大きな心の支えになりますね。
Ryzenを中心に構築して、最新世代のRadeonカードを組み合わせ、夜な夜な机の上にパーツを広げては、冷却の効率や配線の取り回しを考え込んでいたのです。
あのときの達成感は、言葉では上手く言い表せないほど強烈なものでした。
完成したPCの電源を入れたとき、ケースの中でLEDが光り輝いた瞬間。
胸が高鳴って、思わず「やった」と声が出ました。
自分の手で組み立てたという誇らしさ。
一方で、辛い思いもしました。
メモリの相性問題で突然ブルースクリーンが出る。
メーカーごとに問い合わせを繰り返して、結局交換品が届くまで一週間以上かかり、その間はまともに使えない。
結構しんどかったですよ。
正直、平日の疲れた体に追い打ちをかける出来事でした。
あの時、「BTOなら一括対応で楽だったのに」と心から思いました。
ここは大きな差です。
最新パーツへの対応についてもBTOは速い。
新しいRTXシリーズやRyzenが登場したと思ったら、もう翌週にはモデル構成に取り込まれていることすらあります。
自作だと、パーツを求めて複数のショップを探しまわり、在庫切れに落胆する日々。
欲しいときに手に入らない。
時間だけが過ぎていく。
この無駄こそ、社会人にとっては痛恨なんです。
とはいえ、自作が勝っている部分もあるのは事実です。
予算内で工夫を凝らせば、冷却性能や電源効率を上げることができ、それによって安定感のあるゲーミング体験を得られます。
特にApexのように動作の安定が成績に直結するゲームでは、冷却設計が決定的に大切です。
自作で少し良いケースを選んでファンも増設すれば、同じスペックでも驚くほど安定してフレームレートを維持できる。
ただ調子に乗ると失敗します。
私は見た目のデザインに惹かれ、フルガラスのケースを選んだところ、夏場にGPU温度が跳ね上がり、熱暴走しかけたことがありました。
さすがに焦りましたね。
BTOの場合はショップが全体のバランスを考えて構成してくれるため、デザイン性を維持しつつも廃熱効率を確保してくれる。
その安心感を知ると、「やはり専門店の知見は侮れない」と痛感します。
コスト面では、自作が勝てる場面も確かに存在します。
セールでSSDやメモリを格安で手に入れると、その瞬間の満足感は大きいです。
私もCrucialのDDR5を安く見つけたとき、思わず「これはお買い得だ」と喜びました。
ただ、私は結局こう考えています。
最初の一台目で失敗を避け、すぐに快適に遊び始めたいならBTO。
それが一番堅実です。
ストレスなく始められる。
これが何より大事なんです。
一方で、趣味としての深みを味わいたいのなら自作に挑戦すべきです。
二段階戦略ですね。
最初はBTOで安心して始め、次のステップで自作に踏み込む。
働きながらでも無理なく続けられる趣味の形だと、私はそう思います。
要は選ぶ基準です。
安定と安心を求めるならBTO。
自由と達成感を渇望するなら自作。
どちらも人によって最適な答えが変わる。
それが後悔しない選び方です。
私はこの歳になって痛感します。
何を選ぶかはスペックの数値以上に、その人の生き方に直結するんです。
遊びの時間をどう過ごしたいか。
それに合わせた選択をすることが、長くゲームを楽しみ続ける秘訣だと強く感じています。
安心できる選択。
心から納得できる選択。